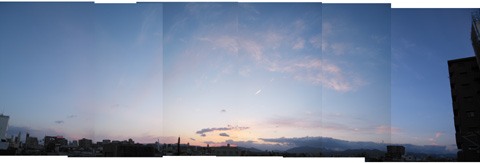新型コロナウイルスによる外出自粛期間中、部屋の壁に射す光をインターバルで撮っていた。
青の時間と呼ばれる薄明の光がどんなふうに変化するのか。
どんなふうにわたしたちのところに夜は訪れるのか。
そんな素朴な疑問から撮りはじめたものの、ただうっすら明暗差があるだけの壁にレンズを向け「なんも撮れへんやろうな」と思いながらインターバル撮影をセットする日もあった。その写真を「手応え薄そう…」と思いながらタイムラプスにしあげてみたら、通常速度ではまったく気づかない微かな光の変化が、外の雲のゆるやかな流れを反映していることに気がついた。なんだか潜像みたいだなと、そのとき思った。
目の前にあるのに、そのままでは認識できないもの。
もうひとつは、ぼやけていた影の輪郭が光の調子の変化によって引き締まっていくさま。それが現像液にひたした印画紙に像がふわっと現れる瞬間にとてもよく似ていて、心揺さぶられるものがあった。
輪郭がゆるすぎてぼんやりとしか認識できない身のまわりの明度差が実は何かの像だとすれば、世界は潜像で満ちているのではないか、と。
この文章を読んで、そんなことを思い出した。
さて、ここで少し遡って考えてみたいのは、現像によって「像」が現れる前に、その真っ白な感光紙の上には何があったのか、ということだ。そこには確かに「像」が準備されていただろう。だが、それは見えない。トルボットは、その不可視の像に「潜像(latent image) 」という名前を与えた。「latent」はラテン語の起源を持つ単語で「隠れて見えない」という意味を持つ。しかし「見えない像」とは、いったいなんのことか?もし不可視な像があるとしたら、それは純粋に観念的なものであり、僕らの頭の中にしか存在しなかったもののはずだ。それが、喩えでもなんでもなく、そこに、その白い紙の上に、実際にあるという。
観念がそのまま日常世界に、呆気にとられるほどの即物性を備えて舞い降りてきてしまったかのような、魔法を見ることにも似た衝撃がここにはないだろうか。「潜像」は、「像」とは未だ呼べない、表象不可能な「像への可能態」だ。こんな「像」のありようは、確かに写真術誕生以前には、決して存在しなかった。
(『自然の鉛筆 The Pencil of Nature』ウィリアム・ヘンリー・フォックス・トルボット著 青山勝編・訳 赤々舎 2016 / 団栗と写真 ゲルハルト・リヒターおよび「像」についてのメモランダム 畠山直哉 p.89より)
像の現れに驚くこと。それが、写真術の始まりだった。現れる以前の「見えない像」に胸をはずませること。それが写真行為の原点だった。写真とは、「見えない像」というパラドックスが現実に成立してしまった時代、つまり僕らの暮らす現代を、驚きの目で眺めることだった。写真はそうして、写真家に限らず、すべての人間の視覚的認識を根底から変質させたはずだ。(同書 p.90より)