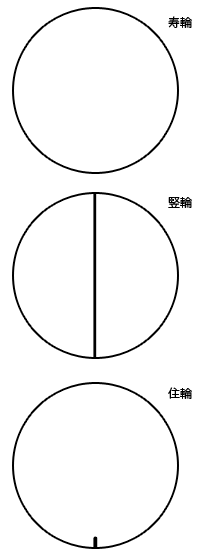昨日の「守宮神(宿神)」では少し寄り道をしてしまった。そもそもは、重森三玲の庭に興味を持って、中世から現在に至る作庭の、背後にある思想とか美意識を知りたいというところからスタートしたのだ。はからずも『精霊の王』に、その答えを見つけたように思う。長いけれど抜き出してみよう。
立石僧や山水河原者は、庭園をつくる職人だ。彼らのおこなう芸能では、ことはさらに抽象的に深められている。庭園の職人たちは、西洋のジャルディニエールたちのように、いきなり空間の造形にとりかかるのではなく、空間の発生する土台をなす「前ー空間」を生み出すことから、彼らの仕事を開始する。「なにもない」と観念された場所に、庭園の職人はまず長い石を立てることからはじめる。この石は伊勢神宮の「心の御柱」や「六輪一露」説に言う輪に突き出た短い杭と同じように、潜在空間からこちらの世界のほうに突出してきた強度(力)の先端をあらわしている。この先端の向こう側には、存在への意志にみちみちた高次元の潜在空間が息づいている。そして、この先端のこちら側には、人間が知覚できる三次元の現実空間が広がっている。庭園職人が「なにもない」空間に打ち立てるその立石は、まさに絶対の転換点となって、空間そのもののはじまりを象徴する。
空間に突き出した猿田彦の鼻のようなこの立石が、「前ー空間」を出現させる。立石の下には、宿神の潜在空間が揺れている。その揺れの中から、三次元をもった現実の空間の原型が押し出されてくる。そして、「六輪一露」説における像輪さながらに、この空間の原型を素材にして、庭園の職人たちはそこに、起伏や窪みや水流や陰影や空気の流れなどでみたされた、現象の世界の風景を造形するのである。
しかし、金春禅竹が像輪についての説明の中で語っているように、そうしてできてくる現象としての風景には、いたるところに「空」が滲入しているのでなければならない。庭園は目で見ることもでき、手が触れることもできる現実の空間にはちがいないのだけれど、その全体が宿神の潜在空間に包み込まれ、細部にいたるまで「空」の息吹が吹き込まれているために、向こう側のものでもないこちら側のものでもない、不思議な中間物質として、蹴鞠の鞠のように、どこか空中に浮かんているような印象を与えるのだ。
宇宙とか、大海原というレベルではなかった。「空間そのもののはじまり」という原初的で動的な現象を象徴するという、ものすごいチャレンジだったのだ。自分の認識をあらためなければならない。そして、自分の考えの射程範囲の狭さを痛感。今年はもう一度、庭園を見に行こう。
そしてもうひとつ気になったことがある。
たいがいの西洋庭園とちがって、このような宿神的庭園では、風景の全体を見通すことができないように、特別な工夫がこらされている。宿神の創造する空間は、つねに生じてくるようでなければならないからだ。そのために、それは出来上がった空間として、全体を見通せるようなものであってはならない。一歩歩むたびに、新しい小道が開け、新しい風景が眼前に生じてくるようでなければ、それはけっして宿神的空間とは言えないだろう。植物は人に見られるものではなく、逆に人が植物によって見られるようになる。前ー空間では主客の分離がおこりにくい。その影響が庭園のすみずみまで浸透しているので、このタイプの庭園を歩いていると、人はだんだんと主体としての意識を薄くして、瞑想的な静けさの中に入り込んでいくようになる。たしかにこれも「六輪一露」に説かれていたとおりのことではないか。
このように宿神を家業の守り神とする「諸芸」の職人や芸人たちのつくりあげてきたものは、どれも空間として特異な共通性をそなえているように見える。運動し、振動する潜在空間の内部から突き上げてくる力が、現実の世界に触れる瞬間に転換をおこして、そこに「無から有の創造」がおこっているかのようにすべての事態が進行していく、そういう全体性をそなえた空間を、職人や芸人たちは意識してつくりだそうとしてきたようなのだ。
(『精霊の王』中沢新一著 講談社 2003 p262-264から抜粋)
このくだりを読んだときに、以前、自分の展示において、どうしても「作品全体を一望できないように展示したい」という気持ちが強かったのを思い出した。
宿神の創造する空間は、つねに生じてくるようでなければならないからだ。
そのために、それは出来上がった空間として、全体を見通せるようなものであってはならない。
自分の制作が宿神の思想に直結しているとまでは言えないけれど、わたしに限らず、この国で生きて生活しているひとびとの、ものをつくり表現する営みの底には、かすかに宿神の思想が潜んでいるのかもしれない。