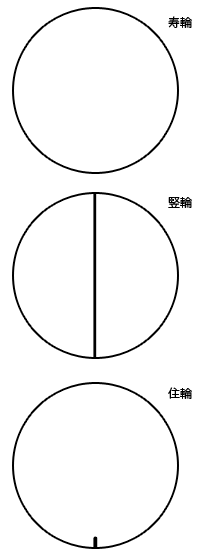写真の画面の中ばかりに意識が向いているなぁ。内に閉じていく方向に向かっているなぁと思ったときに、ふと、以前見た重森三玲の庭の、庭が庭だけで閉じずにもっと大きな世界につながっている感じを思い出した。
そして、それら庭園がどういう意図や美意識のもとに組み立てられているのかということを知りたくなって『枯山水 』を繙いた。(重森三玲著 中央公論新社 2008)
』を繙いた。(重森三玲著 中央公論新社 2008)
読んでみて気になったのは、幽玄、見立てる、空白の3つ。
幽玄
幽玄というのは、その表現の形式なり内容が、なんらかの形で、又は意味で隠されているものを指しているのであって、いわば本体の姿のままの形式や内容の、そのままの表現ではなく、全く異なった形や、内容として、別天地を創造した美の領域を指していることがことがわかるから(後略)(p70より抜粋)
この部分だけを抜き出してもわかりにくいと思う。ここで言っていることの具体例を枯山水に求めると、水に代わるものとしての表現材料として白砂を用い、また見る側も、砂を通して水を見いだそうとしていることが挙げられる。数個の石を立てて滝の表現とするのも然り。
砂を砂の美としてのみ創造もし、鑑賞もすることは、隠され、秘められている美がない訳であるから、これは幽玄ということはできないのである。
砂が水の表現材料として使われているからこそ幽玄であり、砂が砂としてのみ表現され、鑑賞されるのは、それは幽玄ではないのだそう。
このあたり、ものづくりをする際の素材と表現内容の関係を考えるヒントになりそう。
見立てる
庭園においては、園池の池水は池水と見つつ、同時に海景に見立てているのであり、枯山水における白砂は白砂と見つつしかも水と見立てるのである。
象徴というと、西洋絵画のヴァニタスのような、死の象徴としての頭蓋骨や、加齢や衰退などを意味する熟れた果物を思い浮かべるけれど、ここで言われている「見立て」とはまた全然意味が違う。
何が違うのだろうか?
死や、加齢などは、抽象性が高いのに対して、海景や滝、水は具体的である。庭園においては、象徴とする対象もまた具体的なものであるというのが大きな違いではないか。
ここでもうひとつ面白い記述を見つけた。池庭は、基本的には海景を表現しているのであり、そこに置かれる石は島の表現であるが、
池庭の中島などに要求されるものの中に、雲形とか、霞形とか、松皮様などのものがある。池中の中島は大体において、大海の島嶼を表現することが意図されているにもかかわらず、この中島に、雲の形とか、霞の形などといったものを形式上に意図すること、(後略)(p78より抜粋)
とある。で、雲の形や、霞の形のものをどうするかというと、
雲形の中島の場合では、雲が風に吹き流されているような形として表現し、霞形の中島の場合では、霞が二重にも、三重にも棚引いているがごとき姿に作ることが主張されているのであって、(後略)
単純に池水を海と見立て、石を島と見立てるのにあるあきたらず、さらに島と見立てた上に、雲や霞の表現を求めるというのだ。中島を、石と見て、島と見て、雲(あるいは霞)と見る。すごい。
ここで、わざわざ雲が風に吹き流されているような形、霞が二重にも、三重にも棚引いているがごとき姿と書かれていることに気がつく。単に雲のかたち、あるいは霞のかたち、ではなく、雲(あるいは風)の動きや霞の動きを忠実に表現することに重点が置かれている。そう考えると、白砂が表現する波や水紋も、石を複数組み合わせて表現する滝も、水の動きを表現している。
石や砂といった基本的には動かないモノを材料とし、その形状によって、水や雲や霞といったまったく別のものを、その動きまでを含めて表現する。
ものすごく射程の広い話ではないか。
中島を、石と見て、島と見て、雲(あるいは霞)と見るように、同時にAと見て、Bと見て、Cと見るような構造を写真に持たせることは可能なのだろうか。