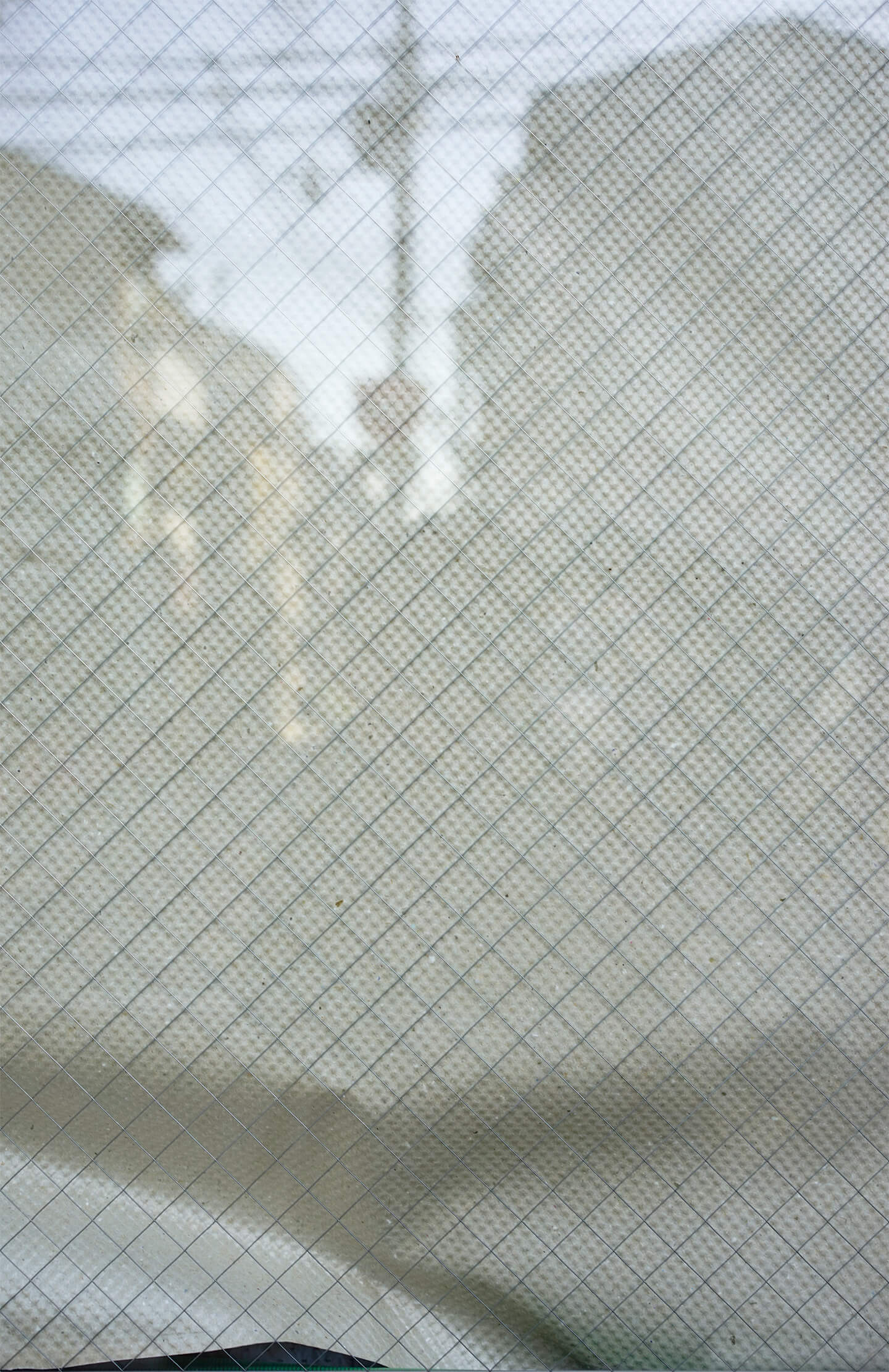『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』に、もうひとつ気になった箇所がある。
望遠鏡と顕微鏡の発明によって、今まで肉眼で見ることのできなかったものが見られるようになり、人々は「見えない世界がある」ことを知った。もちろん、それが周知され受け容れられるまでにはさまざまな葛藤があったが、もうひとつ、この時代に生まれた新しい考え方があった。そのことについて記しておきたい。
当時の自然哲学者たちが、それまで見たこともないまったく新しいものを見たとき、ある困難に直面した。具体的な事例が紹介されている箇所をいくつか抜き出してみよう。
月の表面に見える斑点はクレーターと山の影だとガリレオが見抜くことができたのは、遠近法を学んでいたからだけではない。コペルニクスの地動説を支持していたからでもあったのだ。古代から続くアリストテレス的な宇宙観では、地球は天界の中心にあり、地球を周回するすべての天体は発光性の〈アイテール(エーテル)〉で構成されているとしていた。この宇宙観を頭から信じているものの眼には月の表面は真っ平で輝いているように見え、クレーターや山があるようには見ることができなかった。見えているのに見えてないと考えるようにしているわけではない。先入観が視覚に影響を及ぼし、本当にそう見えていなかったのだ。彼らは輝く月の表面にある斑点が雲に見え、もしくは質の悪いレンズのせいでまだらに見えると考えてしまう。しかしそんな古い考え方に囚われずに、地球も月も太陽を周回する天体だとするコペルニクスの説を受け入れると、月にも地球のように山があったりクレーターがあったりしてもおかしくないと思えるようになるのだ。
『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』(ローラ・J・スナイダー著 黒木章人訳 原書房 2019 p171より抜粋)
血液のなかに赤血球を発見したとき、実際には真ん中が窪んだのっぺりしたかたちなのにもかかわらず、彼の眼には球形に見えた。そう見えたのはファン・レーウェンフックだけではなかった。この時代に赤血球を観察したものは、誰もがみな球形だと述べた。ヤン・スワンメルダムもミュッセンブルーク兄弟も王立協会のフェローたちも、全員が赤血球は球状だと言った。みんながみんな、そんなかたちのはずだと思っていたからだ。(同書 pp416-417より抜粋)
一六七八年に哲学者のジョン・ロックと共にイヌの精子の観察をしていたときのことだ。ロックには、精子の尻尾がなかなか見えなかった。「私には、どうしてもきわめて小さなビーズ球にしか見えなかった」ロックはそう告白している。ファン・レーウェンフックは、自分もあらゆる物質の構成要素がどうしても球状に見えていたことを思い出した。ロバート・ボイルたちが唱えていた、すべての物質は粒子によってできているという〈粒子仮説〉に囚われていたからだ。ファン・レーウェンフックは、何もかもが丸く見えてしまう自分の心と闘い、ようやく精子の尻尾が見えるようになった。(同書 p417より抜粋)
まったく新しいものを見るというのは、そうたやすいことではなかったのだ。
一七世紀の自然哲学者たちは自然界をありのままに見ようとした。これまで信じてきた、自分の支持する説やそれ以外の説には頼ろうとはしなかった。しかし新たな光学機器による観察がどれほど難しくても、観察して見えたものが強固な信念や説に反するものだとしても、見えたそのままに見るためには心の鍛錬が必要だった。それが大きな問題だということを理解していたガリレオは「実際の眼だけでなく心の眼もつかって見なければならない」と述べている。先入観や思い込み、そして願望すらも、実際に眼に見えているものではなく、何か別のものを見せてしまうことを理解しなければならないのだ。(同書 p172より抜粋)
つまり、この時代の自然哲学者たちは「ものの見方は固定観念に影響される」ということを理解しなければならなかった。そして、これこそがまさにこの時代に生まれた考え方だという。新しい世界が(外に)ひらけたことにより、見る側のもののとらえ方(内側)の瑕疵が浮かび上がったというのは興味深い。
それはさておき、この箇所を読んだとき、既視感(既読感?)のようなものを覚えた。似たようなフレーズをどこかで…。そう、モダニズム写真の倫理だ。
エヴァンスに象徴されるモダニズム写真の倫理とは、人間的な意味や表象のフィルターを通さず、カメラ・アイによって対象物自体をじかにありのままに、クリアに撮ること、つまり透明性、純粋性、裸の倫理である。それは、人間の色眼鏡を超えた、汚れなき曇りなきカメラ・アイによってのみ到達可能な「ありのままの世界」、社会の価値や表象の体系の彼方に存在する「ありのまま」のリアリティに対する倫理なのだ。
『プルラモン―単数にして複数の存在 』(清水穣著 現代思潮新社 2011 p48より抜粋)
』(清水穣著 現代思潮新社 2011 p48より抜粋)
「ありのまま」にたどりつけない原因(眼を曇らせるもの)を、片方は先入観や固定観念、願望に、片方は意味や表象のフィルターに求め、それを克服する方法を、片方は心の鍛錬に、片方はカメラ・アイに求めている。まるで相似形のようではないか。
正直なところ、モダニズム写真の倫理を実感として理解するのは難しかった。なんで人間が見ることをそこまで否定するのか? どうしてそんなにカメラ・アイに期待するのか? わたしにはさっぱりわからなかった。けれど、17世紀のパラダイムシフトによってもたらされた考え方や、当時の経験がその下地にあるとすれば、少し理解の方途が見えた気がする。
しつこく抜粋したように、17世紀の自然哲学者たちは具体的な困難を経験していた。赤血球が球状にしか見えなかったり、精子の尻尾がなかなか見えなかったり…それらの困難を克服しようと「ありのまま」に見るための心のありようを模索した。その経緯はよく理解できる。では、モダニズム写真の倫理が生まれる背景にはどのような困難があったのか。何を克服しようとしたのか。