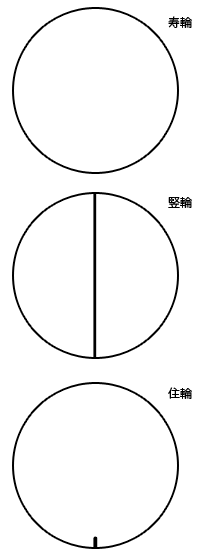松本卓也さんの新著『斜め論 空間の病理学』の第六章「ドゥルーズの無人島論」に印象深い話があった。
自分が建物の正面を見ているとき、その裏側や内部を見ることはできないが、それでもその建物に裏面や内部があると信じることができるのはなぜか?という問いからはじまる。
現象学的に言えば、フッサールの言うように、その建物の私に見えている面の現前と、私には見えていないが他者には見えている面の共現前と一体となって建物が現れるからである。
ドゥルーズは、このような知覚の共同的なあり方を、「私が見ていない対象の部分を、同時に私は他者にとって可視的なものとして措定している」ことから説明している。
(『斜め論 空間の病理学』 松本卓也著 筑摩書房 2025 p.225より抜粋 )
他者のいない世界では、知覚の場はわたしが見ているもの(たとえば、建物の正面だけ)に切り詰められてしまうのである。(p.226)
つまり、知覚を構造化する(先の例では建物の裏面や内部があると信じる)ためには他者が必要である、と。
わたしは電車の旅が好きで、車窓にスマホをぴったり押し当て動画を撮ることがある。昨秋、北陸新幹線の車窓から撮った動画には、高速移動によって遠くの山の見える面がくるくるとかわる様子が収められている。それを見ながら、対象が立体であると認識するためには、視点が動くこと、それによって見える像がかわることが必要なのかもしれないということを考えていた。つまり視点が動き(運動)、それに応じて変化する視覚情報を結びつけることで立体や空間を認識しているのではないか、と。しかしここで「他者」という想像もしない解が示された。より根源的な条件として。
話を戻そう。これに続く事例がとても興味深いのだ。
自閉症の当事者として経験を書き記したグニラ・ガーランド(一九六三年生)は、「私は近所の家々にも内部があることを知らなかった」という。それは、彼女にはすべてが「芝居の書き割り」のように見えており、「自分の家の内部には空間があることは知っていたのに、そのちょっとした知識を向かいの家に結びつけることはできなかった」からである。彼女にとって、「向かいの家は、紙と同じ、平面でしかなかった」のである。(p.226)
現象学者の村上靖彦(一九七〇年生)は、これらの体験を注釈して、「自閉症をもつガーランドにとって、見えないものは端的に存在しない。奥行きと裏側が存在しない」と述べている。(p.227)
奥行きと裏側が存在しない!
しかし、著者はそれを自閉症者に特有の特殊な知覚のあり方だとは結論づけない。國分功一郎による発想の転換を経由し、知覚の場を構造化するために必要な他者を「自分と同じように世界を見る者(類似的他者)」に絞り込む。
國分功一郎(一九七四年生)は、ドゥルーズの無人島論とガーランドのような自閉症者のあり方を参照しながら、「奥行きを認識できる定型発達者と奥行きを認識できない自閉症者がいるのではな」く、「他者が存在しているところに生きている人間と他者が存在していないところに生きている人間がいる」という発想の転換を行なっている。(p.227)
自分と同じように世界を見ている他者がいればこそ、見えていない部分をその他者に託すことができる。(p.228)
自閉症者の知覚のあり方それ自体に何かしら欠陥があるのではなく、自閉症者が「自分に類似した他者を見つけることに苦労する」がゆえに、すなわち類似的他者との出会いの機会が十分にないことによって、知覚のあり方に欠陥が生じさせられているのではないか、と考えることを可能にする。(p.228)
もういちど、先の抜粋を記しておこう。
他者のいない世界では、知覚の場はわたしが見ているもの(たとえば、建物の正面だけ)に切り詰められてしまうのである。(p.226)
—メモ—
1.
建物の正面だけに切り詰められるって、なんだか自分の作品のこと言われてるみたいだな…
2.
奥行きも裏側もない、まんま写真のように世界を平面としてとらえている人がいるということ。そして誰であっても類似的他者なしにはそのような知覚になりうるということ(驚き!)
3.
裏側が存在しないという話から、春に京芸の展示で観た3回生松苗さんの「表裏思索録」を思い出した。彼女が伊藤亜紗さんの『目の見えない人は世界をどう見ているか』から引用していた事例に、全盲の子どもが粘土で壺をつくったときに壺の外ではなく中に装飾をはじめた話があり、視覚によって区分される表と裏はその子にとっては等価なのだと。表と裏はきわめて視覚的な区分で、触覚で世界を知る人にはその区分がない。