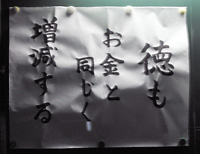タイトルのセンテンスは、昨年末に読んでいた今井むつみさんの『英語独習法』で見つけたもの。思いがけないところで、思いがけないことばに出会うのね。
人は外界にあるモノや出来事を全部(seeの意味で)「見ている」わけではない。無意識に情報を選んで、選んだ情報だけを見るのが普通である。注意を向けて、見るべきもの、次に起こるであろうことを予期しながら外界を(lookの意味で)「見ている」。当たり前のことが起こると、その情報は受け流してしまい、見たことを忘れる。予期しないことが起こり、それに気づけばびっくりする。そのときは記憶に残りやすい。しかし、注意を向けているつもりでも、予期しないものは気づかずに見逃しまうことも多い。
(『英語独習法』今井むつみ著 岩波新書 2020 p7より抜粋)
RIVERSIDEプロジェクトの根幹は、まさにこれだと思って。ふだん何気なく(lookの意味で)見ているものを写真に置き換えることで、seeの意味での見るに変換すること。
いつも見ていたはずだけれど、そうは見ていなかったんじゃない?と。
そして、日本語を使って考えているうちはなかなか言語化しにくかったのが、英語を借用することでこうもあっさり表現できるんだなぁ、と。
ここからはまったくの余談…
ちょうどこの本を読んでいたのと同時期に放映されていた恋愛ドラマに「好きです。likeではなくて、loveです!」という台詞があって、わざわざ英語を借用しないと自分の気もちすら伝えられないって日本語ってちょっと不便じゃない?と。自分の生活でも、漢方医の問診で「喉がかわきますか?」と訊かれたときに、乾く(dry)?渇く(thirsty)?どちらだろう?といつも戸惑う。局所的に喉を湿らせたいのか、身体が水分を欲しているのかは違うニーズだと思うので…。
何かを厳密に定義したり伝達するには、日本語は曖昧ですこし不便な道具なのかもしれない。