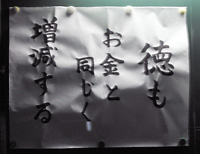先の八瀬の赦免地踊りに続き、この週末は鞍馬の火祭りを訪れた。
この祭りも最後に訪れたのは2019年で、2度目の来訪となる。
はじめて訪れたときは、祭りの熱気と燃え盛る炎に煽られ、執拗にシャッターを切っていたように思う。
今回は、写真を撮るというより祭りそのものを楽しもうと思って訪れたこともあり、鞍馬街道のほぼ最奥で軒を借りて松明が通るのを待っていた。
鞍馬の火祭りは鞍馬寺ではなく由岐神社の神事で、氏子それぞれの軒先で篝(エジ)が焚かれている。両親と同年代と思しきご夫婦が互いに相手の薪のくべ方に注文をつけあっているのを聞くとはなしに聞いていたら、なんとなく氏子同士の立ち話に加わることになっていた。
氏子のひとりが「松の枝を市原に取りに行ったんやけれど、(時節柄、マツタケ)泥棒と疑われんかと思ってな」と話しているのを聞いてあらためて各戸の篝を見てみたら、薪を山のように積んでいるもの、一定量を保ってこまめに薪を足していっているもの、それぞれの個性が滲みでているようすが見えてきた。
篝が焚かれた街道の光景を、できるだけうつくしい画に仕上げようとシャッターを切るのと、それぞれの篝にその火の守りをする人の個性を見出しながらシャッターを切るのとでは、まなざしのあり方はまったくちがう。
先の赦免地踊でも、はじめて訪れたときは切り子燈籠のうつくしさや女性に扮した少年たちの妖しさに魅了されたが、ことしは隣席の方から「今回は息子が燈籠着(燈籠をかぶって歩く役)を、夫が警固(燈籠着のそばについて燈籠を支える役)をしている」と聞いたことで、息子の頭に載せられた5kgもの燈籠を力強く支える父親の手が見えてきた。
それまで見ていなかったもの、見えていなかったものが見えるようになった、という気がしたのだ。
日頃から「見栄えのいい写真を撮ってやろうという欲は時として足枷になる」と自分を戒めてきたが、その欲はよく見ることの妨げにすらなりうると思った。
外から来訪し、フォトジェニックな被写体を追って見栄えのする光景を切り取って帰るより、その場その場で居合わせた人と関わることによって、まなざしがそれまでよりずっと丁寧に細やかになった。個別具体的なひとの営みが、以前よりよく見えるようになった。
翻ると、それまでわたしは、ひとを記号のようにとらえていたのだと思う。
わたしだけではない。その夜、祭りの場でシャッターを切っていたほとんどの来訪者が祭りの担い手を、それぞれの画面を構成する要素/匿名の存在/記号のように扱っていたのではないだろうか?さらに言えば、見知らぬ他者を画面に取り込む写真実践のすべてに同様の問いは潜んでおり、それを不問に付したまま写真は消費されてきたのではないだろうか?
個別具体的な生をもつ他者を、画面を構成するものとしてとらえること、あるいは記号のようにとらえることへの違和。近年芽生えたその違和を、なかったことにせず考え続けたいと思う。