昨夕、三日目の月を見上げながら、もし仮にここを去ることがあるなら、
遺したいのはこの地を愛したということなんだろうな、ということを考えていた。
人生の残り時間を考えたとき、
遺したいのはきっと、この世界を愛したということなんだと思う。
人生の折り返し地点にさしかかって、
去りゆく者として自分を想定するようになった。
2024-02-14
昨夕、三日目の月を見上げながら、もし仮にここを去ることがあるなら、
遺したいのはこの地を愛したということなんだろうな、ということを考えていた。
人生の残り時間を考えたとき、
遺したいのはきっと、この世界を愛したということなんだと思う。
人生の折り返し地点にさしかかって、
去りゆく者として自分を想定するようになった。
2023-12-23
20年前に買いそびれたHysteric Sixを入手したのをきっかけに『なぜ、植物図鑑か』を再読。いま手元にあるのは2012年第3刷の文庫本だから、2000年代初頭の学生時代にコピーか何かで読み、2013年ころ文庫で再読。なので正確には再再読だろうと思う。
その直後、撮影中にふっと考えたことをX(旧twitter)に投稿したので、こちらにも移して(写して)おこうと思う。
季節によっては夜明け前に目が覚めてしまうようになり、ならばと早朝に散歩や読書、ブレストをするようになった。朝のブレストで頭に浮かんだことをメモするかのようにXに書き留めている。もしかしたら今後、Xをメモとして使い、その中から残したいものや話題を広げられるものをこちらに移すというスタイルになっていくかもしれない。
冬至だからなのか薄明から三脚立ててスタンバイしている人を多く見かけ、中平さんのテキストに自身が薄明や夜を撮ることを挙げてその情緒性を批判する記述があったのを思い出していた。学生の頃はそんなものなのかと教科書的に受け止めていたが、だんだんその叙情を排除する姿勢に違和が芽生えたのよね。けっこうそれって極端だよね…と。
そして、そのテキストが書かれた半世紀前よりカメラの性能が格段に上がり、薄明でも夜間でも高感度、拡大表示で対象を視認・凝視することが可能になって、いまや叙情性や情緒性と具体性・客観性・凝視的ふるまいは「どちらか」ではなく両立する可能性があるのではないかと。
これまで叙情的ととらえられてきた光景(ものがはっきり見えにくい状況)をバチッと隅々まで解像して捉えることが可能になったので、写真を巨視的にみて叙情的ととらえるか、微視的、具体的にみて客観的ととらえるかは作家が決めるのではなく、観者に委ねることもできるのではないかと思うようになった。
札幌での撮影以降、見えにくい状況で対象を精密にとらえることにこだわるようになったのは、道具が変わったことが大きいが、何かしら自分が感じた違和に応答するという側面もあったんだと気がついた。
中平さんのテキストをずっと覚えていたわけではない。むしろすっかり忘れていたというのが正しい。それでも、最初にテキストに触れた時点ですでにもう対話に巻き込まれていたんだと思う。
再読、してみるもんだね。
ここまでたどり着いたあなたは相当ニッチな関心領域をシェアしているとお見受けするので、もしよろしければXアカウントのフォローもどうぞ😊
2023-12-07
質感って英語ではtextureなんだよなぁ。textureは織物という実在によって後ろ支えされた言葉だけれど、質感という言葉にはそういった実在による後ろ支えを欠いたふわっとした感じがする…ということを考えていた。(「質感」という言葉には実在による後ろ支えはないが「肌理」にはある)
photographも photo-光 graph 書かれたもの(刻まれたもの)という構造で実在に後ろ支えされているが、写真という言葉にはそれがない。
この実在の後ろ支えがないふわっとした言葉を用いて思考し語ることと実在の後ろ支えのある言葉で思考し語ることとは、相当異なる経験ではないのだろうか?と。
というのも、抽象度が高くなった途端話が通じにくくなるということがここ何度か続き、はじめは自分の理解力や相手の言語運用能力を疑ったが、使う言葉に因る部分もあるのではないか?と考えるようになったのだ。
エティモンライン – 英語語源辞典
https://www.etymonline.com/jp/word/photograph
2023-12-06
なにか考えや問いをもって撮影に向かうたび、おもしろいくらい裏切られたここ数日。写真は常に現実とのせめぎ合いだということを忘れないために、X(旧twitter)の投稿に少し手を加えてこちらに移しておこうと思う。写真はできるだけ同じ画角になるようトリミングしたうえ、後から加えた。
まるで息のあわないダンスのようだ。
2023-12-03
きょうは愛宕山に登るつもりが、電車の遅延と不安定な天候によりショートカット。体力と気もちを持て余し、保津峡駅のプラットフォームで撮り鉄の皆さんの横に並んでみた。ほかの方は保津峡を走り抜けるトロッコ列車を撮っている様子だったが、わたしはそばの枯れ木に覆われた山が目当て。晩秋の山は枯れ木も含め個体によって色がバラつくので、それぞれの木が個として見えてくることがある。
以前、川で撮影をしていたときに、あまりに人出が多く、個として見えていたのが群に見えた途端におもしろみを失うということに気がついた。それからは人出が多すぎるタイミングを外して撮るよう気をつけている。
個と群で関心のありようが変わるのはなぜか? 個として見えていたものが群にしか見えなくなるその臨界点はどこにあるのか?「個と群」にまつわるそれらの問いはずっと意識の底に横たわっていたが、ここ数日の撮影であらためて意識化されてきた感触がある。
「個と群」
2023-12-05
「個と群」について考えてみたいと思って撮影に出かけ、戻って写真を確認したら、高解像度ならではの質感が立ち上がっていて、そちらの方がおもしろい。
意図をもって撮影に臨んでも写真がその意図を裏切る。撮った写真によって意図がどんどん横滑りする。意図したとおりに撮れるより俄然楽しい。ワクワクする。
意図に写真を従わせようとするより、撮れてしまった写真と対話するような感じで進めるほうが自分にはあっている気がする。写真が教えてくれることがあるから、ぜんぶ自力でなんとかしようと思わなくてもいい。
2023-12-05
実体験を通じ、山上付近で巻かれるガスこそが雲とわかっていながら、空を見上げたときに雲になんらかの質感を見出すのはなぜだろうということを考えている。
経験が伴わないのに、鱗雲にはモロモロとした感触を、入道雲にはある種の張りを感じるのはなぜなのか。
2023-12-06
いま見ようとしているものはもしかしたら直射の順光ではないほうが良いかも…と思ったときに、ベッヒャーのような曇天がいいだとか、晴天の順光がいいだとか、他人がもっともらしく言う「いい」を真に受けていたなと気づく。晴天の順光、陰、霞、曇天、雨上がり、湿度の高い低い…どういった環境のどういう光がフィットするか?
マウスひとつでいかようにも色を調整できてしまう時代だからこそなおさら、現場に立って現物を見て、自分の感覚を総動員して確かめたいと思う。
さあ実験だ😊
2023-12-06
枯れ木を遠くから高解像度で撮ると、ふわふわっとした質感が立ち上がる。正確には知覚のバグだと思うのだけれど、被写体が本来備えているものとは違う質感を画像に見てしまう。以前にも似たような経験をしていて、降雪を撮ったらまるでその雪が写真の表面についた霜のように見えたことがある。これも知覚のバグだと思う。そのあたりを少し深堀りしたくなって、きょうも嵐山に向かった。
雨上がり。空気にふくまれる水蒸気が逆光を拡散し、視界が霞む。いつもより目を凝らしてピントを合わせる。質感というよりむしろ不可視性を考える機会となった。過剰な光もまた可視性を損なう。

2023-11-13
なぜ写真なのか?という問いはずっとわたしの中に留まり続けていて、問答のあとで思い至ったことを記しておこうと思う。
かつて同じ問いを恩師に差し向けたことがあって、そのとき返ってきたのが「写真術に恋をしている」ということばだった。な、なんと素敵な…。それを聞いて、この人に学ぶことができて良かったと心底思ったのを覚えている。そう。気がつくと母娘で韓流アイドルの推し活をしているように、好きは感染る。つまり…感染ってしまったのだ。写真への想いが。
カメラを手にとったころはそんな感じだったと思う。それから20年あまり。写真が好きという初々しい気もちは感謝へと変わっていった。前の記事(今でもわたしは)でも触れたが、わたしにとって暗室はアジールのような場所だった。明るい太陽のもとカメラを携え世界の素晴らしさを探し歩く行為は、つらい現実から距離を置くという効果をもたらした。ある時期のわたしは、撮影や現像といった写真にまつわる行為そのものによって支えられていたと言っても過言ではない。そのことへの深い感謝がある。
それともうひとつ。
いつもお世話になっている美容師さんはわたしよりすこし年上の女性で、髪を切ってもらうあいだに交わす会話から学ぶところが多い。先日「70歳になったときにどういう働き方をしているか?」という話になり、彼女が「お客さんは年配の方も多く、これからは訪問でカットするようなことをふやしていこうと思う。髪を整えることで華やいだり、シャンと背筋が伸びるような気もちになるから」と言ったとき、ことばが自分の中の熱いものに触れるような感覚があった。
わたしが忘れかけていたもの、イメージの力だ。
イメージには力があって、間違った方向に使われることもあるけれど、ひとを喜ばせたり力づけたりすることもできる。まだ気づかれていない良さを引き出したり、これまでとは違う側面から光を当てることもできる。見落とされがちなものに価値を見出したり、既存の価値を問うこともできる。イメージの持つそういう力を信じ、誰かのため社会のためにその力を使おうと思って、わたしは視覚表現の領域に進んだ。
なぜ写真なのか?を問ううちに、写真以前、原初の動機に辿りついた。
2023-10-25
先の八瀬の赦免地踊りに続き、この週末は鞍馬の火祭りを訪れた。
この祭りも最後に訪れたのは2019年で、2度目の来訪となる。
はじめて訪れたときは、祭りの熱気と燃え盛る炎に煽られ、執拗にシャッターを切っていたように思う。
今回は、写真を撮るというより祭りそのものを楽しもうと思って訪れたこともあり、鞍馬街道のほぼ最奥で軒を借りて松明が通るのを待っていた。
鞍馬の火祭りは鞍馬寺ではなく由岐神社の神事で、氏子それぞれの軒先で篝(エジ)が焚かれている。両親と同年代と思しきご夫婦が互いに相手の薪のくべ方に注文をつけあっているのを聞くとはなしに聞いていたら、なんとなく氏子同士の立ち話に加わることになっていた。
氏子のひとりが「松の枝を市原に取りに行ったんやけれど、(時節柄、マツタケ)泥棒と疑われんかと思ってな」と話しているのを聞いてあらためて各戸の篝を見てみたら、薪を山のように積んでいるもの、一定量を保ってこまめに薪を足していっているもの、それぞれの個性が滲みでているようすが見えてきた。
篝が焚かれた街道の光景を、できるだけうつくしい画に仕上げようとシャッターを切るのと、それぞれの篝にその火の守りをする人の個性を見出しながらシャッターを切るのとでは、まなざしのあり方はまったくちがう。
先の赦免地踊でも、はじめて訪れたときは切り子燈籠のうつくしさや女性に扮した少年たちの妖しさに魅了されたが、ことしは隣席の方から「今回は息子が燈籠着(燈籠をかぶって歩く役)を、夫が警固(燈籠着のそばについて燈籠を支える役)をしている」と聞いたことで、息子の頭に載せられた5kgもの燈籠を力強く支える父親の手が見えてきた。
それまで見ていなかったもの、見えていなかったものが見えるようになった、という気がしたのだ。
日頃から「見栄えのいい写真を撮ってやろうという欲は時として足枷になる」と自分を戒めてきたが、その欲はよく見ることの妨げにすらなりうると思った。
外から来訪し、フォトジェニックな被写体を追って見栄えのする光景を切り取って帰るより、その場その場で居合わせた人と関わることによって、まなざしがそれまでよりずっと丁寧に細やかになった。個別具体的なひとの営みが、以前よりよく見えるようになった。
翻ると、それまでわたしは、ひとを記号のようにとらえていたのだと思う。
わたしだけではない。その夜、祭りの場でシャッターを切っていたほとんどの来訪者が祭りの担い手を、それぞれの画面を構成する要素/匿名の存在/記号のように扱っていたのではないだろうか?さらに言えば、見知らぬ他者を画面に取り込む写真実践のすべてに同様の問いは潜んでおり、それを不問に付したまま写真は消費されてきたのではないだろうか?
個別具体的な生をもつ他者を、画面を構成するものとしてとらえること、あるいは記号のようにとらえることへの違和。近年芽生えたその違和を、なかったことにせず考え続けたいと思う。
2023-10-10
今年はあいにく体育館での開催となったのだけれど、赦免地踊を観に行った。
はじめて訪れたのは4年前。
市街地から北に向かうにつれ、少しずつ空気がひんやりと、夜がその存在感をましていくように感じられた。そして、山あいの夜の暗さと静けさに圧倒され、蝋燭の灯に揺らぐ切り子燈籠のうつくしさ、女性に扮する少年たちの妖しさに魅了された。
それこそ京都は祭りの宝庫で、雅なものから勇壮なものまで多種多様な祭りがあるのに、なぜこの小さな集落の祭りにひときわ心魅かれるのだろう?と、帰宅後もしばらく考え続けていた。
この数年、訪れた土地の夜の暗さにほっとすることがある。
ここは夜が夜らしい暗さだ、と。
半月ほど前、ある人から「なぜ写真なのですか?」と尋ねられた。
わたし絵が描けないんです/学生時代、自分で問いを立てることが求められたのは写真の課題だけだった。もしその課題が写真ではなく彫刻だったら、わたしは彫刻をしていたかもしれない/暗室だけが安心して泣ける場所だった/なにか素敵なもの、それまで見たことのないようなあたらしいものの見えかた、そういったものに意識を向けながら世界をまなざすこと、太陽の下を歩くという路上スナップの行為そのものが、当時の自分のこころを支えていたように思う
そんなふうに答えたと記憶している。
「もしかして暗室は…」
言いかけた相手のことばを引き取るように、わたしは答えた。
「子宮なのかもしれません。唯一、安心できる場所でした」
山あいの夜の圧倒的な暗さと静けさ。それに抗うのではなく、折り合いをつけるかのようにひっそり執り行われる集落の祭り。自分の輪郭がほどけるような暗さと静けさのなか、揺らめく灯に誘われ、ふだんは届くことのないこころの深い場所に触れられる気がした。
ああそうか。
今でもわたしは暗く静かな場所を求めているのかもしれない。
2023-06-16
モノクロームは輝度のパターンで、カラーだって無数の色が数色に置き換えられたもの。どちらも近似でしかない。
2023-06-05
いつだったか、WEBでRIVERSIDEの作品を観てくださった方に「写真なんですか?絵だと思っていました。」と言われたことがあって、そのときは「写真です。」と答えたものの、編集していると絵のように見えることがある。その事象についてはなんとなくやりすごしてきたが、もしかしたら考える糸口になるかもしれないということばに出会った。
無時間性
そのことばがひっかかったのは、RIVERSIDEの編集中、信号機の赤、少年が跳び上がる瞬間や時計といった、時間を意識させるものを画面の中に見つけたときに、ハッとすることがあったから。そういうものに反応するということは、わたしは自分が撮った写真を無時間的なものと見なしているのではないか?と。
また、はじめて展覧会を開いたときに、会場を提供してくださった企業の方から「三条大橋とか、場所の名前入れたほうが良かったんじゃないですか?」と言われたことがあり、写真が地図のように見えたんだと思ったが、地図ととらえるなら、まさに無時間的だ。
ソフトフォーカスは、写真という媒体が得意とするはずの細部描写を敢えて放棄することで、白黒写真を木炭デッサンと見紛うものに変えることもできる。だが、福原の作品の場合、ソフトフォーカスは写真を絵のように見せるためというよりは、無時間性の印象を補強するために用いられている。第一に、ソフトフォーカスの写真は、写真画像と、我々が肉眼で見ている世界の光景のあいだの差異を拡大することで、前者がまるで別世界の出来事であるかのように見せる。この別世界において、我々が暮らす世界と同じようなペースで時間が流れているのかどうか、我々には知る由もない。第二に、ソフトフォーカスの写真では多くの場合、それがごく短い時間で撮影されたことを示す証拠が画面から取り去られている。マーティンの《海老の籠を運ぶポーター》を例に見たように、人物の表情、洋服の裾といった要素は、ある写真が瞬間的に—おそらく数分の一秒以下の短い時間で—撮影されたことを示唆する。そういった要素はしばしば微細なものであり、ソフトフォーカスによって細部が抑圧されると同時に、写真から消え落ちてしまう。
(『ありのままのイメージ: スナップ美学と日本写真史』 甲斐義明著 東京大学出版会 2021 pp.27-28より抜粋)
無時間性ということばは、ソフトフォーカスの技法についての説明とあわせて出てくるが、ここで注目したいのは、瞬間的に捉えたことを示唆する微細な要素が抜け落ちると無時間性の印象が補強されるということ。
わたしは細部をとらえることにこだわりがあるからソフトフォーカスは用いないが、40mほど離れた被写体を撮るので、必然的に人物の表情や洋服の裾といった微細な情報は脱落する。(その意味では、近距離より遠距離の被写体のほうが無時間性を帯びやすいと言える)
さらに、自転車のような動く被写体は、なるべく像が流れないよう速めのシャッタースピードで撮る。すると「動き」を感じさせる要素も抜け落ちる。上述のソフトフォーカスの話とは逆に、細部をとらえようとすることが、無時間性の印象を補強することにつながっている。
いっぽう、隣接する写真が異なる瞬間に撮られたものであること(時間性)をはっきりさせておきたいという気もちもある。
プリントの工房で「雪は難しいでしょう。つなげるときに濃度が揃わないから。」と言われ、いやむしろ吹雪に緩急があって写真の濃度が揃わないほうがおもしろいと思ったときに、自分が求めているのが滑らかにつながるひとまとまり(全体)ではなく、ひとつひとつの写真が独立しつつゆるくまとまりを仮構する構造であると自覚した。そして、それぞれの写真の独立性は時間性に拠っている。
無時間性を帯びやすい方法で撮りながら、写真どうしの関係においては時間性を拠りどころとしている。そのことが明らかになったのは前進だと思う。絵のように見えることと無時間性のつながりについては、またあらためて。
2023-05-19
先日「ある種の貪欲さ」と書いてから、自分で書いたそのことばが気になり考え続けていた。
ひとと話をしたり、展覧会をいくつか観たなかで取り戻しつつあるのは、得体の知れない写真を撮りたいという気もち。
たしかにそういう写真はこの世にあって、感情移入できるわけでも、ことばで了解できるわけでもなく、むしろ良いとは思えないのになぜか引っかかる。そういう写真を撮りたいと思っていた。
これまでに身につけた知識、同時代的な文脈、自分自身の制作の一貫性…そういったものすべてをかなぐり捨ててでも、もう一度、自分の感覚だけを頼りに世界をまさぐるようなところに戻ってみたくなった。
2023-05-12
自分を駆動してきたのはこういう期待だったと思う。それをいつの間にか忘れてしまっていたのね。自分が自分に期待をしなくなっていた。
今、それを取り戻しつつある。ある種の貪欲さとともに。
2023-01-22
昨年の秋の終わりに、念願だった森田真生さん(独立研究者)の講演を聞く機会を得た。てっきり数学をベースにした話になるとばかり思っていたら、PlayとGameの対比を軸に人類の起源から気候変動に絡む地政学まで、時代と分野を縦横無尽に行き交うとても刺激的な90分だった(頭をぐわんぐわん掻き回されたというのが正しい)。
その講演のあともずっと響いているのが、
「僕には庭師の友人がいて、彼はものを選ぶときにそのものが土に還るかどうかで、いいか悪いかを判断する。」という語りで始まり、
「その視点から見ると、遺跡は土に還らなかったものとも言える。土に還ることを善きこととし土に還った多数の人々ではなく、土に還らないものを残してしまったごく一部の特殊な人々のことばだけを紡いで歴史を記述するのはどうなのだろう?」という問いだった。
この問いはふたつの意味で心に残っている。
わたしは長く歴史に興味が持てずにいたが、網野善彦さんの著書に触れてはじめて、自分は支配者を軸とする歴史に興味が持てないだけで、民衆がどう生きたかという視点で描かれる歴史には強い関心があるとことに気がついた。その経験に通じるものを感じたというのがひとつ。
もうひとつは、作り手として自分の姿勢も問われているように感じたこと。〝土に還る〟というものさしと、どう向き合っていくか。
冬に向けて整理した朝顔の蔓、ユーカリ、南天の小枝などを使って手遊びのリースを仕立てながら、ベランダの植物だけでつくるリースはこの場所でともに過ごした時間の蓄積、ごくごくプライベートな歴史であり、そして気が済んだら土に還すこともできる。土に還るってなんだか安心感があるの、ふしぎだなぁ。ちょうどそんなことを考えていたところだった。
写真に携わっていると当然、劣化させずにどれだけ長期保存できるか?を考えてしまうし、作家としてはついどうやって後世に残すか?を考えてしまう。でも、経時変化を受け入れ、さいごは跡形なく土に還るという作品のあり方を選んでもいいはずなんだよなぁ…
2022-01-14
週末、ホー・ツーニェンの百鬼夜行展を観に、豊田市美術館を訪れた。
彼の作品をはじめて観たのは、2017年に森美術館と国立新美術館で開催された「サンシャワー:東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで」だ。マレーの虎にまつわる映像が強く印象に残っている。
恥ずかしいことに、わたしはこのサンシャワー展をとおして、はじめてアジア地域における日本の侵略戦争、つまり加害の歴史を具体的に知った。
思い返せば、小中学校の課題図書で選ばれるのは、戦争でどのような被害を受けたかという話ばかりだった。歴史の授業でも、近現代史は学年末に足速に通り過ぎるようなものだった。高校では理数系を選ぶと自動的に地理に振り分けられるシステムになっていて、日本史とも世界史とも縁がなくなった。自国の侵略戦争についてほとんど何も知ることなく、あるいは知らされることなく、そして知ろうとすることなく、わたしは大人になってしまった。
くわえて、21世紀を生きるアジアの作家らが前世紀の侵略戦争を主題に選ぶまさにその事実によって、被侵略地域においては戦後何十年経っても「終わっていない」ことを思い知らされた。
加害者側はその先の人生で加害の事実を忘れたりなかったことにできるけれど、被害を負った側はその被害を忘れることもなかったことにすることもできない。加害と被害の立場には必ず、そういった非対称性が生まれる。
わたしが侵略戦争について知らずに生きてこられたこと、制作において侵略戦争を主題化せずに済んできたこと、その状況そのものが加害の立場の特権性なのだ。アジアの作家らが日本の侵略戦争を主題化する傍らで、日本人作家として何も知らずに「見るとはどういうことか」といった抽象的なテーマに取り組んでいられたこと、そこに立場の非対称性が現れている。
サンシャワー展においては、
欧米との関係でしか自らの立ち位置を考えてこなかったのではないか?
前世紀の戦争を被害の立場からしか見てこなかったのではないか?
そういった反省も促された。
近年の展覧会のなかで、もっとも深く考えさせられる展覧会だった。
だから、百鬼夜行展は絶対に見逃せない展示だった。
開催中の展覧会について多くを書くのは控えるが、百鬼夜行展ではとりわけ、ふたつめの『36の妖怪』が印象深かった。一瞬にして観者を傍観者の位置から引きずり下ろすその鮮やかな手際に、思わず息をのんだ。
もしまだ観ていなかったら、是非観に行ってほしい。
2022-01-07
タイトルのセンテンスは、昨年末に読んでいた今井むつみさんの『英語独習法』で見つけたもの。思いがけないところで、思いがけないことばに出会うのね。
人は外界にあるモノや出来事を全部(seeの意味で)「見ている」わけではない。無意識に情報を選んで、選んだ情報だけを見るのが普通である。注意を向けて、見るべきもの、次に起こるであろうことを予期しながら外界を(lookの意味で)「見ている」。当たり前のことが起こると、その情報は受け流してしまい、見たことを忘れる。予期しないことが起こり、それに気づけばびっくりする。そのときは記憶に残りやすい。しかし、注意を向けているつもりでも、予期しないものは気づかずに見逃しまうことも多い。
(『英語独習法』今井むつみ著 岩波新書 2020 p7より抜粋)
RIVERSIDEプロジェクトの根幹は、まさにこれだと思って。ふだん何気なく(lookの意味で)見ているものを写真に置き換えることで、seeの意味での見るに変換すること。
いつも見ていたはずだけれど、そうは見ていなかったんじゃない?と。
そして、日本語を使って考えているうちはなかなか言語化しにくかったのが、英語を借用することでこうもあっさり表現できるんだなぁ、と。
ここからはまったくの余談…
ちょうどこの本を読んでいたのと同時期に放映されていた恋愛ドラマに「好きです。likeではなくて、loveです!」という台詞があって、わざわざ英語を借用しないと自分の気もちすら伝えられないって日本語ってちょっと不便じゃない?と。自分の生活でも、漢方医の問診で「喉がかわきますか?」と訊かれたときに、乾く(dry)?渇く(thirsty)?どちらだろう?といつも戸惑う。局所的に喉を湿らせたいのか、身体が水分を欲しているのかは違うニーズだと思うので…。
何かを厳密に定義したり伝達するには、日本語は曖昧ですこし不便な道具なのかもしれない。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
いただいた賀状のなかに、
コロナ後のソメちゃんの作品がどうなっていくのか、また見せて欲しいです。
という添え書きがあって、年始からハッパがかかったというか、とてもうれしかったです。ありがとう。
正直に書くと、
昨年オンラインの展覧会で手もちの作品をすべて出し切ったあと、気が済んだような状態(もうここでやめてもいいのかも…)になっていました。
正確には、その少し前から、自分の制作がある種の箱庭療法のようなものだとすれば、人様に見せる必要があるのか?という迷いがありました。
というのも、川べりでの撮影で、移動しながら撮影する一連の動作の繰り返しのうちに、トリップのような感じで自分の内面の深いところ(抑圧された感情)に触れるようなことがたびたび起こるようになり、
ちょっとおっかないなぁという思いと、もしかしたら自分を制作に向かわせているのは深いところにある傷なのではないか?という疑い。仮にそうだとすれば、それを視覚表現の文脈に沿わせることへの違和。そして、内面の課題が解決すれば、制作へのモチベーションが失われるのではないかという恐れ。そういったもろもろの思いにがんじがらめになっていました。(これがいわゆる中年の危機やろか…)
そういった感じで迷いに迷っていたのですが、それでもなお欲が残っていることに気がついたのです。
そして、昨年から新しいプロジェクトに仕掛かっています。正確には、手遊びのように試したことに作品化できそうな手応えを感じはじめています。今回は〝何も写らんかも…と思いながら三脚にカメラを据えてみたら予想しなかったものが見えた〟経験からスタートします。
RIVERSIDEプロジェクトが「見てはいるけれど、そのようには見ていなかった」だとすれば、新しいプロジェクトは「見てはいるけれど、見えていなかった」事象をとりあげたいと思います。
RIVERSIDEプロジェクトの作品が、くっきりはっきりだとすれば、新しいプロジェクトの作品はモヤモヤ〜っとしています。
2021-11-18
そもそも、話すのがうまくない。
いつも言いたいことを言えない、言い足りないもどかしさがあって、書くことでやっと出し切る。
そのための道具としてブログを書きはじめ、しだいに生活の中での気づきや、読んだ本の印象深いフレーズをメモ書きのように残すことが増えてゆき…
それでも、書きはじめた頃から、ひとりの人間が作品をつくりながら何を考えどう生きたか、制作のさなかに考えたことをその都度綴っておけば、登山で言うところの踏み跡のようなものとして、あとからこの道を進む誰かの役に立つかもしれないとは思っていた。(そして実際に「読んでます」という若い作家の方が現れてびっくりした)
近年アクセスが安定しつつあるのに加え、自分自身を振り返るのにも役立つようになり、アーカイブとしての側面を少しずつ意識するようになっていった。
さらに今は、写真作品だけでなくこれらドキュメントも含めた営為を制作物としてとらえ直し、作品とドキュメントのつながりをもっと明確にしたいという欲も出てきた。
多くの作家にとってWEBは広報媒体のひとつかもしれないけれど、わたしはここを拠点とする。そう決めたので、これから少し時間をかけて手を入れていこうと思う。
もうひとつ。
20年近くひとつのプロジェクトに携わり、時間とともに作品に対する意味づけが自分の中で変遷するという経験をした。さらに20年続けたら、20年後のわたしは今とはまったく違う意味づけをするかもしれない。くわえて、人間は思っているよりずっとあやふやで一貫性に欠けているのではないか?という疑いもある。少なくとも自分のことは誰より自分がいちばんよく見えて〝いない〟。
つまり…定型フォーマットに則った「このコンセプトでこの作品をつくった」という作者の語りからこぼれ落ちるものが、わたしの意図を超えてここに残るかもしれないと期待している。
2021-04-08
コロナ禍の影響で、商業地では空きテナントが増え、そのガラスにシートや板があてがわれている光景が目立つようになった。いっぽう住宅地では、地方移住の需要を見込んだ旺盛な投資により集合住宅の建設ラッシュ。真新しいガラスがシートで覆われている光景をよく見かけるようになった。
ガラスに映る像を見ようとすると、木目やシートの皺といった支持体が介入する。
木目やシートそのものを見ようとすると、映り込む像に阻まれる。
拮抗やトレードオフといったことばが脳裏をよぎるが、トレードオフは今の社会状況をもっとも象徴することばだ、とも思う。
2021-04-02
三脚を立て水平垂直をあわせ、最後にファイダーを覗きながらピントリングを繊細にまわすとき、世界にやさしく触れているような感覚になる。そして、そのことで自分自身が癒やされたり救われたりしている部分が少なからずあるのかもしれない、とふと思った。なにかにそっと触れるとき、やさしさは触れる対象だけでなく自分にも向けられる。
ここで話題にしたいのは、前段のほう。
ほんのわずかでも回しすぎるとピントが甘くなるので、必然的にピントリングには繊細に触れざるをえないが、その手つきによって、事後的にやさしさが喚起されるのではないか?と。
ほぼ日刊イトイ新聞の糸井重里さんと池谷裕二さんの対談に、興味深い話がある。(https://www.1101.com/ikegaya2010/2010-10-06.html)
イーと発音するときの口をしてマンガを読んだときのほうが、ウーと発音する口で読んだときよりマンガがより面白く感じられるという実験結果について。脳は外界から隔離された存在で、脳それ自体では外界のことはわからず、唯一身体を通じて理解をする。ここで言えば、脳に届くふたつの情報「笑顔をつくっているようだ(イーを発音する口)」と「マンガを読んでいる」から脳は「マンガがおもしろい」という合理的な解釈を導き出すのだそう。身体の状態が先にあって、脳はあとからそれに解釈をくわえる。
だとすれば、繊細な手つきによってやさしい気もちが喚起されることも、あり得ない話ではない。
もうひとつ。
日日是好日という映画で、「お茶はまず『形』から。先に『形』を作っておいて、その入れ物に後から『心』が入るものなのよ。」という台詞があった。ふるまいが先にあって、心は後からついてくる。そのことを、先人たちはよく知っていたのかもしれない。
2021-03-19
おかげさまで、オンライン展覧会 “On Your Side”は、多くの方のご訪問をいただき、感謝しております。
会期も残りわずかとなりましたので、まだの方は、下記URLにてご覧いただけると、たいへんうれしく思います。(終了しました)
https://somedalisa.net/exh2020/
さて、本展の作品表示のためにつくった画像スクロールプログラムのサンプルパッケージを用意しました。ダウンロードが可能です。
きわめてニッチな用途とは思いますが、必要な方はご利用ください。
MITライセンスにて配布しております。
2020-07-15
『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』に、もうひとつ気になった箇所がある。
望遠鏡と顕微鏡の発明によって、今まで肉眼で見ることのできなかったものが見られるようになり、人々は「見えない世界がある」ことを知った。もちろん、それが周知され受け容れられるまでにはさまざまな葛藤があったが、もうひとつ、この時代に生まれた新しい考え方があった。そのことについて記しておきたい。
当時の自然哲学者たちが、それまで見たこともないまったく新しいものを見たとき、ある困難に直面した。具体的な事例が紹介されている箇所をいくつか抜き出してみよう。
月の表面に見える斑点はクレーターと山の影だとガリレオが見抜くことができたのは、遠近法を学んでいたからだけではない。コペルニクスの地動説を支持していたからでもあったのだ。古代から続くアリストテレス的な宇宙観では、地球は天界の中心にあり、地球を周回するすべての天体は発光性の〈アイテール(エーテル)〉で構成されているとしていた。この宇宙観を頭から信じているものの眼には月の表面は真っ平で輝いているように見え、クレーターや山があるようには見ることができなかった。見えているのに見えてないと考えるようにしているわけではない。先入観が視覚に影響を及ぼし、本当にそう見えていなかったのだ。彼らは輝く月の表面にある斑点が雲に見え、もしくは質の悪いレンズのせいでまだらに見えると考えてしまう。しかしそんな古い考え方に囚われずに、地球も月も太陽を周回する天体だとするコペルニクスの説を受け入れると、月にも地球のように山があったりクレーターがあったりしてもおかしくないと思えるようになるのだ。
『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』(ローラ・J・スナイダー著 黒木章人訳 原書房 2019 p171より抜粋)
血液のなかに赤血球を発見したとき、実際には真ん中が窪んだのっぺりしたかたちなのにもかかわらず、彼の眼には球形に見えた。そう見えたのはファン・レーウェンフックだけではなかった。この時代に赤血球を観察したものは、誰もがみな球形だと述べた。ヤン・スワンメルダムもミュッセンブルーク兄弟も王立協会のフェローたちも、全員が赤血球は球状だと言った。みんながみんな、そんなかたちのはずだと思っていたからだ。(同書 pp416-417より抜粋)
一六七八年に哲学者のジョン・ロックと共にイヌの精子の観察をしていたときのことだ。ロックには、精子の尻尾がなかなか見えなかった。「私には、どうしてもきわめて小さなビーズ球にしか見えなかった」ロックはそう告白している。ファン・レーウェンフックは、自分もあらゆる物質の構成要素がどうしても球状に見えていたことを思い出した。ロバート・ボイルたちが唱えていた、すべての物質は粒子によってできているという〈粒子仮説〉に囚われていたからだ。ファン・レーウェンフックは、何もかもが丸く見えてしまう自分の心と闘い、ようやく精子の尻尾が見えるようになった。(同書 p417より抜粋)
まったく新しいものを見るというのは、そうたやすいことではなかったのだ。
一七世紀の自然哲学者たちは自然界をありのままに見ようとした。これまで信じてきた、自分の支持する説やそれ以外の説には頼ろうとはしなかった。しかし新たな光学機器による観察がどれほど難しくても、観察して見えたものが強固な信念や説に反するものだとしても、見えたそのままに見るためには心の鍛錬が必要だった。それが大きな問題だということを理解していたガリレオは「実際の眼だけでなく心の眼もつかって見なければならない」と述べている。先入観や思い込み、そして願望すらも、実際に眼に見えているものではなく、何か別のものを見せてしまうことを理解しなければならないのだ。(同書 p172より抜粋)
つまり、この時代の自然哲学者たちは「ものの見方は固定観念に影響される」ということを理解しなければならなかった。そして、これこそがまさにこの時代に生まれた考え方だという。新しい世界が(外に)ひらけたことにより、見る側のもののとらえ方(内側)の瑕疵が浮かび上がったというのは興味深い。
それはさておき、この箇所を読んだとき、既視感(既読感?)のようなものを覚えた。似たようなフレーズをどこかで…。そう、モダニズム写真の倫理だ。
エヴァンスに象徴されるモダニズム写真の倫理とは、人間的な意味や表象のフィルターを通さず、カメラ・アイによって対象物自体をじかにありのままに、クリアに撮ること、つまり透明性、純粋性、裸の倫理である。それは、人間の色眼鏡を超えた、汚れなき曇りなきカメラ・アイによってのみ到達可能な「ありのままの世界」、社会の価値や表象の体系の彼方に存在する「ありのまま」のリアリティに対する倫理なのだ。
『プルラモン―単数にして複数の存在
』(清水穰著 現代思潮新社 2011 p48より抜粋)
「ありのまま」にたどりつけない原因(眼を曇らせるもの)を、片方は先入観や固定観念、願望に、片方は意味や表象のフィルターに求め、それを克服する方法を、片方は心の鍛錬に、片方はカメラ・アイに求めている。まるで相似形のようではないか。
正直なところ、モダニズム写真の倫理を実感として理解するのは難しかった。なんで人間が見ることをそこまで否定するのか? どうしてそんなにカメラ・アイに期待するのか? わたしにはさっぱりわからなかった。けれど、17世紀のパラダイムシフトによってもたらされた考え方や、当時の経験がその下地にあるとすれば、少し理解の方途が見えた気がする。
しつこく抜粋したように、17世紀の自然哲学者たちは具体的な困難を経験していた。赤血球が球状にしか見えなかったり、精子の尻尾がなかなか見えなかったり…それらの困難を克服しようと「ありのまま」に見るための心のありようを模索した。その経緯はよく理解できる。では、モダニズム写真の倫理が生まれる背景にはどのような困難があったのか。何を克服しようとしたのか。
2020-07-10
ついこのあいだ、不可視性について考えたことをまとめたあと、とてもおもしろい本に出会った。
『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』
フェルメールとレーウェンフックの二人の生涯を軸に、望遠鏡と顕微鏡の発明によってもたらされたパラダイムシフト、当時の人々の世界認識がドラスティックに変わるさまが丹念に描かれている。
これまで遠すぎて見えなかったもの、小さすぎて見えなかったものが望遠鏡と顕微鏡の発明によって見えるようになったときにはじめて、人々は「自分たちの肉眼では見えない世界がある」ことを知り、受け容れなければならなかった。
わたしたちは何の疑問も抱かず、新型コロナウイルスは(肉眼では見えないけれど)存在すると思っているけれど、それは決してあたりまえの認識ではなく、この17世紀のパラダイムシフトを通じて獲得したものである。
望遠鏡が見せてくれるはるか彼方の天界、顕微鏡が見せてくれる微小な生物、それ自体とても大きな発見ではあるが、何より大きい発見は「肉眼では見えない不可視の世界がある」とわかったことだという。
顕微鏡と望遠鏡が幅広く受け入れられるために必要だったのは、その作用原理を説明する光学理論だけではなかった。むしろ、世界は見かけどおりではなく、我々の眼には見えない隠された部分があるということを積極的に受け容れる姿勢のほうが重要だった。肉眼で観測するさまざまな現象の背後には不可視の世界があり、人間の眼に見えない部分にこそ目に目に見える自然現象の原因があることを理解しなければならなかった。この時代は〝世界は見かけ通りのものではない〟という認識が急速な勢いで広まった時期と見ることができる。
『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』(ローラ・J・スナイダー著 黒木章人訳 原書房 2019 p24より抜粋)
この「不可視の世界がある」という17世紀の発見がなければ、見えないものがあるという構造を前提とする無意識は発見されなかったかもしれない。21世紀のいま、わたしたちは実際に道具で観察できるケースだけでなく、無意識のように道具で観察できないケースであっても、「不可視の世界がある」ことを受け容れている。そこがとても興味深い。
2020-06-29
昨年5月に記したメモより。
先日実家で窓の外を眺めたとき、はるか遠くに見える山が紀州山地だということにはじめて気がついた。
神戸の海と山に挟まれたほんなわずかな平地で、しぜん太陽の射す海側に気もちが向くのと、うしろの山(六甲山系)はまなざすには近すぎるのとで、日常生活では、六甲山系よりもむしろ、遠く紀州の山影のほうが視界に入りやすい。
ほぼその上で生活しているにもかかわらず、視界に入らない六甲山系に感じる馴染み深さはどこか抽象的。いっぽう、訪れたことすらない紀州の山々に感じる馴染み深さは日々の生活で見慣れている分、現実的。
近すぎて見慣れない山と、はるか遠くの見慣れた山。
物理的距離と心理的距離は必ずしも一致しないのかもしれない。ひとが土地ととりむすぶ関係は、案外複雑だ。さらに言えば、六甲山系をあたりまえのように「うしろ」と認識しているのもふしぎなことだ。海沿いの埋立地のあたりから六甲山系を眺めるときは、ただ山を眺めているだけなのに、「うしろをふりかえる」気もちになっている。
京都にあっては、必ずしも北が「うしろ」ではないし、特定の方角の山を「ふりかえる」と感じたことは一度もない。
2020-06-03
平時モードに戻る前に、もうひとつ書き残しておこうと思う。
「隔たり」ということばは、ふつう二者の空間的・時間的な距離を指す。それだけでなく、たとえ二者の距離が限りなく近くても、ガラスや壁のような遮蔽物が間にあるような場面でも「隔たり」ということばを使う。これらはまったく異なる状況のはずなのに同じことばを使う。そのことに興味を持った。
この二つの状況に共通点を見出すとすれば、距離や遮蔽物によって二者の接触が阻まれているということではないか?「隔たり」ということばのベースには「触れることができない」(接触不可能性)というチクッと心が痛む経験が横たわっているのではないだろうか?
かつて、そんなことを考えたことがある。(隔たり 2014.04.26)
奇しくも、新型コロナウイルスの感染防止対策として、日常生活ではソーシャルディスタンスを保つよう促され、公共施設や商店の窓口には薄い透明のシートが貼られるようになった。ぼんやり考えていたことが、突然、可視化されてしまった。
2020-02-06
今朝ようやく、はつゆきらしきものが舞うのを見た。
来週末、バレンタインの京都は最高気温21度の予想。
冬がおかしい。
近年、札幌を契機にサンクトペテルブルク、オタワと、都市の雪景を撮り続けているが、
そこには、雪をとおして風景を見る、不可視性云々、といった関心とは別に、
もしかしたら、これからだんだん雪が降らなくなるかもしれない。
雪で覆われた都市は、失われた風景になるかもしれない。
という切迫感がある。
もちろん、そんな状況は全力で回避すべきだと思っているが、すでに近年の京都で雪景を撮るチャンスはほとんどない。
思ったよりもずっと早く、失われつつあるのかもしれない。
2020-01-12
写真の下部ではブツブツのついたシートを見ているはずが、上部に向かうにつれなだらかに、意識はガラスに反射する風景のほうに向き、シートそのものからは後退する。映像の支持体になると、ものの質感や存在感を感じられにくくなるのだろうか?
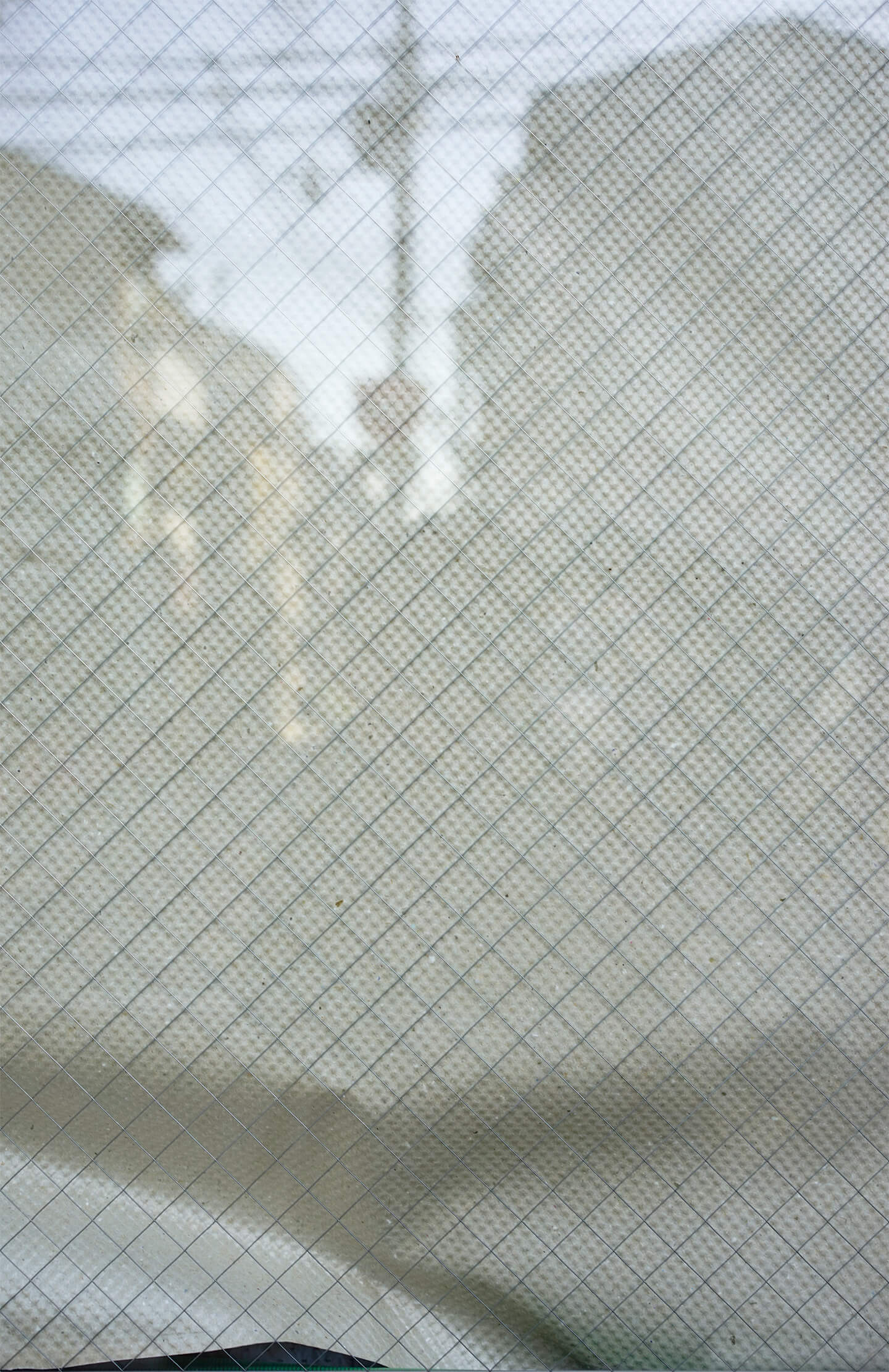
夜、車窓から外を見ようと思っても、光の反射が邪魔をしてなかなか外を見ることができない。幼いころに経験したそういうもどかしさに少し似ているかもしれない。
見ようとしてもなかなか見えない。
2019-12-23
部屋の少しふかいところに陽が射し込むと、
わたしの肩でチリチリと、ジャカランダの影が踊る。
そう。踊るの。
揺れるのでもなく、揺らぐのでもなく。
2019-12-12
透けて見える、あるいは何かを通してものを見ることに関心があり、岡田温司さんの『半透明の美学』(岩波書店 2010)を繙いた。
まず、自分がスナップでよく撮る、窓、影、覆い(ヴェール)といったものが、実に古典的なモチーフであることをあらためて認識し、さらにいくつかの興味深い記述にも巡りあう。そのひとつが、絵画の起源について。
これら三つの神話が紹介されたあと、以下のように続く。
影と痕跡と鏡像、これら絵画の起源とされるものを、それぞれ別のことば、とくに作用を意味する用語で言い換えるとすれば、順に、投影(プロジェクション)、接触(タッチ)、反省ー反射(リフレクション)ということになるだろう。
さて、これらの神話で興味深いのは、いずれも、絵画的イメージが、対象を直に模写したり模倣したりした結果によるものではなくて、媒介物をあいだにはさむことによって生まれたとされていることである。投影にせよ接触にせよ反省ー反射にせよ、それらの作用によってあらかじめ二重化されたものが、対象と絵のあいだの媒介項として想定されているのである。パースの記号論を援用するなら、絵画はもともと、類似にもとづくイコン記号としてでも、約束にもとづくシンボル記号としてでもなく、因果関係にもとづくインデックス記号として誕生した、ということになるだろう。周知のように、プラトンは、この世の事物をイデア界のコピーにすぎないととらえ、そのまたコピーが絵画にほかならない、したがって絵画はイデアからかけ離れることはなはだしいと難じていたのだが、それどころか、これらの神話をプラトン流に読み替えると、コピーのコピーのそのまたコピーということになるだろう。
(『半透明の美学』岩波書店 岡田温司著 2010 p18より抜粋)
今さらながら、対象を直接描いたんじゃなかったんだ!ということに驚く。
とりわけ、ひとつめの影については、なんでわざわざ影?直接描いたものではだめなの?と思ったけれど、よくよく考えてみると、戦地に赴く恋人を見送る立場であれば、「恋人由来の何か」「より直接的に恋人の存在を感じられるもの」を所有することが重要なのだろう。絵画は恋人がその場にいなくても想像で描くことができるが、影は恋人がその場にいなければなぞることができない。存在から得られるもの(存在がなければ得られないもの)。だから影でなければならなかったのだ。
写真の文脈で何度も出てくる、インデックスという言葉。その意味をわかったつもりでいたけれど、ここにきてようやく腑に落ちた。
ちょうど今の時期、太陽が低く影が長く伸びる季節は、ときに一瞥しただけでは何の影かがわからなかったり、ものより影のほうが存在感を示すことがある。そういったものと影の乖離や反転、両者が識別不能なまでに混じりあう様にわたしはどうしようもなく惹かれているが、イメージの起源にまで遡れば、大切な存在をより直接的に感じるための影うつしであった、と。
2019-11-29
15年分のスナップ総ざらえも、あと少し。
ステキと思って撮ったのでは「ない」もの。なんかようわからんけど気になるわと思って撮ったものばかりを集めてみると、自分の関心がどこにあるのかが少しクリアになってきた。
視覚のくせ(エラー)が垣間見えるような場面、画面要素の拮抗状態、前後関係の撹乱をはじめとする識別不可能性。見えなさ。
フェンス(ネット)より手前に突き出ている枝に対しては、立体感や奥行きを感じたりディテールを見ることができるのに、フェンスより奥のものに対しては、奥行きや立体感を感じたりディテールを見ることができない。

むしろフェンスがつくる平面に像がペッタリ吸着されているような気さえする。脳内では面の認識が優先されているのだろうか?
こういった見えているのに見えていないこと。見えなさ。
2019-12-18
ちょうど読んでいた本の中に、ルネサンス期の画家が三次元の世界を二次元平面にマッピングするために、格子状の透明な膜を用いていた、という記述を見つけた。
ところで、アルベルティはまた、絵画を「ヴェール」になぞらえてもいる。いみじくもアルブレヒト・デューラー(一四七一−一五二八)が木版画(図1-1)に残しているように、このヴェールは、窓のフレームに張られた格子(グリッド)状の透明な膜のようなもので、三次元の世界を二次元平面にマッピングするための、透視図法の実践的な装置という役割を担っている。
(『半透明の美学』岩波書店 岡田温司著 2010 p6より抜粋)
図1-1 デューラー《横たわる裸婦を描く男》に相当する図版は、フランス語版のWikipediaから拝借。

Par Albrecht Dürer — Jean-Jacques MILAN 00:00, 23 September 2005 (UTC), Domaine public, Lien
そういえば、デッサンスケール、使ったことあるわ…
2020-07-10
アルベルティのヴェールについて、先日読み終えた『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』に、さらに詳しい記述があったので抜粋しておく。
遠近法の法則を体系化したアルベルティは、三次元の題材をカンヴァスといった二次元の平面上に描く際に役に立つ、単純な器具を考案した。〈アルベルティの薄布(ヴェール)〉とも呼ばれるその器具は、細番手の糸を荒く織った、透けて見えるほど薄い布地を太番手の糸で縫い目をつくって正方格子状に区切り、それを木枠に張ったものだ。画家はこの格子模様のきわめて薄い生地越し題材を見て、その生地と同じように格子状に区切った紙やカンヴァスにそのまま写し取っていく。遠近法を論じた『絵画論』のなかで、アルベルティはこう述べている。「われわれの仲間の間で、〈截断面〉とよび習わしているあのヴェール以上に有用なものは見出し得ないと私は考えている……このヴェールを眼と対象物の間におくと、視的(視覚の)ピラミッドが薄いヴェールを透っていく」(三輪福松訳、一九七一年、中央公論美術出版)
アルブレヒト・デューラーは一五二五年に著した『測定法教則』で〈アルベルティのヴェール〉の別バージョンについて述べている。デューラーが記しているのは薄い布ではなくガラスに正方格子の罫線を入れたもので、それをテーブル上に垂直に立て、画家はガラス越しに題材を見て写し取っていくというものだ。(後略)
『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』(ローラ・J・スナイダー著 黒木章人訳 原書房 2019 pp.122-123より抜粋)
薄い布地だったというのは興味深い。まさしくスクリーンそのもの。ガラスのように透明なものではなく、半透明の布地を透過する像を写していた。ガラスより薄布のほうが、空間を「平面の像に変換」してから描くというニュアンスは、いっそう強くなる。
2019-11-18
人間の視覚では捉えられない無意識の世界をレンズが〜という話ではなく、ひとは見ているつもりになっているが、そもそも目の前にあるものすらあまり見ていない、とあらためて。
2019-07-04
先日、@CKUAで観たジェン・ボー(鄭波)の展覧会で、参考書籍として紹介されていた本の中に、好きな装丁のものがあり、後日、あらためて探し求めた。
ネイティブアメリカンの植物学者が描くうつくしい世界観に触れ、しばらくこちらの世界に戻ってきたくなくなってしまった。それも、ただうつくしいのではなく、現代社会に対する鋭い洞察がいたるところにちりばめられている。心に刺さったところをいくつか書き留めておこうと思う。まずは、経済について。
ネイティブアメリカンの社会では、感謝、とりわけ地球や大地に対する感謝が重視されるが、資本主義社会でドライブのかかった欲望に歯止めをかける力を、著者はこの感謝という行為に見出している。
以下の記述は、著者が夢で見た光景ではあるが、心理描写が興味深い。
つい先日、その市が、鮮やかな質感とともに私の夢に出てきた。私はいつものように腕に籠を抱えて売店を縫って歩き、エディータの店に採りたてのコリアンダーを買いに行く。楽しくおしゃべりをした後、お金を払おうとするとエディータは、要らない、と手を振り、軽く私の腕を叩いて立ち去らせようとする。贈り物よ、と彼女が言う。どうもありがとう、と私は答える。お気に入りのパン屋では、丸いパンの上に清潔な布をかけてある。私はパンをいくつか選んで財布を開けるが、ここの店主もまた、まるでお金を払おうとするのが失礼なことでもあるかのように、要らない、と身ぶりで示す。私は困惑して周りを見回すーー見慣れた市場のはずなのに、様子がガラリと変わっている。私だけではなく、誰もお金を払っていないのだ。私はすっかり嬉しくなって、市場を足取り軽く歩き回る。ここで使える通貨は感謝だけなのだ。すべては贈り物なのである。まるで野原でイチゴを摘んでいるみたいだーー行商人たちは、地球からの贈り物を次の人に手渡す仲介者にすぎないのである。
わたしは自分の籠の中身を眺める。ズッキーニが二本、玉ねぎ一個、トマト、パン、それにコリアンダー。籠はまだ半分空だが、一杯になったみたいに感じる。必要なものは全部揃っている。私はチーズを売っている店に目をやり、買おうかな、と考えるが、買うのではなくてもらうことになることを考え、やっぱりやめることにする。おかしなものだーー市場にあるものが全部、単にとても安いだけだったら、ふだん私はできるだけたくさんのものを買っただろう。でも全部が贈り物となったら、自制心が働いたのだ。必要以上のものは受け取りたくない。そして、明日私は何をお礼に持ってこようかと考え始めた。
もちろん、その夢は消えてしまったが、とても嬉しかった気持ちと自制心は消えなかった。それ以来何度もそのことを考え、私はそのとき、市場経済から贈与経済へ、私有財産から共有財産への転換を目の当たりにしたのだということが今ではわかる。そしてその転換によって私たちの関係は、手に入れた食べ物と同じくらい滋養たっぷりなものになった。(後略)
(『植物と叡智の守り人』 ロビン・ウォール・キマラー著 三木直子訳 築地書館 2018 pp.47-48から抜粋)
市場にあるものが全部、単にとても安いだけだったら、ふだん私はできるだけたくさんのものを買っただろう。でも全部が贈り物となったら、自制心が働いたのだ。必要以上のものは受け取りたくない。
贈与経済では、過剰な欲望は抑止される。これは、大事なポイントではないだろうか。
さらに、「感謝のことば」あるいは「すべてのものに先立つ言葉」として古くからネイティブアメリカンに伝わる慣習を紹介する章では、以下のように記されている。
感謝のことばを聞いていると、否応なく豊かな気持ちになる。それに、感謝の気持ちを表現するというのは素朴な行為に見えるかもしれないが、それは実は革命的な考え方だ。消費社会においては、満足であるというのは過激なことなのだ。自分に不足しているもののことではなく、自分がいかに豊かであるかを認識するのは、満たされない欲求を作り出すことによって繁栄する経済を弱体化させる。感謝の念は充足感を育てるが、経済の繁栄には欠乏感が必要なのだ。感謝のことばは、あなたはすでに必要なものすべてを持っているということを思い出させる。感謝の念があれば、満足感を得るために買い物に行こうとは思わない。満足感というのは買えるものではなく、贈り物であって、それは経済全体を根幹から揺るがす。地球にとっても人にとっても、それは良い薬になる。
(同書pp.146-147から抜粋)
感謝の念は充足感を育てるが、経済の繁栄には欠乏感が必要なのだ。
持続可能な社会に向けて、まっさきに取り組むべきは、感謝の気持ちを表現する、ということなのかもしれない。
2019-07-01
どうしてそれを選ぶのか、自分でその根拠がわからないまま選択を行なっていることは多いという自覚はずっとあった。特にものをつくる場面で。
いちばん身近なものでは、なぜそれを、そのようなかたちで写真に収めるのか?という問い。それはいつも自分につきまとっている。
最近読んだ、『あなたの脳のはなし』には、はっきりとこう書かかれている。
わたしたちはふつう自分の選択の根拠をわかっていない
私たちはふつう自分の選択の根拠をわかっていない。脳はつねに情報を周囲から引き出し、それを使って私たちの行動を導くのだが、気づかないうちに周囲の影響を受けていることが多い。「プライミング」と呼ばれる効果を例に取ろう。これはひとつのことが別のことの知覚に影響するものである。たとえば、温かい飲み物を持っている場合は家族との関係を好意的に表現し、冷たい飲み物を持っているときは、その関係についてやや好ましくない意見を述べる。なぜこんなことが起こるのか?心のなかの温かさを判断する脳のメカニズムが、物理的な温かさを判断するメカニズムと重なり合っているので、一方が他方に影響する。要するに、母親との関係ほど根本的なものについての意見が、温かいお茶を飲むか、それとも冷たいお茶を飲むかに、操られる可能性があるということだ。
(『あなたの脳のはなし』 デイヴィッド・イーグルマン著 大田直子訳 早川書房 2017 pp.111-112から抜粋)
ほかに、硬い椅子に座っているときのほうが、柔らかい椅子に座っているときよりもビジネスにおいて強硬な姿勢を示す、といった例も挙げられている。
もうひとつの例として、自覚されない「潜在的自己中心性」の影響を考えよう。これは、自分を思い起こさせるものに引きつけられる特性のことだ。社会心理学者のブレット・ペラムのチームは、歯学部と法学部の卒業生の記録を分析して、デニースやデニスという名前の歯科医(デンティスト)、そしてローラやローレンスという名前の弁護士(ロイヤー)が、統計的に多すぎることを発見している。
(同書 p112より抜粋)
さらにたたみかけるようにこう続く。
心理学者のジョン・ジョーンズのチームは、ジョージア州とフロリダ州の婚姻記録を調べ、実際に名前のイニシャルが同じ夫婦が予想より多いことを発見した。つまり、ジェニーはジョエルと結婚し、アレックスはエイミーと結婚し、ドニーはデイジーと結婚する可能性が高い。この種の無意識の影響は小さいが数値的な裏付けのあるものだ。
要点はこうだ。もしあなたがデニスやローラやジェニーに、なぜその職業やその配偶者を選んだのかと訊いたら、彼らは意識にある説明を話すだろう。しかしその説明には、最も重要な人生の選択に対して無意識がおよぼす力は含まれていない。
(同書 pp.112-113より抜粋)
これほどまでに、無自覚に環境の影響を受けているのだとしたら、時間をかけて見つけた合理的に思える根拠も、疑わざるを得ない。
想像以上に「わかっていない」ことがわかって、少し恐ろしくなった。
2019-03-10
先日訪れた展覧会で、展示構成がプログラミングのように構築されている印象を受けたのをきっかけに、ひとはどんなモデルで展示構成を考えるのだろうということに興味を持つようになった。
わたしの場合は、音楽的にとらえる傾向があるように思う。
2015年に札幌でペア作品を展示した際、それを表現するのに「主題と変奏」というフレーズが頭に浮かんだ。A/Bのような比較としてとらえられるペア作品ではあったが、2点を同時に視野に入れることはできないので、時間の流れを含んだ「主題と変奏」という表現はしっくりきた。同時に、そういう音楽的な表現がふと思い浮かんだことに、自分でも驚いた。
そう考えると、写真が横に並んでいく作品の構造はそのまま、矩形のユニットが横に並ぶ楽譜をなぞらえているようにも思え、幼少からのピアノレッスンをはじめとする20年余の音楽の経験は、意外なかたちで自分の中に深く根を下ろしているのかもしれないと思うようになった。
展示に限らず、何か構成を考える際に、主旋律、副旋律、転調、インヴェンションの1声、2声、3声の複雑な交錯といった音楽的な構造を、むしろ意図的に援用するのは面白いかもしれない、と思う。
2019-01-20
松本卓也さんの『享楽社会論: 現代ラカン派の展開』(人文書院 2018)の第6章2節 視線と羞恥の構造に、とてもおもしろい記述を見つけた。
“視線が恥(羞恥)を生み出すメカニズムは、一体どのようなものだろうか。視線は、どのように恥ずかしさを生み出すのだろうか。”という書き出しではじまるこの節は、まなざしについての示唆に富んでいる。
なかでも、水着の女性のグラビアを見るときに感じない恥ずかしさを、実際に水着の女性が目の前にいると「目のやり場に困る」と恥ずかしさを感じるのはなぜかという問いから導かれる以下の論考がおもしろい。
水着の女性を「見る」ことそれ自体が恥ずかしいのではない。また、見ることによってその女性を「知る」ことが恥ずかしいのでもない。むしろ、その女性を見る際に、自分のことが知られてしまうのが恥ずかしいのである。女性の身体のどこを見るかによって私たちの欲望が知られてしまうこと。つまり、自分の視線が水着の女性を見ることによって、自分の欲望を知られてしまうことが恥ずかしいのである。それゆえ、「見ること=知ること」という等式を恥ずかしさのメカニズムとして考えるならば、その場合「知る」という行為の目的語は相手ではなくて私たち自身である。(「私が他者を知る」のではなく、「私が他者によって知られる」)という主客の逆転があることによく注意しておかなければならない。
(同書 pp.182-183から抜粋 *太字は本文の傍点箇所です)
その先には、カメラマンについての言及も続く。
(前略)さきに、水着の女性のグラビアを見ることは、見ている側に恥ずかしさを生じさせない、と述べた。窃視症は、これとよく似ている。というのは、窃視症者自身は壁を一枚隔てたところに隠れており、自分のことが相手に知られることがないからである。これは、写真の基本的な構造ともよく似ている。カメラマンは、カメラを用いて「壁」をつくり、被写体を含む外界から隔離されることができるからである。それゆえ、窃視症者やカメラマンには恥ずかしさは生じないのである。
(同書 pp.188から抜粋)
さらに、もう少しだけ抜きだすと、
(前略)カメラマンは、自分と被写体とのあいだにカメラという「壁」を挟むことによって、安全な位置を確保している。グラビアの水着女性が私たちを非難してこないのと同じように、カメラマンも、カメラという「壁」の向こうから攻撃されることはない。覗き魔が隠れる「壁」と同じように、カメラがきわめて安全な位置を提供してくれるのである。(後略)
(同書 pp.188から抜粋)
窃視症との関連でカメラが引き合いに出されたことに少し戸惑いを覚えたが、よくよく考えてみると、撮影対象の中にひとが入っている場面では、たしかに「覗いている」ような気もちになることがある。作品制作においては、あいだに川を挟んでいることもあって、被写体(に含まれている人物)からコミュニケーションをとられる可能性はないし、そもそも被写体に撮られていると悟られることも少ないが、それでも一方的にカメラを向けていることに対する疚しさはぬぐえない。とりわけ、二作目からはひとの営みが画面に写り込むことを意識しているので、なおのこと、疚しくないとは言い難い。
もう少し、写真に引き寄せて考えると、カメラという「壁」によって被写体に対しては隠される撮影者の欲望(見たい、見せたい)は、撮られた写真によって(どういう構図でどこにピントをあわせているかで)事後的に露呈する。しかし、中心的な対象をもたないフラットな画面構成であれば、撮影者の欲望はどこまでも隠し続けられる。
ここでわたしに突きつけられたのは、そういうフラットな画面構成を採用するその背景に、自分の欲望を知られたくないという強い恥の意識、あるいは自分の欲望を知られることに対する強い恐れがあるのではないか?という問いである。
2018-02-13
それまでワンショットでおさめていたものに、何度もシャッターを切っている。
迷いを変化の兆しととらえれば、決して悪いことではないのだけれど、どこか心許なさもつきまとう。気がつくと、ジョージア・オキーフと篠田桃紅の本を手にしていた。
あるときは、思いもかけないぐらい、墨は美しい表情を出すんです。自分でも、こんなにうっとりする線が引けるとは思わなかった、っていうものを授けるんです。ときどき、私を越える。こんなに美しいものを描ける力があったんだって、自分で自分にびっくりする。惚れ直すことができるんです。墨には、それくらい幅があるんですよ。
(『百歳の力 (集英社新書)
』 篠田桃紅著 集英社新書 2014 p146より抜粋)
ときどき、私を越える。
何十年も墨の線を引き続けた作家が、それでもなお、自分を越える美しい線に出会い、驚く。
その事実に、こころが震えた。
2018-02-10
「書くこと」について、友人と話をした。
友人は、わたしがどこに着地するかわからないままでも書き始められることに、すこし興味を持っている様子だった。彼女は、どういうことを書くか決めてからでないと書けないと言う。
書いているうちに思いもよらない方向に展開したり、思いもよらないものに接続することが、即興演奏のようでおもしろいと感じていたが、書く人がみなそういう風に書くわけではない、ということを、わたしはその時はじめて知った。
書くことや、ものづくりで一番おもしろいのは、手を動かしているうちに、まったく想像もしなかったものが生まれる(というより「出会う」)ことだと思っている。とりかかった時点で、何ができあがるか、自分にはわかっていない。むしろ、わからないからこそ、自分の手が生み出す、まだ見ぬ何かを見たいと願う。そして、それが書いたり作ったりする強い動機になっている。
下條信輔さんの、『サブリミナル・インパクト―情動と潜在認知の現代 (ちくま新書)』に、前意識についての記述を見つけた。「知っている」と知っている範囲(意識 conscious representation)の外側に同心円状に、知らずに「知っている」範囲(前意識 sub-conscious representation)が広がっている図を見て、なるほどなぁと思った。
書いたり、手を動かすことが、前意識と呼ばれる部分に働きかけをしているのかもしれない。
ここで特に私たちが考える前意識の知は、意識の知と無意識の知の境界領域、またはインターフェースにあたります。人が集中して考えたり、あるいはぼんやりと意識せずに考えるともなく考えているときに、突然天啓が閃く。スポーツによる身体的刺激や、音楽による情動の高揚、他人がまったく別の文脈で言った何気ない一言などが、しばしばきっかけになるようです。
こういう場合には、新たな知は外から直接与えられたわけではなく、といって内側にあらかじめ存在していたとも言えません。その両者の間でスパークし「組織化」されたのです。
この意味で前意識の知は、意識と無意識のインターフェースであると同時に、自己の心と物理環境、あるいは社会環境(他者)とのインターフェースでもあります。前意識を通してさまざまな情報や刺激が行き来するのです。(後略)
(『サブリミナル・インパクト―情動と潜在認知の現代 (ちくま新書)
』 下條信輔著 筑摩書房 2008 pp.258-259から抜粋)
2018-01-21
久しぶりにクラシックのコンサートを聴きに行った。
ごくあたりまえのことだけれど、さまざまな質の音があちこちから響いてくることや、コントラバスの低い弦の音のゆたかさ、弦をはじく寸前の微かに擦れる音、指揮者ののびやかな身ぶりに自分の身体もどこか同調しているようなこと、いろいろ発見があっておもしろかった。
なかでも、ヨハンシュトラウスの「ばらの騎士」でバイオリンが近くの音、遠くの音を奏で分けている箇所。音だけで空間の奥行きがグンと広がったことに鳥肌が立った。音の強弱だけでなく、明瞭さや肌理といった音の質も奏で分けられていたように思う。実際の劇場の空間よりも、広さや奥行きを感じられたのが不思議だった。
音楽の道に進もうと思っていた10代の頃、ひたすら譜面を追っていた時期には、気づかなかったことばかりだ。離れたからこそ、気づくことがあるのかもしれない。
2017-12-28
『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い (岩波現代文庫)』にあった遷宮の話が、ずっとひっかかっていた。世界遺産への登録が検討された際、遷宮によって建て替えられた“新しい建物”をどうとらえるかが議論になったという。
コピーがオリジナルにとってかわるという存在のしかたが取りざたされたようだけれど、わたしたち自身、その細胞は日々新しいものに入れ替わっている。むしろ遷宮のシステムは、生物の在りように近いのではないか、とも思う。「存在のしかた」は、ひとつではないのだ。もっと世界に視野を広げれば、もっと多様な「存在のしかた」が見つかることだろう。
それと同時に、あたりまえに交わされる「オリジナルとコピー」という議論が、実に西欧的(西欧ローカル)な問いであることにも気づかされた。
最近、芸術の枠に組み込まれていない視覚表現に関心を持つようになった。そういったところから、芸術における議論を相対化する視点が得られるのではないか、と期待している面もある。そう考えるようになったきっかけは、この遷宮の話だ。
以下、『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い (岩波現代文庫)』 高階秀爾著 岩波現代文庫 2009より抜粋。
ところが、伊勢神宮においては、コピーが本物にとって代わる—というか、コピーこそが本物である—という、西欧の論理ではあり得ないはずのことが、現実に行われている。神殿が二十年ごとに建て直されるというのは、もともとは建物が古くなって損傷が激しくなったから新しいものに代えるという理由から始められたものであろうが、それは、本物がいたんできたからコピーで間に合わせるというものではない。新しく出来上がった瞬間に、それは「本物」となるのである。(p31より)
問題は、もちろん伊勢神宮だけにあるのではない。日本古代のこの神殿が、西欧の論理を戸惑わせるようなやり方で今日まで生き続けているということは、とりも直さず、それが日本人の心性、価値観、ものの味方と、深いところでつながっているからであろう。
差し当たりまずはっきりしていることは、日本人は西欧人ほどものそのものに価値を置いていないということである。あるいは、ものそのもののなかに本質はないと考えている。と言ってもよいかもしれない。伊勢神宮で大事なのは、建物そのものではない。いや建物はむろん大事ではあるが、その大事だということが、建物の材料であるものとは、必ずしもそのまま結びついていない。現実には二十世紀に建てられたものであっても、あるいは途中で何回も壊され、建て直されたものであっても、現在の伊勢神宮は、われわれにとって、やはり千数百年前とまったく同じ価値を持っている。(p32より)
この「形見」という言葉は、もともと「かた」(型、形)に由来するものであろうが、とすれば、そのこと自体、きわめて意味深い。事実、西欧に「ものの思想」というものがあるとすれば、日本には「かたの思想」とでも呼ぶべきものがあって、ものそのものよりもかたないしは形の方を重要視する傾向が強いからである。伊勢神宮が六十回も建て直され、そのたびにものとしてはまったく新しい別の存在になりながら、一貫して同じ価値を保ち続けた理由は、それが同じ「かたち」を受け継いでいるからなのである。
日本人のこのような価値観は、宗教の世界を離れて日常の世界においても、その現われを見出すことができる。さしずめ、歌舞伎の名跡などというものはその代表例であろう。
かつては、梨園においてのみならず、武家でも商家でも似たようなことが行われていたが、団十郎とか歌右衛門という名前は、それを名乗る人が何回入れ代わっても、一貫してある一定の価値を示している。ちょうど伊勢神宮が、何回建て直されてもつねに伊勢神宮であるのと同じである。(p38より)
2023-01-22
『 空間の経験 身体から都市へ』 にも、遷宮についての記述があった。
形態は、崩壊しやすいものでしかない特定の実体より重要である。形態を復活させることは可能であるが、形態をつくり上げている材料が崩壊するのは必然なのである。日本の神道の古くからの習慣は、このような再生の観念によって説明することができる。神道の神社は一定の期間ごとに完全に建てかえられ、備品と装飾も一新される。とくに、神道の中心である伊勢の大神宮は二十年ごとに建てかえられる。それに対して、ローマのサン・ピエトロ大聖堂、シャルトル大聖堂、カンタベリー大聖堂といった大きな教会堂は、何百年ものあいだ風雪に耐えてそこに立っている。長い期間に渡る建築の過程でその形態は変化していくが、ひとたびそこに存在するようになった実体は不変のままなのである。
(『 空間の経験 身体から都市へ』 イーフー・トゥアン著 山本浩訳 ちくま学芸文庫 1993 pp.338-339より抜粋)
高階秀爾さんが『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い』(2009)で述べている、
西欧に「ものの思想」というものがあるとすれば、日本には「かたの思想」とでも呼ぶべきものがあって
というくだりと見事にパラフレーズしている。
2017-12-14
いくらでも考えるべきことはあるのだけれど…
造形や表現を生み出すときの、プリミティブな衝動や、感覚を忘れないように。
頭だけで考えることも危険。ほんとうに「腑」に落ちているか。身体に訊いてみる。
一見、理屈が通っているように思えることも、実感がともなわなかったり、違和を感じるときは立ち止まろう。
写真は、被写体の意味や物語に安易に回収されてしまうから気をつけること。あくまでも「画面で何が起こっているか」「画面との間に何が立ち上がりうるか」に留まり続けること。
2017-12-08
祖父が遺した朝顔の種を播いたのは一昨年のこと。
その花が種を落としていたのか、今年は播いたつもりのない鉢から二株の朝顔が芽を出した。
せっかくだからと鉢をわけて育ててみたら、片方は葉っぱも花も強く縮れた畸形だった。
しばらくのあいだ、畸形の株をかばうような心もちで水をやっていたのだけれど、ある朝、堂々と花を咲かせているのを見て、これがこの花の個性なんだと気がついた。
その発見はなんとも嬉しく、清々しさと開放感に溢れていた。ほんの少し自分の心がふくよかになった気もした。
つまりは、息苦しかったのだ。
正常や標準といった狭い範囲をくくり、そこから外れたものを排除したり、標準に近づけようとする社会の圧は日増しに強くなっている。その圧が恒常的であるがゆえに、気づきづらく、さらには、知らずしらず内面化してしまっていたのだろう。ずいぶん、無頓着になっていたものだ。
朝顔の花から学んだものは、大きい。
一昨年は、朝顔のつるを巻いて他者に寄りかかるありさまに、嫌悪感を隠せなかった。
できることなら、向日葵のように己の力ですっくと立っていたい、と思ったものだ。
でも今夏の台風で、強い風にあおられるなか、朝顔だけがまったく動じない様を見て、
他者の支えを前提として生きるしなやかな強さを朝顔に見出した。
平時だけを考えれば、向日葵の生き方でもいいのかもしれない。
けれど、有事を想定すれば、朝顔の生き方にも一理ある。
朝顔ひとつとっても、見える景色が変わることもあるのだと知った。
2017-12-04
昨夕、水餃子を湯がくのに、ふと思いついて「OK google! 4分測って!」とお願いしたら、ちゃんとスマホのタイマーが起動して4分が計測された。調理中のような、両手が塞がっている場面では、音声でコントロールできるのは、ものすごくありがたい。長時間露光の撮影でも、使えるんじゃないかと思う。
先日、1年ぶりに訪れた漢方医で。
それまでは、話を聞きながら先生が問診内容をタイピングしていたのが、その日は、先生がこちらを向いて話を聞いているだけで、わたしの回答が画面の電子レシピにリアルタイムで書き加えられていくのに驚いた。よく見ると、奥に助手が座ってタイピングをしていたのだけれど。
先生がきちんと自分のほうに身体を向けているだけでも、ずいぶん印象が違う。それまでは、発話のタイミングを先生のタイピングのペースにあわせていたのが、普通に会話ができるようにもなった。
問診がスムーズになった分、診察時間は短縮されたが、「ながら聞き」ではなくなったので、コミュニケーションの質は高くなったと感じられた。(生産性の向上やなぁ)
医師は、医師にしかできないことをするべきで、タイピングをする必要はないという当たり前のことに気づかされたのと同時に、いずれこの部分は音声入力に取ってかわられるだろう、と思った。
最近の音声認識は、思っているよりずっと精度が高く、わたし自身、スマホの入力はほとんど音声に頼っている。
さて、こんなことを書いたのは、WEBが今後どうなっていくのかを考える機会があったから。
音声認識とアシスタントの能力がどんどん高くなれば、視覚ベースが音声ベースのコミュニケーションにとってかわられる場面も増えていくだろう。WEBはアシスタントにリーダブルな構造に変化していくだろうと予想している。
そういうことを考えていたせいか、膨大な撮影データから「あなたにオススメの被写体」をカメラにおすすめされたり、過去に設定された露出の解析をもとに、被写体に応じて「わたし好み」の画が得られる設定をカメラが自動的にほどこす時代がくるのではないか、というようなことを妄想した。
たぶん、技術的には可能だろうけど、そこまでいくと、撮影者の主体性が脅かされ、撮影する楽しみが奪われるから、あえて踏みとどまる(踏みとどまっている)のではないだろうか。
「オススメ」を裏切りたくなる天邪鬼な心根が、撮影者をよりクリエイティブに駆り立てる、ということになるのかもしれないが。
2017-11-05
第二に、泥絵が人事・風俗のモティーフを排除するのに対して、浮世絵は人々の営みを前景化する。それは、絵師の関心の中心が、街を背景として繰り広げられる人間の〈出来事〉にあることを意味する。それに対して、人事・風俗モティーフがほとんど見られない泥絵の場合に際立つのは、都市空間そのものの〈フィジカル〉な存在である。つまり泥絵が描くのは、都市のハード面を形成する坂や道、建築物など不動のものである。主役は街そのものであって、街に生きる人間ではない。それに対し、浮世絵は都市のソフト面を描く。人事・風俗などはまさに運動する都市のイメージである。
第三に、浮世絵が表象しようとしているものとは、移ろいゆく時間的モティーフであるといえるだろう。花鳥風月などをはじめとする循環する時間を指示する季節の景物は、広重の浮世絵にとって非常に重要な構成要素である。気がつけば過ぎ去るが、また返ってくるという循環する時間。そこに浮世絵の受容者は〈情趣〉を感じるにちがいない。また広重は、夕暮れや夜景、雨や雪など、一日の特定の時刻や気象を指示するモティーフも執拗に描いた。一瞬のうちに過ぎ去っていってしまう時間のはかなさもまた広重が好んで描くところであり、受容者はその〈情趣〉に感情移入しやすかったにちがいない。それとは反対に、泥絵の場合、花見や雪などきわめて稀な例を除いて、季節を判別することはほとんど不可能に近い。季節を表示する自然物がほとんど表象されることがないのと同様に、時刻を表示するモティーフもほとんど描かれない。泥絵には、朝焼けも夕暮れも夜景も存在しないのである。存在するのは、昼日中の抜けるような青い空の真下に静かにたたずむ江戸の街なのである。広重が時間的なものを〈情緒的〉に描くとすれば、泥絵はむしろ空間的なものを〈理性的〉に描いているといえるだろう。
『トポグラフィの日本近代―江戸泥絵・横浜写真・芸術写真 (視覚文化叢書)
』 佐藤守弘著 青弓社 2011 pp.41-42より抜粋
これは、泥絵と浮世絵を比較した記述だけれど、自分の関心が浮世絵師のそれとほぼ重なることにどきっとした。むろん、そのままなぞるつもりなどさらさらなく、むしろ〈情緒的〉にしか表現されなかった題材を〈理性的〉に扱おうと思っているのだが。
2017-11-01
熊谷晋一郎さんの著書を読むのは『リハビリの夜 (シリーズ ケアをひらく)』以来。外出先で読んでいたのに、思わずうるっときてしまった。
未踏の社会に対して、失敗しつつも一歩を踏み出しつづけられるのは、どこかで社会のこと、他人のことを信頼している子供です。その、いわば根拠なき他人への信頼は、おそらく親との関係によって育まれる部分が大きいように思います。困ったときに誰か助けてくれるはずだと信じ、助けを求められるようになるには、困ったときに、下手でもいいから誠意をもって応じてくれた親との関係の記憶が、何よりの財産になるでしょう。そしてまた、自分を育てるにあたって、困った親が社会にヘルプを出したということ、そして、社会が親を救ってくれたということを、子は見ています。小さい子にとって、自分と親の境界線はあいまいで、親が社会によって助けられる姿は、自分が社会によって助けられる姿と不分離なものです。子が社会を信頼できるようになるという意味でも、育児を抱え込まず社会にヘルプを出す姿を子に見せることは大変重要だと思います。
『ひとりで苦しまないための「痛みの哲学」
』 熊谷晋一郎 大澤真幸 上野千鶴子 鷲田清一 信田さよ子 青土社 2013 p108より抜粋
人が社会(他者)に抱く印象は、その人と養育者との関係とパラレルだと、うっすらと感じていた。養育者への不信感は、そのまま社会(他者)への不信感だ。だから、まず、我がこととして刺さったというのもある。でもそれ以上に切実なのが、今の不寛容な社会が、想像以上のダメージを次世代に与えるかもしれないという危機感。
今、子育てをしている親たちは、不寛容な社会の中で、多かれ少なかれ萎縮していると思う。社会の側から「助けるよ」というメッセージを明確に示さない限り、「ヘルプを出す」ことすら難しいのではないかと思う。親たちを救えるように、また、親たちが躊躇なく救いを求められるように、社会を整えることが急務だと思う。
2017-10-29
〈パノラマ的視覚〉の一語に勢いづいて、ヴォルフガング・シヴェルブシュの『鉄道旅行の歴史 〈新装版〉: 19世紀における空間と時間の工業化』を繙いた。
のっけからすごい表現だなぁと思ったのが、この「時間と空間の抹殺」という表現。そのくらい、当時の人々にとって鉄道のもたらした速度は脅威だったのだろう。
時間と空間の抹殺、これが鉄道の働きを言い表す十九世期初期の共通表現(トポス)であった。この観念は、新しい交通手段が獲得した速度に由来している。所与の空間的隔たりを踏破するためには、伝統的にはある決まった旅行の時間または輸送の時間が必要であったが、この距離が、突然その時間の何分の一かで踏破されることとなり、これを裏返せば、同じ時間で昔の空間的な隔たりの何倍かが進められることになった。
『鉄道旅行の歴史 〈新装版〉: 19世紀における空間と時間の工業化
』(ヴォルフガング・シヴェルブシュ著 加藤二郎訳 法政大学出版局 1982) pp.49から抜粋
(前略)抹殺されたものとして体験されるのは、伝統的な空間及び時間の連続性である。この連続性は、自然と有機的に結びついていた昔の交通技術の特徴である。昔の交通技術は、旅をして通過する空間と模倣的関係にあったので、旅行者には、この空間を生き生きとした統一体として知覚させたのである。(後略)
鉄道が空間と時間とを抹殺するという考えは、交通技術が突然に全く新たな他の交通技術によって代替されたときに見出される、知覚のこのような現実喪失と理解することができよう。鉄道が作り出す時間・空間の関係は、技術以前の時代のその関係にくらべると、抽象的なものに見え、時間・空間感覚を阻害するものと写る。(後略)
同書 p53より抜粋
高速移動があたりまえの時代に生きる者としては、「抹殺」とまで言う衝撃は想像しにくいけれど(正直、大げさだなと思うし)、翻って考えると、鉄道以前の旅では、それだけ濃密な関係が、人と空間の間にあったということなのだろう。
このことで少し思いあたることがある。
写真を撮るようになってから、歩くことで、その土地への親近感が増すのに気がついた。ひと月に満たない滞在でも、歩いた土地には愛着が湧く。徒歩の次が自転車。逆に、バスで観光地を巡るパッケージツアーでは、そのような親近感は抱き難い。
「歩くと、土地との関係が近くなる」というのが、近年のわたしの発見で、鉄道の登場以前に馬車や徒歩で移動していた時代には、むしろその感覚のほうがデフォルトだったのかもしれない。
十九世期初期の人々に抹殺とまで言わしめた、鉄道の速度がもたらした「時間・空間感覚の阻害」は、朝夕通勤電車にゆられ、ときに新幹線で移動するわたしたちに、もはや何の違和感ももたらさない。テクノロジーによって、ひとびとの知覚のありようが変わるということは、今後もっと顕著に起こるだろう。
シンギュラリティーに戦々恐々としているわたしたちの有様は、22世紀からまなざせば、なんと大げさな、と、とらえられるのかもしれない。
2017-10-21
最近は、本来の目的とは違うところで、興味深い文章に出会うことが多い。今日は、横浜写真について調べようと繙いた本から。
文化史研究者ヴォルフガング・シヴェルブシュ(Wolfgang Schivelbusch)が看破したように、十九世紀後半の鉄道の発達の結果、ヨーロッパ人の知覚は劇的に変化した。産業革命以前は旅行者は、自らがそのなかに含まれる前景を仲介として、常に景観と同一空間に属していた。ところが、高速で移動する鉄道の車窓からでは、飛び去るように過ぎていく前景を捉えることはもはや不可能に近い。車上の人と景観の間には「ほとんど実体なき境目」が挿入されることになる。この前景なき空間認識を、シヴェルブシュは〈パノラマ的視覚〉―刹那的・印象派的とも言いかえられる視覚体験―と呼ぶ。(後略)
(『トポグラフィの日本近代―江戸泥絵・横浜写真・芸術写真 (視覚文化叢書)
』佐藤守弘著 青弓社 2011 p112より抜粋)
「車窓から見える景色が映像的に見えるのはなぜだろう」という、10年来のモヤモヤがすっと解消した。
前景を認識できないから(処理が追いつかない)→景観と同一空間内に自分を定位することができず→景観と自分との関わりが希薄になり→リアリティの欠如→結果、景観を「映像的」と感じる、ということか。
こういう視覚の綻びが見え隠れするところが、いちばんおもしろい。
2017-10-10
昔の投稿を繰っていて「移動焦点の原理」を見つけた。
ちょうど、少し前に遠近法と視線について書かれたものを中心に読んでいたので、あわせて書き留めておこう。
まずは猪子さんの基調講演についての記事
[CEDEC 2011]日本人は,遠近法で風景を見ていなかった。9月8日の基調講演「情報化社会,インターネット,デジタルアート,日本文化」をレポート
http://www.4gamer.net/games/131/G013104/20110910008/
以前、英語のステイトメントに「絵巻やスーパーマリオブラザーズのようなスクロールゲームに影響を受けている」と書いたとき、わたしの中でその2つは別々のものだったけれど、上の記事にその2つが同根だと分析している話があって、とても興味をそそられた。
それから、高階秀爾さんの『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い (岩波現代文庫)』
〈洛中洛外図屏風〉のように、画家の視点が自由に移動して、それぞれの視点から眺められた細部を並列的に画面に並べていくという画面構図法では、画面は、統一的な空間構成をもたず、平面的に左右にいくらでも拡がっていく傾向を持つ。西欧の遠近法的表現においては、アルベルティの『絵画論』のなかにはっきりと述べられているように、画家はある一定の視点に位置して眼の前の世界を眺め、その世界を、あたかもひとつの窓を通して見たかのような一定の枠のなかに秩序づけて表わす。その窓枠にあたるものが、すなわち画面そのものにほかならない。したがって、西欧の絵画においては、画面の枠というものは、統一的な空間構成を成り立たせるために、画家の視点と同じようにやはり不可欠の前提である。ところが、画家の視点が自由に移動する日本の画面構成においては、原理的には、画面は、視点の移動にともなっていくらでも拡大することができる。むろん実際には、屏風なり襖なりの現実の画面によって作品の枠は決定されているのだが、そのなかに表現された世界は、枠のなかだけで完結するのではなく、その枠を越えてさらに外に拡がっていく傾向をもつ。
(『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い (岩波現代文庫)
』 高階秀爾著 岩波現代文庫 2009 pp.20-21から抜粋)
「画家の視点が自由に移動する日本の画面構成においては、原理的には、画面は、視点の移動にともなっていくらでも拡大することができる」つまり、画面構成そのものが、フレームの強度に影響を与えるということか。
2017-10-06
『ウェルビーイングの設計論-人がよりよく生きるための情報技術』からの流れで読み始めた本の中に、興味深いフレーズを見つけた。
以下、『謎床: 思考が発酵する編集術』(松岡正剛、ドミニク・チェン著 晶文社 2017)より抜粋
- ドミニク
「うつる」がおもしろいのは、写真の「写」だし、映像の「映」だし、しかも移動の「移」ですね。
(p125より抜粋)
- 松岡
平行移動に近い。バーチャルもリアルも混在して平行移動していくんですね。日本はスーパーフラット状態なんですね。ですから、浮世絵のようなああいうスーパーフラットな絵が描ける。そこに村上隆も関心をもったのだと思いますが、こちら側と向こう側が同じ大きさで描いてある。奥村政信や広重や華山ぐらいから少し遠近法が入りますが、それまでは全部同じ大きさですね。
もともと、「源氏物語絵巻」などの吹抜屋台画法で描かれる王朝の絵巻のパースペクティブがフラットにできているんです。それとも関係があるし、鈴木清順が自作の映画の中で解明していましたが、日本の空間は視線が水平移動するんです。バニシング・ポイントがないんですよ。
- ドミニク
ああ、絵巻とかは本当にそうですよね。
- 松岡
一点透視にならない。だから「モナ・リザ」のようなああいう絵は生まれない。バニシング・ポイントをもたず、フラットに平行移動しながらすべてを解釈していく。絵巻は右から左へ見ていきますが、そうしたあり方が日本の物語、ナラティヴィティを成立させているとも言えるわけです。どこもかもがフラットなので始まりと終わりも曖昧で、どこからでも話を始められる。その代表的なものが『伊勢物語』で、そこには伊勢が出てこない。在原業平が東下りしているだけ、平行移動しているだけの話です。
(p127より抜粋)
ちょうどスクロール用のスクリプトを調整しているさなかに、このくだりに出くわした。
バニシング・ポイントをもたず、フラットに平行移動しながらすべてを解釈していく
バニシング・ポイントがあると、どうしてもそこに視線がひっぱられる。フラットな画面だと構成要素の吸引力が等しくなり、視線が自由になる。画面の構成要素の力関係。
どこもかもがフラットなので始まりと終わりも曖昧で、どこからでも話を始められる
ディスプレイがもっと高解像度になれば、プリントにこだわらなくてもいいかもしれない。ブラウザベースであれば、映像と違い縦横比は自由自在。ループ再生で好きなところから見て、好きなところで見終えるのもよし。そんなことを考えていたところだった。
作品が長いので、展示では空間にあわせて作品を端折ることがある。ふつう、空間にあわせて作品の一部を切ったりはしない。それこそ、展示空間の都合でモナ・リザの右端を切り落としたりはしないだろう。なのに、端折ることにまったく躊躇を感じなかった。「必ずしも全部を見せなくてもいい、と思うのはどうしてだろう?」とずっと不思議に思っていた。はじめに選んだ形式(フラットであること)によって、すでに、さまざまなこと(自分の態度まで!)が決まっていたのかもしれない。
日本の物語の構造までは考えたことはなかったけれど、媒体(絵巻)の形状が、物語のあり方を規定するということは、大いにありうることだろう。まずは『伊勢物語』を読むところから。
2017-06-30

作品のポータブルな形態として、最初は冊子、それから折本にしてみたけれど、
ロシアで撮影した作品はあまりに長く、折本に仕立てるのすら難しいと判断。で、第3形態、巻子。
わたしは、日本美術の影響を多分に受けている、という自覚がある。先行する写真作品群よりずっと深いレベルで、日本美術の影響を受けている、と思っている。
でも、それは画面の構造的な問題であって、テイストとして和を取り入れることや、安易なエキゾチシズムに回収されるような表現は、絶対に避けたいと思っている。そういうこともあって、巻子の形態を採用するのに過剰なほど警戒心を持っていたのだけれど、巻子は固定されたフレームを持たないという点で、作品にもっとも適した形態である、と、ある日ふっと腹に落ちた。
実際作ってみると、巻子は、シンプルな構造でありながら大量の情報を輸送することができる、非常に優秀なアナログツールだと思う。一方、リニア編集とか、シーケンシャルアクセス、ということばを久しぶりに思い出すくらい、「前から順に」しか目標にたどり着けない、まどろっこしさもある。(カセットテープを思い出した)
そして、手で繰ってみた実感として、わたしの作品には巻子の形態がいちばんしっくりきている。
写真集を…と長らく思っていたけれど、作品の性質として、そもそも冊子には向いていないのかもしれない。
2017-05-02
友人のすすめで3年前にはじめたアシュタンガ・ヨガ。特に、時差が大きかったり極寒の地に赴いたとき、心身を整えるのに効果覿面で、ふだんも、ゆるゆると練習を続けている。
あるとき、たまたま手に取った本が、ジョン・カバット・ジンの『マインドフルネスストレス低減法』で、それをきっかけに、ヨガの練習後に、少しだけ呼吸に意識を向ける時間をもつようになった。
それから1年半くらい経つだろうか。
日常生活で、自分があたりまえと思っていたことが「もしかしたら、そうじゃないかも?」とか「そうじゃない考え方もあるよね?」と気づくことがふえたように思う。
たとえば、難しいヨガのポーズに対して、それまでは、できるようになりたい、の一点張りだったけれど、その朝は、「昨日と筋肉の張りや、伸ばしたときの気もち良さが違うな」ということが妙にリアルに感じられたので、「じゃあ今日は、できるできないじゃなく、からだがどう感じているかをじっくり味わってみよう」と意識の向け方を変えてみた。というようなこと。
できるできないのこだわりから離れたせいか、呼吸がそれまでよりやわらかくゆったりとしたものに変わって、そこでもう一度発見があったり。
似たようなことが、日常生活の中でも、ふえつつある。
それは必ずしもいいことばかりではなく、今まで気づかなかった微細な感情の揺れに気づくような場面もある。「あれ?こんな些細なことで、もしかしてわたし傷ついてる?」といったように。
それでも、ふとしたきっかけで、今までとは違った考え方や感じ方にひらかれ、それまで当然としていた前提を相対化できるのは面白い。たとえそれがどんなに些細なことであったとしても。
ここ数年、撮影旅行や、展覧会でバタバタしていて、知らぬ間にものが増えていた。
引っ越しや、トランクルームの利用も考えたけれど、まずはものを減らしてみようと思い、不要品の処分と部屋の整理に取り掛かったのが1年ほど前のこと。最近になってようやく、目に見えてものが減って気づいたことがある。
はじめは、身軽になりたいという思いに突き動かされていたのだけれど、ものが減って部屋が片づくと、
(誰もが言うことだけれど)まず、とても気分がいい。
そして、予期せぬ収穫は、今まで気づかなかったことに、気がつくようになったこと。
部屋のカーテンをシンプルなものにかけかえたら、翌朝、外から射し込む光が、窓ガラスを通すのと、通さないのとで、ほんの少し、緑み、あるいはマゼンタみ、を帯びていることに気がついた。
もしこれが、部屋がごちゃごちゃしていたり、にぎやかな柄のカーテンを吊っていたら、きっと気づかなかったろうと思う。日常生活での些末な気づきは、もっともっと、数え切れないくらいたくさんある。
ものが多いときは視覚刺激が多すぎて認識できなかったものが、ものが減って刺激が少なくなったせいで、より繊細に認識できるようになったのだと思う。感度が少し上がったのかもしれない。
どうしたら見る感度を上げられるか、ということをずっと考えていたけれど、意外なところにヒントがあった。
余計な刺激を減らせばいいのだ。
2017-04-21
小学生の頃、わたしは家から少し離れたスイミングスクールに通っていた。
帰りのスクールバスは、夕暮れどきの千里ニュータウンをぬって走る。
ぽつぽつとあかりが灯りはじめる高層住宅をバスの窓から見上げながら、ひとつひとつの部屋に、それぞれを中心とした別々の世界が同時に存在する、ということを、ぼんやりと考えていた。そこはかとなく寂しい気もちで。
それからずっと後、哲学の講義で「それまでは自分と世界をひとつのものだと思っていたのが、自分とは関係なく世界が存在していることに気づいたときの幼児の痛み」という話を聞いたとき、「自分とは関係なく」のワンフレーズに、寂しさの出どころを言いあてられた気がした。
「自分とは関係なく、それぞれを中心とした別々の世界や物語が、同時に、そして無数に存在する」
幼い頃、ヒリヒリするような寂寥感とともに身につけた世界観が、自分の作品のベースにはある、と思う。
2017-04-20
自分のなかですでに「ゆるぎなく決まっていること(選択や判断)」があって、その理由を何年もかけて探しながら作業をしているようなところがある、と気づいたのは最近のこと。
昨年サンクトペテルブルクで撮った写真は300カットを超え、地道に編集作業を続けていると、正直「長すぎる…」と心が折れそうになることもある。その一方で、冗長であることに確信を抱いてもいる。手を動かしながら、「なぜそんなに冗長性にこだわるの?」と、問い続ける。思い返せば、ずっとそんなふうにして作品を作ってきたのかもしれない。
というのは、「コンセプトがあって、それに向けてつくる」という枠組みで作品の説明を書くたびに、落ち着きの悪さや、嘘がある感じ、を抱いていたから。
作っている自分も、はじめから全部わかっているわけではないし、見通せているわけでもない。手を動かしながら、徐々に明らかになっていくことがある。
もしかしたら、それがおもしろくて作り続けているのかもしれない、とすら思う。
2017-03-23
部屋の整理をしていると、古い印画紙の箱と一緒に、大学時代、暗室で焼いたモノクロの写真が出てきた。
いま見ると拙いものばかりだけれど、せっかくなので何枚か残そうと選びながら、印画紙の質感っていいなぁ、と感じ入る。たぶん、当時のわたしはそんなふうには思っていなかった。
グラフィックデザインを志して進学したにもかかわらず、ずぶずぶと写真にはまり込んでしまった理由のひとつは、暗室作業が好きだったから。
暗室での作業が、ただただ楽しかった。
赤いランプの下、現像液のゆらめきの中で像が浮かび上がる瞬間がものすごく好きだった。もしかしたら、しあがった写真より、像の生まれる魔術的な瞬間を愛していたのかもしれない。
暗室の隣には立派なスタジオもあって、あるとき恩師がその重厚な扉に穴を穿ち、スタジオをまるっとカメラ・オブスキュラに仕立ててしまった。その小さい穴から射し込む光が結ぶ、さかさまの像は、それこそ魔術的だった。
すっかり忘れていたけれど、写真をはじめた頃、わたしにとって写真は、魔術のような世界だった。
作品云々よりずっと手前のところで、その魔術性に魅了されてしまったのだと思う。
フルデジタル化して、ずいぶん遠のいてしまったな。
もう一度、暗室作業、やってみようかな。
2017-03-20
ふんわり漂うのは沈丁花の香り。
ついつい惹き寄せられる。
いいにおい。
春のあたたかい陽射しにくるまれるのも心地がいい。
あるときはストライプに、あるときはまだらに落ちる光と影。
くぐるようにそこを通り抜けるのもまた、楽しい。
ふと思う。
シャッターを切るときのトリガーは、必ずしも視覚によるものではない、と。
いま、ここ、にわたしの感覚を総動員しているのに、
写真におさめて「視覚に縮約する」とはどういうことだろうか。
2017-03-15
物理学では、科学者はモデルや理論をつくって、この宇宙に関する観測データを記述し、予測をおこなう。その一例がニュートンの重力理論であり、もう一つの例がアインシュタインの重力理論だ。これらの理論は、同じ現象を記述していながらも、まったく異なるたぐいの現実を表現している。ニュートンは、たとえば質量を持った物体が力を及ぼしあうと想像したが、アインシュタインの理論では、その効果は空間と時間の歪みによって起こるものであり、そこに力としての重力の概念は含まれていない。
リンゴの落下はどちらの理論を使っても精度よく記述できるが、ニュートンの理論のほうがはるかに使いやすい。一方、運転中に道案内をしてくれる、衛星を使った全地球測位システム(GPS)で必要となる計算をおこなう際には、ニュートンの理論は間違った答えを与えるため、アインシュタインの理論を使わなければならない。現在では、どちらの理論も、自然界で現実に起こっていることの近似でしかないという意味で、実際には間違いであることがわかっている。しかし、適用可能な範囲で自然をきわめて正確に、そして有用な形で記述してくれるという点では、どちらの理論も正しい。
(『しらずしらず――あなたの9割を支配する「無意識」を科学する
』レナード・ムロディナウ著 水谷淳訳 2013 ダイヤモンド社 p66より抜粋)
旧い話だけれど、工学部に在籍していたころのわたしは、とてつもない落ちこぼれだった。
次々と出現する記号にとまどい、まったく内容が理解できない講義に「母語がこんなに理解できないなんて!」と驚きすら覚えながら、暗号を書き留めるかのように板書を写す、そんな学生時代だった。
たぶん電磁理論の講義のあとだったか。「なんで、こんなわけのわからん記号をようさん使わなあかんのやろ。」とぼやく私に、
「aはbの3倍である、bはcを6つに等しく割ったうちの1つである。と文章で記述されるより、a=b×3 b=c÷6 のほうが簡潔やし、パッと見て事実関係がわかりやすいやろ。数式は、いくつかある表現のなかで、もっとも使い勝手のいいものと思ったらええねん。」
と級友が諭すように言ったのを思い出す。
そのときにはじめて、数式を「唯一の真実」ととらえるのではなく「数ある表現のうちのひとつ」ととらえることを知った。
同じころ、言語学の講義で、that節が入れ子になっているような英文は、日本語に訳すより英語のままのほうが事実関係を把握しやすいという話を聞いた。
CがDを嫌っていることをBが悩んでいるらしい、とAが言っていた。
というような、少し複雑な状況を説明するには、英語の構造のほうが日本語の構造よりも適している、と。
そこで、記述(表現)方法と対象とのあいだには、向き不向きがある、ということを知った。
ここに出てきた物理学の理論。数式、言語。もちろん、視覚表現も然り、だろう。
記述(表現)方法と対象とのマッチングについて、あらためて考えてみる必要があるな、と思った。
2017-03-13
昔、教習所で「動くものに視線をとられるから、フロントガラスに揺れるものをぶら下げないように」と言われたことを思い出したのは、降雪の中で撮影をしていたとき。ピントをあわせるために被写体を凝視しても、雪のチラつきにずいぶん注意を奪われることに気がついた。
それから、人は動くものに、(本人たちが思っているよりもずっと強く)注意がそがれてしまうのではないか、と考えるようになった。逆に言えば、写真の「静止していること」がもたらす効果は、想像以上に大きいのではないか、と。
静止しているからこそ、つぶさに観察ができる。
誰もが知っている、ごくあたりまえのことだけれど、これは案外、重要なことではないだろうか。
先日、ふと手に取った本にいくつか視覚に関する興味深い記述を見つけた。
適切な条件下で、ある映像を左目に、別の映像を右目に同時に見せられると、その両方を何らかの重なり合った形で見ることはなく、一方の映像だけが知覚される。そして、しばらくするともう一方の映像が見え、その後再び最初の映像が見えるというように、二つの映像が際限なく切り替わる。
しかしコッホのグループは、片方の目に変化する映像を、もう片方の目に静止した映像を見せられると、変化する映像のほうだけが見え、静止した映像はけっして見えないことを発見した。つまり、右目に、卓球をしている2匹のサルのビデオを、左目に100ドル札の写真を見せられると、左目はその写真のデータを記録して脳に伝えているにもかかわらず、本人はその写真に気づかない。
(『しらずしらず――あなたの9割を支配する「無意識」を科学する
』レナード・ムロディナウ著 水谷淳訳 2013 ダイヤモンド社 p56より抜粋)
このあと、変化する映像が優先的に意識にのぼり、変化しない映像は無意識の領域で処理されるという話につながっていくが、無意識の話はさておき、変化する(動く)映像のほうしか意識にのぼらないというのはすごいな、と思う。
それほどまでに、視覚のなかで「動き」が優先して処理されるとは思っていなかったから、ただただ驚いた。
2016-12-11
先日、とても興味深い話を聞いた。
現在子育て中の友人。
彼女は母親から「昔、子育てをしていたときあなた(友人自身)は神経質で、寝ついても音ですぐ目が覚めたけれど、孫(友人の息子)はよく眠ってくれる」と言われたのだそう。
わたしの知る限り、神経質なのは友人の母親のほうで、友人自身はおおらか。きっと友人の母親は、娘の寝つきの悪さを、ふつうの人よりずっとずっと心配したのではないかと想像する。
この話を聞いたとき、「投影」ということばが頭をよぎった。他者をとらえようとするとき、そこには「私」の気質や性質が否が応にも投影されてしまうのではないかと思う。
自他の境界は、思っている以上に曖昧なのかもしれない。
2016-12-10
年末なので溜まっていた手紙をすこし整理することにした。
が、そういうときに限って、読み耽ってしまうもの。
友人や親戚、家族から、あたたかい心遣いや言葉をたくさんかけてもらっていたことに、あらためて気がつく。そして、あたたかい言葉は時間を越えて、もう一度わたしの心をあたためる。
時間を経て読み返すと、そのときどきのわたしに寄り添い、励まし、勇気づけようと、慎重に言葉を選んでくれたことが、よくわかる。きっと渦中にいるときより今のほうが、その心くばりの濃やかさがよくわかる。
紙の香りや手ざわり、したためられた文字の勢い、やわらかさ。そういった「情報としての文字」ではないものを堪能しながら、メールもLINEもFacebookも便利だけれど、やっぱり気もちを伝えるのは手紙のほうがいいな、と思う。
ということで、取り出した手紙は全部箱にしまい、明日はバースデーカードを買いに出かけようと思う。
2016-09-27
『数学する身体』(森田真生著 新潮社 2015)から気になった箇所を。
(前略)はじめは紙と鉛筆を使っていた計算も、繰り返しているうちに神経系が訓練され、頭の中で想像上の数字を操作するだけで済んでしまうようになる。それは、道具としての数字が次第に自分の一部分になっていく、すなわち「身体化」されていく過程である。
ひとたび「身体化」されると、紙と鉛筆を使って計算してたときには明らかに「行為」とみなされたことも、今度は「思考」とみなされるようになる。行為と思考の境界は案外に微妙なのである。
行為はしばしば内面化されて思考となるし、逆に、思考が外在化して行為となることもある。私は時々、人の所作を見ているときに、あるいは自分で身体を動かしているときに、ふと「動くことは考えることに似ている」と思うことがある。身体的な行為が、まるで外に溢れ出した思考のように思えてくるのだ。
思考と行為の間に、はっきりとした境界を引くのは難しい。そのことを強調するために「数学的思考」の代わりに、しばしば「数学という行為」と表現していくことにする。
(pp.39-40から抜粋)
昔、制作に行き詰っていたときに、恩師から「ただ考えるのと、手を動かしながら考えるのは違うから(手を動かしてみてはどうか)」と言われたのを思い出した。
ある作家のコンセプチュアルな写真作品。実際に作品を見るのは、ほとんどはじめてのことなので、とても期待をしていた。しかし、そのクオリティの高さとコンセプトへの見事なアプローチにも関わらず、ほとんど何も感じるところや考えるところ、思うところがなかったことに驚いた。
それから、そのことをずっと考え続けている。
作品を前にしたときに、観者は、言語化できなかったり、明確に意識化できない「何か」を受け取っているのではないか?そして観者の認知や判断は、少なからずその「何か」に依存しているのではないか、と。
少し前に読んだ『数学する身体』(森田真生著 新潮社 2015)の興味深い記述を思い出した。
かいつまんで書くと…
進化電子工学の研究で、ある課題を実現するチップの設計プロセスそのものを、人間の手を介さずに人工進化の方法だけで試みたところ、興味深い結果を得た。四千世代ほどの進化の後に、無事タスクをこなすチップが得られたが、そのチップは人間が設計した場合に最低限必要とされる論理ブロックの数を下回る数の論理ブロックしか使用していない。普通に考えるとその論理ブロックの数では機能するはずがない。数が少ないうえに、ほかの論理ブロックと繋がらず機能的にはどんな役割も果たしていない論理ブロックが5つも見つかった。だが、この5つの論理ブロックのどれ一つを取り除いても、回路は働かない。(おもしろくなってきた…)
そこで、この機能を果たしていないかのように見えるチップを詳しく調べたところ、この回路は電磁的な漏出や磁束を巧みに利用していたことがわかったという。
普通はノイズとして、エンジニアの手によって慎重に排除されるこうした漏出が、回路基板を通じてチップからチップへと伝わり、タスクをこなすための機能的な役割を果たしていたのだ。チップは回路間のデジタルな情報のやりとりだけでなく、いわばアナログの情報伝達経路を、進化的に獲得していたのである。
(『数学する身体
』 森田真生著 新潮社 2015 pp.34-35から抜粋)
同じようなことが作品を介したコミュニケーションでも起こっているのではないだろうか。
言語として整えられたコンセプト(作家の意図)から漏れ出たノイズのようなものを、わたしたちは暗黙のうちに受け取っているのではないだろうか。とりわけ写真はノイズと親和性のある(というよりノイズにまみれた)メディアであるにもかかわらず、わたしが見た作品からはノイズが排除されすぎていたのではなかろうか。
2016-08-06
七夕の夜、珍しく母に作品の話をした。
フレームの中に何を選びとり、そして、焦点によってどの奥行きを選んで際立たせるか。写真は徹底して「選ぶ」ことに依拠しているけれど、フレームとピントによる選択を無効化してもそれでも作品として成立するだろうか?ということを考え続けている。と。
母に話したのはそこまでだけれど、選択を無効化するということを目指しながらも、それでもやはり周到に避けている(選ばないでいる)ものがあることには薄々気がついていて、最近は、何を撮るかより何をフレームからはずしているか、に関心が向いている。
先日、IZU PHOTO MUSEUMでフィオナ・タンの《Accent》を観た。
戦後、検閲は廃止され、報道の自由が保障されるようになったが、アメリカは検閲を行い、日本人の愛国心をかきたてるおそれがあるとして、映画から富士山のシーンを削除した。そして、その検閲は日本国民には知らされず、富士山の削除自体がわたしたちの認識から削除されていた。
わたしが展示室に入ったのは、おおよそ、そのような内容のセリフが語られているシーンだった。(正確にセリフを覚えていない)
少し面食らった。
時間軸(タイムライン)から削除されたり、フレームからはずされたりしたものがある、ということに、ふつう人は気づけない。
さまざまな情報戦が繰り広げられるこの時世に、はずされたものについて考える重みをずっしりと感じた。
2016-06-30
抑制の効いた表現に、ぐっときた。
あるときは、アウシュビッツを描いた体験記録に。またあるときは、広島をうつした写真群に。
むしろ、抑制が効いているからこそ、なのかもしれない。
「淡々と描かれているから読めるのよ」そう母は言った。それ以来、抑制が効いているからこそ、ということを考えるようになった。
はっきりいえば、私たちは他人の「涙」に泣くのではなく、他人の抑制に泣くのである
多田道太郎
涙の記憶は誰にも数知れずあるから、他人のそれにもついほだされる。けれどもそのとき人は「泣きたい心持ちをぐっとこらえるその抑制の身ぶり」に涙しているのだと、仏文学者は言う。かつて泣きたくても泣けぬ口惜しさを必死でこらえた自分への憐憫(れんびん)? 実際、抑えきれるのは演じうるということでもあって、それに騙(だま)された人も少なくはない。「しぐさの日本文化」から。(鷲田清一)
折々のことば http://digital.asahi.com/articles/ASJ6C779DJ6CUCVL006.html?rm=130 より
2016-06-11
『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』(ダニエル・L・エヴェレット著 屋代通子訳 みすず書房 2012)の以下のくだりは、ものすごく興味深い。それぞれの文化のなかで、(ふだん意識していないが)ものごとを認知するうえで何に重点を置いているか、ということが言語からあからさまにわかる例。
(前略)マッチの火が瞬いて消えそうになる。男たちは、「マッチがイビピーオする」と言った。別の晩にも、消えかかるキャンプファイアーを前に、この言葉が同じように使われた。このような状況では、イビピーオは副詞として用いられてはいなかった。
(中略)ある物質が視界に入ってくる、または視界から出ていくという状態を表すために使われるものなのだ。誰かが川の湾曲部を曲がって現れるのは視界に入ってくることだし、それならば何かが視界から消えるとき、たとえば飛行機が水平線の彼方に見えなくなるのにピダハンがこの表現を使うのもうなずける。
(p183から抜粋)
イビピーオは、ぴったりと重なる英語の見つからない文化的概念ないし価値観を含意していると思われる。もちろん「ジョンは消えた」とか、「ビリーがたったいま現れた」という言い方をすることはできる。しかしこれはイビピーオと同じではない。第一に英語では「消えた」というときと「現れた」というときに別々の言葉を用いるのだから、両者は別々の概念だ。またここが肝心なのだが、われわれ英語圏の話しては、現れたり去って行ったりする人物のほうに焦点を当てていて、誰彼がわれわれの知覚の範囲に入ってきたとかそこから出て行ったとう事実に着目しているのではない。
最終的にわたしは、この言葉が表す概念を経験識閾と名付けた。知覚の範囲にちょうど入ってくる、もしくはそこから出ていく行為、つまり経験の境界線上にあるということだ。消えかかる炎は知覚経験のうちと外を絶えず行き来する炎なのである。
(pp.183-184から抜粋)
現れる、あるいは消えるという現象に重きをおくピダハンの認知のありようから、翻って、自分の属する文化の認知のありようはどうなのか?と、考えるきっかけになる。
先の『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』(ダニエル・L・エヴェレット著 屋代通子訳 みすず書房 2012)から、認知と文化に関する記述で気になったところを書き留めておく。
“写真を読み取るという一見ごく誰でもできそうなことの背景にも、文化が色濃く関わっている”
アナコンダを流木と見誤ったこの経験から、わたしは心理学者がとうの昔に知っていた事実を教わった。認知とは学習されるものなのだ。わたしたちは世界をふたつの観点から見聞きし、感じ取る。理論家としての視点と宇宙の住人としての視点と。それもわたしたちの経験と予測に照らし合せて見ているのであって、実際にあるがままの姿で世界を見てとることはほとんど、いやまったくと言っていいほどないのである。
(p.314から抜粋)
わたしのような都会人は、道を歩く時には車や自転車、ほかの歩行者には注意を払うが、爬虫類を警戒はしない。ジャングルの道を歩くときに何に気をつければいいのか、わたしにはわからない。この夜のことも、認知と文化に関する教訓であったわけだが、とはいえそのときにはそれをはっきり意識していたわけではなかった。わたしたちは誰しも、自分たちの育った文化が教えたやり方で世界を見る。けれどももし、文化に引きずられてわたしたちの視野が制限されるとするなら、その視野が役に立たない環境においては、文化が世界の見方をゆがめ、わたしたちを不利な状況に追いやることになる。
(pp.345-346から抜粋)
都市の文化的社会ではジャングル暮らしの秘訣が身につかないように、ピダハンのジャングルを基盤とした文化では都会生活への備えがうまく身につかない。西洋文明育ちなら子どもでもわかるようなことが、ピダハンにはわからない場合もある。たとえば、ピダハンは絵や写真といった二次元のものが解読できない。写真を渡されると横向きにしたりさかさまにしたりして、ここにはいったい何が見えるはずなのかとわたしに尋ねてきたりする。近年彼らも写真を目にする機会が増えてきたので、だいぶ慣れてはきたが、それでも二次元描写を読み解くのは、彼らには難儀なようだ。(後略)
写真を読み取るという一見ごく誰でもできそうなことの背景にも、文化が色濃く関わっていることが、ここからもわかる。
(pp.347-348から抜粋)
2016-06-02
先のピダハンの続き。方向の認識のくだりが印象的だったので、少し長いけれど抜き出してみる。
その日の狩りの間、方向の指示は川(上流、下流、川に向かって)かジャングル(ジャングルのなかへ)を基点に出されることに気がついた。ピダハンには川がどこにあるかわかっている(わたしにはどちらがどちらかまったくわからなかった)。方向を知ろうとするとき、彼らは全員、わたしたちがやるように右手、左手など自分の体を使うのではなく、地形を用いるようだ。
わたしにはこれが理解できなかった。「右手」「左手」にあたる単語はどうしても見つけることができなかったが、ただ、ピダハンが方向を知るのに川を使うことがわかってはじめて、街へ出かけたとき彼らが最初に「川はどこだ?」と尋ねる理由がわかった。世界のなかでの自分の位置関係を知りたがっていたわけだ!
(中略)いくつもの文化や言語を比較した結果、レヴィンソンのチームは局地的な方向を示す方法として大きく分けてふたつのやり方があることを見出していた。多くはアメリカやヨーロッパの文化と同様、右、左のように体との関係で相対的に方向性を求める。これはエンドセントリック・オリエンテーションと呼ばれることがある。もう一方はピダハンと同様、体とは別の指標をもとに方向を決める。こういうやり方をエクソセントリック・オリエンテーションと呼ぶ者もいる。
(『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』ダニエル・L・エヴェレット著 屋代通子訳 みすず書房 2012 pp.301-302から抜粋)
最初はこの方向の認識を、ふしぎに感じたけれど、よくよく考えると、わたしたちもけっしてエンドセントリック・オリエンテーションだけで生活しているわけではない。
友人が京都に来たときに「西宮や神戸での生活が長いと、どうしても山があるほうを北だと思ってしまう。だから京都に来ると山に囲まれているから、うっかり東山のほうを北だと勘違いしてしまう」と言っていたのを思い出す。地元、神戸の百貨店では店内の方向を示すのに「山側」「海側」という表示が採用されている。
友人の話を聞いたときは、「ふーん、そうなんだ…」と、まったくひとごとのように聞いていたけれど、札幌で撮影をしたときに、南に山があるせいで方向感覚がからっきし狂ってしまって驚いた。「山=北」の認識は相当根深いようだ。「北」と言葉で認識するというよりは、山を背にして左手から日が昇るものだと思っている、というほうが正確かもしれない。
3週間強の札幌滞在の最後まで、山を背にして右から日が昇ることに馴染めなかった。「なんでこっちに太陽があるの?」と違和感を感じては「そうか、山は南にあるんだ」と思い直す。毎日ずっと、それを繰り返していた。
2016-05-29
ずっと読みたいと思っていた『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』(ダニエル・L・エヴェレット著 屋代通子訳 みすず書房 2012)。
ピダハンには「こんにちは」「ご機嫌いかが」「さようなら」「すみません」「どういたしまして」「ありがとう」といった交感的言語使用が見られない(感謝や謝意、後悔の気持ちは言葉ではなく行動で示す)。彼らは色の名を持たず、数を持たず、左右の概念を持たない。また、彼らは精霊を見ることができ、夢と日常をほぼ同じ領域のもの、同じように体験され、目撃されるものととらえている。絵や写真といった二次元のものを解読できないが、暗闇の中で30m先に佇むカイマン(ワニ)の存在を感知することができる。
伝道のためにその地に赴いた著者が、最終的には無神論者になってしまう結末は小気味いい。”ピダハンは類を見ないほど幸せで充足した人々だ”と著者に言わしめるほど幸せに見え、そもそも迷える子羊ではなかったのだ。
どれも興味深いのだけれど、その中でもいちばん興味深いのは、ピダハンの文化では体験の直接性が重んじられること。
ピダハンは食料を保存しない。その日より先の計画は立てない。遠い将来や昔のことは話さない。どれも「いま」に着目し、直接的な体験に集中しているからではないか。(p.187から抜粋)
ピダハンの言語と文化は、直接的な体験ではないことを話してはならないという文化の制約を受けているのだ。(p.187から抜粋)
叙述的ピダハン言語の発話には、発話の時点に直結し、発話者自身、ないし発話者と同時期に生存していた第三者によって直に体験された事柄に関する断言のみが含まれる。(pp.187-188より抜粋)
そして、色名や数を持たない理由が、この文化的制約に結びつく。
ここに挙げられたピダハンの表現をできるだけ逐語的に訳すと、「血は汚い」が黒、「それは見える」または「それは透ける」が白、「それは血」が赤、そして「いまのところ未熟」が緑だ。
色名は少なくともひとつの点で数と共通項がある。数は、数字としての一般的な性質が共通するものをひとまとめに分類して一般化するものであって、特定の物質だけに見られる、限定的な性質によって区分けするわけではない。同様に色を表す表現も、心理学や言語学、哲学の世界で縷々研究されてきたように、多くの形容詞とは異なり、可視光線のスペクトルに人工的な境界線を引くという特異な一般化の役割をもっている。
単純な色名がないとはいえ、ピダハンが色を見分けられないとか、色を表現できないというわけではない。ピダハンもわたしたちと同じように身のまわりの色を見ている。だが彼らは、感知した色を色彩感覚の一般化にしか用いることができない融通の利かない単語によってコード化することをしない。その代わりに句を使う。(pp.169-170から抜粋)
直接体験したことを話すのに、すでに一般化された単語では用をなさないということか。思わず太字にしてしまったこのくだりが、ものすごく刺さった。
2016-02-28
マルシュルートカから地下鉄に乗り継ぐЧёрная Речка(チョールナヤ レーチカ)の駅前。撮影の行き帰りに通る駅なので、帰りにこれを見かけると、なんだかほっとする。いつの間にかヒゲ生えとるし。

2016-02-24
最初、木にひっついている目と口っぽい造作を見たときに「たまたま?」と思ったけれど、いくつか同じようなものがあったので雪遊びなんだと確信。

こちらはベースに色をつけている。

滞在中に見た中で一番いいなぁと思ったのは、この木にへばりついている謎の動物。しかも、脚がはずれたりしていたら、通りすがりの子どもがちゃんと補修していた。

2016-02-16

フィンランド湾に浮かぶコトリン島の中にクロンシュタットという街があります。要塞だったのでお堀に囲まれているゾーンがあり、レジデンスはこのエリアに位置します。サンクトペテルブルクの市街地へは、マルシュルートカ(K-405)と地下鉄を乗り継いでおよそ1時間半。
ところで、以前、ブリューゲルの雪景の絵を見たときに「ほんとうにこんな色なんかなぁ?」と疑ったことがあったけれど、ほんとうにこういう色に包まれることがあるのね。
旅をして、はじめて知る光の色があるなぁ。
2016-02-15
聞くところによると、1月には-25度まで下がったというのに、到着した時点では雪はほとんど残っておらず。気温も3度と例年よりも高く、「このまま春になるかな」と茶化されたりしたこともあって、不安に思っていたところ、ようやく雪が。

2016-02-11
同時期に滞在するアーティストが日本人だということを到着するまで知らなかった。奇しくも年齢も同い。ロシア西端の小さい島で、同い歳の日本人と一緒に滞在するとは思わなかった。
Jun’ichiro ISHIIはフランス在住のアーティスト
http://www.reart.net/
2016-02-09
2016年2月10日〜3月10日までの1ヶ月間、サンクトペテルブルクにて、NCCA(National Centre for Contemporary Arts)のARTIST IN RESIDENCE PROGRAMに参加します。
サンクトペテルブルクの雪景の撮影を計画しています。
2015-11-14
テレビで、「手で洗うのは効率は悪いけれど、固さやハリで、ネギの甘みや出来がわかる」と農家の方がネギを洗いながら話している場面があった。
おもしろいなぁと思う。
ふだん洗いものをするとき、洗い残しがないか最後指でなぞって確認するように、意識していなくても、目で確認しきれないものを指先の感覚がとらえることを、わたしたちは知っている。手の繊細さは、なにも特殊な技能習得者だけのものではない。
指先を切ってパックリ傷口があいたとき、その感覚がまったく狂って困ったことがある。こんな小さな傷で、こんなに困るのか!と驚いたことを思い出す。
わたしたちは生活の中で、うまいこと感覚を使い分けている。
そして、案外、多くの場面でその感覚に頼っている。
2015-11-06
同僚が買ったばかりのおもちゃを嬉しそうに見せびらかしていた。
RICOH Theta
テレビショッピングさながらに機能を披露していたが、そのなかでもおもしろかったのが、360度の動画。動画なのに、視界を自分の好みの方向にかえられる。それもYouTubeにアップされた360度動画を、PCやスマホで見ることができる手軽さがすばらしい。
今まで、静止画の360度をおもしろいとは思ったことがなかったけれど、なぜかこれが動画になるとおもしろい。ストーリー性の強い動画、例えば事件の起こっている場面で、全然関係のない方を向くこともできる。フレームが解体された動画だ。
もしフレームがないと成立しないのであれば、逆に、どれだけフレームに依存していたかということがあぶりだされる。暗黙のうちに了解されていた映像の文法が無効になることで、逆に、どういう文法を使っていたのかということが明らかになるかもしれない。
もうひとつおもしろかったのが、スマホで見る場合、画面を操作するのではなく、スマホ本体を右に向けたり左に向けたりすると、360度動画の視界も右や左に移動する。マウスやタッチパネルで操作するよりも、スマホをリアルに動かすほうが、映像が連動する感動が大きいのと、リアリティを感じる。スマホが異空間に向けて穿たれた穴のようにすら思えてくる。操作が日常行為に近ければ近いほど、映像とリンクしたときのリアリティが強いのかもしれない。
2015-10-24
最近、実家の冷蔵庫に千切りキャベツの袋が常備されるようになって、野菜は、その滋味を味わう以前に、健康(あるいは美容)のために食べなきゃいけないもの、という記号として消費されている側面が大きいよなぁ…ということを考える。
切った状態で袋に入っていると、それが新鮮なのか、美味しそうな体をしているのか、まったく判別できないから、わたしは絶対に買わない。そう考えると、日常生活でいちばん集中してものを見るのは生鮮食品を選ぶときかもしれない。
色つや、肌理、張り…そういうものを見極めるときの「見る」経験を作品化したいとずっと考え続けている。
記号と、たたずまい。
2015-10-23
マリオンは「ディスタンス(距離)」について語っています。それは神と人間との距離であり、父なる神と子であるキリストの距離です。「偶像」はこの距離を縮めます。イコンはこの距離を尊重します。(後略)
(『贈与の哲学―ジャン=リュック・マリオンの思想 (La science sauvage de poche)
』岩野卓司著 丸善出版 2014 p148-p149より抜粋)
このあとには、肯定神学、否定神学を通じてどのように神との「距離を尊重するか」という話が続く。
「距離を尊重する」ということばが、とてもしっくりくる感じがあって、本筋を離れてどんどん思いはふくらむ。ひとつは、写真における距離の問題。もうひとつは、人間関係の距離の問題。
特に後者。同世代の友人と話をしていると、人間関係の不調は結局、(心理的な)距離感の齟齬として話が着地することが多い。それをずっと、距離の近さ、つまりは量的な問題だと捉えていたけれど、このくだりを読んで、量の多寡ではなく、相手との距離を尊重することができるかどうか、姿勢の問題かもしれないと思った。
2015-10-20
そもそも偶像とは何でしょうか。それは「見えないもの」を「見えるもの」にしたものだと、ひとまずはいえます。神という見えないものを見えるようにしたのが偶像なのです。
これをマリオンは「眼差しが支配する」と表現しています。われわれの眼差しが、対象を自分に引き寄せ、それで像を作ってしまう。本当は見えない神を「まあ、このあたりでいいだろう」と考えて作ってしまうわけです。このことは、実際に像を作ることだけではなくて、われわれのものの考え方においても、見えないものを見えるレベルまで落として拝んでいることにつながってきます。
(中略)
ここまで語ってきた「偶像」に対して、マリオンはもうひとつ「イコン」という概念を考えます。古代ギリシア語では「アイコーン」で、似姿やイメージを指す言葉です。有名なのは聖書や聖人などの逸話を描いた聖画像ですね。カトリックにもありますが、東方教会がよく知られています。イコンというと、聖人は描かれますが、神は出てきません。神を描くのはやはりまずいわけですね。マリオンの考えでは、イコンにおいても見えざる神様への通路があるのです。「見えないものがある」というふうに描いていくのが画家の腕で、見えるものから見えないものへと無限に遡行して近づいていくのが、こうした聖画像の特徴です。
ここで整理すると、見えないものを見えるもののレベルまで押し下げてしまったのが、「偶像」でした。いっぽう「イコン」は、見えるものから見えないものへ遡っていきます。
(『贈与の哲学―ジャン=リュック・マリオンの思想 (La science sauvage de poche)
』岩野卓司著 丸善出版 2014 p138-p139,p142-143より抜粋)
少し遠出をして散策した場所が、昔見た作品の撮られた現場であることに気づいた(あ、ここか!)のがつい最近のこと。
そしてこのテキストのおかげで、ようやく10年前に見た作品のことが少しわかりかけている。その展示では、細心の注意を払わないと見えないこと、見えるものを通して見えないものの存在が垣間見えること…そういうさまざまな「見る」を構造的に扱っていた、と。
当時は、写真の美しさや世界観だけで充分成立しているように思えたのだけれど。
2015-10-19
贈与論だと思って手にとってみたら、ところどころ芸術に話が及んでいる。少し気になる箇所を抜粋。
なぜなら、芸術作品はそれが与える効果において現れているものだからです。絵画鑑賞の際にわれわれの眼差しに現れるものの中に、物質性、有用性、存在を「還元」しても残るような、視覚を超えたものを芸術は与えてくれる、と彼はいいます。これは純粋に現れているものなのです。これは視覚で捉えるけれども、ふつうに視覚で捉えている物質的なものを超えています。メルロ=ポンティの『見えるものと見えないもの』を引きながら、何か見えないものがある、それをわれわれは見ている、という言い方を彼はしています。
こういった意味で、芸術は純粋に与えられているものといえます。あるいは、もっと正確には、芸術は自らを与える出来事なのです。だから、芸術作品の芸術性について考えていくと、物質性、有用性、存在は「還元」され、「与え」が現れてくるのです。「還元をすればするほど与えがある」というわけです。
(『贈与の哲学―ジャン=リュック・マリオンの思想 (La science sauvage de poche)
』岩野卓司著 丸善出版 2014 p29-p30より抜粋)
現代のテクスト理論にも影響を及ぼしていますね。フランス語だと作家や作者は「auteur」です。また、神は「Auteur」で、大文字の作者、世界を創造した人、ということになります。こういうアナロジーがあることから、「神の死」から「作者」という概念自体も問い直そう、という考えが出てきます。
僕らが作品を書くとき、僕らは何らかの意図とともに作品を書きますが、できあがった作品の中には、僕らの意図を超えて無意識をはじめいろいろなものが入ってきます。言語というのは僕らが意識的に統御できないもので、神の概念も終焉を迎えたのだから、「作者」に支配されないテクストの独自の動きを考えていいのではないか、というわけです。(後略)
(同著 p129-p130より抜粋)
2015-10-18
少し肌寒くなってきたせいやろか。
友人のことばを借りると、感受性の針がふれやすくなっているのかもしれない。
実家で切り花の落とした房をわざわざ小さいコップに飾ってあるのを見つけては、わたしも同じことをしてる(これはMOTTAINAIとかわいそうがないまぜになった気もちだな)…やっぱりこのひとの娘なんだなぁとしんみりしたり。
店でboursinが少し手ごろになっているのを見かけては、昔boursinをつかった美味しい手料理をふるまってもらったことを思い出す。テキパキと料理をつくる後姿を見ているのが好きで、いざ料理ができあがると、まだ見ていたかったとほんの少し残念な気もちになったことまでありありと蘇る。
2015-09-21
あろうことか、デジタルカメラを全滅させてしまい、久しぶりにアナログの35mmを持って出かける。しかもフルマニュアル機。これが思いのほか新鮮やった。
露出を測って、絞りとシャッタースピードを全部手であわせるので、スナップにしてはずいぶん手間がかかるけれど、手間がかかる分、何を撮りたくて、何を撮りたくないかのフィルタリングが厳しくなる。
デジタルのスナップだと刺激に応じて矢継ぎ早に撮っていたのが、アナログのフルマニュアル機だと、撮りたいと思ってから撮るまでに溜めができて、被写体との関わりが少し変容するように思う。浅い呼吸が、少し深くなるような感じかな。ちょっとスピードを落としてみるのも悪くないなと思う。
2015-07-04
写真は、空間を平面に圧縮するのだけれど、webに携わるときは、ディスプレイの平面上でいかに立体あるいは空間を表現するか、という逆ベクトルの要請を受ける。
たとえば、ボタン。
あからさまにツヤップリッとさせるのはさすがに時代遅れだけれど、まんまフラットでは訴求力が弱い。押すことを促すために、フラットに見せかけつつ、気づかれない程度の影をつけたりする。10%以下の濃度でたった1pxの影。それでもひとの目はよくできているもので、まったく影のないものに比べると、手前に浮き出ているように感じる。
数年前に流行ったパララックスも、手前として設定したオブジェクトと、奥にあると設定したオブジェクトの速度に差をつけて、奥行きや立体感を表現する。
つどつど、わたしたちが何によって手前-奥を認知するのかということを考えさせられる。
まったく、空間を平面に圧縮すること、平面に空間を立ち上げること、の往還の中におるわいね。
2015-07-03
20年近く前に亡くした祖父の朝顔の種。
なんとなく持ち続けていたのを、今年は、なぜかふと植えてみる気になった。
植物の種とはすごいもので、そんな昔のもの(採取されたのはもっと前かもしれない)でもしっかり蔓を伸ばし、青々と葉を茂らせている。
みるみるうちに蔓を伸ばす朝顔を朝に夕に眺めながら、紫陽花には紫陽花の、向日葵には向日葵の、朝顔には朝顔の生存戦略がある、ということを考える。
2015-06-19
気ぜわしく、なんでも頭で処理しようとしている。
落ち着いたこころもちで耳を澄ます。
光の肌理をたしかめる。
もう少し感覚を信頼する。
2015-05-29
こころが少し疲れてしまった人と話をするとき、自分の呼吸を相手の呼吸とあわせるようにすると、相手も話しやすく、そして自分も相手の心理状態が少しわかるのだ、と教えてくれたのは中学校の養護教諭をしている友人。
その友人が顧問をつとめる大所帯のマンドリン部で、指揮者なしで数十名がタイミングをあわせて音を出すには、文字通り息を、呼吸をあわせるのが重要だという。
そんなことをふと思い出したのは、安田登さんの『日本人の身体 (ちくま新書)』にこんなくだりがあったから。
エスキモーには、鯨を獲るクジラ・エスキモーとトナカイ(カリブー)を狩るカリブー・エスキモーがいます。クジラ・エスキモーの人たちは音痴ではありません。同じエスキモーでも音痴なのはカリブーを狩る人たちだけです。
彼らも歌を歌いますが、二人で歌っても、音程や拍子を合わせることをしません。それに対してクジラ・エスキモーの人たちは、非常にリズム感がいい。同じエスキモーなのに、なぜこう違うのか。
それはクジラを獲るためにはリズム感が必要だからです。
クジラを獲るチャンスが年に二回しかありません。非常に少ない。しかもクジラが息を吸うために氷の割れ目に現れた、その瞬間しかありません。そのときに、みんなで息を合わせて一斉に攻撃する、それができなければ獲ることができません。
一本や二本の銛が刺さってもクジラはびくともしません。みなの銛が一斉に刺さってはじめて捕獲することができるのです。「せーの」で一斉に銛を投げる、そのためにはリズム感が必要です。
このようにクジラのような大型の獲物を捕獲するときには、みんなで息を合わせることが必要になります。ですから、クジラ・エスキモーの人たちは音痴ではなくなるのです。それに対してカリブー(トナカイ)はひとりで捕獲できるので、他人と息を合わせる必要がない。音痴でも全然かまわないのです。(『日本人の身体 (ちくま新書)
』安田登 ちくま新書 2014 p215-216から抜粋)
2015-03-30

奥行きのある空間が写真によって平面に圧縮される作用を考えるうえで、フェンス(と手前奥にまたがる樹木)はとても興味深く、よく観察するのだけれど、実家近くの校庭のフェンスを見てびっくり。剪定の際にフェンスに絡んだ部分が残ってしまったんやろね。前後の脈絡が欠落してフェンス面にのみ桜の木の痕跡が残っているのは、立体の断面というよりは、数学のグラフの断面をとったようで抽象的。
心情的には痛々しいけれど、考えさせられるところの多い光景。
2015-03-08
わたしたちは裸眼で世界を見ているつもりになっているが、じつはいつもあるフレームワークのなかで見ている。言葉で世界を分節し、一定の概念の枠に沿って分節されたものを関係づけつつ、ものごとを経験し、思考している。この眼鏡はたえず調整され、ときに別の眼鏡に取り換えられることはあっても、眼鏡というものを外すことはできない。眼鏡を外しては見られないのであるから、その眼鏡の精度を、それを通して見られるもの(世界)を基準にして測ることはできない。眼鏡をはめたままその精度を、それを通して見られるもの(世界)を基準にして測ることはできない。眼鏡をはめたままその精度を測るほかないのである。
精度を高めるためには、それを通して見える世界にたえず問いかけてゆかねばならない。そしてそれが正しく見えているのか、問いたださなければならない。どのような問いを世界に向けるか、どのような問いをおのれに対して立てるかということが、世界の探求とおのれの視線の検証とには死活的に重要である。
では、どこに目をつけたらよいのか。世界のその見えが歪んでいるところ、ぶれているところ、他の見えと整合しないところ、人によって異なって見えるところ、均衡を失って崩れかけているところ。あるいは矛盾が露呈するところ、論理が破綻するところ、どうにも説明がつかないところ。事象と理解のフレームワークとが軋みだしているところ。さらには事象の構造が想像もつかないところにずれだしている気配、思考の気流の変化……。(後略)
(『哲学の使い方
』鷲田清一 岩波新書 2014)
「哲学のセンス」と題された章の抜粋だけれど、ふと、知り合いの美術家を思い出す。
それまで、わたしはアーティストとは天性のセンスでもって(霊が降りて来るかのごとく)作品をつくるものだと思っていた。二十歳を過ぎたころ、はじめて生身の美術家と知り合い、その作家が日常の中の違和感、感覚のほつれを繊細にひろい上げ、そこから思考を重ね作品へと昇華させることに、衝撃を受けた。
抱いていたアーティスト像が崩されたのが重要なのではなく、日常の中の違和感や感覚のほつれを繊細にひろい上げるような世界への接し方が、わたしにとってとても新鮮で、きわめて興味深かった。
なので、順序が逆だ。この本のこの記述にひっかかりを覚えるのは、20年前の出会いがあったからだ。
一望できない形態の作品をつくっていながら、編集や記録の段階で、全体を把握したいと思うことがある。そこに端を発し、ことあるごとに、全体を把握したい(一望したい、俯瞰したい)という人間の欲望の深さを感じるようになった。
身近なところでは、「結論から言うと」という物言いに集約される結論から先に述べる習慣が挙げられる。できるだけ早く、できれば一瞬で全体を把握したい欲望は、当然のものとして社会全体を覆っている。
そして、写真はその欲望を叶えるのに最適なメディアである、とも思う。
一方、小説や物語、音楽、映画のように時間経過のなかで展開することにこそ意味のある表現もある。
最近でこそ、そういった時間性に関心を持つようになったけれど、最初から時間性を意識していたわけではない。そもそもは写真の具体性をどう担保するかというところに関心があった。それがどうして時間性に結びついたのか、自分の中で整理できていなかったのかもしれない。あまりに端的に示している文章に出会って驚いた。
宇宙を研究するために可視光線で撮影している場合もあり、X線で撮影している場合もあり、電波望遠鏡の場合もある。それぞれ別の像が得られますが、宇宙はそういう個々の見え方を超えて一つであるものでしょう。私たちは、何かの手段を選んで、それぞれ限界のある図を得ることしかできません。なるほど人間は、さまざまな手段を使うことによって個々の宇宙像を少しずつ超えることができます。しかし、「具体的にして全体的なもの」をついに人間が一望に収めることはできないと思います。全体的であろうとすれば抽象的たらざるをえず、具体的なものは必ず部分的であるというのが、私たち人間の世界認識の限界です。
(『徴候・記憶・外傷
』中井久夫著 みすず書房 2004)
2005年のインスタレーションを組み立てるにあたり「写真の内容を具体的に見てもらうためには、自分が今見ているものは部分でしかないという認識を持ってもらうことが必要だ」ということを直感的に考えていた。そして、作品を一望できない展示形態を採用した。一望できないということは、全体を把握するためには時間の幅が必要になる。
ようやく合点がいった。
2015-02-20
大きめのサングラスをかけ、ファーのついたジャガードのコートをはおり、チェックのパンツに黒いブーツ。
実家に向かう途中、交差点で信号待ちをしている女性があまりにかっこよくて目を奪われる。
久しぶりに惚れ惚れしたのは、自分の母親より10も15も年上であろう白髪の女性。
そう。芦屋や岡本のあたりでは、ものすごくスタイリッシュな70代、80代に出会うことがある。
長年ずっと手を抜かずにお洒落をしてきた集大成だから、色もバランスも素材も抜群。そして何より板についている。
そういう方に巡り会うと一日中嬉しいきもちになる。
「ファッションは他人の視線をデコレートするもの」というのはほんとうだと思う。
その前日、祖母が愛用していた薄いグレーのポンチョをはおってみた。
とても上品なグレーだけれど、今の自分の髪は黒すぎて似合わない。祖母の綺麗な白髪だからこのグレーが似合ったのだな、と。
白髪だからこそ映えるということもあるのだ。
巷ではアンチエイジングの大合唱だけれど、そういうふうに白髪になる日を楽しみにするのも好いなぁと思う。
祖母のポンチョと、スタイリッシュな白髪女性から、年を重ねる楽しみをいただいた気がする。
2015-01-31
おかげさまで無事、
第3回札幌500m美術館賞グランプリ展「SNOW」オープンしました!
2015年4月24日までの開催となります。
お近くにお越しの方は是非ご高覧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
同時開催されている田村陽子さんの「記憶する足形」も素敵な展示なので、ぜひ!
場所:札幌大通地下ギャラリー500m美術館
会期:1月31日(土) 〜 4月24日(金) 無休
時間:7:30~22:00 ※最終日は17:00まで
料金:無料
札幌大通地下ギャラリー500m美術館
http://500m.jp/exhibition/3263.html

2015-01-16
粘りに粘ったラボでは、最終日に美味しいお寿司のお相伴に預かり、
加工業者さんには、いろいろ知恵を絞っていただいたうえに、
丁寧な施工サンプルを送っていただき、
近所のパン屋さんでは、持ちきれなくて困っていた材に縄をかけてもらった。
この数日だけでも、いろんな人のお世話になりまくってる!
と思っていたら…
今日は大家さんが、角材切り出すのに電ノコ使っていいよ!と声をかけてくださった。
2mの角材を運びこんで加工のできる賃貸物件なんて、そうはないよね。
ほんとうに、ほんとうに、ありがたいことだらけです。
2015-01-05
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。
この年末年始は1月末から札幌で開催する展覧会の準備に追われています。
1/31(土)〜4/24(金)まで、
札幌の大通りのギャラリーにて写真を展示します。
2014-12-01
最終日は、もうほぼ撮り終えたという安堵のせいか、緊張がほどけていたんだろうな。たくさんの方から「いい写真撮れましたか?」と、話しかけられた。
そうやって通りすがりに話しかけてこられる方、落としたSDカードを雪道をわざわざ届けてくれた高校生、定食屋のご主人、レジデンスのスタッフの方々。こそっとキャラメルをくれたおそうじのナベシマさん。いきつけの六花亭の店員さん。(撮影の携帯食に六花亭のどらやきが最適だった…)
札幌では、みな好意的に接してくれたなぁと思う。
その土地の方が好意的かどうかは、けっこう強く印象に残るもので、夏に訪れた欧州でも、最後、スキポール空港でキャセイの係員と雑談をしながら、I will be back soon.と言った記憶がある。とりわけオランダの居心地が良かった。
札幌を発つときも、また1月末に戻ってきます、と言ったものね。
その土地に少し愛着がわくと、不思議と「また来ます」ではなく「戻ってくる」という表現になるんだな。
オランダに「戻れる」のはいつになるかなぁ…
2014-11-26
くたくたになるまで歩いて一日を終え、
あたたかい部屋で、空からこの街をとらえた美しい写真を眺めながら、
うとうと、と眠りにつく。
そんな日々も、もうあと少し。
すっかり冬の空。
そう思って夜空を見上げると、さっとひとすじの流星。
ささやかだけれど、たいせつな願いを、ひとつ。
2014-11-19
札幌にとって母なる川なんだよ。
というフレーズを、聞くのは二度目だ。
札幌と豊平川の歴史と、五輪の時期の開発の話を聞かせてもらった。
展示スペースと被写体との関係についての示唆に富んだ話。
ものすごくおもしろかった。
札幌に来てから、おもしろい出会いがいくつもいくつも。
2014-11-17
日の出が6時、南中11時すぎで日の入り4時、となると、
撮影のためにしぜんと朝型生活になる。
朝ごはんをつくっていると、同じ時間帯にキッチンを利用する方がいて、
それぞれ自分の朝ごはんを作りながら、作品の話をするようになった。
相手の質問が鋭くて、最初はたじたじやったし、
朝6時台からえらい切り込んで来るなぁ…と思ったりもしたけれど、
それはそれで、だんだんおもしろくなってきた。
ろくに自己紹介もしないまま、
朝ごはんを「つくっている間」だけ話をする関係が一週間ほど続き、
彼の滞在の終盤でやっと、お名前と作品を知る機会が得られた。
はじめから作品や経歴を知っていたら、もっと身構えていたかもしれない。
半分パジャマで頭ぼさぼさの無防備な状態だったから、
ベテラン作家からの突っ込んだ質問にも、率直に答えられたのもしれない。
いま思えば、とても貴重な時間やった。
2014-11-16
見てすぐにパシャっと撮るのではなく、
三脚を立ててピントをあわせるのにじっとファインダーをのぞいていると、
ファインダーの中に、人やものがこまごまと動く小さな劇場みたいなのが出現する。
(たぶん、あまり遠近法的な構図ではない場合によく出現すると思う)
デジタルのファインダーだと、それが映像のようにも見えるのだけれど、
中判を使っていた頃から、なんかこの暗いハコの中に小さな劇場があるな、とうすうす気づいていた。
そして、その小さな劇場の中で人が動いたり、ものが動いたりしている様が、なんとも愛おしいのだ。
もう、実に実に愛おしい。
雪の中、対岸の建物のタイルの目地を目安にピントをあわせながら、
ピントをあわせるために凝視する、その所作にともなう時間に「幅」があるからこそ、その小さな劇場の存在に気づけるのかもしれないな、と、あらためて思った。
2014-11-09
ドローンでの撮影が広く普及したら、わたしたちの視覚は、重力からも身体からも開放され、今までとは比べものにならないくらい可能性が広がるだろうな、と思う。
撮影者は、そのときその場所に居合わせる必要もなくなる。法が許せば、遠隔で映像を見ながらシャッターチャンスを狙うという方法が主流となるかもしれない。ドローンを用いたスナップというジャンルが登場するかもしれない。
新しい視覚は目新しさだけでは淘汰されるにせよ、撮影者の身体が介在しない写真が広く普及したときに、それでもなお身体を拠りどころとするだろうか。実際にその場に立つことでしか撮れないものがあると、言いきれるだろうか。
その場にいて実際に見ることによって喚起される「撮りたい」という欲望と、映像を見て喚起される欲望は同じだろうか。それとも異なるだろうか。
2014-11-08
昨日、何組かの展示を眺めながら、近くで見るよりも、遠のいて見たほうが映えるものがあるなぁ…と思ったのがきっかけになったか。
近づいたほうが、対象をよりよく把握できる場合と、遠のいたほうが、よりよく把握できる場合がある。特にノイズが入る場合は、遠のくほうが把握しやすくなるのかもしれない。今日は、そういうことを考えてながら歩いていた。
そして、ふと友人の作品を思い出す。遠のいて見たらすごい作品やった。
2014-11-07
先日訪れたみんぱくの「イメージの力」展。
パネルの文章がすごく良くて、その中でも印象的だったのが「物語を視覚化する試みは、いわば、時間にかたどりを与えるもの」というの。
時間性の問題が、このところずっと、ひっかかっていたからかもしれない。
時間にかたどりを与える、ということばが耳に残った。
展示ももちろん、とてもとても楽しめます。
入ってすぐのところにある作品。造形としてのインパクトもすごいけれど、驚いたのはこれが「椅子」やということ。実用品やったんや…

2014-11-03
次の10年は、もっと集中して作品に向き合えるといいな、と思う。
集中して制作を続けてきたそのひとの10年を想うと、
自分の、ふらつき具合、遅さ、考えるところが多すぎて。
2014-10-31
一年でいちばん人恋しくてたまならない、
美しくも妖しい季節を、わたしはひょいと飛び越える。
人類が発明した動力をかりて、冬のはじめに足をかける。
既知のものが、既知のものに見えなくなるときが、いちばんおもしろい
このフレーズはずっとたいせつに抱えてきた宝物。
2014-10-27
誰に相談するか、相手を選んだ時点で、
もうすでに自分の中で結論が決まっていたんだろうな。
自分の欲望の輪郭をつかむのが、いちばん難しい。
2014-10-26
フレーミングについて前から考えていたこと。
画面の中の何らかを際立たせるために、撮影者は画面からさまざまなものを排除する。
物理的なフレーミングと抽象的なフレーミングで。
なるべくフレームを意識させないような体裁を採用し、
できるだけ排除しない、という見せかけをしているにもかかわらず、
そこにフレーミングは存在している。
自分は何を排除しているのか。
物理的な矩形によるフレーミング
徹底的に排除するのは、此岸の情報。
対岸にフォーカスするためには、撮影者の置かれている状況を示すものは排除
撮影者と被写体との関係性を見えなくすることで、撮影者の存在をできるかぎり見えなくする。
ピント位置による奥行きの中でのフレーミング
ある奥行きにピントをあわせ、その奥行きにあるもの以外をぼかすことで、
ある奥行きにピークをつくる。わたしはこの方法はとってはいない。
撮影条件の選択による抽象的なフレーミング
くっきりとした画を得るために、悪天候は忌避。
逆光や、順光でも影が濃すぎる状況は忌避。
長時間露光による被写体のブレも極力避けている。
何が周到に排除されているのか、完成物を見せられた者が想像するのはほんとうに難しい。
おそろしいほど無防備に、画面の中の世界をありのままに信じてしまうきわどさ。
この夏、経験したばかりではないか。
写真のドキュメント性を手放さないのであれば、
自分が何をフレームアウトしているかを自覚しなければ。
今まであたりまえに選択してきたフレームをゆさぶることはできないだろうか。
それが今、興味を持っていること。
2014-10-17
たとえば、部屋に差し込む光がいいなぁと思って、カメラを構える。
ピントをあわせようとすると、カメラが自動的に拡大して見せてくれるから、数メートル先のカーテンの織のパターンまでしっかり把握できる。
確かにピントはものすごくシビアにあわせられるんやけど、最初に撮ろうとカメラを構えた欲望が何だったのかを忘れてしまうくらい、突如違う視覚にすり替えられる。
カメラを構えたつもりが、顕微鏡やったんか!と思うくらいの、不思議な経験。
ひとは慣れた道具を使うとき、自分の身体感覚を道具と一体化させたり拡張させたりする(※)、というけれど、わたしはこの機械と、どこまで身体感覚を一体化させられるのだろうか。
実は、かなり戸惑っている。
※『〈身〉の構造―身体論を超えて』
2014-10-14
プレゼンのためのプリント出力。
色のコントロールに悩んでいたけれど、春のあたたかい雰囲気が感じられる色で出たので、ほっとする。
友人は「NSっぽい色が出てるね」とニヤリ。またマニアックな…
小さいサイズで見るのとは全然、違う。
ものとして実物があがってくると、急にプランに現実感が生まれる不思議。
実寸で確認しておきたかった懸念点もクリアできて、少し肩の荷が下りた感じ。
友人から激励を受け、帰宅。
プレゼンに通っても、通らなくても、このプリントは宝物だ。
2014-09-22
つらいものやきついものを、ただただ受け止めた上で陽気を心がけるということと、見ないようにして散らして浮かれるというのは、似ているが大きく違うと思う。
小説だからと油断すると、ゴリッと本質的な言葉にあたる。これは、吉本ばななの『スナックちどり』の主人公の言。
2014-09-05
安田登さんの『あわいの力 「心の時代」の次を生きる』に興味深い文章をみつけた。
「閉じることができる」という、行為に対する負の方向の可能性こそが、その器官の主体性を担保している、というところが、すごくおもしろい。
顔には、目と口と鼻と耳の四種類の穴があります。このうち目と口には「みる」という動詞が使われます。味を「みる」といいますよね。そして、耳と鼻は「きく」。香りは、中国(漢文)でも、かなり古い文献から「聞く」という動詞を使っています。
「みる」と「きく」の違いは何かというと、「みる」器官(目と口)は自分の意思で閉じることができるのに対し、「きく」器官(耳と鼻)は自分の意思では閉じられないというところにあります。「みる」器官には閉じたり開いたりする筋肉があるけれども、「きく」器官の筋肉は退化しているか、かなり弱くなってしまっています。耳と鼻も手や道具の助けを借りれば閉じることはできますが、しかし完全に外とのつながりを断つことはできません。耳栓をしても外の音は聞こえてきますし、強烈な匂いがするところでは、鼻を塞いでも匂いを遮断することはできません。
ところが、「みる」器官である目や口は、自分の意思でいつでも、しかも完全に外とのつながりを断つことができます。見たくないものは目を閉じれば絶対に見えないし、食べたくないものは口を閉じれば食べなくて済みます。
ロロ・メイは、五感を「主体的(subjective)」と「客体的(objective)」の二つに分けます。そのうち「みる」器官は「主体的(subjective)」であり、「きく」器官は「客体的(objective)」であるというのです。
(『あわいの力 「心の時代」の次を生きる
』安田登著 ミシマ社 2014 p47より抜粋)
2014-08-23
そういえば、京都に巡回しているなぁと思って、ふと手に取ったのが『バルテュス、自身を語る』という本。(バルテュス著 河出書房新社 2011)
まだ彼の作品を見ていないのだけれど、彼の貫いた姿勢には学ぶところが多い。
ときに成功している芸術家の、ほとんどビジネス書のような持論に呆然とすることもあるのだけれど、バルテュスの言葉は違和感なくすうっと馴染む。彼のような姿勢は、彼が生きてた当時から、そして今もきっと「当世風」ではないのだけれど…
忘れてしまわないように、ここに少しとどめておこう。
画家はつねに鋭い視線でものを見ます。重要なことは実際に目に見えるものより遠くへ行くこと、しかしこの「より遠く」は現実のなかにもすでにあります。そういう研ぎ澄ました視線を持たなければなりません。そのものを見つづけること、そういうふうに注意して見なければならない。といっても現在の私のように視力が弱くてもあまり関係がなく、重要なのは内なる視線の緊張度。物事の内部に深く入り、想像もできないほど豊かな魂を持って生きていることを確認するやり方。(p235)
光はとらえがたく、画家には暴君的で、しかしつねに探し求められています。なぜなら光が照らすことで顔は崇高になり、身体は天使のようになるからです。私は仕事をとおしてずっとこの光の神秘を追い求めてきました。(p245)
絵を描くことは自分自身から抜け出すことです。自分を忘れ、何よりも無名でいることを好み、ときには危険をおかしてもその時代や身近な人たちと協調しないことです。流行に抵抗し、自分にとってよいと思うことには何がなんでも固執しなければなりません。(p274)
絵を描くことはまず知ろうとすること、真実を明らかにするためにあらゆることを試すことです。(p275)
私の人生で最良であり要なのは、絵との穏やかでひそやかで、直感的な関係です。見えないものに向かっての努力。画家に要求されるこの労苦。(P277)
2014-08-12
盆は嬉しや
別れた人が
晴れてこの世に会いに来る
三条会を自転車で走っていて、
掲示板に書かれている句がパッと目に飛び込んできた。
今までは、お盆を「実家にお坊さんが来る時期」として慣習のように受けとめていたけれど、別れた人がわざわざ会いに来てくれる、と思うと、嬉しいよね。
流星とともに、戻っておいで。
2014-04-26
その日は、保育の仕事をしている友人と話をしていた。
休日に仕事を持ち帰ったという話をきいて、家に持ち帰らなければならないほど仕事量が多いのかと問うたところ、
新学期の帳面に子どもたちの名前を書くの、バタバタしている仕事中ではなくて、心をこめて書きたいから。という返事がかえってきた。
心をこめて名前を書く
という話が、おそろしく新鮮に聞こえるくらい、心をこめて何かをする、ということからわたしは遠ざかっていた。
彼女曰く、テキパキと合理的に仕事をするよりも、心をこめて名前を書くようなことのほうが、むしろ自分にできることなのではないか。と。
そのとき、わたしは虚をつかれた感じだったと思う。
わたしの仕事観のなかには、テキパキ合理的というチャンネルはあったけれど、ゆっくり心をこめて何かをするというチャンネルは、存在すらしていなかった。
少し話はそれるけれど、視覚表現に携わるなかで感じてきたことのひとつに、「ひとは、言語化されたり明示された内容よりも、その表現のもつニュアンスのほうに、大きく影響を受けるのではないか」というのがある。
たとえば、ひとが話をしていることばやその内容よりも、間の置きかたや声色、トーンといったもののほうから、より多くの影響を受けるようなこと。
そうであればなおさら、表現する立場のひとが「心をこめる」ことはとても重要だ。
受けとるひとは、心のこもっているものと、そうでないものを、とても敏感にかぎわける。
なのに、わたしはずっとそれをないがしろにしてきた。
心をこめる、ということをもう一度、考え直したい。
あの日は隔たりということを考えていた。
隔たりとは、すなわち、距離(distance)なのだろうか。
たとえば、2者の間に遮蔽物があり、距離としては非常に接近できたとしても、実際に触ることができない、という状況を考えてみる。数値的には距離を限りなく0に近づけたとしても、接触不可能な限り、そこには隔たりが存在するのではないだろうか。
だとすれば、隔たりとは、2者の接触可能性に基づく概念であり、そこには身体性が深く差しこまれているのではないだろうか。と。
2014-03-23
先日潜入した、東洋医学の養生のクラスで、先生が興味深いことをおっしゃられていた。
春は上半身、とりわけ頭に血が昇りやすく、
前のめりに、あれもやりたいこれもやりたいというきもちになって、
下半身が追いつかないのだそう。
さらにPCやネットがそれを助長していて、
PCだと、頭で考えたことをクリックひとつで実現できてしまう。
けれど、現実ではわたしたちには身体があって、
クリックひとつで何かを実現させられるようには、身体は動いてくれない。
これはPCでの制作作業を生業としている身としては、とても興味深い話で、
素材との格闘のないPCでの制作、
とくに最終成果物がモノとして存在しないWEBデザインに関わっているときは、
集中すればするほど、モノと対峙する時間が切実にほしくなって、
調理をする時間を生活の中につくってバランスを保っていたように思う。
春という時期に限らず、職種的な視点でも、
頭だけがどんどん先にいってしまって、身体が追いつかない、
ということに対しては、よくよく気をつけようと思う。
ちなみに、養生の観点からは、
スクワットとか、腹式呼吸、足首をまわす、など、
上にのぼったものを、下におろしてくるのが良いそうです。
2014-03-20
クラフト・エヴィング商會の「星を賣る店」の展示会場で、月下密造通信という名の壁新聞をいただいた。
その壁新聞に
子供のころにも思い、いまもなお実感するのですが、人は皆、夜の静かな時間を持つべきかもしれません。その時間に何をするか、何もしないか、何もしないとしても、どんな時間が流れるかを見守ったり考えたりする。船が港に帰ってきて、夜の海の底に錨をおろすみたいに。(中略)世の中にはさまざまな本がありますが、自分はつまるところ、こうした冬の夜に心静かにひもとく本があれば、あとは何も要らないのです。
というくだりがあって、ものすごく共感してしまった。
Dzibilnocac という遺跡。
現地の方にすらなじみが薄い遺跡のようだったけれど、どうしてもどうしても見たくてユカタン半島に向かった。それは、ル・クレジオの『歌の祭り』の、ジビルノカク、夜の書 で描かれていた情景がものすごく美しかったから。
寺院の名は、ジビルノカク、「夜の書」という意味で、伝説によるとここにはマヤの文化英雄、文字の発明者である偉大なるイツァムナの弟子のひとりがかつて住み、長い夜を幾晩も費やして、イチジクの樹で作った紙片に神聖文字を描き、空にマヤの人々の秘密を読みとったのだという。(中略)
ぼくがジビルノカクのことを語りたいと思ったのは、夜を費やして人が文字を書くというこの孤立した場所の伝統が、ぼくには美しいと思われるからだ。世界でもっとも居心地のよい場所。世界を忘れてただひとり、記号の中へと入ってゆくための影の部屋のように美しい。その記号が石に刻まれたものであれ、アコーディオンのように折りたたまれた紙に描かれたものであれ、夜の沈黙の中で人がゆっくりとめくる絵のない本のびっしりと文字がつまったページに印刷されたものであれ。夜、書き、夜、読むことは、あらゆる旅のうちでもっとも驚くべき、もっとも簡単な旅だ。(『歌の祭り
』 ル・クレジオ著 菅啓次郎訳 岩波書店 2005 pp.204-205から抜粋)
つまるところ、
静かな夜にことばを紡いだり、本をひもといたり、
そういうことを、わたし自身が、ものすごく愛しているのだと思う。
静かな部屋で雨音を聞きながら、
つくづく、そう思った。
2013-12-01
ブーツを試着しているときに、店員さんが言った。
「黒は黒でも、あかるい黒ですから」
そのとき、わたしは、
あかるい黒という表現にはっとした。
webの世界で、黒は#000000。それ以外は、グレーに分類される。
デジタルで編集されるデータで黒はR0 G0 B0。
あかるい黒、くらい黒、というものは、ない。
もしかしたら、アパレル独特の表現なのかもしれないけれど、
自分が、黒を数値でしか定義していないことに、
そのことに、何の疑いももたなかったことに、
つまり、感覚を動員することを怠っていたことに、
あやうさを感じている。
2013-11-04
重森三玲の庭が見られるということで、真如院の特別拝観へ。
撮影禁止だったから、気がついたことを手帳にメモ。
スケッチは下手だけど、それでもいざ描きとめはじめると、
連鎖的にいろんなことが気になりだして、植木の刈り込み方までじっくり観察。
いろんな色と形の石を組み合わせることでリズムをつくっているな、とか、うろこ石が上流部分で二手に分かれていて、囲んでいる石がグリーン系の場所ではうろこ石もグリーンっぽいもの。囲んでいる岩がマゼンタ系の場所ではうろこ石もマゼンタ系のものを配置しているな…とか。
普段はそこまで見ていないかもしれない。
カメラを構えているときは、
対象そのものに対しては、早々と「了解」してしまって、
それよりも、どうすれば良い写真になるか、どうすれば対象を魅力的にとらえられるか、
ということを中心に考えている気がする。
実はあまり対象そのものに注意を払っていないのかもしれない。
もしかしたら、今日は、撮影禁止だったからこそ、気づいたこと、多かったんじゃなかろうか。
2013-10-14
という表現があまりにも的確すぎて、かなしい。
つい、いつものように写メールを送ろうとしたり、してしまう。
もうこの世にいないのに。
それでも、送ってみようと思うこともある。
読まれなくても、返事がなくても、いっぱいつたえたいことがある。
いっぱい共有したいことがある。
深いつながりのあっただれかが死ぬということは、わたしをその思いの宛て先としてくれていた他者を失うということである。これがなぜ痛いのか。その理由はそんなに不明ではない。〈わたし〉という存在は、だれかある他者の意識の宛て先としてかたちづくられてきたものだからだ。「わたし」が「他者の他者」としてあるとするならば、わたしをその思いの宛て先としていた二人称の他者の死は、わたしのなかにある空白をつくりだす。死というかたちでの、わたしにとっての二人称の他者の喪失とは、「他者の他者」たるわたしの喪失にほかならないからである。以後、わたしの思いはいつも「宛先不明」の付箋をつけて戻ってくるしかない。そのとき、わたしもまたその「他者」の他者としては死んだと言える。
(『〈ひと〉の現象学』 鷲田清一著 2013 筑摩書房 より抜粋)
2013-10-06
あまりに殺風景なので、観葉植物を導入してみた。
ちょっとグリーンがあるだけで和むわね。
調子にのってふやしすぎないようにしないと、
引越しのたびに鉢を引き取ってもらってるおかんから苦情が来そう…
(本当はうっそうと緑が生い茂るジャングルみたいな部屋にしたいけど…)
2013-09-26
この花は、ほんとうにお彼岸の頃に咲くんだ、と、今年はじめて知った。
彼岸と此岸。
向こう側とこちら側で、コミュニケーションが断絶する。
それがどういうことなのか、いまわたしは、いやおうなく思い知らされている。
2013-09-15
写真を見るしかた、というのはいろいろあると思うのだけれど、
抽象的な意味だとか、画面からたちのぼるニュアンスの伝達、というのではなく、
ただただ映っている像を具体的に見る、ということ自体のおもしろさ。
というのがある、と私は信じていて、それを探りたいというのが、
川のシリーズをしつこくしつこく続けている理由だと思う。
対岸のバーが窓辺に並べているウイスキーのラベル、自転車のリム、洗濯物を取り入れるご婦人だとか。
そういう像をただただ具体的に詳細を見ることのおもしろさ。
その意味で、昨日見た定点観測の写真集はのっけから面白かった。
画面のあちこちで建物が壊されては建つという変化が起こっているから、細部から目が離せない。まったく油断ができない。
「定点観測というのは、なにかひとつの建物がつくりはじめてからできあがるまで、だけれど、自分の写真はそうではない。万物の流転。」
と作家が明確に意図を語っているように、ひとつの大きなストーリーに回収されてしまわない定点観測。
同じものを、異なる時間に何度も撮影する以上、そこには何らかのストーリーが生まれるが、画面中にそのストーリーが無数に畳み込まれている。
言いかえれば、画面内の無数のストーリーを等価にとらえる定点観測。
前後の写真の差異(時間変化)をトリガーとして、地と図の転倒が起こること。
それが、画面のそこここで起こっているから、
いったん写真集として完結しているものの、ここにさらに新しい写真が加わることで、今ある写真の読み方がかわる可能性にひらかれていること。
久しぶりにドキドキした。
2013-08-21
a=1/(a+1) a=(√5-1)/2
この式は、わたしにとっての他者は、私と他者の両方を合わせた普遍的な神のような視点から見た私の姿に等しい、ということを言っている。汝の隣人を愛せよ、なぜなら神は、汝が隣人を見ているのと同じ仕方で、背後から汝を見給うから、というわけだ。すなわち、私が、私を見る神の視点をもって隣人を見るとき、隣人の中に、神にとっての私の姿が見えてくるのである。そんな場合の私にとっての隣人が、黄金数、すなわち対象aである。このことはむしろ、事態を逆にして考えてみるとその重要性が明らかになる。すなわち、隣人の中に対象aが触知されるとき、それは私自身が神の目をもって私を見ているのだ、ということである。(『ラカンの精神分析』 97項)
『純粋な自然の贈与 (講談社学術文庫)』(中沢新一)の中で、この抜粋を見つけた。
隣人の中に対象aが触知されるとき、それは私自身が神の目をもって私を見ているのだ
このくだりにどきっとする。
思いあたるのは、他人のことを低く言う人ほど、
自分自身に対する自己肯定感が低かったりする。
他人に対して否定的な感情をもつ、ということは、すなわち、
私自身が他者のまなざしをもって、自分自身を否定的な感情をもって見ている。
ということなのだろうか…。
これは抜粋だけでは真意がつかめない。現物読むか。。。
2013-08-06
全力で、いつもどおり、今まで通り、に日々を暮らそうとしている。
そうしないと、どこか日常の生活にほころびができたら、
そこからするするっと抜け落ちてしまうかもしれない、と思っている。
悲しくても、なんとかご飯が食べられるように、
毎朝起きて、会社に行って仕事をして、帰る。
くらいは、今のところ、できている。
必死で惰性にしがみついているのかもしれない。
そして、惰性に救われているのかもしれない。
新幹線の窓からぼんやり。
街並とか家が、ふだんとは違うスピードで西面-正面-東面とくるくるっと画角がかわるのに妙なリアリティを感じながら、「スピードと現実感」ということを考えて、うとうと。
この週末は、会うつもりだったひとに会えず、会えると思ってなかったひとに会えた。
その人のほんのひと言で、カチッとスイッチが入ったのかもしれない。
「あなたのこと、いちおう、作家だと思っているから」
久しぶりに制作ノートを開いてみた。
空振りに終わった目標や、空白の期間を目の当たりにすると、つらくなる。
けれど、少し前を向いてみようと思う。
2013-06-27
御堂さんのところに掲示されていた。
雨の日には雨の日の 悲しみの日には悲しみの日の
かけがえのない大切な人生がある
かけがえのない、ということばに
ほんの少し救われたのかな。
もう二度と、悲しくない日なんか来ない。と思っているから
悲しみの日は、悲しみの日のまま、それでも、かけがえがないものだ、
と言ってもらえたのが、うれしかったのかもしれない。
悲しいなりに、生きていかなければならないのだから。
2013-06-20
千島列島の海辺の葦の中で救出されたあと、リンドバーグ夫妻は東京で熱烈な歓迎をうけるが、いよいよ船で横浜から出発するというとき、アン・リンドバーグは横浜の埠頭をぎっしり埋める見送りの人たちが口々に甲高く叫ぶ、さようなら、という言葉の意味を知って、あたらしい感動につつまれる。
「さようなら、とこの国の人々が別れにさいして口にのぼせる言葉は、もともと「そうならねばならぬのなら」という意味だとそのとき私は教えられた。「そうならねばならぬのなら」。なんという美しいあきらめの表現だろう。西洋の伝統のなかでは、多かれ少なかれ、神が別れの周辺にいて人々をまもっている。英語のグッドバイは、神がなんじとともにあれ、だろうし、フランス語のアディユも、神のみもとでの再会を期している。それなのに、この国の人々は、別れにのぞんで、そうならねばならぬのなら、とあきらめの言葉を口にするのだ」
(『遠い朝の本たち』 須賀敦子著 ちくま文庫 2001 より抜粋)
ものごころついたときから、そうだった。
どうしようもなくかなしいときは、むさぼるように本を読んで、いっとき、現実から身をひく。
今日もまたそのように現実から遠ざかろうとして、当の文章に引き戻された。
さようなら
「そうならねばならぬのなら」
91歳で他界した祖母の葬儀で、
最後に母が棺の中の祖母に向けて「おかあさん、さようなら」と言ったのを覚えている。
そのときの、さようなら、には、
その別れを、かなしみもろとも受け入れる、母の決意が感じられた。
「そうならねばならぬのなら」
でも、一生かかっても、
さようなら、と諦めることのできない別れも、あるんじゃないだろうか。
2013-04-10
先日読んだ『チベットのモーツァルト』の中の身体技法に関する部分から、視覚と世界認識に関わるところを抜き出しておこう。
観想は映像的な想像力の訓練にかかわっており、視覚がたえまなく外の世界を構成しつづける対象化の意識作用に変容をもたらそうとしている。観想の訓練をおこなおうとするには、生き生きとした視覚的なヴィジョンにみちた像を、自分の前方ないし頭上の空間にありありと想起させ、また自分の身体そのものまで神々の純粋なイメージに変容させていかなければならないタントラ仏教は訓練のあらゆる場面で、この技法をフルに活用しているのである。
太陽や月や星あるいはロウソクの炎などを凝視する訓練も、それにおとらず重要な技法だ。それは意識を一定の対象に集中することによって、意識の内部でたえまなく立ち騒ぐ認識作用を静止にむかわせる。それはまた、外界の対象世界を静止像として固定するためにめまぐるしく動き回っている眼球の運動まで停止させていこうとするから、視覚による世界の構成作用にいちじるしい変化がもたらされるのだ。
(『チベットのモーツァルト』中沢新一著 講談社 2003 p148-149より抜粋)
もういっちょ。
「風の瞑想歩行」の訓練は、わたしたちをただちにタントラ仏教の身体論や意識論の心臓部にいざなっていく。それは、この歩行訓練が、「風の究竟次第」とか「管と風」などと呼ばれる密教身体論(それは同時に意識の本性をめぐる教えなのである)の核心にふれる重要なテーマを学んでいくのに必要な準備段階をなしているからである。
この瞑想歩行は、身体をめぐる意識に確実な変容をもたらす。この訓練は「内部の対話」を止めていく。間-主観的なディスクールが構成するリアリティの喚起力を静止に向かわせようとするのである。そのために「からだの重さをまったく感じなくなった」歩行訓練中の行者には、自分の身体とそれをとりまく世界とがまったく異なるように体験されるようになる。眼球が外にとらえている世界には、対象志向性をもった意識が構成する現実につきものの「人間味」のようなものが消えている。周囲の光景は「まるで夢の中に出てくるように」どこか超然としているし、それを見ている意識主体も奇妙な宙吊りの状態にある。しかも夢のなかとちがって、日常の客観的現実につつまれた身体感覚を失いながらも、身体はそれとは別種の直感的な意識の流れにしたがって、正確な実際行動をおこしているのである。
この歩行訓練は、身体が対象化のできるたんなる客観的リアリティではなく、そこを貫いていくいくつもの層に折りたたまれた意識の流れが構成する、これまた多層的なリアリティにほかならないことを体得させるために、絶妙の効果を発揮する。ことによると、身体が稠密な物質でできているという考えはまちがっているのかもしれない。それはこちたき幻影の皮膜として身体の本性をおおいかくし、もともとそこにあってそこを貫いている「風」のように軽やかな運動体を見えなくさせているだけなのかも知れない。(中略)
「風の究竟次第」の身体技法は、日常的意識がたえまなく「内部の対話」をつづけながらかたちづくっている稠密な表層的身体(表層的と言っているのは、それがのちに言語シンタックスに展開していくような二元論化する構造潜勢力のつくりあげる現象学的身体であるからだ)の脱ー客体化ということを、おしすすめる。そして同じ場所に、微細な差異の感覚をともないつつ運動し、流動していく無数の力線を見出し、そのダイナミックな現実領域に手違いなく踏み込んでいくためのテクノロジーをあたえていこうとしているのである。
(同書 p155-157より抜粋)
密教修行の記述が続くので、これだけ読んだ方は、「そめちゃんは一体どこに向かっとるんやー」と、少し戸惑うかもしれない。けれど、世界のとらえかたを変えるための方法のひとつのバリエーション、あるいは、現状の世界認識のありかたを対象化するために、まったく違うフィールドの知の体系に対して自分をひらくておくというのは必要なことだと思う。
話を写真に戻すと、先日、写真家とのやりとりの中で、「なんで自分がそれを撮ったのか自分でもわからない写真があって、それがおもしろい」という話がでていたことを思い出した。
撮った自分ですらわからないものに、そのときの自分が反応していた、という事実はとても興味深い。なにかを感じシャッターを押すにいたった経緯を言葉として整理できないまま、それでもなお、なにがしか「気にかかる」感触だけを残している。このことは、もしかしたら、ここで抜粋した「対象志向性をもった意識」からするっと抜け落ちたなにかを身体がひろった…とは考えられないだろうか。
2013-03-19
『チベットのモーツァルト』読了。
最近、かなり読書のペースが落ちているにもかかわらず、自分にとって必要な本にはうまく出会うものだなあと思う。
いきなり呪術とか聞きなれないことばが出てくるので面食らうかもしれないけれど、大事なことが書かれているので抜き出してみよう。
カスタネダによればこの老呪術師は人類学者にむかってつねづね、呪術というもののもっとも大きな課題は「世界についての考えを変える」ことにつきるとまで語っている。彼は「世界」のリアリティというものが、人々がおたがいに会話を交換しあう間-主観的な過程をつうじて構成されると考える現象学者と、とても似た考え方をもっていた。つまりドン・ファンによれば、わたしたちは子供の頃から「他人が世界とはこうこうこういうものだ」と話すのを聞いて育ったおかげで、一定の形式をそなえた世界についての考え方とか感覚を獲得してきたのである。言いかえれば、他者のディスクールを中継点にしながら、世界のとらえ方をかたちづくってきたわけである。しかもわたしたちはこうして意識の内にとりこまれた他者のディスクールとのたえまのない「内部の対話」をくりかえし、そのディスクールの秩序にしたがって「現実」なるものを不断に構成しつづけている。だから「世界がかくかくでありしかじかであるというのは、ひとえにわしらが自分にせかいはかくかくでありしかじかであると言いきかせているから」なのであって、多様なレヴェルでたえまなく流れつづけている「内部の対話こそがわしらを縛りつけているもの」にほかならない、とドン・ファンは言いきるのである。
だがその言いきりに関して、このインディアンの呪術師のほうが、同じことを主張するヨーロッパの現象学者よりもずっと自信にみち、さらにその先にある地点にまで踏みこんでいこうとする確かな手ごたえさえ感じられるのは、呪術師には現象学的認識を越えでていくのを可能にする確実な身体技法の伝統があるからだ。(中略)
じつを言えば、チベット仏教の「風の行者」たちの場合も、それと同じなのだ。彼らもただたんに超能力なんてものを身につけるために、こんな訓練をしているのじゃない。そこからよけいな仏教的外皮をさっぱりぬぐい去ってみれば、早い話が「風の行者」のめざしていることも「世界についての考えを変える」ことにほかならないからである。チベットの密教行者たちも、「現実」が多層的な構成をもち、またその「現実」の表層部分の構成にたいしてディスクールの秩序が決定的な重要性をもっているという現象学的思考を前提にしている。しかも彼らはさらに、幻覚性植物ならぬ精巧をきわめた瞑想の身体技法を駆使して「内部の対話」を止め、たえまなく流れつづけている「世界」の構成作用を停止して、ダイナミックな流動性・運動性にみちた別種の「現実」のなかに踏みこんでいこうとしている。
(『チベットのモーツァルト (講談社学術文庫)』 中沢新一 講談社 2003 p153-154から抜粋)
そんな大それたことばを使って考えたことはなかったけれど、自分が写真表現に携わるうえでやりたいと思っていることは「世界に対する認識をかえる」ことだと思っている。ガラッとではなくても、認識を少しズラすくらいのことでもできれば、現在あたりまえとされているものの見方(世界に対する考え方)を、多少は対象化できるのではないか、と思っていた。そして、日常の生活世界のかすかな破綻、亀裂のようなものを探すような方法を探ってきたと思う。
わたしは神秘主義者ではないし、西洋式のものの考え方にどっぷり身を浸しているほうだとは思うけれど、身体技法の獲得という方向からアプローチする、という方法は一考の価値ありだと思う。
というのも、ヨガの実践を通じて、ほんの少しの予備動作や運動イメージの持ち方によって、身体の可動範囲が広がったり、難しいバランスがとれたり、まさか自分がこんなことができるとは思わなかったことが、わりとあっさりできてしまうという体験をして、実はわたしたちは身体のごく限られた能力しか使っていないのではないか。逆に言えば、正しく修練すれば、違った身体のありかた、精神のありかた、ものの感じ方、にたどりつけるのではないか、と思うようになっていたからだ。
実際、いまのやりかたに行き詰まりを感じているし、方法を変えてみるというのは、安直な気がしないでもないけれど、もし修練のすえに違った世界認識や、世界の見えが得られるのであれば見てみたいと思うのは、視覚表現に携わる者として、まっとうな願いなのではないかとも思う。
2013-01-04
昨日、樂 吉左衞門さんの番組を見ていて、自然と同化するものを作りたいと思っても、土から何かを作り、何か表現をした瞬間、自然と相容れないものになっていくという話があって、磐座のことを思い出した。
はじめて磐座を見たのは、友人と一緒に自宅の裏の保久良神社に参詣したときのこと。
境内にある大きな岩の説明書きを読んだ友人が、「この岩、本殿よりよっぽど古いんだ。弥生時代だって。そのころからここは信仰の場所だったみたい。」と。
気になって周囲を見まわすと、不自然に大きな石が点在している。それだけのことなのだけど、そこには人為の痕跡が感じられた。
それからというもの、磐座が気になってしかたがなかったのだけれど、なぜなんだろうと考え直してみると、自然からモノを取り出して(磐座の場合は)並べるという、造形より手前の、いちばんプリミティブな人為(表現)をそこに見い出したからかもしれない。
表現というものの起源や、どうしてわたしたちは表現せずにはいられないのか、という疑問が、ずっと根っこにあるのだ。
新年あけましておめでとうございます。
毎年、新年の抱負を考えてみるのですが、今年は
のふたつをとことん肝に命じ、
イメージをモノに落とし込むところまで持って行きたいと思っています。
このところ、ああでもないこうでもない、とイメージをいじくりまわす、というのをやりぎた感じがしています。
あるいは、イメージをまぎれもないモノとして存在させてしまうことを、こころのどこかでこわがっていたのかもしれません。
こんなところで立ち止まっていないで、モノに落とし込んでみたら、そこから見えて来るものがあるのではないかと思っています。
まずは、結果が良かろうと悪かろうと引き受ける、気構えで、
逃げないで作品に向き合おうと思います。
昨年お世話になったみなさま、どうもありがとうございました。
そして引き続き今年も、どうぞよろしくお願いします。
2012-12-20
『リハビリの夜 (シリーズケアをひらく)』(熊谷晋一郎 医学書院 2009)を読む。
少し気になる文章があったので抜き出しておこう。
車いすに乗ったときに見える三次元の世界は、床に寝そべっていたころに見た二次元の世界とは異なる。それはただ単に、視点の位置が高くなったということだけではなくて、時間の流れの感じ方や、空間の広がりの感じ方にも変容をきたすものだ。
まず空間の〈近いー遠い〉という感覚について考えよう。
現在の私には車いすから降りたとたんに、それまで近くにあったモノが、急に遠くへ離れていってしまうような感覚がある。おそらく世界にある対象物への〈近いー遠い〉という距離感覚は、「対象との協応構造にあいた隙間」によって大きく影響を受けているように思う。
たとえば、協応構造の隙間が小さくてすぐにつながることのできる範囲、すなわち手を伸ばせば届く範囲が「近くの場所」で、息切れしない程度の移動でつながれるところは「少し離れた場所」、やっとの努力でつながれる場所は「遠くの場所」、努力してもつながれない場所は「向こう側」というふうに。
だから床の上に転倒した二次元の世界では、多くの人や、モノとのあいだに大きな隙間が生じるために、それらが遠くの場所や向こう側に存在しているように感じられる。二次元の私にとってモノたちや人々は、数十センチの至近距離にこない限り、私とは関わりのない遠くの存在なわけで、それは壁や天井と違いのない風景とも言える。
このように、協応構造にあいた隙間の大小によって空間の感じ方は変容する。その関係を整理するならば、「身体外協応構造の隙間が大きいものは遠くに、小さいものは近くに配置する」ということになるだろう。そして、空間の中で隙間が最も小さいのが「身体」である。
(前掲書 p169-p170から抜粋)
写真にたずさわるうえで、へだたり、遠近、ということについて、無関心ではいられない。ここでは、協応構造という専門的な用語が使われているが、距離あるいはへだたりの感覚が、単なる計量的なものではなく、生身の身体を介する「かかわりのもてなさ」としてマッピングされていることを、あらためて思い起こさせられた。
電動車いすに乗っているときの世界の感じ方は、乗っていないときとはまるで違う。さまざまな場所へ機敏に移動できるようになるだけで、外界との隙間が小さくなり、それまで自分には関わりのなかったモノや場所が、急に遠くから近くにやってきたような感じがして、空間の距離感覚も変わる。運動の変化量、ひいては世界の見え方の変化量が大きくなることで、時間の流れ方も早くなるような気がする。行動の選択肢が格段に増えることで、自己身体のイメージもより可能性を持ったものとして感じられるようになる。
このように電動車いすは、身体を含めた世界のイメージをすっかり変えてしまうのである。
(前掲書 p171から抜粋)
ここでさらに変数が増える。運動の変化量、時間の感覚。
ここまではっきり認識したことはないけれど、体調の悪いとき、からだをかばいながら少し緩慢に動いて撮影しているときは、普段立ち止まらないようなものにぐっと引き寄せられることがある。いつもとは違うものに呼び止められるような感じ。それは、さっさと機敏に歩いているのでは気づかないようなこと。
あるいは、移動手段が歩くのと、自転車に乗るのとだけでも、撮影対象もそこで撮る写真もまったく違ってくる。それが車になり飛行機になると、まったく次元が違ってくる。そう。運動の変化量が上がるにつれて、遠いものを撮ることが多くなる。こういった経験から、運動の変化量と距離感覚とに関連があることは、少し想像がつく。
それに加えて時間の感覚。著者は電動車いすによる、加速する方向の変化について書いているけれど、わたしにとっては、スロウダウンのほうがよりリアルだ。これも、体調が悪く緩慢に動くときの、じっと床を這うような時間の感覚をよりどころにするしかないのだけれど。
さまざまな場所へ機敏に移動できるようになるだけで、外界との隙間が小さくなり、それまで自分には関わりのなかったモノや場所が、急に遠くから近くにやってきたような感じがして、空間の距離感覚も変わる。
このフレーズは、今の自分にとってすごく大事な気がする。
そして、電動車いすは、身体を含めた世界のイメージをすっかり変えてしまうという文章の「電動車いす」を、車や飛行機にかえてみてもいい。
飛行機と車で移動しながら撮影をする写真家の作品を思い起こす。彼の作品のバックボーンは、その運動の変化量の大きさ。動力を利用することで、ヒューマンスケール(生身の身体)のリミットをはずしてしまったところにあるのではないか、ということを考えていた。
身体を含めた世界のイメージをすっかりかえるという経験を、身体感覚を研ぎすます方向で見いだそうとしていたけれど、運動の変化量をかえる、ということで得られるのであれば、これを試さない手はないだろう。
これはまだまだ、もっともっと時間をかけて考えていきたい。
2012-12-17
『リハビリの夜 (シリーズケアをひらく)』(熊谷晋一郎 医学書院 2009)を読む。
医学的な運動論かと思っていたら、官能を軸にして、運動や他者との関係性について語られていて、それがすごく新鮮だった。
規範からはぐれそうなときには体をこわばらせ、規範から解放されればほどける。そしてこのような、規範をめぐるこわばりとほどけの反復運動には、官能が伴う。
なるほど。たとえば文章であったり、ひとのありように色気を感じるとき、わたしはその対象のほどかれように官能を見いだしていたのだと、妙に納得した。
では、我が身は?となると、身構えているのが意識化されないくらい常態になっていて、ほどかれるというのはなかなか難しい。
そして、本書で何度も繰り返されるキーワードのひとつ《ほどきつつ、拾い合う関係》には、ものであれひとであれ、拾ってくれる他者が必要とされる。
2012-10-14

中沢新一さんの『精霊の王』を読んで以来、猿楽の祖である秦河勝をまつっている大避神社(兵庫県赤穂市坂越)に行ってみたいなぁと思っていたところ、10月の第2日曜日に船祭りを開催するらしいので、その祭りにあわせて出かけることにした。
猿楽の祖をまつっているといっても、大避神社の境内には、舞台のようなものはなく、境内じたいはシンプル。境内から坂越の浜と、神域とされる生島が見渡せる。
船祭りは、祭神である秦河勝が漂着した生島のお旅所へ神輿をお供する神事で、本祭の日は朝から船飾りがすすめられ、昼に神輿に大神さまの分霊をうつして、獅子舞を奉納し、船歌を唄い、頭人が拝礼をする一連の神事が執り行われる。それが終ると、一行は鼻高(猿田彦命)が先頭に、神社から浜のほうへ行列が繰り出す。

浜に神輿が着くと、神輿を船に載せるための板(バタ板)かけの練りがおこなわれ、無事神輿が乗船すると、漕船二隻が獅子船、頭人船、楽船、神輿、歌船を曳航して浦をぐるっと一周し、生島のお旅所へと向かう。

見どころは、和船の造作と、この祭礼船が、獅子を舞い、雅楽を奏で、船歌を歌いながら巡航する様子。この日は少し雲が厚かったので、色が少し沈んで見えたけれど、晴れた日なら、もっと綺麗に見えたのかもしれない。

日が暮れ、浜でかがり火がたかれるなか、生島での神事を終えた船が戻って来るのも、素敵な光景だった。
今年、国の重要無形文化財の指定を受けたが、それでも、少子化で漕手が少ないため、祭りのために坂越の出身者が東京や北海道をはじめ、全国各地から戻ってきて祭りに参加しているとのこと。大人も子どもも総出で、坂越の人々が大切に守ってきた祭りであることがよくわかるお祭りだった。
300年以上の歴史を持つ祭りだけれど、秦河勝が没したのが647年で、船祭りは江戸時代初期にはじまったと言われるから、その間に千年ほど経っている。なぜそのタイミングで祭りがはじまったのか、が気になるところ。

祭りと坂越の主要な産業である廻船業との間には深いつながりがあると、配られた資料に書かれていた。ちょうど今、読み始めている海民について書かれた網野善彦さんの本に、廻船業と芸能との関係について書かれていた箇所があったので、何かつながってきたらおもしろいなぁと思う。
最近は、中沢-網野両氏(この方々は甥と伯父の関係なのですね…)の著書の影響で、この国の歴史のなかで、芸能がどういう役割を果たして来たのか、とか、芸能民と呼ばれるひとびとがどういう人たちだったのか、ということにふつふつふつと興味が湧いている。
2012-10-10
本町ガーデンシティに坂茂さんのレクチャーを聞きに行く。いくつか気になったことを書きとめておく。
すごいなぁと思うのは、建築のディテールまでデザインする緻密で美的な作業と、コストから資材の再利用まで、さらには現地の雇用までを視野に入れたプランニングの両方ともができること。
何より、社会に対して(建築は、デザインは、写真は、自分は、)何ができるかという視点でものを考えるのを、ずいぶんさぼっていたなぁと気づかされるレクチャーやった。
2012-10-08
久しぶりの更新。
3連休の最終日、ふらっと神戸にお出かけ。
秋物のシャツを探しに元町のStjarnaに。
お目当ての黒いシンプルなシャツはなかったけれど、かわりに白い動きやすそうなシャツを購入。
店長さん、今日は朝から姪の運動会に行ってきたそうな。
姪は走るのが得意ではなくてすごく悔しそうだった、という話を聞いて、そういえば、走るのが遅いとか、大人だったら一週間もすれば忘れることでも、子どもにとってはすごく重大でとても深刻だったりするんですよね、ということを話す。
それから岡本に戻って、甥の誕生日プレゼントを買いにひつじ書房へ。
絵が気になっていたおばけの絵が表紙の本を探していると伝えると、店長さんが少し怪訝な顔をして「子どもをこわがらせるの、あまり良くないと思いますよ」とおっしゃられ、眠るときに読み聞かせる本だったら、こちらのほうがいいですよ、と「おやすみなさいおつきさま」という本を薦めてくださった。おばけの絵が表紙の本は子どもによっては怖がって破いてしまったりするそうな。
少し戸惑いながら、薦められた本を開いてみると、綺麗な色づかいで、うさぎが眠る前にいろんなものにおやすみなさいと挨拶していく本で、すごく愛らしく素敵だったので、迷わずこちらをプレゼントに。
こわがらされて眠るより、一日のなかでお世話になったものたちそれぞれに、順におやすみなさいを言って眠るほうがおだやかで良いよなぁ。
今日は「子どもは思っているよりずっと繊細な生きものだ」ということを思い出すための日だったのかもしれない。そして、自分のこころの在り様が、日に日に殺伐としていってるよなぁ…と思い知らされもした。
2012-08-07
無意識に排除しているものをひとつひとつ検証しよう、ということと、
撮ったものの画面の上で何が起こっているのかを、徹底的に見直すこと。
ささやかな気づきを、気づきのままで放置せずに掘り下げること。
この数日で思い改めたこと。
2012-07-08

読んでいた本の中で少し気になる文章を見つけた。それもごく最近、龍安寺の石庭を見に行ったところだ。
この庭には、砂と石と石にへばりついた苔しかありません。石は全部で一五個、大小の違いがあって、かりに庭を左右に分割してみることが許されるならば、左にある二群の石は、右にある三群の石よりも、全体的に大きいものが配置してあります。非対称にもとづく石組みの配置が、微妙な均衡をつくりだしているとも言えるでしょう。石はとりたてて特別面白いという形をしていません。むしろ平凡な石という印象のほうが強く、そこに座り込んだ人は、石そのものに関心を引きつけられるよりも、石と石の関係や、全体配置のなかでも個々の石の位置のほうに、注意がいくように配慮されているように感じられます。つまり、これらの石には「自性」がないのです。
(中略)
これをさきほどの、『華厳経』の思想について書かれた井筒俊彦の文章と比べてみると、仏教思想の構造と庭園の構造とがあまりにみごとに照応しあっていることに、驚かされます。この石庭のなかに置かれたそれぞれの石は、「自性」というものを持っていません。しかし、それぞれの石にはほかの石との関係から発生するところの、全体的関連性のなかでの独自性の感覚がそなわっています。無「自性」なのに、そこにはたしかにものがある、という存在感を生み出しているわけです。
ところが、そういう石が個体としての存在感を持ち出したとたんに、足許の苔がそれをあざ笑うかのように、個体性の幻想を解体してしまうのです。(後略)
(『対称性人類学 カイエ・ソバージュ 5 (講談社選書メチエ)』中沢新一著 講談社 2004 p195より抜粋)
「自性」のくだりがわかりにくいので、少し手前の文章も抜き出しておこう。
(前略)私たちのひとりひとりが、宇宙の中でのかけがえのないたったひとつの個体であることの認識から、仏教は出発します。ここで西欧的な思考は同じように、個体性のかけがえのなさの認識から出発して、個体の確立という思想に向かっていくでしょう。つまり、個体性というもののベースに潜在している非対称性を、あらゆる思考の基礎にすえようとするでしょう。じっさいアリストテレスはそうやって、個体性というものを自分の哲学の出発点にすえました。そうすると、非対称性の論理学を使って、多くのことが矛盾なく説明できるように思われたからです。
しかし、仏教はそこから反転して、この個体というものを対称性の思考の中に投げ込むことによって、非対称性と対称性の共存として発達してきた野生の思考の(バイロジック的な)知恵を、できるだけ完全なかたちにまで発達させようと試みてきました。(中略)自分はこの宇宙でたったひとつのかけがえのない存在なんだという、個体性の鋭い意識を保ったまま、すべてのもの(存在)のあいだに同質性をみいだしていこうとする対称性の思考を作動させることによって、宇宙のなかの極小部分としての個体や個人の自由ということについて、考えてみようとしたわけです。
そのことを最初に、意識的に表現してみせたのが『華厳経』です。そこではまず、仏教思想の基本にのっとって、ものには自性(そのものとしての本質)はない、という認識から出発します。ものとものを区別し、分離する非対称的な意識の働きを止めて、そこに対称性の思考を働かせるとき、高度な哲学的思考の試練をへている仏教は、それをたんに「同質的である」というのではなく、もっと哲学的に「自性はない」と表現するわけです。そのうえで、あらためて今度はものには自性はないけれども、しかもものとものとのあいだには区別がある、ということを言い出すのです。
(同書 p190-191から抜粋)
ここで自性についての記述を深く追うのは控えるけれど、仏教における、ものの存在についての抽象的な思考を、この石庭がたえず現象させているというところが肝要なのだと思う。
2012-06-01
昨日の「守宮神(宿神)」では少し寄り道をしてしまった。そもそもは、重森三玲の庭に興味を持って、中世から現在に至る作庭の、背後にある思想とか美意識を知りたいというところからスタートしたのだ。はからずも『精霊の王』に、その答えを見つけたように思う。長いけれど抜き出してみよう。
立石僧や山水河原者は、庭園をつくる職人だ。彼らのおこなう芸能では、ことはさらに抽象的に深められている。庭園の職人たちは、西洋のジャルディニエールたちのように、いきなり空間の造形にとりかかるのではなく、空間の発生する土台をなす「前ー空間」を生み出すことから、彼らの仕事を開始する。「なにもない」と観念された場所に、庭園の職人はまず長い石を立てることからはじめる。この石は伊勢神宮の「心の御柱」や「六輪一露」説に言う輪に突き出た短い杭と同じように、潜在空間からこちらの世界のほうに突出してきた強度(力)の先端をあらわしている。この先端の向こう側には、存在への意志にみちみちた高次元の潜在空間が息づいている。そして、この先端のこちら側には、人間が知覚できる三次元の現実空間が広がっている。庭園職人が「なにもない」空間に打ち立てるその立石は、まさに絶対の転換点となって、空間そのもののはじまりを象徴する。
空間に突き出した猿田彦の鼻のようなこの立石が、「前ー空間」を出現させる。立石の下には、宿神の潜在空間が揺れている。その揺れの中から、三次元をもった現実の空間の原型が押し出されてくる。そして、「六輪一露」説における像輪さながらに、この空間の原型を素材にして、庭園の職人たちはそこに、起伏や窪みや水流や陰影や空気の流れなどでみたされた、現象の世界の風景を造形するのである。
しかし、金春禅竹が像輪についての説明の中で語っているように、そうしてできてくる現象としての風景には、いたるところに「空」が滲入しているのでなければならない。庭園は目で見ることもでき、手が触れることもできる現実の空間にはちがいないのだけれど、その全体が宿神の潜在空間に包み込まれ、細部にいたるまで「空」の息吹が吹き込まれているために、向こう側のものでもないこちら側のものでもない、不思議な中間物質として、蹴鞠の鞠のように、どこか空中に浮かんているような印象を与えるのだ。
宇宙とか、大海原というレベルではなかった。「空間そのもののはじまり」という原初的で動的な現象を象徴するという、ものすごいチャレンジだったのだ。自分の認識をあらためなければならない。そして、自分の考えの射程範囲の狭さを痛感。今年はもう一度、庭園を見に行こう。
そしてもうひとつ気になったことがある。
たいがいの西洋庭園とちがって、このような宿神的庭園では、風景の全体を見通すことができないように、特別な工夫がこらされている。宿神の創造する空間は、つねに生じてくるようでなければならないからだ。そのために、それは出来上がった空間として、全体を見通せるようなものであってはならない。一歩歩むたびに、新しい小道が開け、新しい風景が眼前に生じてくるようでなければ、それはけっして宿神的空間とは言えないだろう。植物は人に見られるものではなく、逆に人が植物によって見られるようになる。前ー空間では主客の分離がおこりにくい。その影響が庭園のすみずみまで浸透しているので、このタイプの庭園を歩いていると、人はだんだんと主体としての意識を薄くして、瞑想的な静けさの中に入り込んでいくようになる。たしかにこれも「六輪一露」に説かれていたとおりのことではないか。
このように宿神を家業の守り神とする「諸芸」の職人や芸人たちのつくりあげてきたものは、どれも空間として特異な共通性をそなえているように見える。運動し、振動する潜在空間の内部から突き上げてくる力が、現実の世界に触れる瞬間に転換をおこして、そこに「無から有の創造」がおこっているかのようにすべての事態が進行していく、そういう全体性をそなえた空間を、職人や芸人たちは意識してつくりだそうとしてきたようなのだ。
(『精霊の王』中沢新一著 講談社 2003 p262-264から抜粋)
このくだりを読んだときに、以前、自分の展示において、どうしても「作品全体を一望できないように展示したい」という気持ちが強かったのを思い出した。
宿神の創造する空間は、つねに生じてくるようでなければならないからだ。
そのために、それは出来上がった空間として、全体を見通せるようなものであってはならない。
自分の制作が宿神の思想に直結しているとまでは言えないけれど、わたしに限らず、この国で生きて生活しているひとびとの、ものをつくり表現する営みの底には、かすかに宿神の思想が潜んでいるのかもしれない。
2012-05-31
先日の「幽玄」の続き。この文章に中世の芸能者や職人の思想が垣間見える。
(前略)もっと普通には、芸能の達人たちはこの神=精霊の実在を、超感覚ないしは直感的にとらえていたように思える。つまり、自分の身体や感覚を、三次元の物質で構成された空間を抜け出して、そこに守宮神が住むという柔らかく律動する特殊な空間の中につないでいき、その音楽的な空間の動きを自分の身体の動きや声の振動をとおして、観客の見ている普通の世界の中に現出させていこうとしたのである。
蹴鞠は蹴鞠の形をした守宮神(宿神)の助けを借りて、驚異の技を演じてみせようとした。ほかの芸能についても事情はほぼ同じで、「昔ハ諸道ニカク守宮神タチソヒケレバ」こそ、常の人の能力を超えた技芸の達成を実現することもできたのである。石を立てて庭を造るのにも、花を生ける(石の場合と同じように「花を立てる」、といったようだ)のにも、「諸道」の者たちはただ自分の美的感覚や造型の技術を頼みにすればよいというのではなく、それぞれの道にふさわしい守宮神の護りを得る必要があった。それはたんなる神頼みというものではなく、その神をとおして、それぞれの芸がどこかで「へその緒」のようなものをとおして、揺れ動く「シャグジ空間」につながっている必要を感じていたからである。そういう空間から立ち上がってきた石や花でなければ、霊性にひたされた芸能とは呼ぶことのできない、ただ美しいだけのただの物質的現象にすぎない、と見なされた。
(『精霊の王 (講談社学術文庫)』 中沢新一著 講談社 2003 p17-18より抜粋 原文は太字なし)
ここで出てくる「シャグジ空間」は先の記事では潜在空間と表現されていたものと同じである。では、このシャグジ空間とはどのようなものなのか。
あきらかに、守宮神が住処とする特別な空間の様式というものが、猿楽の徒には明瞭に直観されていたのがわかる。それは、神々以前からあって、神々を自分の中から生み出す空間である。しかも生まれたばかりの神々を優しく包んで、破壊されないように守る役目をしているのも、この空間だ。この空間には荒々しい霊威が充満している。それが神々の背後にあって発動をおこなうとき、前面に立つ神々も奮い立って、それぞれの神威をふるうことができるのだという。宇宙以前・空間以前からすでにあったコーラ Chola(場所)とでも言おうか、物質的諸力の影響を受け付けないシールド空間とでも言おうか、これはきわめて難解な構造をした力動的空間であって、猿楽者たちはそれを直観によってつかみとろうとした。
(同書 p22-23から抜粋)
守宮神=宿神の住む空間は、時間性と空間性において、私たちの知覚がとらえる時空間とは、ラジカルな違いをもっている。過去・現在・未来という時間の矢に貫かれながら進んでいく、私たちの知覚のとらえる時間の様式とは違って、「シャグジ空間」では時間は円環を描いている。そこには遠い過去のものと未来に出現してくるものとが、ひとつの現在の内部で同居しているのだ。また「シャグジ空間」は三次元の構成を越えた多様体としての構造をしている。そのおかげで、やすやすと鞠の表裏をひっくり返したりもできる。つまり、この世界にいながら、高次元の空間の内部に、するすると入り込んでいくこともできる。
(同書 p25-26から抜粋)
そして、この守宮神=宿神。その音韻の構造からも、胎生学的なイメージを擁している点においても、樹木との連関においても、諏訪のミシャグチと多くの共通点がある、と論は進み、こうまとめられる。
私たちがすでに見てきたように、宿神はこの列島上できわめて古い時代から生き続けてきた「古層の神」の一形態である。もともとは境界性をあらわそうとする「サないしス音+ク音」の結合として、さまざまに発音されてきた共通の神の観念のつながりの中から、宿神と呼ばれるこの芸能者の守護神はかたちづくられてきている。この「古層の神」はミシャグチの名前で、諏訪信仰圏では独自な発達をとげた。
(同書 p148から抜粋)
重森三玲の庭からスタートして、幽玄を経由し、宿神、そしてミシャグチと、気がついたら「古層の神」にたどり着いた。ずいぶん深追いをしてしまったけれど、ここまで来たのだから少しだけ寄り道をしたいと思う。
猿楽の先祖たちは、神仏の鎮座する空間の背後にしつらえられた「後戸」の空間で、その芸をおこたったと記録されている。薄暗いその一角を芸能の徒たちはものごとが変容をおこし、滞っていたものが流動をとりもどし、超越性のうちにこわばってしまっているものに身体の運動性を注ぎ込むための、ダイナミックな場所につくりかえていこうとしたのである。
そうしなければ、前面に立つ神仏たちの「霊性」が発動することはできない、と考えられていたからだ。「後戸の神」は神仏たちの背後にあって、場所を振動させ、活力を励起させ、霊性に活発な発動を促す力を持っている。それゆえ、日本人の宗教的思考の本質を理解するためには、折口信夫が考えたように、芸能史の理解が不可欠なのである。ここでは神仏は芸能的な原理と一体になって、はじめてその霊性を発揮する。
ヨーロッパ的な「たましいの構造」において、舞踊的・霊性励起的・動態的な原理が、「ディオニソス」の名前と結びつけられて、神性の構造の内部深くに埋め込まれていることは、よく知られている。ところが、私たちの「たましいの構造」にあっては、同じ舞踊的・励起的な原理は、神仏の内部にではなく、その背後の空間で活動をおこなうのである。ヨーロッパ精神が「入れ子」の構造をもつとしたら、私たちのそれは異質な二原理の「並列」でできている。そして、このことが、日本人の宗教や哲学の思考の展開に、決定的な影響をおよぼしてきたのである。
(同書 p96から抜粋)
一番驚いたのはこのくだりだった。
神仏の背後には古層の神(後戸の神)の空間があって、その震えや活力がなければ、神仏が霊性を発動できない…。そんな複雑だとは想像もしえなかった。
諸芸についても、すでに完成した宗教的世界観を表現するものだとばかり思っていたから、古層の神の空間と神仏を架橋し、神仏の霊性の発動を促すものとして芸がとりおこなわれたということに、かなり衝撃を受けた。
この国における芸能の位置づけということについては、またあらためてとりあげたいと思う。
ここでひとつとどめておきたいのは、わたしにはこの話が宗教だけ歴史の中だけの話にとどまらないように思えるのだ。わたしたちが日常的に交わしているやりとりの中の「場の空気を読め」という暗黙のルールの中には、「主体のあいまいな空間」を前提とする独特の考え方があるように思う。もしかしたら、そこには、神仏の背後に古層の神の空間を据えるような複雑な思想構造が大きく影響しているのかもしれないし、気づいていないだけで、もっとほかの局面においても、影響を受けていることがたくさんあるのかもしれない。
半年ほど前。写真とか視覚のことばかりを考えていて息がつまるというか、もう少し視野を広げようと思ったときに、ふと重森三玲の庭を思い出し、庭がただ庭としてあるのではなく、庭でありながら、より大きな存在を感じさせる構造をとっていることについて考えたいと思った。(「秘スレバ花ナリ」)
写真でも同じよう構造をもたすことができないだろうか?という野望をほんの少し抱きながら、彼の作庭の背後にある思想や美意識を知りたいと思って、三玲の著書『枯山水』を繙いた。そこではじめて幽玄ということばに出会う。その後で世阿弥の『風姿花伝』の現代訳も読んでみた。(「風姿花伝」)
正月に実家の裏にある保久良神社を参詣し、その裏にある磐座の存在を知った。ただ巨石がいくつか並んでいるだけなのに、なにかうっすらとひとの作為が感じられ、表現のいちばんプリミティブなかたちを見たような気がして、淡い関心を抱いた。ちょうどその頃に読んでいた『枯山水』のはじめのページに保久良神社の磐座の図版を見つけ、驚くとともに、磐座や先史時代に対する興味がいくぶん加速された。
それから半年間、磐座、縄文というキーワードに導かれて中沢新一さんの著書を読むようになり、仏教や神道が成立する以前のひとびとの精神世界に興味を持つようになった。そういう経緯で手に取った『精霊の王』で、はからずも、幽玄ということばに再会する。今回は世阿弥ではなく金春禅竹の『明宿集』の引用で。
幽玄という概念は、住輪に描かれた短い杭または嘴状の突起に関わっているということが、この記述からはっきりわかる。そこは潜在空間から現実世界に突き出した岬であり、特異点であり、この短い突端の部分で転換がおこっているのだ。猿楽の芸人はこの要所をしっかりと会得することによって、「幽玄」の表現をわがものとすることができる。無相無欲の清浄心をもって、この岬に立てば、現実世界に顕われることも潜在空間に隠れることも、自在である。
(中略)猿楽の芸は、三輪清浄として示されたこの潜在空間を背後に抱えながら、演じられるのである。本来が物真似芸(ミミック)である猿楽は、自然界のさまざまな存在をミミックとして表現する。そのときに、目に見えない潜在空間を背後に抱えた芸能者は、具体物でできた現象の世界を一体どうやって表現していったらいいのか。禅竹の思考はここからいよいよ深く猿楽芸の本質に迫っていくのである。(『精霊の王』中沢新一 講談社 2003 p234-235より抜粋)
目に見えない潜在空間を背後に抱えた芸能者は、
具体物でできた現象の世界を一体どうやって表現していったらいいのか。
この一文は、猿楽や作庭に対するわたしの認識をより鮮明にしてくれると同時に、思っていたほどことは単純ではない、ということも教えてくれた。
まずここで、作庭家や猿楽の芸能者は、
目に見えない潜在空間を背後に抱えながら具体物でできた現象の世界を表現する
ということがはっきりした。
しかし、作庭の場合で言えば、宇宙や大海といった(目に見える)ものを、石や砂で表現(あるいは象徴)している、というだけでは十分ではない。むしろ、目に見えない潜在空間と現実の世界をどう架橋するかに重きが置かれている。
この「目に見えない潜在空間」というのが、ものすごく深い。仏教や神道の成立以前の精神世界まで射程を広げないと、理解できないのだ。
特定の芸術分野(作庭)における思想や美意識を追っているつもりが、大変なところに合流してしまった…という感じ。
長くなるので、続きは後日。
2012-05-24
真っ暗な部屋に入ったときって、身体はガチガチになりますよね。本当はそういうときこそしなやかな身体であるべきなのに、真っ暗な部屋で、この先に何があるかわからないときに、人間は硬直してしまう。逆に、遠くまで見通せるときって、運動の自由度はすごく上がるでしょ。遠くまで見えると、肩の力を抜いて、すたすたと歩いていける。
これから自分が進む道についてはっきりとした下絵があると、下絵とまったく違うことができるんですよ。下絵の縛りがあると自由になれる。逆に下絵がないと何にもできない。何が起こるかわからないから、いつもどぎまぎしていて、思いがけない、ほんのわずかな、砂粒のようなものに蹴つまずいて転んでしまう。
ですから、「予祝」の「予祝」たるゆえんというのは、「予め」ということにあると思うんです。自分の身にこれから起こることに関してある種の予断を下してしまう。「私はこれからこうなる」と断定してしまう。これはすごく大事なことなんです。「『こうなる』と決めちゃうと、あとあと不自由になりませんか?」と訊かれることがありますけれど、そういうものじゃないんです。「私はこれからこうなる」と決めてしまうと、いくらでも変えられるのです。逆に「何が起きるかわからない」と思っていると、わけのわからないことが起きたときにコントロールできない。不思議なもので「決断」と「不決断」が同時に自分の中で行われている状態が一番生きる力が強くなっている。
(『現代人の祈り―呪いと祝い
』 釈徹宗 内田樹 名越康文 サンガ 2010 p61-62から抜粋)
選択の自由やあそび(機械などの少しの隙間のほうのあそび)の余地をと思って、いろいろ判断を留保してきたけれど、実はそれは自分で思い込んでいたほど前向きなものではなくて、むしろ、臆病になっていたのかもしれない。しばらくフリーランスを続けていたことで、つい「この先に何が起きるかわからない」と思って、計画を立てるのを避ける癖がついていたのだと思う。
逆に下絵がないと何にもできない。何が起こるかわからないから、いつもどぎまぎしていて、思いがけない、ほんのわずかな、砂粒のようなものに蹴つまずいて転んでしまう。
これは、ぐさっときたなぁ。
確かにそうなのだ。ほんのわずかな、砂粒のようなものに蹴つまずいて転んでしまう。
旅などで、なりゆきまかせが、本当になりゆきまかせになってしまうと、実はあまり実りがない(大枠を決めておいた方がうまくいく)ことが多いというのは経験済み。いろいろ留保しておくよりも、多少、不確定要素があっても、決められることはさっさと決めてしまったほうが自分もすっきりする…とつい最近、身をもって学んだところだ。
とりあえず、ひとつ決めよう。
2013年は必ずヨーロッパに撮影に行く。
そして少し時間をかけて、今後の生活の下絵を描こう。
2012-05-18
前に、友人とミラーレス一眼の話をしていたとき、否定的な意見の中で、友人のひとりは、映像の微妙な遅れを問題にし、わたしは液晶の像でピントをあわすことの難しさを問題にしていた。
今日、ふとその話を思い出したのは、ピントをあわせる最後の段階になると、「見る」のモードが、ものの肌理や質感を確かめるモードになっていることに気づいたから。
ピントがあっているかどうかの判断は、視覚というより、輪郭がキリっと際立つときに感じるザラっとした感覚、むしろ触覚に近い感覚をあてにしているといったほうが、正確かもしれない。
普通にものを見るときのモードではない気がする。だから液晶画面を介しても正確にその感覚が作動するか、を、すごく不安に感じている。
2012-04-24
母のところから拝借して寝しなに読んでいた『日本の文脈』(内田樹 中沢新一著 角川書店 2012)。サルトルとレヴィ=ストロースを比較した話の中で、少し気になる箇所があったので抜き出しておく。
(前略)レヴィ=ストロースの場合、まったく方向が違う。外へ出て行くんですね。自分の手持ちの理論や学説で説明できるものには興味がない。自分の理論で説明できないことに惹きつけられる。そこに自分の理論を適用するためじゃなくて、自分の理論を書き換えるために外部に向かう。植民地主義的に適用範囲を広げて行くタイプの知性じゃなくて、自分自身の足元を揺るがすような「未知のもの」に魅了される。(p152から抜粋)
二つの点で気になっていて、ひとつめは、外部との関わり方において、植民地主義的でない関係があるとすれば、どういう可能性が考えられるだろうか?という点において。
もうひとつは、まったくレヴィ=ストロースの話とは関係がないけれど、根本的にカメラを持って出かけるときは、自分の設定している思考の枠組みを揺さぶる何かに出会いたいと思って出かけているのだということを、あらためて確認した。
さすがに作品に落とし込む段階では、先にある程度枠組みをつくって、そこから被写体の条件を割り出して、その枠組みにおさめなければ成立しないのだけれど、それ以外では、それまでのことがすべてひっくり返されるような未知のもの、未知の光景に出会うために出かけているのだ。
気がつくと、カタログのようにある適用範囲内でバリエーションを集める作業に終始しているときもあって、そういうときはすごくつまんないなぁ…と思うことがある。そうではなくて、自分の写真や思考を書き換えるために外に出る、と自覚するとすっきりした。
また少し話がずれるけれど、ひととの出会いも同じだと思う。最近流行のルームシェア。わたしも学生の頃にルームシェアをしていたけれど、その友人の影響をとても受けたと思う。自分では当たり前だと思っていたことが当たり前ではないことを知って戸惑うこともあったけれど、自分のいろんなことが書き換えられた。それはまったく想定外のことだったけれど、自分が書き換えられるというのはものすごい快感だった。
それからは、ひとと出会ったり、何かを一緒にする醍醐味って、自分が書き換えられるような経験をすることにあるのではないかと思うようになった。だから、知り合う相手に最初からいろいろ条件をつけるのとか、つまんないと思うのだけど…。
2012-04-19
紅白梅図屏風の水面は、川の流れを抽象化した表現だとずっと思っていたけれど、これを見てると、けっこう写実的なんじゃない?と思った。

2012-04-03
重森三玲の『枯山水』を読んでから気になっていたので、市村宏さんが全訳注をつけた風姿花伝を読んでみた。
秘スレバ花のくだり、どうも文脈が少し違うみたい。
通釈によると…
1、秘する花を知るべきこと。秘すればこそ花で、秘するのでなくては花ではないのだというのである。このけじめを理解するのが大事の花なのだ。そもそもあらゆる事、諸道諸芸において、その家々に秘事といってあるのは、秘するによって大きな効果があるためである。それ故、秘事ということを白日の下にさらけ出すと、何も大したことではない。だが、これを大したことでもないという人は、未だ秘事ということの大きな効用を知らぬからなのである。
(『風姿花伝』 全訳注 市村宏 講談社学術文庫 2011 p200より抜粋)
この通釈だと、秘伝というシステムについて書かいた文章のように読めるけれど、重森三玲は「秘事ということの大きな効用」という点を文脈から切り離して、枯山水の象徴性にあてはめて書いているように思う。
とにもかくにも「秘事ということの大きな効用」というポイントは見逃せないなぁ。
風姿花伝、もっと抽象的なものかと思っていたら、観客を飽きさせない工夫や年齢相応の精進のしかたなど、意外なほど具体的な内容が多くて面白かった。
2012-03-25
ずっと前に、どこか良い川ないかなぁ…と友人に尋ねたときに、大川が良いよ!とおすすめされていたのを思い出す。桜の季節の前に確認しておこうと思って大川沿い(東岸)を歩く。
いくつか気になったことを書き留めておく。
次は西岸を歩いてみよう。
2012-02-19
写真の画面の中ばかりに意識が向いているなぁ。内に閉じていく方向に向かっているなぁと思ったときに、ふと、以前見た重森三玲の庭の、庭が庭だけで閉じずにもっと大きな世界につながっている感じを思い出した。
そして、それら庭園がどういう意図や美意識のもとに組み立てられているのかということを知りたくなって『枯山水』を繙いた。(重森三玲著 中央公論新社 2008)
読んでみて気になったのは、幽玄、見立てる、空白の3つ。
幽玄というのは、その表現の形式なり内容が、なんらかの形で、又は意味で隠されているものを指しているのであって、いわば本体の姿のままの形式や内容の、そのままの表現ではなく、全く異なった形や、内容として、別天地を創造した美の領域を指していることがことがわかるから(後略)(p70より抜粋)
この部分だけを抜き出してもわかりにくいと思う。ここで言っていることの具体例を枯山水に求めると、水に代わるものとしての表現材料として白砂を用い、また見る側も、砂を通して水を見いだそうとしていることが挙げられる。数個の石を立てて滝の表現とするのも然り。
砂を砂の美としてのみ創造もし、鑑賞もすることは、隠され、秘められている美がない訳であるから、これは幽玄ということはできないのである。
砂が水の表現材料として使われているからこそ幽玄であり、砂が砂としてのみ表現され、鑑賞されるのは、それは幽玄ではないのだそう。
このあたり、ものづくりをする際の素材と表現内容の関係を考えるヒントになりそう。
庭園においては、園池の池水は池水と見つつ、同時に海景に見立てているのであり、枯山水における白砂は白砂と見つつしかも水と見立てるのである。
象徴というと、西洋絵画のヴァニタスのような、死の象徴としての頭蓋骨や、加齢や衰退などを意味する熟れた果物を思い浮かべるけれど、ここで言われている「見立て」とはまた全然意味が違う。
何が違うのだろうか?
死や、加齢などは、抽象性が高いのに対して、海景や滝、水は具体的である。庭園においては、象徴とする対象もまた具体的なものであるというのが大きな違いではないか。
ここでもうひとつ面白い記述を見つけた。池庭は、基本的には海景を表現しているのであり、そこに置かれる石は島の表現であるが、
池庭の中島などに要求されるものの中に、雲形とか、霞形とか、松皮様などのものがある。池中の中島は大体において、大海の島嶼を表現することが意図されているにもかかわらず、この中島に、雲の形とか、霞の形などといったものを形式上に意図すること、(後略)(p78より抜粋)
とある。で、雲の形や、霞の形のものをどうするかというと、
雲形の中島の場合では、雲が風に吹き流されているような形として表現し、霞形の中島の場合では、霞が二重にも、三重にも棚引いているがごとき姿に作ることが主張されているのであって、(後略)
単純に池水を海と見立て、石を島と見立てるのにあるあきたらず、さらに島と見立てた上に、雲や霞の表現を求めるというのだ。中島を、石と見て、島と見て、雲(あるいは霞)と見る。すごい。
ここで、わざわざ雲が風に吹き流されているような形、霞が二重にも、三重にも棚引いているがごとき姿と書かれていることに気がつく。単に雲のかたち、あるいは霞のかたち、ではなく、雲(あるいは風)の動きや霞の動きを忠実に表現することに重点が置かれている。そう考えると、白砂が表現する波や水紋も、石を複数組み合わせて表現する滝も、水の動きを表現している。
石や砂といった基本的には動かないモノを材料とし、その形状によって、水や雲や霞といったまったく別のものを、その動きまでを含めて表現する。
ものすごく射程の広い話ではないか。
中島を、石と見て、島と見て、雲(あるいは霞)と見るように、同時にAと見て、Bと見て、Cと見るような構造を写真に持たせることは可能なのだろうか。
2012-02-11
水曜日のテレビ番組で、「行政の大きなお金を使って大きなモニュメンタルな建築をつくって、本当にひとのためになっているのか?と自問していたことや、難民キャンプや震災の現場で紙管の構造体が利用されたことで、建築がひとの役に立つことを実感した」という坂茂さんの話が印象に残っていた。
そして翌日、建築事務所を営む友人とご飯を食べながら話していたときに、その友人が、「最近、自分はかわってきたと思う。以前は綺麗なものが好きで、自分の設計した建物に趣味の悪いタンスが置かれてたらいやだなぁと思ったけれど、最近そういうのは気にならなくなった。むしろ、そこにひとがいることこそが大事やと思うようになった。」と言っていた。
どちらも、もの(作品)ではなく、ひとを中心に据えるというところで、共通していると思う。立て続けにそういう話を聞いたので、今日はずっとそのことばかり考えていた。では、写真はどうなのか?
もうひとつ、彼女に訊かれた「最終的にはどういうものを撮っていこうと思っているのか?」という問いも、意外と鋭く刺さっている。たぶん、いまの段階ではわからない。風景/ポートレイト/うんぬん…という既存の分類の中のひとつを選ぶような選択にはならないと思う。得手-不得手や、撮るもの-撮らないものはあるけれど、もっと違う分節の仕方をすると思う。その場では、そういうことをうまく説明できなかった。
彼女の問いはドキッとしたけれど、ものすごく嬉しかった。学生時代は仲間同士で相手の制作の核心に近いところまで遠慮なく切り込むことも多かったけれど、最近そういう問いを投げかけてくれる人はめっきり減った。
あるいは、わたし自身が避けていたのかもしれない。
2012-01-23

2010年の撮影分は明らかに使えないのではずして、2008-2009-2011の3年分のサンプルを作成。
2008年は17時スタート。2009年と2011年は18時スタート。当初は、もっとなだらかなグラデーションを描いて暗くなっていくものと思っていたら、ほんの数コマを撮っているうちにガクンと暗くなるということがわかった。
同じ風景でもつなぎ方でずいぶん違いが出てくることもわかった。
撮影するごとに気になることが出てきて、そのたびに改善はしているけれど、2008年から計4回撮っているので、もう仕上げの作業に入ろうと思う。スタートを少し早めにして、撮影のピッチを細かくする。
2012-01-11

2012-01-05

2012-01-04
紅葉の頃からものの色が気になってしかたがなくなって、よくある光景でも、こういうのは色が多くて少し目眩がする。

2012-01-01
保久良神社からの眺め。元旦の空と神戸の街。カラッと快晴という風でもないけれど、どんより、でもないから、まあいいか。
今年はいろいろ祈願をするというより「今年は昨年より少し前に進めますように」という心もち。わたしという個人においても、深いダメージを負った地域においても、そして日本という国においても。

2011-12-28

最近、ものの色が気になってしかたがない…
2011-12-02

これを撮りながら、モネの睡蓮を思い出した。水面に映る映像(木々)と、浮かんでいる紅葉によってかろうじて規定される透明な水面と、透けて見える川底の藻や石。実体と映像が交差していて、たまに自分が何を見ているのか混乱する。とりわけ写真では、ピントをどこにあわせるかを厳密に要求されるから、「何を見ているのか」を絶えず自問せずにはいられない。
2011-11-08
先日読んだホックニーの本でセザンヌのりんごが出てきたけれど(「りんご」)、また全然違う文脈でセザンヌのりんごが登場していたので、メモしておこう。前者においては、単眼で見た世界と双眼で見た世界の違いの例としてとりあげられていたが、ここでは、見る行為に含まれる原初的な経験(なぞる-なめる)との関わりで紹介されている。両者で共通しているのは、視点は一点に固定されていない、ということ。
(前略)なぞるためには、まずはそれに触れなければならない。舌を押しつけるのであれ、歯茎で齧るのであれ、唇で挟むのであれ、はたまた舌先や唇、さらには指先で間を測りながら、そっとつついたり、さすっとり、撫でたりするのであれ。なぞるのは、まず輪郭である。物の外皮、物の表面をなぞりながら、ひとはその形状を、つまりはそのカーヴを、テクスチュア(肌理)を、そしてその硬軟を知る。カーヴやテクスチュアや硬軟は、口や手といった触れる器官で知る。けれども、物のそのカーヴは、物の全体的な輪郭の一部であるからには、視覚的にこそより完全にとらえられるもののようにおもわれる。メルロ=ポンティはその点について、描画といういとなみにふれてこう言う。
林檎の輪郭を、続けて一気に描けば、この輪郭がひとつの物になるが、この場合、輪郭とは、観念上の限界であって、林檎の各面は、この限界を目指して、画面の奥の方へ遠ざかるのである。いかなる輪郭も示さなければ、対象から、その自同性を奪い去ることになるだろう。ただひとつの輪郭だけを示せば、奥行きを、つまり、われわれに、物を、われわれの前にひろげられたものとしてではなく、貯蔵物にあふれたものとして、汲み尽くしえぬ実在として示してくれるような次元を、犠牲にすることになるだろう。それゆえに、セザンヌは、色で抑揚をつけるに際して、対象のふくらみにしたがい、青い線で、いくつかの輪郭線を引くということになるわけだ。(M・メルロ=ポンティ「セザンヌの懐疑」粟津則雄訳)
対象をあやすように、愛おしむようにしてその表面をなぞる手の運動、まるでその奇跡を視覚的にたどり、再現しているかのような、ひょろひょろとしたセザンヌの描画の線。セザンヌの描く林檎のひゅっひゅっと走るあの無数のかすり傷のような輪郭は、舌で舐め廻し、指でなぞる、そういうわたしたちの原初的な知覚の轍のようにみえないこともない。三木の表現をあらためて引けば、そうした「目玉による舐め回し」には、口による、そして手による対象の舐め廻しの記憶が蓄えられている。そうしたことがあるから、メルロ=ポンティは、「われわれは、対象の奥行きや、ビロードのような感触や、やわらかさや、固さなどを、見るのであり—それどころか、セザンヌに言わせれば、対象の匂いまでも見る」とまで言い切ったのである。これは、視覚から触覚、嗅覚まで、異なる感覚とされるものがその実、単独の感覚である以前にまずはたがいに交叉しあい、また深く侵蝕しあう、シネステジー(共感覚)の現象を言いかえたものであり、さらにそのことを敷衍して、別の著書では次のように書いている。「質・光・色彩・奥行といったものは、われわれの前に、そこにあるものではあるが、しかしわれわれの身体のうちに反響を喚び起こし、われわれの身体がそれを迎え入れるからこそ、そこにあるのだ。この内的等価物、つまり物が私のうちに引き起こすその現前の身体的方式、今度はそれが、これもまた目に見える見取り図を生ぜしめないわけがあろうか」(M・メルロ=ポンティ『眼と精神
』滝浦静雄・木田元訳)、と。
(『「ぐずぐず」の理由
』 鷲田清一著 角川選書 2011 p132-134より抜粋)
セザンヌに関する記述だけ抜き出したけれど、その前段には、以下のような文章がある。
乳を吸う、味わうといういとなみに飽いてくると、つぎに赤子は口で外界の探索をはじめる。いやというほど物を舐め、しゃぶり、くわえ、齧る。人間のばあい、外界の物は、まずはしゃぶること、舌と唇と歯茎でなぞることで知られるのだ。
幼児たちは、やがてこの口の過程を卒業し、もはや内臓とは関係のない「手と目」の両者だけで満足するようになってくる。そこでは、この二種の触角による“撫で回し・舐め回し”の感覚・運動の共同作業が営まれるのであるが、そのうち、ここから“手を退き”、ついに目玉という、たった一つの触角でもってこと足りる世界が開かれて来ることになる。
しかし、重要なことはその次にある。たしかにひとは、まずは口で、次に手で、そして眼で「舐め回す」ようになるのだが、「この最後に残った目玉による舐め回しの奥底には、かつてえんえんと続けられてきた本物の“舐め回し”の記憶が、そこではかけがえのない礎石となって、そうした視感覚をしっかり支え続けている」。
(同書 p131-132より抜粋)
これに関して、少し思いつくこと。
2011-11-04
カメラのチェックしてたら、半年前の写真が出てきた。薄明かな。

2011-11-02

2011-11-01

2011-10-23

今福龍太さんの『レヴィ=ストロース 夜と音楽』を読んで、気になっていた一冊『人種と歴史
』(クロード・レヴィ=ストロース 荒川幾男訳 みすず書房 1970)。
込み入った部分は消化不良気味だけれど、2点気になった箇所を挙げておこう。特にひっかかったところを太字にしておく。
諸々の人類文化が、相互にどのように、またどの程度異なるのか、その相違は互に消しあうのか対立しあうのか、あるいはいっしょになって調和ある全体をなすのかどうか、を知るには、まずその明細目録をつくってみなければならない。だが、まさにここから困難がはじまる。というのは、諸々の人類文化は、相互に同じ仕方で、また同じ平面で異るのではないことに気づかざるをえないからである。われわれは、まず、あるいは近くあるいは遠く、しかしいずれにしても同時代に、空間に並列された諸社会に出会う。次には、時間のなかで継起し、直接体験をもっては知ることのできない社会生活の諸形態を考慮に入れなければならない。(中略)最後に、《野蛮》とか、《未開》とか呼ばれる社会のような、文字を知らない現存の諸社会も、やはり、たとえ間接的な仕方をもってしても実際には知ることのできない別の諸形態が先行していたことを忘れてはならない。良心的な明細目録は、それらに対して、何ごとかを記録しうると思われる欄の数よりも、おそらくずっと多くの空欄をとっておかねばならないのである。(p11-12から抜粋)
「同じ平面で異るのではない」というのが、しっくりきた。他者というのはそういうものなんだと思う。人類文化というほど大きな枠組でなくても、比べようにもそもそもの構造がまったく違うということがままある。他者との差異に関しては、そのくらい「違う」こともありうると思っておいたほうが良いということには薄々気がついていた。そして、自分のモノサシでははかれない、あるいは自分の感覚では感受できない「なにか」があるかもしれないということをあらかじめ勘定に入れておくことも。「何ごとかを記録しうると思われる欄の数よりも、おそらくずっと多くの空欄をとっておかねばならない」
卑近な話になるけれど、友人であれ恋人であれ、人と知り合って関係をとり結ぶことの醍醐味は、他者のあり方に自分が影響を受けることだと思う。ときに他者との差異によって苦痛を感じることもあり、ときに、自分自身が大きく変わらなくてはならないこともある。そして、どれだけドラスティックに変われるかは、相手との差異のあり方に関わっている。世界を受けとめる構造からしてまるごと違う方が、影響の受け方も深い。そういうことをぼんやり考えていたところだったから、この文章に反応したんだと思う。
もう一点は、
もっとも古くからある態度は、自分のものだとする文化形態にもっとも遠い道徳的、宗教的、社会的、美学的な文化の諸形態を、無条件に拒否するもので、それは、思いがけない状況におかれたとき、われわれのひとりひとりのなかにまたしても現れでてくるのだから、おそらく固い心理的基盤に立っているのであろう。《野蛮人の習慣》、《それはわれわれのものではない》、《それは許されるべきではなかろう》等々、われわれとは縁のない生き方や信仰の仕方や考え方に当面して、これと同じような身震い、嫌悪をあらわす粗野な反応がいっぱいある。こうして、古代は、ギリシア(次いでギリシア・ローマ)文化に属さぬものを、すべて同じ未開barbareの名のもとに一括した。次いで、西洋文明は、同じ意味で野蛮sauvageという言葉を用いた。これらの形容詞の背後には、同様の判断がかくされている。すなわち、未開(バルバール)という語は、語源的に、人間の言葉の意味値に反する鳥の啼声の不分明と不文節に関連しており、野蛮(ソーヴァージュ)という言葉は、人類文化に対立する動物生活の分野を思わせる。この二つの場合、ひとは、文化の差異という事実すら認めることを拒んでいるのである。自分たちが生きる規範と同じでないものは、すべて文化の外に、すなわち自然のなかに投返そうとするわけである。
この素朴だが大ていのひとの心に深く根を下した見方は、ここで論ずる必要はない。というのは、この小冊子がそれをきっぱりと反駁しているからである。ここでは、この見方が、なかなか意味深長なパラドックスを蔵していることを指摘すれば足りよう。この、人類から《野蛮人》(あるいはそう思うことにしたものすべて)を除外する思考態度は、まさに当の野蛮人自身のもっとも顕著な特有の態度なのである。(中略)アメリカ発見の数年ののちに、大アンティル諸島では、スペイン人が原住民が魂をもっているかどうかを調べるために調査団を派遣したのに対して、原住民たちは、かれら白人の死体が腐敗を免れるものか否かを長い間見届けて確かめるために、白人の捕虜を水葬にすることにしたのである。
この異様で悲劇的な挿話は、文化的相対主義のパラドックス(それは本書の別の個所で別の形でも問題にしよう)、をよく示している。つまり、自分が否定しようとするものともっとも完全に一致するのは、諸文化や慣習の間に区別をもうけようと主張する場合だというわけである。その文化ないし慣習をもっているもののなかでも一番《野蛮》で《未開》にみえるものに人間性を拒否しておいて、かれらの典型的な態度の一つを、他ならずかれらから借りているのである。(後略)(p16〜p18から抜粋)
「ひとのことをバカと言うひと(のその行為)がバカなのよ」と昔よく親に叱られた。このようなパラドクスに陥る危険は、身近な生活の中にも潜んでいる。
2011-10-16
ホックニーの本を読んでから、また少し絵巻のことが気になって、高畑勲さんの『十二世紀のアニメーション―国宝絵巻物に見る映画的・アニメ的なるもの』を取り寄せた。合点がいくところと、絵巻の技術の妙にうならせられるところがたくさん。
まずは、『信貴山縁起絵巻』で絵画としては奇妙な構図がなぜ採用されているのか?という箇所。
『信貴山縁起』の、鉢の外に導かれた倉は画面上端を大きくはみだして飛び、米俵の列は上端ぎりぎりに沿って遠ざかる(飛倉の巻)。また尼公は、空白に等しい霧の画面の下端を、見逃しそうな大きさで歩む(尼公の巻)。とくに尼公と米俵の列は、その場の主人公であるにもかかわらず、画面の隅に小さく押しやられているだけでなく、まるで紙の端でその一部が切断されたかのようだ。
これらの大胆な表現は、その箇所を抜き出してただの静止した「絵画」として鑑賞すれば、いかにも奇妙で不安定な構図に見えかねない。
しかし、絵巻を実際に繰り展げながら見進んでこれらの箇所に出会えば、なんの不自然さも感じないばかりか、この不安定な構図表現こそが、物語をありありと推進していく原動力となっていることに気づく。
なぜこのようなことが起こるのだろうか。
それは、ひとことで言えば、連続式絵巻が、アニメーション映画同様、絵画でありながら「絵画」ではなく、「映画」を先取りした「時間的視覚芸術」だからである。
映画では、人物が画面を出たり入ったりする(フレームアウト・フレームイン)。しばしば人や物を画面枠からはみださせ、背中から撮り、部分的に断ち切る。ときには空虚な空間を写しだす。映画では、たとえ画面の構図を安定させても、そのなかを出入りし動くモノ次第で、たちまちその安定は失われてしまう。
右に挙げた二例も、絵巻を「映画的なるもの」と考えれば、まず、モノ(尼公と米俵の列)抜きの構図があって、そこをモノが自由に行き来して構図の安定を破るのは当然なのである。
(『十二世紀のアニメーション―国宝絵巻物に見る映画的・アニメ的なるもの』高畑勲 徳間書店 1999 p51より抜粋)
ここで2点。
以前、展覧会を見られた方から、「一本のシネフィルムを見るようでした」という感想をいただいていたことを思い出した。
観者の意識を細部に誘うために「全体を一望できないかたちで展示して、見ているのが部分でしかないという認識を観者に持たせる」という目論みだったのが、制作者の意図を越えて、観者に「時間性」を感じさせた。展示をしてみてはじめて、時間性というキーワードがわたしの認識にのぼった。が、そもそも絵巻という形式それ自体が、時間性を持っているということを確認したのが一つ。
もうひとつは、絵巻から離れるけれど、ずっと以前に、動画を撮って再生と静止を繰り返して、被写体が見切れる構図は、写真の世界ではあまり見かけない構図やなぁと新鮮に感じ、実験を繰りかえしていたことを思い出した。(「見切れるフレーミング」)動画のコマを前後の脈絡から切り離して、一コマだけ抜き出して写真として見ようとすると、とても奇妙に見えるのだ。動画が要請する構図と、静止画が要請する構図は、まったく異なるものだということをここで再確認。この件は、もっと掘り下げる余地がある。
絵巻は、動画が要請する構図を採用しながらも静止している、というマージナルな存在であり、だからこそ絵巻の特徴をつぶさに観察することで、静止画(あるいは動画)の形式が暗黙のうちに要請し、わたしたちが盲目的に従っている文法のようなものを明らかにできるかもしれない、と思う。
2011-10-09
300mmあたりをカバーできる望遠ズームを探してカメラ屋さんに行く。デジカメのボディを持って行って、4種類のレンズをつけかえて壁をパシャ。8mくらい先の壁にかかっている商品のパッケージ。こうして見てみると描写にずいぶん差があるもんだなぁ…とつくづく思う。

いちばん左が古い設計で順に新しくなって、いちばん右が最新の設計だそう。4種類の中で一番古い設計のやつが、いちばん鮮明(で、いちばん安かった)。やっぱり実際にテストしてみないとわからんもんです。
2011-09-22
(前略)西欧人である民族学者によって見出される「未開社会」、という不可避の植民地主義的構図を、結局は彼自身がブラジルにおいて追体験し、言説として再生産するほかなかったという事実への苦い反省が込められている。
伝統文化の消滅に力を貸しながら、一方で知的ノスタルジーとともにそれを戦利品として展示・消費する西欧文化=学問の近代的な「しつけ」(ディシプリン)にたいし、レヴィ=ストロースほど自責の念にかられ、またそれにたいして倫理的な潔さを貫いた人類学者も二〇世紀においてはいなかった。小著ではあっても、西欧近代の人種主義の偏見と前進的歴史への過信にたいする激烈な批判である『人種と歴史』(一九五二)が、『悲しき熱帯』に先立って刊行されていることの倫理的意味を、わたしたちは再度確認しなければならないだろう。過去のフィールドへの追憶に浸る前に、彼は民族学という学問の根にある植民地主義と進歩への幻想とを、明晰にえぐり出しておく使命を感じたのだろう。
(『レヴィ=ストロース 夜と音楽』今福龍太著 みすず書房 2011 p46より抜粋)
以前清水穣さんの講義で聞いた、写真のモダニズムの話をふと思い出した。目に見える世界の向こう側には、手つかずのありのままのまっさらな世界、タブラ・ラサが存在するという、写真のモダニズムが前提とした世界観は、そのまま植民地主義の構図に置き換えられるという話。その話は目から鱗だったし、同時に、とても怖かった。無批判に作品をつくることの怖さ。そのとき、特定のイデオロギーを強化することに、意図せず加担するようなことにならないためにも、自分にも、自分のつくるものに対しても批判的でありつづけることが必要だと切実に思った。
レヴィ=ストロースが反省や自責の念を抱えながら、ブラジルとどう関わり続けたのか。まだ彼の著書を読んだことがないので、『人種と歴史』から順を追って読んでみようと思う。
2011-09-15
『秘密の知識』の中でカラヴァッジョの『果物籠』(1596)と、セザンヌの『7つのりんご』(1877-8)に描かれたりんごを比較している箇所がずっと気になっている。
図版を置いて、そこから離れて見れば見るほど、カラヴァッジョのりんごは見えにくくなり、画面に沈み込んでいく。逆に、セザンヌのりんごは、より強烈により明快になっていく、という記述。前者がレンズを通した単眼によって描かれているのに対し、後者は双眼による視覚を前提に描かれているという。
実際に自分も本を置いて離れたところから眺めてみて、なるほど、と思った。あまり話が抽象的になると、話についていけないことがあるけれど、こうやって実際に経験しながらであれば理解しやすい。
まず、離れて見てみてそこで現象することを捉えるという、こういう観賞の仕方があるということをはじめて知る。そして、写真に携わっているので、単眼による視覚と双眼による視覚の違いについては、どうしても関心を持たざるを得ない。「レンズという単眼による独裁の世界」という表現にはちょっと違和感を感じるけれど。
(前略)セザンヌの新しさは視点が定まらないことを意識し、ということはわたしたちは対象をつねに複数の、ときには矛盾する視点から見ていることを自覚したうえで、絵のなかに画題と自らの関係にまつわる疑問をもちこんだところにある。ここには人間らしい双眼の世界(二つの目、二つの視点、それにも伴う疑念)が展開している。それとは対照的に、レンズという単眼による独裁の世界(ベラスケス)は、つまるところ人間を数学的な位置に還元し、かれを空間、時間と切り離された位置に固定してしまう。
(『秘密の知識
』 青幻舎 2006 p190より抜粋)
2011-09-07
先日読んだ、ホックニーの『秘密の知識』に、絵巻に関する記述があったので、メモしておく。
ここに1347年に中国で描かれた風景画の絵巻がある。本ではページを捲ることになり、巻物のように少しずつ繙くことはできないので、部分ごとに分けてお見せするしかない。これはアルベルティの窓とはちがう。これを見る者は情景の外側にいるのではなく、身近な風景の中をそぞろ歩くのである。視点は(ただひとつでなく)多数ある。これはわたしたちが歩き回るときの視点のあり方と変わらない。
わたしの手許にある絵巻は、湖の辺の小さな村を見下ろす景色から始まる。そこから水辺へと降りると、湖面越しに彼方の山並みも望める。つづいて湖畔沿いに蛇行する道を行くと、頭上には山が聳え、小さな渓谷も目に入る。丘を昇り、湖を見下ろし、再び平野に下り、再度山に登る。ただひとりのひとがゆっくり巻物をひもといて初めて、このように目で見、感じることができる。巻物をすっかり拡げてしまえば、また美術館の催す展覧会ではそうならざるを得ないが、こうした効果は期待できず、風景はどことなくぎこちなく見えてしまう。図版をよりよく見るには虫眼鏡を使うことをお薦めする。わたしはこの絵巻からじつに多くを学んだ。この手法は[移動焦点の原理]と呼ばれる。この絵巻を原始的と呼ぶのは、どう考えてもふさわしくない。これは洗練を極めたもので、もしどこかに消失点があれば、それは動きを止めたこと、つまり見る者がもうそこにはいないことを意味すると気づかされる。
(『秘密の知識』 ディッド・ホックニー 青幻舎 2006 p230から抜粋 太字はわたしが勝手に)
要点をまとめる
・鑑賞者は画面の外側にいるのではない。身近な風景の中をそぞろ歩く
・視点は多数ある
・図版をよく見るには虫眼鏡を使うこと
・消失点があれば、それは動きをとめたことになる
《RIVERSIDE》のことを「大きな絵巻なんだね」と表現されたことがあって、それから絵巻の特徴や構造について、少し考えるようになった。
実は、作品化されずにお蔵入りのフィルムがいくつかあって、視界を遮るものがなく遠景まですぅっと抜けて見えてしまう風景の場合、絵としてあまりおもしろくない、というのがボツにした理由だけれど、この文章でひとつヒントを得た気がする。「消失点があれば、それは動きをとめたことになる」。消失点への求心力が、視線の水平方向の運動を妨げるということは大いに考えうる。ボツフィルムをもう一度見直して、考えてみようと思う。
「移動焦点の原理」というタームでgoogle先生に尋ねてみたけれど、芳しい回答が得られない。「移動焦点の原理」は、原文ではどうなっているんだろう。掘り下げて調べたいところ。
ひとつ言えるのは、カメラ(単眼)を使って絵巻構造の作品をつくるというのは、本質的な矛盾をはらんでいるということ。
2011-09-06
おもしろいのは、アングルの肖像画(1829)を見たときに、フォルムが正確で精密なわりに素早い線で迷いがなく、さらに、ウォーホルがプロジェクターを用いて描いた作品の描線に似ているという、画家ならではの気づきからこのプロジェクトがスタートしているところ。
オールドマスターの作品を年代順に壁に並べることによって、自然主義の歩みが緩やかに進行したのではなく、突然の変化として現れたことが明らかになる。そして、その急な変化は、線遠近法の登場だけでは説明しきれない点が多いこと。さらに、画面中に、ピンぼけ、遠近法の歪み、複数の消失点など、光学機器ならではの特徴が見出されたことで、光学機器を利用したという仮説につなげていく。
絵画なのにピンぼけが確認されたり、線遠近法に基づけば一つしかないはずの消失点が2つ存在したり。いわゆる”エラー”に光学機器の存在がチラリ垣間見えるのが興味深い。
さらに、本来上から見下ろす視点で描かれるべきものが、なぜか正面から見た図となっているという点に着目し、当時の光学機器では広範囲を一度に映写できないため、人物ごと、あるいは部分部分に分けて描きコラージュしたのではないか?という説が浮上する。
あくまで仮説の積み重ねであるが、最終的には、
西洋絵画の根底をなすもっとも重要な二つの原理、つまり線遠近法(消失点)とキアロスクーロは、光学的に投影した自然の映像観察から生まれたことを理解した(p198)
というところまで進んでいく。線遠近法を獲得したことにより新しい空間表現が生まれたのではなく、まず先に光学的に投影された映像があって、そこから線遠近法が生まれたという。
さて、ちょうどこの本を読んだ直後に『カラヴァッジョ~天才画家の光と影~』という映画を観た。映画の中で、画家は平面鏡を利用していた。ホックニーは、鏡に映ったものを見るのと、鏡が投影したものを見るのはまったく違うという。
果たして画家はどのようにして描いたのだろうか。
2011-09-02
David Hockneyの『Secret Knowledge(秘密の知識)』を精読する。
彼の仮説は、
というもの。すでに確証されたフェルメールのカメラ・オブスクーラの使用より、はるかに早い時期に光学機器が用いられており、それがかなりの影響力を持っていたという。いずれも仮説なので、ことの真偽は留保しておくにしても、とても興味深い内容だった。
前からカメラ・オブスクーラの存在は知っていたけれど、わたしはごく一部の画家が部分的に用いた補助的な道具というニュアンスで受けとめていた。著者は実際に、明るいところにモデルを座らせ、暗い部屋でその像を写しとる実験をしている。その実験の様子を見て、はじめて「光学機器の使用」がどういうことかを理解した。
暗い部屋の中で、紙の上に投影された映像の輪郭をなぞっていたのだ。それは描くというより、写しとる作業に近い。画家が独自の線を生み出すという思い込みが崩れた。わたしにとっては、光学機器の使用がはじまった時期云々より、画家の光学機器の使い方が明らかになったことのほうがよっぽど衝撃的だった。
印画紙が発明されるまで、いわば画家たちはカメラの中で映像を画布に写しとっていたということになる。写真のフィールドからすると、射程に入れるべき映像の歴史が4世紀ほど前倒しになる可能性が出てきたのだ。
カメラが19世紀に発明されたと誤解している人は少なくない。カメラは発明ではなく、自然現象である。暗い部屋の雨戸に小さな穴が開いていれば、それだけで光学的な映像の投影はごく自然に起こる。カメラ・オブスクーラとは文字通り「暗室」を意味する。レンズも鏡も必要ではない。ただしそのままでは映像は薄暗いか、ぼんやりしているか、あるいはその両方である。大きな開口部にレンズを取り付けると、映像はずっと明るくなり、ピントも鮮明にあわせることができる。「写真」の発明とは、じつはカメラの内部に投影される情景を定着する化学薬品の発明にほかならない。しかしカメラのなかに投影された映像は、写真以前の何百年にもわたり、人びとの目に触れてきた。
(『Secret Knowledge(秘密の知識)
』David Hockney著 青幻舎 2006 p200から抜粋)
2011-08-13

友人と一緒に滋賀県の竹生島へ。
学生の頃に一度訪れる機会を失したこともあって、すごく気になっていた都久夫須麻神社(つくぶすまじんじゃ)。
まずは宝厳寺の本堂で、弁才天にお参り。芸能の…ということなので、念入りにお参りする。少し階段を下りて、立派な唐門から入り、船廊下を渡って、都久夫須麻神社へ。
船廊下の端で、宝厳寺と都久夫須麻神社が妙にきっぱり分けられているのが不思議だったので自宅に戻ってから調べると、もともとは神仏習合だったものを明治の神仏分離の際に「宝厳寺」と「都久夫須麻神社」に分けたのだそう。なるほど…
伏見城の遺構とも言われている都久夫須麻神社の本殿。2009年以降一般の参拝客には中は非公開とのことで、外から見えるところだけじっくり拝見。木彫装飾の過剰な感じが印象的。
鳥居に向かって土器をなげる「かわら投げ」を楽しんでいると、船の出発時刻が近づいてきたので、慌てて下山。船のスケジュールで70分しか島に滞在できないけれど、丁寧に見てまわるには90分は欲しかったな。
2011-08-01

友人に譲ってもらったminoltaのフィルムカメラを持って撮影にでかける。
contaxのRTS2がオシャカになってからだから、久しぶりのフィルムカメラでのスナップ。電池も不要のこのカメラは、露出を自分で設定しないといけないから、うすぐもり、露出が安定している今日みたいな日は撮影しやすいと思う。
シャッター音が、ちゃんと機構が働いている音のようで清々しい。仕上がりを見てみないとわからないけれど、けっこう相性の良いカメラだと思う。
フィルムも現像料もどんどん高くなっていって、いずれフィルム撮影が「道楽」と呼ばれる日が来るのだろうけど、フィルムカメラが要求する作法が、普段なおざりにしていることを見つめ直すきっかけにもなるので、わたしにはまだまだ必要なものだと思う。
2011-07-30
昨年中にどっさり蓄えた体重をなんとかしようと思い週2のペースで泳ぎはじめて早4ヶ月。プールって意外と無言のコミュニケーションが発達する場なのだと気づいた。
同じコースにいる相手のスピードと自分のスピードを勘案して、スタートするタイミングを調整してくれる人と同じコースになると、ペースを乱されずに長く泳げる。滅多にないことだけれど。
自分より遅いひとのときは、スタートを少し遅らせて相手との距離を稼いでおくとか、自分より早いひとの邪魔にならないように、良いタイミングでうまく抜かしてもらえるように相手の位置に応じてスタートをズラす。自分のスピードとまわりの人のスピードを客観的に比較できないといけないし、けっこう頭脳戦。
コースの端と端。話をするわけでもアイコンタクトをするわけでもないけれど、ちゃんと調整してもらっているときは、がぜん泳ぎやすいので、そのことがとてもよくわかる。直接コンタクトを取るわけではないけれど、うまくいったときだけは、コミュニケーションが成立している実感がある、不思議なコミュニケーションだ。
2011-07-25
思っていたより晴れていたので、一部夕陽が逆光になる場面あり。少し撮影ポジションをズラして対応。建物の窓に反射する夕陽に対応するのが難しかった。歩行者、自転車の往来が例年より多かった。
2011年7月23日(土)
17:50〜21:30
絞り8.0
シャッタースピード 1/60〜2min
79コマ(有効数70くらい)
2011-07-11
アウラとは、時間が映像を燃えあがらせ、音を立て、その音を消し去るときに作用する何かを名ざしている。それは、ベンヤミンが「視覚の無意識」と呼んだもの、すなわちプンクトゥム、盲点、可視的なものにおける接触と距離の盲点へわれわれを召喚して、危険と破滅の淵にさらすのだ。
だがアウラとは、十九世紀には写真のある種の技術的問題、それもかなりやっかいな問題も意味していた。じつはその問題は、間接的にではあるが、ベンヤミンが語ろうとしていたことにもまさしく関連している。
それは光暈と「ヴェール(かぶり)」の問題である。ある被写体が、よく理由のわからないまま偶然光の輪で取りまかれてしまうという、発光現象、あるいは光を防衛する現象の問題である。これは映像内に遠方が過剰に取り込まれることに関係するのだろうか。しばしばそのように考えられ、その過剰の理由が求められてきた。「なぜ写真は遠方を過剰に取り込むのか」が問われてきたわけである。
これはまた、写真におけるスペクトルの問題、「スクリーン」と、ヴェールのかなたの啓示の問題、すなわち写真の魔術的で、悪魔的、涜神的な性質そのものの問題である。それは最終的には距離を隔てた接触という問題である。写真はそのあらゆる既知事項を覆したのだ。なぜなら写真に関しては、光のタッチや痕跡というのは虚辞ではなくなるのだから。以上のことを、医師イポリット・バラデュックの作品につかのま足を止めつつ描き出してみよう。(後略)(『アウラ・ヒステリカ―パリ精神病院の写真図像集
』 J・ディディ=ユベルマン著 谷川多佳子・和田ゆりえ訳 リブロポート 1990 p132〜p133から抜粋)
ところで、子供は神経質な女性に劣らず「感じやすい(感光しやすい)」存在である。ある日バラデュックは自分の息子を撮影した。その子はたまたまこのとき、幼い両手のなかに雉の死体、それも殺されてまもない死体を持っていた。誰がその死骸を彼の腕に置いたのか、父親はわれわれに告げてはいない。いずれにしろその映像は、ヴェールがかかったふうに現像された。
精神科医のバラデュックは、そこに、魂が帆に風を孕んだような状態が何か別の光によって乾板上に描き出されているのを見てとった……。こうしてアウラが初めて彼の眼前に現れたのである。この日を境にバラデュックは、アウラがその全貌を明らかにするまで、飽くなき探求を続けることになった。(後略)(同書 p134より抜粋)
(前略)彼はそれを「魂の運動と光」のカテゴリーとして包摂した。なぜ魂の運動かといえば、魂とは軌跡をもたない運動、したがって分離を伴わない距離、距離を隔てた接触を可能にするものだからである。なぜ魂の光かといえば、アウラとは、内在的で、霞んだ、不可視の、しかしながら(非常に感光しやすい乾板を用いさえすれば)図示できるものだからである!
(同書 p135より抜粋)
アウラは図示できる?!
わたしがはじめてアウラという言葉に接したのはベンヤミンの著書であり、もっと抽象的なものと思っていた。こんな具体的な現象のことなの?と混乱したので、ここで少し整理してみたい。上述のバラデュックがアウラを図像化した『人間の魂』を著したのが1896年。ベンヤミンが『複製技術時代の芸術』を著したのはそれからおよそ40年後の1936〜1939年とされている。つまり、ここで書かれているのはベンヤミン以前の話。「アウラ・ヒステリカ」ということばも、精神科医シャルコーにより、ヒステリー発作の前兆をさして名づけられたが、それも19世紀のことである。
いま現在、作業をしていてかぶりの現象が見られれば、撮影環境を調べたり、レンズや機材に不備がないか、ということをまず考える。それに比べると、バラデュックはずいぶん奇妙なとらえ方をするようにも思えるが、その差こそが、19世紀と21世紀の社会における写真の受容のされ方の違いなのかもしれない。かぶりの現象がどこか魔術的な意味あいを帯びて捉えられていることや、「なぜ写真は遠方を過剰に取り込むのか」という問いのうちに、19世紀の社会において写真がどのように受容されていたのか、その一端が垣間みえるようで興味深い。
もう一点、気になったのは、サルペトリエール病院で、写真の実践が病院の一部門(service)の高みにまで昇ったことについての記述。
service(部門)とは、それにしても恐るべき小語である。そこにはすでに隷属(servitude)と虐待(sévice)の意がこめられている。私の問いは単に写真が何に奉仕(servir)したのかということにとどまらない。サルペトリエールで、誰が、あるいは何が、写真映像への隷属を強いられたのかも問うているのだ。
(同書 p73より抜粋)
この本では、映像(写真)を生み出す過程で、ときに搾取の構造をとったり、ときに共犯関係をとりむすびながら、医師と患者たちがどう巻き込まれていったかということが描き出されているが、ふと、隈研吾さんの『負ける建築』の一節を思い出した。
写真という二〇世紀メディアは、二〇世紀建築のデザインの方向性を逆向きに規定したのである。
かたや建築、かたや精神病院の症例写真だが、写真というメディアの特性が、単に属性としてその内側に大人しくとどまっているのではなく、それをとりまく人やものに力学的な影響を及ぼしているという点で共通している。そう考えると、写真とは何かという問いを、写真の内へ内へと探るだけではなく、写真をとりまくものとの関係の中にも、何か見えてくるものがあるのかもしれないと思った。
『アウラ・ヒステリカ―パリ精神病院の写真図像集』
思いのほか写真論の色が濃かったけれど、19世紀〜20世紀の精神医学の進歩が社会にもたらした影響についてもっと明るければ、より得るところの多い本だと思う。今のところ、このあたりがわたしの限界なので、時間を置いてもう一度読み直したいと思う。
2011-06-04
毎日コツコツ英語の勉強をしていると言いはっているので、ちょっと母の単語帳をのぞいてみる。
skip out…夜逃げする
become a beer belly…ビール腹になる
…この単語、いつ使う気なんやろか。
2011-05-22
最近また‘身体’に関心が戻ってきて、パラパラと読んでいた本のなかに、少し苦いフレーズを見つけた。
(前略)詩として成立する言葉と成立しない言葉がある。その違いというのは直感的にしか言えないことなんだけれど、詩にならない言葉というのは「うるさい」と谷川さんは言うんです。「わたしが、わたしが」と言い立てる詩は、どんなに切実であっても、うるさい。たった三行でも、「わたしが、わたしが」と言いつのる詩はうるさい。逆に、言葉が、詩人の「わたし」から離れて、自立している言葉というのは、言葉自身が静かで、響きがよいということを言ってらした。
今の若い人たちが、単一の「自分らしさ」をあらゆる場で押し出すというのは、谷川俊太郎的に言うと「うるさい」ということですね。そのうるささ、その不愉快さというのは「礼儀正しくない」とか「敬意がない」というようなレベルのことではなくて、「わたしが語る」ということそのものの不快さなんです。
(『身体(からだ)の言い分
』内田樹 池上六朗著 毎日新聞社 2009 p24・25より抜粋)
後半の若いひとたちが…のくだりでイメージされているのは、キムタクが扮する若者役に代表されるような若者像だと、ほかの著書で読んだ記憶がある。たしかに、彼の役柄はいつもいつも鼻についた。だから話はよくわかる。それでも、不思議なことに、自分のことばかり話していても、それが鼻につくひとと、つかないひとがある。その違いはどういうことなんだろう。
自分の目の前でしゃべっている人が、正直者か詐欺師かって必ずわかりますよね。わかるのは、結局、相手のメッセージを受信する時に「コンテンツ」を聴いているわけじゃない、ということです。何を聴いているのかというと、メッセージの「送り方」を聴いている。正直な人がまっすぐに語っている言葉は直接深く入ってくる。それは言葉の内容が理解できるできないとは別の次元の出来事なんですね。わからないけど、わかっちゃう。頭を使っているわけではないんです。もっとトータルな関わりですよね。
(同書 p83より抜粋)
メッセージのコンテンツではなく送り方を聴いている、というのは面白い。
なぜかこのひとの話は聞いてしまう、ということもあるし、
逆に、このひとの話すことばはまったく響いてこない、ということもある。
「わたし、わたし」というコンテンツでも、余裕なく切羽詰まった様子で話されるのと、本人自身が客観視できる程度に余裕を持って話されるのでは、受け手には違って聞こえてくるのかもしれない。大事なのはむしろメッセージの「送り方」のほうなのか。
きっと(芸術)作品においても、コンテンツだけでなく、作品の差し出し方まで、
観賞者にまるごと観られているのだろう。実際、視覚表現領域でもコンセプトを押しつけてくる作品は「うるさい」。
だから、ここらへんの話は、うかうか人ごととして読んでいられないのだ。
2011-05-06
リアリズム的でイリュージョニズム的な芸術は、技巧を隠蔽するために技巧を用いてミディアムを隠してきた。モダニズムは、技巧を用いて芸術に注意を向けさせたのである。絵画のミディアムを構成している諸々の制限—平面的な表面、支持体の形体、顔料の特性—は、古大家たちによっては潜在的もしくは間接的にしか認識され得ない消極的な要因として取り扱われていた。モダニズムの絵画は、これら同じ制限を隠さずに認識されるべき積極的な要因だと見なすようになってきた。マネの絵画が最初のモダニズムの絵画になったのは、絵画がその上に描かれる表面を率直に宣言する、その効力によってであった。印象主義はマネに倣って、使用されている色彩がポットやチューブから出てきた現実の絵具でできているという事実に対して眼に疑念を抱かせないようにするために、下塗りや上塗りを公然と放棄したのだった。セザンヌは、ドローイングとデザインをキャンバスの矩形の形体により明確に合わせるために、真実らしさと正確さを犠牲にしたのだった。
しかしながら、絵画芸術がモダニズムの下で自らを批判し限定づけていく過程で、最も基本的なものとして残ったのは、支持体に不可避の平面性を強調することであった。平面性だけが、その芸術にとって独自のものであり独占的なものだったのである。支持体を囲む形体は、演劇という芸術と分かち合う制限的条件もしくは規範であった。また色彩は、演劇と同じくらいに、彫刻とも分かち持っている規範もしくは手段であった。平面性、二次元性は、絵画が他の芸術と分かち合っていない唯一の条件だったので、それゆえモダニズムの絵画は、他には何もしなかったと言えるほど平面性へと向かったのである。
(『グリーンバーグ批評選集』藤枝晃雄編訳 勁草書房 2005 p64・p65より抜粋)
(前略)古大家の作品は一点の絵として見える以前に、その中に存在するものが見られる傾向にあるのだが、一方モダニズムの絵画は、まず最初に一点の絵として見えるのである。もちろんこれは、古大家のものであれモダニストのものであれ、どんな種類の絵画でも最高の見方なのだが、モダニズムはそれを唯一の必須の見方として強いるのであり、モダニズムがそうするのに成功することは自己-批判に成功することなのである。
(同書 p66・p67より抜粋)
(前略)古大家たちは、ひとがその中へと歩いて入っていく自分自身を想像し得るような空間のイリュージョンを作り出したが、一方モダニストが作り出すイリュージョンは、人がその中を覗き見ることしかできない、つもり、眼によってのみ通過することができるような空間のイリュージョンなのである。(同書 p70より抜粋)
このあたりのことは大学の講義で聞いていたはずなのに、すっかり記憶から抜けている。もう一度、マネやセザンヌの作品をきちんと見たい。できれば、モダニズム以前の作品との比較で見たい。
これらはモダニズムの絵画についての記述だけれど、では写真において、ミディアム・支持体・平面性といったものに対して、(モダニズム如何にかかわらず)どういうアプローチがなされてきたのか。そして、モダニズムの下の写真とはどういったものであるのか。
2011-04-02
予想するとか、仮説を立てるというのは大事だけれど、ものをつくるにあたっては、とにもかくにも、やってみないとわからない。ということが多い。
でも、経済合理性を優先して、できるとわかっていることだけ、時間の予測がつくことだけをやっていると、つくるものが、どんどん、ちまちま、つまんないことになっていく。
失敗してもそこから学ぶだけの余裕をもつ。
失敗をおそれず取り組む勇気を携える。
最近の作業を顧みて思ったこと。
最終更新から6ヶ月以上経っているなんて…
パウル・クレー展に行きたいなぁと思って調べていたら、少し本を読んでみたいと思って。以下、メモです。
入手困難なものもあるので、手に入るのから。環境の変化を理由に、ずいぶん長い間、思考が停止してる。
2011-03-23
すいません。
2011年3月現在、神戸市に住んでおります。
関西に帰ってきてるので、どうぞよろしく☆
お知らせもせぬまま転居を繰り返してしまって、わたしの居所がわからない方もおられるようなので、念のためお知らせします。
2011-02-01
いつもはつくる側だけれど、大きな予算を用意してつくってもらう側に立つことになって、見えたことはすごく多い。
400社ほどの制作会社の実績に目を通して、そこから絞って絞って、打ち合わせに臨んでみて、最後にお任せしたいと思ったのは、若いひとたちが活き活きと仕事をしている会社だった。
人数も少なくて、他社よりリスクもあるけれど、可能性を感じたのと、何より、この人たちと一緒に仕事をしたら楽しいだろうな、この人たちにつくってもらえたらうれしいな、と強く思った。
逆に、話が金銭のことに終始している会社にお任せしたいとはまったく思わなかった。
自分たちのやっている仕事を本気で楽しんでいる人たちは、本人たちが思っている以上に、そのことがクライアントに伝わっている。
そういうことが実はすごく重要なポイントだということに、あらためて気がついた。
つまるところ、クライアントも人なのだ。
2011-01-19
「そもそもmusicに音を楽しむなんて意味はないのよ。日本人が勝手に音という字と楽しむという字を充てただけで、楽しもうとなんてしなくていいの。」
中学生のころ、声楽の先生に言われたことを思い出した。
これから音楽の世界を志そうと思っている中学生にとっては、酷なことばに思えた。
でも、photograph(photo 光の graph 描かれたもの)に‘写真’ということばをあてがった際に前提とした「真を写す」という考え方が、そののちもたらした影響の大きさを考えると、ことば自体を疑ってみるというのも、悪くないのかもしれないと思う。
画像、という呼び方のほうがよっぽどシンプルだしね。
2011-01-08
都度転送されてくる年賀状。
つくづく賀状ってよいものだなと思った。
年に1度でも、相手のことを「覚えている」サインを送る機会があるのは好い。賀状がなかったら、とっくに切れていたご縁もたくさん。賀状でかろうじてつながっているご縁は意外と多い。
広島で、映画監督を目指す後輩。
地元ともだちの近況。
退官された恩師からのあたたかいことば。
きっかけがなければ、つながる機会のないひとと、ひとときつながる貴重な機会。
たった10ヶ月。Uターンどころかヘアピンカーブと母に揶揄された東京滞在。あまりにスピーディーに居所がかわるので、転居のお知らせすらままならず。それでもご縁がつながっていられるのは、賀状のおかげだと思う。
2011-01-04
明けましておめでとうございます。
「今年の抱負は?」と妹に尋ねられて、「口のかたい女になる」と真剣に答えたのに、「だめ。やりなおし」と一蹴される。
おみくじは大吉。
人生、ちょっと期待しちゃおかなぁ…と、ゆるい滑り出しですが、2011年もどうぞよろしくお願いします。
ところで、電気工学科同窓生のみなさまに連絡です。
河崎 善一郎先生(カミナリの先生)が2/5のワンダーワンダーにご出演されるそうです。どうかお見逃しなく!
はるかエジプトから、年始にメールをいただきました。
2010-12-05
東京にいるうちにやりたい10のこと。
のひとつ、バッハのコーヒーをいただきに南千住に向かう。

いつもと違う方角にスカイツリーを眺める。
以前バッハを訪問したことのあるナオエちゃんから、「バッハは西成みたいな雰囲気の街にあるんだよ」とは聞いていたけれど、たしかにこの街並は新世界を思わせる。スカイツリーもこの方向から見ると通天閣に見えなくもない。
もちろんオーダーはぺルー。
思ったより温度が高くてびっくりしたのだけれど、すごく芳醇で美味しかった。
飲み終わる頃、キツい香水をつけたイカツい革ジャンのおっちゃんが隣に座るや否や、「ドンパチ・ゲイシャ」と頼むのを聞いて、耳を疑う。
ドンパチ?ゲイシャ?
棚を見ると「パナマ・ドンパチ・ゲイシャ」という瓶が。
ドンパチ…ゲイシャ…
あまりにハマりすぎというか、どうしてそんなネーミングなのか…気になって仕方がないので、帰宅してからネットで検索。
パナマにあるドン・パチ農園のゲイシャ種だそうです。
(ドンはドン・コルレオーネのドンと同じで、ゲイシャはエチオピア南西部にある地名「Gesha」が由来)
なるほど。おっちゃんのイカツさとは何の関係もなかった。ちなみに、ドンパチ・ゲイシャは他の豆より数段高い豆でした。
2010-12-04

Barnett Newmanの作品を観るために千葉の佐倉を訪れた。
遠かったけれど、ちょうど紅葉の季節なのが幸い。
はじめて訪れたのは、12年前。
エジリちゃんと一緒に閉館間際に駆け込んだのを覚えている。でも何を観たのかさっぱり覚えていないというあたりが、だらしない。
Barnett Newman展、
全体的には、作品点数が少なく、遠くから足を運んだだけにもの足りなさを感じる。作品の中では、版画の作品の微妙な赤の差と、《アンナの光》の色とそのスケール感が印象に残った。
“大切なのはサイズではなく、スケール”
閉館時刻ぎりぎりまで粘っていたら、外はすっかり影絵の時間。

2010-11-21
あっと言う間に秋も深まり。
えっちゃんと駒込で合流。
六義園のライトアップに行くつもりが、ライトアップには早いので、スペインバールに入ってしまう。まぁ、この方と会うと、だいたいどんな企画でも早い段階で酒が入るんだわな。
都合3時間半、ワイン片手にたわいもないことを話す。
大学時代の同級生女子は、「単位取得率の高い順に結婚しとる」という偉大な(?)法則を編み出す。結婚は計画性の問題なのだろうか。
本題の六義園のライトアップは、残念ながらまだ色づきはじめ。
「葉は赤くなっとらんが、わしらが赤くなっとる!」とはようゆうてくれたもんだ。横でえっちゃんが一生懸命葉が色づいているところを想像してるのが可笑しかった。
東京滞在もあと2ヶ月となると、会っておきたいひとと会うのに忙しくなってきた。来週末はナッちゃんとこに寄せてもらう。生まれたての赤ちゃんとの対面。楽しみでござる。
2010-10-24
先週に続き、会期末に追われるように、SCAI THE BATH HOUSEに名和晃平さんの展示 Synthesis を観に行く。2度目なのにすっかり道に迷ってしまう。そんなときに目についたのがエントツ。
そうか、BATH HOUSEだから、エントツを目指せばいいのだ。
名和さんの展示を観るのはメゾンドエルメス以来。
平面の作品をはじめて見る。
でも印象に残ったのは、立体の作品のほうだ。
パッと見たときに、あれ?前に観た鹿の作品かな?と思ったら、違うのだ。
微妙に位置をずらした二重の鹿になっている。(2匹の鹿ではなく二重の鹿ね)
画廊の用意したテキストにはコピー&ペーストとあるが、まったくその通り。立体版コピペ。
とてもいい案配で位置をズラしてある。
長らく業界の話題となっていた「オリジナルとコピー」という二項対立を前提から揺さぶる。その手際の鮮やかなこと。そして、像といったときのボリュームを持った実体としての「像」と、いとも簡単にコピペできてしまう映像としての「像」の、どちらともとれるような存在の仕方が強く印象に残った。
すごい作品だった。
18時の発送をもって、やっと作業がひと段落。
かねてからの目標であった「ちくわぶ」という、関西ではあまり見かけない妙な食材を調理する機会がやってきた。(周囲の関西出身者からは評判の悪い食材だが…)
おでんって、ちゃんと作ろうと思ったら下ごしらえがけっこう大変。大根はお米の研ぎ汁で下ゆでし、じゃがいもはふかしてから皮を剥いてしばらく冷蔵庫に寝かせる(ただいま寝かせ中)。出汁をとったり、ゆで卵をつくったり…と、コンロはフル稼働状態。こんな手間のかかるのは時間があるときでないとできないからなぁ。
ということで、作業が終った開放感を、おでんづくりで満喫。
でも怖くて「ちくわぶ」にはまだ手をつけていない…
2010-10-16
今日が会期末。山本現代で開催されている高木正勝さんの映像作品。イメネ。
清澄や、京都の下京みたいに、ここも、ひとつのビルの中に複数のギャラリーがフロアごとに運営されているスタイル。
やはり作品を見ていて考えさせられるのは、「わたしたちがものの質感をどういう風に感じているのか」ということ。
液体のねばりけなんかは、そのてりっと光る加減だとか、とあわせて、ぬちゃっという音や、どろっとした動きの緩慢さなど、複合的な情報でその質感を感知しているのだと思う。
その液体がさらっとしているか、どろっとしているか、ということは、動いているところを見ることではじめてわかる「質感」なのかもしれない。
そういう動きによって生まれる質感が映像としてめまぐるしく変化するさまが印象的だった。
実体がないのにもかかわらず、映像の動きによって質感だけが立ち上がったり、あるいは、被写体自身のもつ質感とはまったく別の質感が、映像の動きによってもたらされるのは、すごくマジカルなことだと思う。
大容量の画像データを扱うにあたって、さすがにメモリ1Gはしんどいので、電気街に出かけて増設用のメモリ4Gを購入。パソコンのパーツショップだから仕方がないのかもしれないが、客が男性100%のその店舗におそるおそる入店。なんだか妙に緊張。
それから、きびすを返し、山本現代に展覧会を見に行く。
そして帰り際、オシャレ男子オシャレ女子+外国の方がたが列をなすマルイチベーグルでお昼ごはんのサンドイッチを買う。そのオシャレっぷり…電気街とのあまりの違いに軽く目眩を覚える。
帰宅してさっそく、メモリ増設。512MB×2→2G×2にパワーアップ。
突然そんなことをする気になったのは、所長の「iMacのHDD入れ替え武勇伝」に触発されたのかもしれない。
今回のパワーアップ作戦は、外付1.5TBのHDD増設とメモリ3G増設でしめて17,000円ほど。いっときに比べたらやっぱり安いよなぁ…
さ、これから作業しよ。
2010-10-13
5キロのさつまいも。フロム KAGOSHIMA。
これを受け取るために、そそくさ帰宅したのだよ。
「いも5キロ送るよ」という妹からのメールに、深く考えずに「はいはーい」と返事をしたが、その時点ではいも5キロがどのくらいの量か想定できていなかった。多い…
2キロの米を食べるのに数ヶ月…5キロのいもって…
ま、こぶりなので、小腹がすいたときに、ちょこっと焼き芋にして食べるには良い。でもやっぱり多いなぁ…さつまいも料理のレパートリーを増やそう。まわりのひとにお裾分けもしちゃおう。
まだ焼きいもしかしてないけれど、実においしいです。そして、よく見ると箱に書いてある文字もなんだか愛嬌があってかわいらしい。
九州物産のお礼に、今度チョコレートバーガーでも送ろかな。
2010-10-10
モザイクが守るのは、被写体ではなく、往々にして作り手の側である。それを掛けてしまえば、できた作品を観た被写体からクレームがつくことも、名誉毀損で訴えられることも、社会から「被写体の人権をどう考えているのか」と批判されることもない。要するに、被写体に対しても、観客に対しても、責任を取る必要がなくなる。そこから表現に対する緊張感が消え、堕落が始まるのではないか。
(『精神病とモザイク タブーの世界にカメラを向ける (シリーズCura)
』 想田和弘著 中央法規 2009 p53より抜粋)
そして、精神病院の様子をモザイクなしで映し出した作品『精神』について。
実は、僕と配給会社は、『精神』の広報活動の戦略を練る際、テレビを含めた日本のメディアが、映画やそれに出ている患者さんたちをセンセーショナルに、いわばホラー映画のように扱うことを、最も警戒していた。そのための対策も、いろいろ議論したりした。
ところが、それは僕らの杞憂に過ぎないことが分かった。メディア側はむしろ、映画の登場人物やその近親者を傷つけたり、彼らから反感を買ったりしないよう、細心の注意を払っていた。腫れ物に触るがごとく、警戒していた。
そして、そういった態度は、患者さんの顔にモザイクが掛かっていないことにこそ起因していることは明らかだった。モザイクが無いので、映画を取り上げる彼らにも被写体に対する責任が生じ、やりたい放題するわけにいかないのである。
(同書 p216より抜粋)
この文章の最後のほうに「モザイクを掛けないことが、実は被写体のイメージを守っているという、その逆説」とある。
モザイクのくだりについては、なるほどな、と思った。
つくり手の率直な言葉で綴られていて、好意的に読んではみたのだけれど、文章を読む限りにおいては、主題である患者の生きざま、よりも、それを「モザイクなしで見せること」に、作家が執心しているように感じられ、そのことに少し違和感を感じた。
なによりまず作品自体を見てみないと…。
2010-10-05
カメラ屋に行って、3Dデジカメで遊んでみる。いやぁ、おもしろいわ。
手前に物体A、奥に物体Bがあるとすると、AとBとの前後関係がすごく強調されて、AとBの間にある奥行きの空間はすごく意識されるんだけれど、AとBそのものの奥行きや量感があまり感じられなくて、物体そのものはペラリンとした感じ。
不思議だ。
ステレオ写真とかが流行った時代の視覚が、復権してきたともとれる。ちょっとおもしろくなりそう。
2010-10-03
(前略)とりわけ、十九世紀に入って地球全体が世界資本主義の網の目にとらえられていく過程では、生産力の向上、技術革新、国際的規模での分業体系の深化、商品輸出や資本輸出のための市場争奪戦と帝国主義戦争の勃発、第二次大戦以降ではとくに西欧資本主義国間の貿易競争や商品開発競争の激化、といった現象が次から次へと展開し、この過程にまき込まれる個々人の日常生活は多忙をきわめるだけでなく、人生の浮沈も激しい。個人の人生は、経済という戦場で闘う戦士の人生のごときものであって、こういう個人に要求される資質は身体頑健、決断力、つねに生き生きしていることであり、つまるところ、若さである。経済戦争は老人ではやりぬけない。戦士は、つねに青年であり、せいぜい年をくってもかぎりなく青年的な壮年者でなくてはならない。経済戦争に耐えることのできないものは、たとえ若者であっても、老人であり、本物の老人がこの戦いで勝ちぬける見込みははじめから閉ざされている。近代や現代の経済生活では、老人であることはつねにマイナスの価値であり、老いの価値ははじめから極小値をとる。
偏見をはなれていえば、幼年、青年、壮年、老年といったライフ・サイクルの各時期の間に価値の上下はない。本来は、それぞれの人生局面にはそれ固有の意義があるはずであり、子供と老人は社会のクズで、青年や壮年が社会の大黒柱だということはありえない。純粋に肉体的にみれば、若い者が強いのはあたり前だ。しかし肉体的に強いことと価値的に高いこととは、ストレートには結びつかない。にもかかわらず、近現代社会では、肉体的強さ=若さと価値観的プラス性とがストレートに結びついてしまった。それは個人の先入見とか、物の考え方の軽薄さといったものではない。近代市民社会とそれをドライブする資本主義市場経済が生みだしたイデオロギーこそ、老いの価値低下をひきおこしてきたし、今もそうである。
(『精神の政治学―作る精神とは何か (Fukutake Books)
』今村仁司著 福武書店 1989 p141-142から抜粋)
もう20年以上も前に書かれた本。21年前だと、わたしは14歳か。両親がそろそろ「介護」に向き合わなければならなくなりはじめた頃に書かれたものだ。
それでも、この文章がそんなに古く感じられないのは、この20年の間に、老いを支える制度はそれなりに整いつつあっても、老いをとらえる人びとの意識それ自体は、それほど変わっていないからだと思う。
昔、撮影を依頼された商品が「アンチエイジング」を謳う化粧品だった。宣材写真を撮るのははじめてのことだったから、撮り方を教えてもらおうと思って頼んでいたひとに、まっこうから拒絶された。
肩こりの薬が肩こりに効くというのは単に効能を示すもの。
でも、アンチエイジングは、イデオロギーだ。
あなたはそれに加担するのですか?
と。
その時点では、まったく意味がわからなかった。
けれど、今ならよくわかる。
2010-10-02
今年もまたこの季節がやってきて、みなさまからあたたかいメッセージや、お祝いの品々をいただきました。どうもありがとうございます。
今年はなんとまぁ、立派なまげわっぱのおべんとばこだとか、本革のがま口だとか、
実用的で、かつ、渋いセレクトのプレゼントが、
京都から熊本から届きました。どうもありがとう!
(あ、所長にシーサーのガムももらったわ☆)
KUMAMOTOと書かれた、’からしれんこんポストカード’も秀逸です。
そして毎年恒例のように風邪をひく…(気温が下がる時季に生まれたんだよなー)
2010-09-20
スキャン待ちの読書が食傷気味になったので、DVDを借りてみる。ディスプレイが2台あると、こういうときに便利なんだな。
ツ●ヤの戦略にまんまとはまり、4本レンタル。
かたつむり食堂、プール、妹おすすめのクヒオ大佐…と、もう1枚はヒミツ。
かもめ食堂、西の魔女が死んだ、かたつむり食堂、と、料理をつくることと食べることに軸を置いて、暮らしを描き出す作品が最近増えているな…と思う。
飽食のこの国にあって、あたりまえであったはずの、料理を丁寧につくって食べることが、ユートピアのように描かれる不思議さ。
生活者の実感としては、素材の値段に関わらず、こんなもんでいいかと適当に食べ物を口に運ぶときががいちばん貧しく、丁寧に料理したものをゆっくりいただくときがいちばん贅沢に感じられる。
だが、こうも繰り返し理想化しなければならないくらい、わたしたちの食の風景は貧しくなっているのだろうか。
敬老の日の「ご長寿」特集で伝えられるところによると、家族と一緒に食事をする方は、たくさんの品数を会話をしながらゆっくり食べるため、血糖値の上昇がゆるやかにおさえられ、長生きの傾向にあるとのこと。
妙に真剣に見てしまった。
2010-09-18
感情や情緒は行為である。それは世界の中にあって世界を作り変える。まだないものを先取りし、この先取りによってすでに世界の外に出る。外に出ることでいまの生活世界を批判する。
(『精神の政治学―作る精神とは何か (Fukutake Books)
』今村仁司 福武書店 1989 p90より抜粋)
すごい作品と出会うと、こんなに自由で良いんだ、ということを思い知らされる。そして、それらの作品は、既存の枠をやすやすと越え出る奔放さを備えている。
いや、ことの順序が違うな。
それら作品を前にし、その奔放さに触れることによってはじめて、自分たちがとらわれている枠が認識される。
事前に自明な枠があるのではない。
作品に出会ってはじめて、自分がとらわれている枠が認識できるのだから、枠の出現は後だ。
だから、何かに対する批判そのものが目的である作品よりもむしろ、
ふわっと越え出てしまった作品にこそ、強い批判性を感じる。
この文章を読んで、そういうことを思い出した。
94コマ目のスキャンが終わる。
2010-09-15
昨夜とうってかわって、今夜は虫の音。
重なり合って、まったく音の輪郭がとれないから、擬音にすらならぬ。
カタカタカタカタカタカタ…
昨日よりは、音が混じり合う感触。
秋の夜長、虫の音にくるまれ、スキャニング。
あ、雨が降ってきたみたい。
あるコマから突然色が安定しなくなっているから、補正に時間をとられているけれど、今夜90コマ目までスキャンできたら、先ゆきが明るい。
スキャン待ちの時間に読んでいた『映像人類学の冒険』もそろそろ終盤に。きもち敬遠気味だった『知覚の宙吊り』を手もとに引き寄せてみる。
2010-09-14
カタカタカタカタ…
小刻みなスキャナの音と、まったく異質な雨音が、違った層で響いている。
音のレイヤー構造。
こんなにゆっくり耳を澄まして雨音をきくこと自体、ずいぶん久しぶり。
好い夜だ。
84コマ目のスキャン。残り30コマをきる。
雨音をきくとき、その地面との衝突のぴちゃっと跳ねる様子、湿り気、そういったものをまるごと感じている、という話を現象学の講義できいたのを思い出す。
まだ雨の匂いはしない。
2010-09-07
妹「季節的にそろそろタケコプタ」
姉「9月はまだ猛暑日が続くのでANAをご利用ください」
妹「じゃぁ通り抜けフープ」
姉「ご、ごめん。フープ、在庫きらしてる…」
妹「フープ在庫切れ?」
妹よ、安心するがいい。
遠く熊本に住んでいようが、きみのこのしつこさは関西一流だ。
2010-09-06
土曜、あわててハンス・コパー展を観に行く。
独特の薄さをそなえ、陶器の形そのものよりも、どうしても陶器が内包する空間のほうに意識が向く、いや、そんな抽象的なものではないな。
この薄い陶器の膜に内包されたの空気の’きもち’になるようなこと。
内包された側になりすます、というのか。
それがいやおうなく体感されるのが不思議でならなかった。
もう少し客観的にとらえなおすと、重量や、いわゆる塊としての量感から解放された世界。
くわえて、最初は一体化していた台座とオブジェの関係性がどんどん進化していく様子が興味深い。
そしてその美しさはおそろしくストイック。
後半のルーシーリーの作品の前で立ち止まって、不覚にも「ほっ」としてしまった。そのくらい、ハンス・コパーの作品を見ているときは、見ている側も張りつめていたのだと思う。
それにしてもルーシーリーの作品、良いなぁ。
印刷物でしか見たことがなかったけれど、実物の色、質感、えもいえぬバランス、に見蕩れてしまった。大阪での展示を楽しみにしておこう。
早めに出て由比に寄り、名産の桜えびの”かきあげ丼”で腹ごしらえをしてから、IZU PHOTO MUSEUMに向かう。
木村友紀さんの展示。
作品点数こそ多くなかったものの、あまりに面白くて、何度もくるくる会場をまわってしまった。
複数の要素で構成される作品群。
たとえば写真Aに映っている窓辺の色紙3色と、写真Aの上に置いてある写真Bに映っている車の色3色とにが呼応し、なおかつ写真Aに映っている椅子と、そっくりの椅子が、写真Aを乗せている台と組み合わされていたり、と、複雑に要素が絡み合っている。
写真の前にどかっと植物が置いてあって、それがいかにも写真の中の世界にも置いてありそうな植物で、それが邪魔でイメージが見れないけれど、なんだかしっくりしてもいる。
そうやって、写真と現実のモノが介入しあっているのが、ものすごくおもしろい。
そして、離れた場所に展示してある作品Cにも、写真Aの作品で使った椅子と同じ椅子が使われていたり、写真Aがまた別の場所の展示では、別のモノとの関係性で別の作品として存在している、音楽でいうところの変奏のような展開の仕方であったり…(ここまで書いていてことばで説明する難しさを痛感…是非一度見てみてください)
いろんな関係の可能性が、見るたびに発見されるのがおもしろかった。
木村友紀さんの作品は、展示よりも展示写真を見ることのほうが多かったので、難解そうな印象を抱いていたのだけれど、今回、じっくり見てみて、実際に展示を見ることのうちに、その可能性の多くが含まれているのだとわかった。
‘新しいルール’を感じさせる作品群。
駿河平は遠かったけれど、行って良かったと思う。
今年の夏はいろいろ作品を見たけれど、いちばん刺激的で、そしていちばん考えさせられる展示だった。
数点ずつ毎日スキャン、というコツコツ作戦で、08年春の撮影分、113点中、70点スキャン終了。残り1/3ほど。
スキャンに40分、そのあとの保存にいやに時間がかかる。HDDの残量が少ないからだろうか…。
暑い夏にスキャニング三昧。
せめてもうちょっと涼しくなってくれないかなぁ…
2010-08-29
短い期間に何度か同じタームを耳にするとすっかり刷り込まれ、気がついたらドラッカーの本を手にしていた。
そうそう、電通のセミナーのシライシさんの話の、「今世紀末にはほとんどの企業が、NPO、NGO化している。あるいはそれに近い状態になるとドラッカーが予測している」というくだりが印象に残っていたんだ。
読んだあとで気がついたのだけれど、前の晩に読んだの?というくらい、シライシさんの挿話がドラッカー“まんま”。それがちょっと可笑しかった。
あたりまえだけど、たいせつなことが書かれている。
“重要なことは、正しい答えを見つけることではない。正しい問いを探すことである。”
“人は費用ではなく資源”
さて、寄り道はこれくらいにして…分厚すぎるというそれだけの理由で敬遠していた『知覚の宙吊り』、そろそろ読まなくちゃ…
2010-08-22
結局、昨日、もう一度、原のエグルストン展に行った。
6月に見に行った時点では図録が発売されておらず、図録を調達しがてら…のつもりが、図録に掲載されている画像の、妙にきついシャープネスが気になったので断念する。
結局、展示をもう一度ゆっくり見ることに。
この夏は、原で2回、谷中で1回、都合3回、エグルストンの展示を見た。
贅沢な夏だったと思う。
原の展示ではドローイングもあわせて展示されていたが、エグルストンの目には、ドローイングのような色面の構成、それも動きをともなった色の世界に見えているのだろうか…
ということと、
70年代の作品と、近作で、画面の構成の仕方が、がらっとかわっていること。
70年代にカラーで作品を出したときの状況をもっと具体的に想像ができたらいいのに、という思いと、それが、どのような変遷を経て、近作のようになってきたのかを、きちんと追いたい。
陽射しのきつさは相変わらずだけれど、2時3時の時点ですでに影が長くなっとる。
秋が待ちどおしい。

帰省時に持ちかえってゆっくり読もうと思ったパノフスキーの『象徴形式としての遠近法』
本文70ページほどであとは全部注と画像なのに、何度読んでも頭に入って来ないのは暑さのせいか?このテの本は、何度読んでもちんぷんかんぷん…
だからしつこく何度も読む。
遠近法は、ある時代固有のものであり、そしてその時代の世界観とリンクしている
ということは、わかった。
遠近法の作図による像と、実際の人の目に見える像の違い(ゆがみの部分)を、もう少し丁寧に読み直したい。
2010-08-21


2010-08-20
一、
静岡のあたりを通り過ぎるのが、ちょうど陽の沈むころ。
夏の空にしては、意外なほど優しく淡い色が、徐々に明度を失っていくのが、
はかなく、そしてうつくしかった。
一日を見送ることができて、嬉しい。
夏の海は好い。
それも暑さの勢いがそがれる頃の日暮れが好い。
二、
薄曇りの夕刻、あわてて出かけた道すがら、
名前を知らぬ花の紫の花弁が、アスファルトに散らばっているのを見かける。
咲いている花よりも、むしろアスファルトを背にグレイバックで見るほうが、
その紫は鮮やかで、艶かしく。
三、
電車の窓から見る彩度の低い空に、これまたさらに彩度を失った木々の緑。
その組み合わせに、なぜか、そこはかとなくありがたみを感じた。
もう身体が思うように動かなくなるくらいの年になってやっと、芸とは何か、ということがわかるのではないだろうか。そして、そこに辿り着くためには、いまこの時期にこそ、精進しなければならない。
そのようなことを、海老蔵が語っていた。
どうにでも自由がきき、無理もできる若い時期、ではなく、自由がきかなくなる、身体の制約が課される頃になって「こそ」、というところが、すごい。
老い、が、ただただ、人生のピークからの引き算でしかとらえられない時代にあって、こういう考え方に接することはなかなか少ない。
そうだ、思い出した。
22,23歳の頃、老齢のピアニストを見て、つくづく思ったのだ。
年を重ねることが、技の円熟につながるような仕事をしたい、と。
『定年』などという他人に決められた期限で途切れるような仕事ではなく、一生、精進し続けられるような仕事をしたい、と。
そう思って、でも結果を急ぎすぎてからまわりをしていた時期があって、そこで「長丁場で行こう」と思い直したときに、多少なりとも、わたしは自分を甘やかした。
違うのだ。
結果を急いてはならないけれど、でも、
この先で、少なからずなにかを体得したければ、
いまこそ精進しなければならない。
2010-08-15

ブラジルみやげをいただく。
左のコーヒー豆はどっさり1kg。
そして右は、ブラジル…と言えばのビ☆ニ。
どちらもパッケージが綺麗なのがうれしい。
雑誌なんかでは、色のどぎつい、大味なデザインの安っぽい雑貨が紹介されていることが多いのだけれど、案外、ラテンアメリカのもの、綺麗な色づかいでデザインの良いものが多いのだよ。
なにより、デザインがおおらかなのが良い。
日本にはチマチマしたデザインが多いし、自分でデザインをしているときも、手を加えれば加えるほど、チマチマしてくることが多い。
そういうときに、はっとするきっかけになるのが、こういう海外のちょっとしたもの。
どうしたらもっと、おおらかで、繊細で、うつくしいものが、作れるようになるんだろうな。

決して動物が好きなわけではないのだけれど、3年間ネコ屋敷に住んだせいか、猫を見るとついカメラを構えてしまう。
しかし、猫って器用に寝るもんだなぁ。寝返りうたんのか…
2010-08-14
久しぶりに、時間をかけて神戸の街をブラつく。
元町で電車を降りてさっそく昼食。
18種類のスパイスで、水を加えずに煮込んだカレー。
トマトの酸味とスパイスが程よく効いて美味。
中華街をスルッと抜けて、海のほうに向かう。
中華街は意外と人通りがなく、そして、店舗が抜けているところがあることに、少し驚く。
そのかわり、その海側の栄町界隈は、若いひとの出店が多く見られ、活況を呈している。
ターゲットが少し大人向けだし、個性的な店も多い。
楽しいガラクタばかりではなく、良質なものをリーズナブルな価格で扱うお店も発見。
京都ほど土地柄をウリにしてない分、素直な印象を受ける。
数年前に来たときには、こんなにいろいろお店があるとは気づかなかった。
知らない間に、ずいぶんおもしろい街になっているじゃないか。
また遊びに行こう☆
会期末だということに気づき、あわてて、畠山直哉さんの「線をなぞる / 山手通り」を見に行く。
線をなぞる、のシリーズは、どう見たら良いのか、少し戸惑う。
空間の尋常ではない入り組み方が、写真によって平面に写し取られたことで変位するようなところが気になる。すっきりしない感じで、これはしばらく気になり続けるだろうなぁ。
Slow Glassのほうは、もっと素直に見る。
水滴のひとつひとつが、それぞれが独立したスクリーンであることが、発見のひとつ。
ガラス越しの背景にぼやけて見える像と、水滴に映る輪郭のはっきりとした、しかしデフォルメされた像との対比がおもしろい、と思った。
写真に写しでもしなければ、こんなに真剣に窓の水滴を凝視することはないから、やっぱり写真っておもしろい。
ある視点から見た光景を留めおくことによって、ディテールを凝視することができる、というのが、写真のおもしろさのひとつだと確信している。
2010-07-29
電通のセミナーに出席。
いろいろおもしろい話が聞けたのだけれど、ひとつ印象的だったのが、わかりやすい文章を書くには、文章を書いたら声を出して読んでみる、ということ。
おおかたの日本人は、ものを読むときに、音にして認識するので、声を出して読んだときに、すらすらと読めない文章は、目で追いながら読んだとしても、読みにくいのだ、と。
ということで、いま、わたしはこの文章を、声を出しながら書いている。
ちょっと込み入ったことを書こうとしたら、途端に、ことばがぎこちなくなるときがある。
そういうときも、声を出して読んでみたら良いのだ、と思えば、少し気が楽になった。
お、なんだか口述筆記みたいになってきたぞ。
2010-07-24
最近読んだ2冊の本に、立て続けに家族についての記載を見つけたので、少し気になった。とりあえず、抜き書きをしておこう。考えるのはあとにして。
たとえば核家族が住まうための家を建てることに、二〇世紀の人々は懸命になった。二〇世紀の経済を下支えしたのは、「持ち家」への願望である。従来の地縁、血縁が崩壊し、近代家族という孤立した単位が、大きな海を漂流しはじめたのが二〇世紀であった。近代家族という不確かで不安定な存在に対して、何らかの確固たる形を与えるために、彼らは住宅ローンで多額の借り入れをしてまで、家を建て、家族を「固定」しようとした。あるいはコンクリート製のマンションというかたい器のなかに収容することによって、存在の不安定を「固定」しようとした。地縁、血縁が崩壊したことで不安定になってしまった自分を、コンクリートというがちがちのもので再びかためたいと願ったのである。
(『自然な建築』 隈研吾 岩波新書 2008 p9より抜粋)
このことを建築家の山本理顕さんは、もう少し厳しい口調で次のように書いている。「〈家族という—引用者注〉この小さな単位にあらゆる負担がかかるように、今の社会のシステムはできているように思う。今の社会のシステムというのは、家族という最小単位が自明であるという前提ででき上がっている。そして、この最小単位にあらゆる負担がかかるように、つまり、社会の側のシステムを補強するように、さらに言えばもしシステムに不備があったとしたら、この不備をこの最小単位のところで調整するようにできている」、と。
その最小単位じたいが、いま密度を下げている。独特の密度を可能にする閉じた関係を内蔵しにくくなっている。塗り固められた燕の巣のように、内部を密閉する鉄の扉によって、かろうじてイメージとして維持されているだけの内部を外部からがちっと遮断しているだけだとしか言いえないような家族も増えている。この防波堤が外されれば、イメージとしてかろうじて維持されている家族の形態もすぐにでもばらけてしまいそうだ。
(『わかりやすいはわかりにくい? 臨床哲学講座
』 鷲田清一 筑摩新書 2010 p148より抜粋)
ちょうど、児童虐待のニュースが取りざたされていたから、余計に気になったのかもしれない。
子育て中の友人を訪ねて行ったとき、「わたしなんて、まだ仕事をしているから良いけれど、そうでなかったら24時間ずっと赤ちゃんと二人っきりなんだよ。大変なんだよ。会いに来てくれて嬉しかった。」としみじみと言われたことを思い出す。
そのとき、子育て中のお母さんは、想像以上に孤独なのだと思った。
そして、ひとつの命の責任を24時間引き受けることの重圧。
自分の親も決して100点満点の親ではなかったけれど、その親を相対化できる程度には、さまざまな大人に『からまれていた』と思う。
ズケズケ物を言う友だちのおかん、親よりも厳しいピアノの先生、いつも美味しい料理で迎えてくれる祖母、周囲の大人との関係が、案外、親子関係の弾力となっていたのかもしれない。家族関係を小さく小さく密閉することで、そういう弾力性が削がれていっているのかもしれない、という気がした。
『負ける建築』が存外おもしろかったのを思い出し、隈研吾の著作を読みはじめたのだけれど、造形と社会との連関の話だから、建築にとくに関心が強いわけではなくてもすごくおもしろい。
(前略)コンクリートは突然にかたまるのである。それまではドロドロとしていた不定形の液体であったものが、ある瞬間、突然に信じられないほどかたく、強い物質へと変身を遂げる。その瞬間から、もう後戻りがきかなくなる。コンクリートの時間というのは、そのような非連続的な時間である。木造建築の時間は、それとは対照的である。木造建築には、コンクリートの時間のような「特別なポイント」は存在しない。生活の変化に従って、あるいは部材の劣化に従って、少しずつ手直しし、少しずつ取りかえ、少しずつ変化していく。
逆な見方をすれば、二〇世紀の人々は、コンクリートのような不連続な時間を求めたのである。(『自然な建築
』 隈研吾 岩波新書 2008 p8より抜粋)
最近、時間のことを考えていた。
決定的な完了時点があるから、グラフィックの仕事のほうが好き。
ウェブはどこまでいっても終りがないからつらい。
ずっとそう思っていたけれど、ここにきて、継続的に手をかけて育てていかなければならないウェブという媒体、「育てる」というのが、案外、性にあってるんじゃないか…と思いはじめていた。
そうか、ウェブの時間は連続なのだ。
写真にしても、1点ではなく、複数の関係性によって何が見えてくるか、ということのほうに関心があって、連続と不連続との境界あたりを、おもしろいと思っているのだ。
仕事のあとのその足で、SCAI THE BATHHOUSEにウイリアム・エグルストンの展示を観に行く。
猛暑日の午後、暑い中よくもこんなに…と思うほど、ギャラリーは若いお客さんで盛況。
ふと脇を通り抜ける男性。赤いシャツに赤いキャップ。
一度もじかに会ったことはないけれど、ひと目でそのひととわかった。
中平卓馬さん。
小柄な体躯から、独特の緊張感が放たれていた。
気後れがして、挨拶も握手もお願いができなかったけれど、その後ろ姿になんとなく”ごりやく”がありそうな気が(笑)。今日行って良かったー。夏の太陽に負けなくって良かったー。
原の展示と同じ作品もいくつかあったけれど、ギャラリーの展示にしては、ずいぶん充実した内容。
もう一度、客の少ない日にゆっくり見に行こう。
DVDも欲しいなぁ…
2010-07-21
タイトルすら確かめず、ゴロゴロしながら、観るつもりもなく観ていたイタリア映画が、存外良かったのだ。
後で確認したら、ジュゼッペ・トルナトーレの作品だった。
そういうことか。
神戸から瀬戸内にかけての夏の光、そしてあの地域独特のヌケの良さ、開放感を、心底愛しているけれど、でもやっぱりおそろしく暑い。
結局、夏は、本を読むか、映画を観るか…なのね。
久しぶりにロマン座で、マカロニウエスタン観たいなぁ…。
2010-07-18
19時に撮影をスタートする。少し遅れたかなぁ…とか。
長時間露光の途中にひとや自転車が横切ることが多かったので、遮光板を持ち込んだのは大正解だったと思う。昨年は、その度に、撮り直しをしていたから、その分、撮影も早く進められる。
今年は、最後のコマの位置でカップルが花火をしていたのが、良かったなぁ。
2008年から3年、17時スタート、18時スタート、19時スタートで撮ったから、並べて見比べてみようと思う。
川がずいぶん増水していたけれど、とにもかくにも、雨が降らないで良かった。
◆備忘録
撮影 7/18 19:00〜22:30
60コマ前後(220のフィルム 3本以内で納まる)
F8.0 1/4〜2min
2010-07-17
しばらくぶりの中判での撮影。
準備をしていて、フィルムの種類が減っていることに気づく。
NS160は、5本セットでしか売ってないし…
うまいこと梅雨が明けてくれたので、この週末のうちに撮りたい。
ずいぶん体力が落ちてるやろなぁ…
いろいろ問題含みの現状。
なんとか整理して、早くもとのペースに戻したいものです。
2010-07-04
金曜日の夜、建築はどこにあるの?を見に行く。
とうもろこし畑、赤稿といった作品は、見るひとの立ち位置や関わり方によって、様相がかわって見え、インスタレーション作品として、とてもおもしろかった。全体としては、説明書きを読んでコンセプトは理解できても、”体験として伝わるもの”が薄いと感じる作品のほうが多かった。
インスタレーションだけに、作品と対峙していろんな体験ができるものだと期待していた分、残念な気持ち、に。
そして常設展に足を運ぶ。
まさかこんなところで、出会うとは思わなかった、Gordon Matta-Clark の建築をぶった切る映像が見られたのが、大収穫。

破壊行為だと思っていたけれど、
実はすごく丁寧に緻密に、建築をぶった切っていたことを知る。
その切り込みによって、構造物の中にすっと光が射し込んでいる様子が、内部からのアングルで見られたのがすごく良かった。映像のなせるわざだ。モノクロの映像だから、色はわからないけれど、それでも射し込む光に”silver light”という表現はぴったりだと思った。
例年よりひと月ほど遅いのだけれど、日没の時刻は3分しか変わらないということがわかり、今年も”夏の夜”の撮影をする。
少なくとも、去年の反省を活かしたいので、今年はレンズフードを調達。昨年のネガには、相当変な方向からの光が入っていた、と思われる。
あとは、ストップウォッチと、遮光板の用意。今週末にはテスト撮影をし、来週本番。
久しぶりにブローニーのフィルムも買わなければならない。撮影までにもう少し体力をつけておかないと。
スケジュールが具体的になると、俄然やる気になる。
2010-06-25

2010-06-22
妹(27)と姉(34)のメール。
妹「あぁ、帰りたい(涙)」
姉「帰りたい(涙)」
妹「あーん、どらえもーん(涙)」
姉「どこでもドアがほしい(涙)」
妹「タケコプタ」
姉「これからの季節、暑いのでは?」
妹「う…」
どっちが先に音を上げるかな。
どこでもドアほしい…
久しぶりに視力検査をする。裸眼で1.5をキープ。
「え?裸眼?すごいですね」と褒められて、ちょっと良い気分。
まだまだ大丈夫!な気がした。
2010-06-18
やっと週末☆と思って帰宅したところに、母親からのメール。
「祖母が肺炎で入院」
90を過ぎた祖母のこと。何があってもおかしくない。
あわてて一番早く神戸に帰られる足を確保する。
23時の高速バス。
2週つづけての帰省は体力的にはきついけど、それでも、家族であるということは、大事な局面に都度「居合わせる」ということなんだと思う。そしてそれは、わたしが何より大切にしていることなのだ。
ということで、そろそろ準備をして家を出ます。
2010-06-17
できるだけ、馴染まぬように。
そう思っていたのに、気がつくと、まわりとそっくりなもの言いをしていた。
昨日、発した自分のことばで、気分が悪くなるくらいいやなことばのつかい方をしているな、と思った。
ああいうのっていやだなぁ…とひとのことを思っていたはずが、同じように自分が振る舞っている、と気づいたときの、言いようのない嫌悪感。ほんの数ヶ月で、わたしがわたしを、どんどん嫌いになっていってる。
わたし気が小さいから、おっちゃんがビッグイシューを売ってると、つい、買ってしまうのよね。と母親が言っていたのを思い出す。
ちょうど交差点で、ツナギを着たおっちゃんが、ほがらかに高らかにビッグイシューの宣伝をしていた。
風が吹いて、パラッとめくれたファイルから、覗いた表紙がたまたまアート特集だったから、「5ヶ月前のだよ」と言われても、”つい”買ってしまった。
やなぎみわさんがゲスト編集長で、特集は、高嶺格、志賀理江子、ウィリアム・ケントリッジ。
けっこう良い買い物じゃないか、と、うれしい気もちに。
あのタイミングで風が吹いてページがめくれなかったら、きっと買ってはいなかったから、これもまたご縁だな。
2010-06-12
そして結局、京都に帰りました。
四条河原町のノムラテーラーで、姪のワンピースにと素敵な花柄の生地を買い、大宮に戻って、三条会の「やのじさくえん」で麦茶とほうじ茶をオトナ買い。
オトウトの家に寄って自転車を借り、ロマンザで髪を切ってもらう。
進々堂でパンを買い、そのあと、出町柳でハルさんと待ち合わせ。
出町柳の北西角にいます。とメールを打つ。
空が広い。
「自転車じゃないと、なんだか疎外された気がするの」と言ってハルさんに「そういうところ寂しがりやなんだ」と嗤われる。
下鴨神社に行ったものの、その蛍は「放流モノ」と知り落胆。
気を取り直して、疎水に向かうがすっかりフラれ、最後、哲学の道に向かう途中で穴場スポットを発見。
蛍が舞っている。
ふーわふーわ舞いながら、光をともしたり、すっかりひかえてしまったり。
はかなげな様子にぐっと魅きこまれる。
たしかあの夜も蛍を見た。
鴨川を自転車を押しながら歩いていたとき、蛍を、そして、つがいのカモを見たのだ。
つんと胸が傷む。
また出町柳に戻り、年代もののビートルズバーで軽い夕食をとる。
この土地で出会ったひとは、みなウルトラ繊細でやさしいひとたちばかりだったんだ、と、あらためて思い知る。
ほんのひとときの穏やかでやさしい時間。
2010-06-07

友人が、気負いなくブログに写真を載せているのを見て、ちょっとうらやましくなってしまった。魔がさしてる。
そろそろ、蛍の季節じゃないか。
2010-06-06

ほどよい日よりだったので、少し遠出。
原美術館のウィリアム・エグルストン展を見に行く。
まさにエグルストン日和。
展示している作品を見るのは初めて。
思っていた以上に、色の組み合わせが綺麗。
こんなに世の中は色に溢れていて、なのに、見落としている色、見過ごしている色がなんと多いことか。
被写体の捉え方に、ティルマンスを想起する。
わたしたちの世代は、エグルストンよりも先にティルマンスに出会っているのだ。
帰り道は、いつもよりほんの少し、色が、多く見えた。

2010-06-01
自由でありたい
という想いにとらわれることの不自由。
陽の落ちる手前、
薄い茜の空を見上げて、
ふとそう思った。
これは、
不自由な関係にあえて身を置く自由。
ということばの対偶だろうか。
世界はそんなに単純ではない
ということを、思い知る。
あることが、昨日とは全然違う様相を見せた。
昨日の自分の判断をくつがえすような事象が、今、現れた。
それも、己自身の関与によって。
自分は透明な観察者などではなくて、環境、あるいは対象に作用を及ぼす存在である、ということ。
関係性というのは、流動的でかつ相対的である、ということに加え、その複雑な関係性の項として、いやおうなしに自分自身も関与せざるを得ないのだ。
単純な二項対立の図式にあてはめられるような事象も、状況を俯瞰の位置から眺められるような状況も、実のところ「ほとんどない」のではなかろうか。
解なし。
あるいは、解は一つではないのかもしれない。
2010-05-25
大手町で待ち合わせて、なっちゃんと会う。
新丸ビルで会うのはこれで2回目。
なんだかんだ、間を置かずに大学時代の友人と会っている。
いよいよ、のおなかを大事そうに抱えて現れたなっちゃんは、
あいかわらず、わたしより年下なのに、ずぅっと大人。
ほんの少しほっとした。
幼稚な関係性のなかに引きずり込まれて、知らず知らずのうちに、自分もずいぶん幼稚になっているんじゃないか、傲慢になっているんじゃないか。そんなふうに自問自答をする日々を過ごしていたから。
相手が幼稚だからって、幼稚な態度で接していいわけではないのだ。
相手が傲慢だからって、傲慢な態度で接していいわけではないのだ。
なのに。
いまのわたしは状況に甘んじて、無自覚のまま、少しずつ少しずつ、幼稚に、そして傲慢に、なっていってると思う。
友だちのおかげで、見失いかけていた自分の本来のポジションを、確認することができたと思う。
つかの間の休息は、まるでクロールの息つぎ。
もうちょっと先まで、泳げるかなぁ。
2010-05-22
仕事が入ってるし行けないかな…と諦めていた、オセロットのコンサート。
必死でチャリをとばしてなんとかワタリウムに到着。
木村友紀さんや青木陵子さんなど、久しぶりの京都勢の顔ぶれを拝見して、ちょっとほっとする。やっぱり京都に帰りたいよ…。
いろいろな音が多層化している感じが新鮮なコンサート。
音楽もまた、このくらい自由で良いんだ。と、清々しい気もちに。
落合多武さんの展覧会は後日またゆっくり拝見しよう。
2010-05-16
ちょっと近くまで来たので、ご挨拶を。というメールが届く。
老人会(という名の同窓会)のキュウちゃんだ。
遠くに住まうことの利点のひとつは、近くに住んでいたら会わずにいるひとと、会うきっかけができることだと思う。
自転車で待ち合わせ場所に向かおうとしたら、道に迷う。余裕をもって40分のつもりが、都合1時間10分自転車をこぎ続けて無事到着。
どちらもお酒が強くないので、ケーキセットで夜茶コース。ちょっと仕事の話やら、結婚の「け」の字もないです報告やら。
気持ちはあっても無精者ばかりの老人会。
こうやってマメに連絡をくれるキュウちゃんが、かろうじてご縁をつないでくれているのだ。
どうもありがとう。
気をつけて帰ってね。
2010-05-15
2008年春のフィルムを再スキャンするところからはじめようと思う。
計113コマ。
ディテール、時間性という要素で認識していたけれど、ここで、被写体の運動方向という要素が浮上する。
よし、買い出しから戻ったら作業をはじめよう。
2010-05-13
2010年の上半期も終わりに近づいている。
今年は数ヶ月単位でロスが発生している。
今年の夏は撮影できるだろうか。
それより前に、考えなければならないことがある。
まったく同じような手法で撮っていても、2008年に撮った春の作品と、
2008年、2009年の夏の夕刻に撮った作品の本質は違う。
それぞれ、どういう大きさでどういう見せ方をするのがいいのか、とかいうことを、もう一度考え直している。考えても答えが出なければ手を動かしてみよう。
2010-05-11
GWは実家で1歳直前の姪と遊ぶ。
義妹の話で興味深かったのは、赤ちゃんが立とうとしたり、高い高いを喜ぶのは、新しい視界を得ようとしているからだ、という話。新しい視界を得たいという欲望は、そんなに早いうちから点火されていたのか、と思うと、ちょっと戦慄が走った。
その姪は、口のまわりについたご飯を拭こうとすると、激しく拒絶する。
もしかして…と思って、自分の手が姪の視界を遮らないように、あごのほうからふきんを口のまわりに持って行くと、これがおもしろいくらい、嫌がらなくなった。姪が嫌がっていたのは、口のまわりを拭かれることではなくって、視界を遮られることだったのかもしれない。
これはなかなか、奥が深そうだ。
いまの姪にとって「見る」がどういうことなのか、どういうことになっとるのか…うーん、ものすごく興味深い。
2010-05-09
所有することは、ほとんど必然的に所有されることだ
ガブリエル・マルセル
荷物の間からメモが出てきた。
メモにしてはひどくマニアックなんだけど。
いま、このタイミングでひらりわたしの目前に現れたことに、なにか特別な意味があるのではないか、と、考えてしまう。2月の緊急レクチャーで、クリストが「所有できない作品形態」について説明していたことを思い出す。
所有によって制約を受けることがある。作品は自由でなければならない、と。
2010-04-18
法貴信也さんの作品を見に行くはずが、日曜休廊とのことで、予定変更で、ジョン・ルーリーのドローイング展を見に行く。フロアは若いひとでごった返していたけれど、けっこう集中してじっくり見ることができたと思う。
ポップでもなく、でも深刻になりすぎず、見るひとに負担をかけない絶妙の案配。
ひとつの画面を構成する筆致の差異だとか、色、前後の重なり、など、とてもおもしろく見ました。あと、タイトルのセンスが良いなぁと思う。
もう一度くらいは見に行きたいけど、行けるかなぁ。
正直なところ、最近は、写真作品よりも、ドローイングの作品を見るほうが楽しい。
2010-04-14
ミックイタヤさんの個展、提灯を見に行く。ずっとお世話になっている美容室、ロマンザのマークがミックさんの作品で、それまでも作品集を見る機会もあったりしたから、「提灯?」と思いながらも遠出をした。
線で描かれた作品がすごく好きなのだけれど、提灯(立体物)のラインもやっぱり繊細なのが印象的だった。
展示の脇に置かれている、ちょっと良いつくりだなぁ…と思う本は、だいたい光淋社が出版したもの。20代前半のころ買っていた光淋社のzyappu。「かわった雑誌」くらいの印象しか持っていなかったけれど、いまなら、この出版社の心意気がよくわかる。
惜しいなぁと言うには、あまりに時間が経ちすぎているんだけど、この出版社を失ったことは、やっぱり惜しいと思った。
2010-04-11
京都に帰りたい、と、
一心に願う。
離れてみてはじめて、あの街は、街自体が文化なのだ、と判る。
はやく京都に帰りたい。
桜の季節が去ると、大家さんが大切に手入れしている藤棚が紫色に染まり、しばらくすると蛍の季節を迎える。祇園、大文字と街が観光客でごったがえすのを脇目で確認しているうちに、ふと秋風がほほを撫で、紅葉の季節がやってくる。
おだやかな陽射しのなか川べりで本を読んだり、近くで汲んできた湧水で美味しいコーヒーをいれたり。なにより、急かされずにものごとを考えられるだけの、ゆったりとした時間の流れがそこにはあった。
そういうかけがえのないものを、わたしはいとも簡単に手放してしまった。
ここには過剰なほどなんでもあるけれど、大事なものはまだ何も見つからない。
桜を見ると京都を想ってしまうから、
今年だけは、桜を見たくなかった。
2010-03-06
立派な流星を見た
すっかり葉を落とした薔薇に新芽がいぶく
あたまでいろいろ考えるより、
そういうことを信用しようと思う
あの夜、つがいの鴨にそっと背中を押されたように
わたしはいま、東へむかう風に乗る
2010-02-06
返却期限がきていたから、
空の案配を見て、DVDを返しに出かける。
出がけには降っていなかったのに、
レンタルショップにつくころには、大きな牡丹雪がマントに白く積もっていた。
結局、タイミングをはずしたなぁ…と思いながら、
返却の手続きを済ませる。
本屋をのぞいて、店を出ると、
さっきまでの雪がうそのようにあがっている。
雪上がりの星空は、綺麗なんだ。
せっかくだから少し歩こうと思い、
自転車を押して南へ下る。
すると、空にすぅっと一筋。
流星?こんな時期に?
半信半疑で空を見上げていると、
さらに大きな流星が、これでもかというくらい、ゆーーっくり、
長いしっぽを見せびらかすように、流れた。
トロいわたしでも願いごとができるくらい、充分スロウに。
すごい…今日のはLサイズ。
そのうえサービス精神旺盛や。
圧倒されて、愉快だった。
すっごい良いことがありそう、とかではなく、
自分を信じてもいいような気もち。信じてがんばろうという気もち。
そういう気もちにさせてもらった。
丸太町まで戻って来たところで、また雲が空を覆いはじめ、
大ぶりの雪が舞い降りてきた。
Lサイズの流星を見せるために、ほんの一瞬雪がやんだような、
天国にいる誰かさんのはからいを感じさせる、そんな夜やった。
ひどく寒い。
外出をずるずるのばしのばしにして、
借りていた『西の魔女が死んだ』を観る。
アイロン台が、茶色く焦げてしまっているのがずっと気になっていたので、
DVDを観つつ、その張り替えもする。
古くなったアイロン台は、
布を張り替えたらリニューアルできるのだ、ということを、ネットで知る。
ほとんど、のりで接着されていたので、
霧吹きで水をかけてしばらく置いたら、古い布も紙もはがれる。
もともとのクション材に、新しいクラフト紙を巻いて、
その上から布を巻いてタッカーを打ち、土台に固定する。
製本のりの配合を参考にして、
のりと、木工用ボンドと水を混ぜたものを、紙に刷毛で塗り、
その紙を、台の裏側に貼る。これは布の端を始末するため。
はずしておいた脚を、もとの位置にねじで留め直したら、できあがり。
買ったまま数年使っていなかったヴィンテージの生地で巻いたものだから、
ことのほかガーリーな仕上がりになる。
ガーリー。
こまごまとした家財道具は、
気がつくと、10年、15年選手になっているだなぁ…とつくづく思う。
とすれば、この先10年、ガーリーでいくのか?いけるのか?
それはさておき、
20代に、とりあえず「ひとりぐらし」をはじめるために慌てて買い揃えた家財道具。
さすがに30代も半ばにさしかかると、その安っぽさが気になるようになって、
少しずつ入れ替えはじめている。
慌てて買って「もたなかった」んだから、慌てて買い替えるのは愚かだ。
気に入ったものに出会ったら、都度、おさいふと相談、という感じで入れ替えている。
そんなふうに、身のまわりを少しずつリニューアルしていると、
でもそれって、自分自身も、同じなんだな、と気づく。
10年、15年、こころの中にわだかまっていることや、
執着し続けていることがあるとすれば、
そういうものこそ、都度、入れ替えていかなければならないんだ、と思う。
それも、ひといきにやろうと思うんじゃなくて、ぼちぼち、ね。
そんなことを考えていたら、
昨晩読んだ内田樹さんの本の「居着く」というくだりを思い出した。
(中略)「こだわる」というのは文字通り「居着く」ことである。「プライドを持つ」というのも、「理想我」に居着くことである。「被害者意識を持つ」というのは、「弱者である私」に居着くことである。
「強大な何か」によって私は自由を失い、可能性の開花を阻まれ、「自分らしくあること」を許されていない、という文型で自分の現状を一度説明してしまった人間は、その説明に「居着く」ことになる。
人をして居着かせることのできる説明というのは、実は非常によくできた説明なのである。あちこち論理的破綻があるような説明に人はおいそれと居着くことができない。居心地がいいから居着くのである。自分の現況を説明する当の言葉に本人もしっかりうなずいて「なるほど、まさに私の現状はこのとおりなのである」と納得できなければ、人は居着かない。
そして一度、自分の採用した説明に居着いてしまうと、もうその人はそのあと、何らかの行動を起こして自力で現況を改善するということができなくなる。
(『邪悪なものの鎮め方
』 内田樹 2010 バジリコ p90より抜粋)
2010-02-03

節分です。
今年のホームメイド恵方巻の参加者は、
しいたけ
みつば
たまご
うなぎ
です。
お米二合で、太巻4本。
とりあえず、写メで記念撮影。
すると、熊本に住む妹から「我が家の自慢の太巻」写メが届く。
妹は関西を離れて、余計に関西を意識しだしたのでしょう。ふふふ。
写メを介し、ちょっとした太巻対決。
恵方巻なので、今年の恵方、西南西を向いて無言で食す。
意外とボリュームがある。
残り3本を横目で見つめ、途方に暮れる。
味が落ちないうちに食べ切るのは無理…。
ということで、
吉田神社の節分祭に行く約束をしていたハルさんに、1.5本献上することに。
吉田神社の節分には、日本中の神さまがやってくるそうです。八百万。
にぎやかでいいじゃないですか。
22時。百万遍で待ち合わせをし、まずは、本殿でお参りする。
そのあと、お菓子の神さまにも手をあわせて、
さらに八百万の神さまの集合場所らしきところに行って、お参り。
地方名とやたらと具体的な神さまの数(?)が書かれたお社を
よくわからないままに、ぐるぐるまわる。
寒いので、日本酒のぬる燗をいただき、
からだも温まって良い気分になったところで、23時。
飲食の神さまのところに少し寄ってから、メイン会場に向かう。

2/3のメインイベント。激しくお札が焼かれています。
一年の無病息災を祈るそうです。
無事、この1年を乗り切れますように。
炎って、やっぱりテンションがあがる。
寒い夜だったから、あったかくてありがたい、というのもある。
炎のまわりは、ぎゅうぎゅう押されて大変でした。
(太巻の具材になった気分が味わえます)
純粋な信心だけでお参りしているのではなくって、
こういう行事っておもしろいんだと思う。
厄年にお参りした壬生寺の節分のほうらく割りだって、
すごく楽しかった。
炎であったり、やたらたくさんのお社であったり、
参拝者がおもしろいと感じる「仕掛け」がそこここにあって、
そこには、ちゃんとテンションがあがる要素や、
関心をひきつける要素が盛り込まれている。
そして、みな気分良くおさいふを開く。
積極的に、燃やすとか割るといった破壊行為がとられるのは、
そこに個々人の破壊衝動が転嫁されることで、
日常生活の「ガス抜き」の機能も果たしているのかもしれないと思った。
ひとを集め、ものを見せ、体験させるしくみとして、
お祭りとか寺社の年中行事だとかは、
相当練られたシステムだとあらためて思った。
え?このテンションは日本酒のせい?
2010-02-02
申し訳なさそうに言われたものだから、
かえってこっちが申し訳ないきもちになる。
郵便局の窓口でのこと。
紛失の届出のところに粉失と書いて、
まったく間違いに気づかずに堂々と書類を提出したところ、
郵便局員さんに、やんわりと訂正されてしまった。
ことばには執着があるほうだから、
こんな間違いに気づかないなんて、はじめてのことだと思う。
(正確には、間違いに気づかなかったことに気づかされたのが「はじめて」だ)
ショックである。
書く能力が著しく低下している。
タイピングする分には全く不都合はないのだけれど、
いざペンを持って書く段になると、
適切な漢字が思い出せずにすこぶる不自由をするということに、
うすうす気がついてはいた。
でも、書き損じることはあっても、
書き損じたことに気がつかないほど、アホになっているとは思わなかった。
これは、能力の低下というより、ほとんど退化だ。
意識的に手でものを書くようにしておかないと、
ほんとうに、書く能力を“粉失”してしまうかもしれない。
2010-01-18
まったく別件で、デジタルブックを作成するツールを探していて、zoomifyというソフトを見つけたので、先日できた2009年撮影のラフで試してみる。
zoomifyで書き出して、mediaboxを使って設置するのに、半日ほどかかってしまったけれど、このツールは使えると思う。本当に便利な世の中になったものだ。
露光時間のせいで変形した月が、たぶん4つ映ってる。(4つめはおぼろ月)
2010-01-15
しかし、コルビュジエ達は、大衆社会における芸術と社会との関係を正確に理解していた。その理解に基づいて作品を作り、また、その理解に基づいた巧妙なやり方で、作品を社会に投入したのである。
大衆社会において、建築は一個の商品(オブジェクト)として大衆に受け入れられる。この決定的事実をコルビュジエ達は正確に理解していたのである。(中略)商品は、なによりもまずひとつの強固でわかりやすい図像性を持っていなければならない。一目見てはっとするようなパッケージをまとっていなければならない。そのパッケージの図像性が要請される。そのために彼らはまず建築を、その外部の世界から切断することを考えた。
商品というものは通常、移動可能な自立したモノとして把握される。建築もまた環境から切断されてはじめて、商品として、人々から受け入れられると彼らは考えた。そのためにコルビュジエは列柱(ピロティー)を用いて建築を大地から浮上させて切断し、ミースは古典主義建築が行ったように、乱雑な大地の上にまず基壇を築き、その上に自らの芸術作品をうやうやしく配置したのである。ピロティーや基壇で切断された芸術作品には、単純でわかりやすい形態が与えられた。
(中略)切断への関心は、危機感の反映でもある。二〇世紀においては、商品化という操作によってのみ、芸術と社会とが回路を結びうるとするならば、二〇世紀の建築の置かれた位置は絶望的ですらあった。絵画や彫刻はすでに額縁や台座(基壇)によって、二〇世紀のはるか以前から、環境とは明確に切断されていた。ルネサンス以降の近代化のプロセスの中で、すでにその切断をはやばやと達成していたのである。さらにこれらの領域では、貴族的なパトロネージが、二〇世紀に到っても依然として力を保ちつづけており、商品化の必要性はより希薄だった。それに対し、建築の危機は深刻であった。額縁はなかったし、パトロネージも風前の灯火であった。
(『負ける建築
』 隈研吾著 岩波書店 2004 p94-95から抜粋)
「額縁はなかったし」というところが、建築の側の本音ぽいのが可笑しかった。
ものを「作品」として他者に認識てもらうための道具立て、プロトコル、そしてその効能には、充分注意をしなければならない、と思ってはいたけれど、ここで、フレームの本質的な機能が、環境との切断ということをあらためて確認する。
作品のなかには、額縁や基壇などのわかりやすい道具立てに頼っていないとしても、そのほかの方法で、環境との切断を果たすことで、作品として成立しているものがあるのかもしれない。そういった作品群を環境との切断という視点を頼りに再検討することで、「作品」の成立前提を、考えたいと思う。
2010-01-12
58カット。歌舞練場前。(の切り抜き)

1ケ所広く間が空いてるのは、きっと1組立ち去ったに違いない。
カップルを狙って撮っているわけではないんだけど、映っていると気になるなぁ…。夏の風物詩、現代版の風俗絵巻みたいなところやよね。
2010-01-11
3コマ並べて、前後のコマと比べながら色の補正を進めている。こう横に並べると、ひとつ気になることがある。
鴨川のカップルは等間隔に並ぶ、というのは、本当だろうか?

狭めだけどきっちり等間隔の場所と、ちょっと広めで等間隔を保っている場所とがある。全体的に等間隔なんじゃなくて、局所的に等間隔が保たれている様子。妙に律儀な感じがなんだか可笑しい。
長時間露光なので、動く被写体は輪郭がはっきり映っていないけれど、いろんなこと(顔だとか、何をしているのだとか)が判定できないくらいほうが、かえってありがたいのかもしれない。
暗い時間のコマは色補正が難しくて、なかなか作業がはかどりません。つい脱線してしまう。
2010-01-09
50コマ目。
唐突に不審な青い光が横に5つ等間隔にならんでいるのを見つける。
まさか…
昔、五条のカフェでマユミちゃんとお茶をしていたとき、わざわざ奥の席から、窓辺に席を移してもらったのに、マユミちゃん、コーヒーカップを持ちながら、悠然と、「川、死体がようさん見えるわ」と言うてたことを思い出す。(わたしには何も見えませんでした。)
夏に鴨川で写真撮って何も写り込まへんわけがないわな…
とは思っていたけれど、ついに来たか。
露光中にライトをつけた自転車が前を通ったり、なかなか撮影条件が悪かったので、そういうのが原因かな、とも思ったけれど、それだと規則的に5つ等間隔に並んだりはしない。
まずは、ネガのチェック。現像ムラではない。
ライトボックスでじぃっと見る。
スキャンしたデータも見る。
ん?
正面の建物の照明が5つ等間隔で並んどる。
不審な5つの点と、中心に対して対角くらいの位置にあるし、なんだゴーストか。
良かった。
いや、良くはないけれど、原因がわかって良かった。
それでも、相手は夏の鴨川。
一旦、気持ちがオカルトモードに入ると、編集するのが少し怖い。
2010-01-08

1階の作業場から見える不自然な自然。
カメラのモード設定を試すのに、何枚かとって色補正をしてみる。
ぜいたく(?)なことに、北側の母屋との間にある中庭とは別に、南側にも1ツボほどの空間がある。どういういきさつで、こんな中途半端な空間ができてしまったのか知る由もないのだけれど、この地味な空間がけっこう好き。
水やりをしないから、
それでもなんとか自生している植物だけで構成されているプチ庭。
閉じらた空間にいるのは自分のほうなのに、
なぜかいつも、ガラスケースを覗くような心持ちで眺めてしまう。
そういう事実関係と知覚のズレみたいなの、おもしろいと思う。
2010-01-07
本日はスキャナがすこぶる不調。
昨年の暮れに『負ける建築』(隈研吾著 岩波書店 2004年)を読んでから、わたしは 、けっこう長い間思考停止していたんじゃないかと思っている。
そのくらい、すっきりとして批判的な文章であり、なによりも、この本を貫く作家の批評的な姿勢に学ぶところが大きかった。
いちばん興味深かったのは、20世紀の建築-経済-政治の関係についての記述で、写真と直接関係ないのだけれど、建築の立場から書かれた「写真の性質」についての記述は少し気になったので、抜き出しておこう。
ライトの根本にも「建築の民主主義」があったことは間違いがない。その証拠に彼は自由で流動的な空間に着目し、生涯、人間を拘束しない自由な空間を追求し続けた。しかし、同時に、空間の性状、空間の流動性を、二〇世紀の支配的メディア(すなわち写真)を使って伝達することがいかに困難であるかも、ライトは熟知していた。それゆえ彼はフォトジェニックな建築エレメントである空中にはり出したキャンティレバーをしばしば用いた。
写真は空間を伝達することには、不向きだった。空間は形態的ヴォキャブラリーに変換されて、初めて写真上に表現される。大きくはり出した屋根やスラブの形態を見て、人はやっとのことで、その空間の流動を感知することができる。キャンティレバーという形態を通じて、屋内と屋外が相互に浸透しあう様子を感知できる。特に写真のフレームの端部にうつされたキャンティレバーは、広角レンズの生み出す歪みによって、一層、その空中への大胆な持ち出しを強調するのである。ロビー邸(一九〇九年)(図17参照)はそのようにして「傑作」となった。あるいは、ライトが三〇年代のユーソニアン住宅と呼ばれる一連の住宅でしばしば試みたように(図30)、木製の横羽目板に、さらに水平のボーダーを打ちつけることではじめて、水平の流れは誇張され、空間の流動性は写真的に伝達された。写真という二〇世紀メディアは、二〇世紀建築のデザインの方向性を逆向きに規定したのである。
(『負ける建築
』 隈研吾著 岩波書店 2004年 p107から抜粋)
建築は、重く大きい建築物そのものを動かすことはできないから、その流通においては、いちばん写真に頼らざるを得ない分野であり、それだけに、写真の特性に対してシビアに、あるいは敏感にならざるを得ない、ということを知る。
写真を撮る側からは、差し出された被写体に対して、写真の特性をどう有利に働かせるか、というアプローチをとるのだけれど、その逆のアプローチ—写真の特性に応じて、被写体自体の形状が決定づけられるということ—が、建築という規模(テレビ映りを気にして痩せるタレントの比ではなく)で行われていることに驚き、そして、写真というメディアの持つ影響力の大きさをあらためて思い知らされた。
2010-01-06
本日はキャリブレーション初め。(変なの)
現像に出していたフィルムを京都駅に引き取りに行く。
ちょうど夕暮れどきだったので、自転車からおりて、街の色をたしかめながら、てくてく。
今日の収穫。「夕暮れの街は、けっこうマゼンタに寄っている」
写真の色補正をしていて、夕方から夜にかけての写真が、妙にマゼンタ寄りに仕上がるな…と思っていたら、実際の景色もけっこうマゼンタに寄っているのだ。
2010-01-05
新年は二日からこもって作業。
1点1点、水平垂直を調整してると、被写体に対して正面からきっちり撮れているか否かということが重要になるので、魚拓のようなものを扱っている印象を受ける。
shootしたもの、というよりstampしたもの、という感じ。
夜景はやっぱり難しくて、昼間撮ったものより、よっぽどフレている。撮影時は、どんどん露出がかわるし、夜で露光時間が長い分、撮影時間も長くなるから、焦りもあるんだろうけれど、思っていたより精度が悪い。春までに、改善案を考えよう。
2010-01-02

明けましておめでとうございます。
2010という数字を前に、
新しい世紀を迎えてからもう10年も経つのかと。
例年よりいちだんとストイックな年になりそうですが、
どうか、どうぞ、今年もよろしくお願いします。
すこやかに、ほがらかに、
この1年を過ごせますように。
2009-12-15
ふたご座流星群がやってきている、とのことで、
夜半にふらりと公園に向かう。
こないだ、ハルさんに「夜に公園に行っちゃダメだよ」と釘をさされたところやけど、
ごめんね、近くで夜空を広く見られる場所は、あいにくここしかないんだよ。
公園に着くまでにひとつ、公園でよっつ、帰りにふたつ、
合わせてななつの流れ星を確認する。
どんくさいことに、全部、願いごとのタイミングをはずしたけれど、
しっぽの長いのが、夜空をすぅっと横切るのを見るのは、
それだけで充分、愉快です。
年賀状の入稿も終ったし、
さて、今夜もそろそろ見に行きますか。
2009-12-09
2009年初夏撮影のフィルムをスキャニング中。
高解像度のスキャニングでは、ずいぶん待ち時間があるのだけれど、あまりPCに負担をかける作業はできないので、しぜん、ネットで調べものをしたり、読書をしたり、ということになる。
画面がスクロールするという点で、絵巻物の表現がとても気になっていて、ネットで「絵巻物」で検索をかけると、こんなページが見つかった。
早速、地獄草子絵巻をクリックする。
なんとまぁ…
春画と見まごうような赤裸々な性表現。
たまに性的な表現が出てくる、とかではなくて、全体的にそういうことになっとる…。
こういった美術作品をwebで詳細に閲覧できるというのも贅沢なことやと思うし、この横スクロールで表示のできるシステムが、良いなぁ。
昔、作品を見せるためにFLASHで横スクロールさせようと試みたけれど、読み込む画像の幅に制約があって、全体をスクロールさせることができなかった。
RIVERSIDEについては、はじめからつなげようと思って撮ったのではなくて、川向こうの光景をぽつりぽつり撮っているうちに、この被写体群を前にフレーミングする意味を見いだせなかったから、つなげることにした、といういきさつで、はじまったものだから、四角い枠で区切ってフレーミングした状態で作品を見せることに戸惑いがある。
お、やっとスキャニングが終った。
スキャンした画像を拡大して、現場で肉眼では確認できなかったディテールや、予期せぬものが写っているのを見るのが楽しい。顕微鏡で風景を見るような感じです。
夜景やから、ひとが動いたところとかは、ふわっと光の帯みたいになっているけれど、動かないものは、やっぱりくっきり輪郭が写っている。中判の解像力ってすごいなぁ。
2009-12-03
昔、ふたりのお嬢さんの家庭教師をしていたご縁もあって、いろいろお仕事をいただいていました。最初にお目にかかってから、もう15年近くになりますが、こうして忘れずに本を送ってくださるのは嬉しいかぎりです。
家庭教師としてうかがっているときに、一緒に食卓を囲みながら、いろいろ会社のことについてお話をきく機会があったのですが、ひとつひとつ断片的だった話が、この本を読んで筋道がつきました。成功も、失敗も、あらいざらい書かれているなぁ、正直な人柄がにじみでている文章やなぁ、というのが率直な感想です。
いつもけつまずくゴミ箱があったら、足をひっかけない場所にゴミ箱を移す、経営というのは、そういうこまごまとした改善の積み重ねなのよ、とおっしゃっていたことを、ことあるごとに思い出します。
かわいいお嬢さんたちは、もう大人の女性になっているのかしら。
と楽しい想像をふくらませて、そろそろお礼状を書きましょう。
2009-12-01
少しまえの夕方、ふらりと御所に出かけたら、夕暮れの光の中で、銀杏の木がことさら明るく輝いて見えていた。不思議な光景だったので、もう一度見たいと思って昼間にでかけたら、あの日の夕暮れほどパッとしなくてがっかりする。
あ、そうか…。
黄色いものは、もともと黄色に対応する波長だけを反射し、それ以外の波長を吸収する。緑色のものも同様に、緑の波長に対応する波長だけを反射し、それ以外の波長を吸収する。
夕暮れの光には、赤〜黄色に対応する波長がたっぷり含まれていて、それ以外の波長が少なかったんだ。だから、緑や青いものにとっては、もともと射してくる光に、反射すべき波長がないから、射してくる光のほとんどを吸収して、暗く沈んで見えていたのね。
そういうことを考えながら、しばらく散策。
どうして、わたしたちは、紅葉という現象を美しいと感じるのだろうか。どうして、葉は、散り際にわざわざこんな鮮やかに発色するのだろうか。(生物の生存戦略としてどういう合理的理由があるのだろうか…)とか、そんなことを考える。
ものをつくる立場としては、なにか「いい」と感じるとき、その対象のどういう要素に対して「いい」と感じるのかを考えざるを得ない。
そうして、一枚、落ち葉を持ち帰る。

なかば強引にハルさんを食事に誘い出す。
こんな紅葉まっさかりの季節に生まれてきたのに、
なんで寒色ばっかり好きなんやろ?
と尋ねたら、ハルさんは、
それでも、この季節は、玄関にいっぱい紅葉を敷き詰めてる。と言う。
あの落ち葉をふむカサカサという音が家の中で聞こえるのは、ちょっと楽しそう。
おかんの話。
何年か前の同窓会で、幹事をしていたノブちゃんが、
幹事の打ち上げの席で、感極まって泣きそうになったんやけど、
おてんばで名のとおったノブちゃんを人前で泣かしてはいけない、と思って、
かわりにわたしが泣いてん…という。
かわりにわたしが泣く???
(まぁ、他人に先に泣かれたら泣けなくなるものね…)
おかんって、そんなんやったっけ?
ほんまなら、ちょっといいやつやん…。
おかんで30余年、ハルさんは10年くらいのつきあいだけれど、
まだまだ知らないことがいっぱいあるんやなぁ、と思う。
ひとのありようにこころが触れる、ということは、
このところめっきり減っていたのだけれど、
これは、たてつづけにふたつ、ほんのりこころがあたたまった。
2009-11-05
9月下旬、歯痛が激しくなって歯医者に行った。
まえに一度、歯医者ではいやな思いをしていたので、
少し慎重に選んだ町の歯医者さん。
同い年くらいの若い歯科医は、
状況を丁寧に聞き取りレントゲンをとる。
目立った原因が見当たらない。
初診で彼はそう言った。
そうして、とんぷくを処方され、しばらく様子を見ることに。
激しい歯痛のせいで肩や首のあたりがずっと力んでいて、
ついには頭痛まで併発していたので、
早く、早く、痛みをとりのぞいてもらいたかった。
でも、その歯科医は、慎重に時間をかけて様子を見る。
とんぷくで、多少、痛みは軽減されているものの、
集中力を欠いて仕事に身が入らない状態だった。
10日ほどかけて様子を見ているうちに、少しずつ原因が明らかになっていった。
すでに神経をとって銀をかぶせてある歯の根っこのほうにヒビが入っていて、
そこが化膿しているとのこと。
状況によっては、抜かないといけないけれど、
その前後の歯も綺麗だし、できるだけ残す方向で処置していきましょう。と。
2年前、同じように激痛に襲われて駆け込んだ歯科医院では、
原因も特定できないまま、あてもののように、つぎつぎと3本、神経を抜かれた。
「これだけ抜いてまだ痛いようなら、あなたは化け物ですよ」
そう言われて帰ったあと、まだ痛みが続いていたから、慌てて歯医者をかえた。
そのときの処置のことを、いまお世話になっている歯医者さんに話したら、
「神経をつぎつぎと抜くなんて、そんな処置は絶対にしたらいけない」と、
苦々しい顔でつぶやかれた。
2年前は、
次々と神経を抜いた歯に保険適用外のかぶせものを勧めてきた時点で、
その歯医者がヤバいことが決定的になったのだけれど、
同業者の意見を聞いて、やっぱりダメだったんだと納得する。
でも…と思う。
わたし自身、医者に行けばいとも簡単に、痛みをとってもらえる、
と思っていなかっただろうか?
正直なところ、今回の通院では、原因がはっきりわかるまでのあいだ、
なんで痛がってるのに、積極的に痛みをとる処置をしてくれないんだ?と
相当恨めしく思っていた。
自分の身体の不都合を、簡便に解消してもらえる。
そう期待したのは、ほかならぬわたし自身ではなかったろうか?
2年前に不適切な処置をした歯医者をずっと非難がましく思ってきたけれど、
慎重な処置よりも「いますぐ痛みをとってほしい」と、
まるでファストフード店やコンビニに期待するのと同種の期待をしたのは、
ほかならぬわたし自身ではなかったろうか?
今回、抜かない歯医者さんにめぐりあって、そう気づいた。
「一週間で3kgダウン」というような謳い文句のダイエットも然り。
コンビニエントに、自分の身体をどうにかできる、どうにかなる、
なんて、考えてはいけなかったんだ。
2009-10-21
ようやくDICのカラーガイドを入手する。
いや、お金を払えば誰でも簡単に買えるものだし、入手しようと思えばいつでもできた。
仕事の内容的に、そろそろ入手してもいいのではないか、と、
ようやく思えたというほうが正確かもしれない。
思えば12年前からずっと欲しかったのだ。
もっと言えば、ポスターのデザインがしたいというのが12年前の夢で、わたしにとって、色指定のためにひっつけるカラーチップは、その仕事を象徴するとても素敵でキラキラしたものだった。だから、DICのカラーガイドは、わたしにとって、ただの道具ではない。デザインに携わるという夢そのものなんだと思う。とても遠いところからデザインの世界に憧れていたあの頃のキラキラした気持ちが、この小さいチップにぎゅぅっと詰まっている。
近づいてみたら、その世界は決してキラキラしているだけではなかったし、むしろ実際は泥臭くて地味な作業の積み重ねなのだけれど、それでも憧れてるだけではわからなかったものづくりの醍醐味に触れられて、結果オーライ。憧れと現実は違ったけれど、それでもやっぱり好きでいられたし、こっちの世界に来て良かったと思う。
ずっしり重いカラーガイドをめくりながら、
あの頃見上げていた山の、裾野くらいには辿り着いたのかなぁ…なんて。
さて、このカラーガイド。
最初は「こんなにたくさん!」と感激したのだけれど、
いざ、作業に入ると欲しい色にばっちり同じ発色のインクなんて見つからない。
欲しいのは、このチップとこのチップの間くらいの色…というように、のっけから難儀する。
写真でも色でいちばん苦労するけれど、ほんとうに色って難しい。
特色どうしを重ねたらどんな色になるのか、とか、
いろいろ知りたいこと、見てみたいことがたくさん。
そこらへん、まずは実験かなぁ。
やってみんとわからんことだらけやけど、だからこそ、
ものをつくるのは楽しいんやと思う。
2009-10-17
散歩ついでに、三月書房に足を運ぶ。
遠くに聞こえていた声明がだんだんと大きくなってきて、
寺町二条界隈に托鉢修行のお坊さん数名の声が響きわたる。
少し外に気を向けながら、本を物色していると、
「ほら手分けして、こっちにも来て」と、
リーダー格のお坊さんが指示を出している声が聞こえる。
え…手分け…托鉢修行は分業制やったんか。
妙に現実的で合理的な「指示」がビジネスライクに聞こえてしまって、
なんだか、ありがたみが目減りした感じ。
店を出て、寺町を下がる。
秘仏公開のポスターを見て、
わたしも、作品展示を50年に1度のご開帳にすれば、
どんなスローペースでも仕上げられるやろうし、ありがたみ(!)も増すよなぁ…と、
罰当たりなことをぼんやり考えながら、てくてく、てくてく。
その翌日、ともだちに送る荷物を準備していたときのこと。
いくつか素敵な切手があったのだけれど、
あちこちにペタペタ切手を貼ると、郵便屋さんに迷惑やろうから、
紅葉の切手だけ貼って、あとは現金払いにしようと思って、
1枚だけ切手を貼った荷物を近所の郵便局に持ち込んだ。
荷物を手にした窓口のお姉さんが、うーん、と唸りながら電卓をたたく。
?
「せっかく綺麗な切手はってはるからね。」
そうおっしゃって、チラリとかわいい切手を見せてくださる。
どうも、手もとにある切手のなかから風情のあるものを何枚かつけたそうと思案してくださっていたみたい。何円の切手を何枚はって残りは…という計算をしてはったみたいで、最終的に、京都のお祭りのかわいらしい切手を何枚か貼りたして、あとは普通の切手を二枚ほどはって料金調整というところに落ち着く。どうもありがとう。
結局、当初わたしが遠慮した「あちこちにペタペタ切手をはった荷物」ができあがってしまったのだけれど、それがほかならぬ郵便局員さんの仕業なのが可笑しかった。
ここ三日ほどのできごと。
2009-10-14
幼なじみから本が届く。タイトルは『はじめての麦わら帽子』。
本をいただく、というのはとても嬉しい。作業の手をとめて少し読んでみる。
しばらくして、思い直して、表紙カバーを脱がす。ふふふ。
表紙カバーの絵がらの淡いオレンジと花ぎれの色、
同じく表紙カバーの水色と本体表紙、栞もおそろい。淡く補色にちかい色づかいが綺麗な本です。
まだ読みはじめたところだけれど、娘さんのこと、だんなさんのこと、そして強烈に個性的なおかんのこと、おとんのこと、日々の生活のことが丁寧であたたかなまなざしでとらえられている。彼女の文章を読んでいると日だまりでぬくぬくしているような気持ちになる。
出産の際に病院をかわったことは聞いていたけれど、こんな大変で、身を切るような思いをしていたとは…。大変だったことでもひょうひょうと話すから、つい安心してきいていた。ごめんよ…。
いつもわたしのほうが励まされてばっかりだったけれど、いっぱい大変だったんだ。
活字をつたって、もう一度、ともだちと出会い直すかな。
2009-10-10
先日、内田樹さんのブログに、「こびとさんをたいせつに」というタイトルの文章があって、ちょっとおもしろかった。
私たちが寝入っている夜中に「こびとさん」が「じゃがいもの皮むき」をしてご飯の支度をしてくれているように、「二重底」の裏側のこちらからは見えないところで、「何か」がこつこつと「下ごしらえ」の仕事をしているのである。
そういう「こびとさん」的なものが「いる」と思っている人と思っていない人がいる。
「こびとさん」がいて、いつもこつこつ働いてくれているおかげで自分の心身が今日も順調に活動しているのだと思っている人は、「どうやったら『こびとさん』は明日も機嫌良く仕事をしてくれるだろう」と考える。
暴飲暴食を控え、夜はぐっすり眠り、適度の運動をして・・・くらいのことはとりあえずしてみる。
それが有効かどうかわからないけれど、身体的リソースを「私」が使い切ってしまうと、「こびとさん」のシェアが減るかもしれないというふうには考える。
「こびとさん」なんかいなくて、自分の労働はまるごと自分の努力の成果であり、それゆえ、自分の労働がうみだした利益を私はすべて占有する権利があると思っている人はそんなことを考えない。
けれども、自分の労働を無言でサポートしてくれているものに対する感謝の気持ちを忘れて、活動がもたらすものをすべて占有的に享受し、費消していると、そのうちサポートはなくなる。
「こびとさん」が餓死してしまったのである。
知的な人が陥る「スランプ」の多くは「こびとさんの死」のことである。
「こびとさん」へのフィードを忘れたことで、「自分の手持ちのものしか手元にない」状態に置き去りにされることがスランプである。
スランプというのは「自分にできることができなくなる」わけではない。
「自分にできること」はいつだってできる。
そうではなくて「自分にできるはずがないのにもかかわらず、できていたこと」ができなくなるのが「スランプ」なのである。
それはそれまで「こびとさん」がしていてくれた仕事だったのである。
最初の大学のころは、卒業研究のCのプログラムをさくさく組んでくれるこびとさんがいた。二度目の大学では、課題の提出間際になって焦るわたしに、横からそぅっと手を貸してくれる少し大きなこびとさんがいた。それは、どちらも目に見えるこびとさんで、そのうえ、こびとさんがこびとさんを呼び、複数で作業にあたってくれたりして、とてもお世話になったことを今でもときおり思い出す。
自分で仕事をするようになると、そういう目に見えるこびとさんはもういなくて、自分のなかのこびとさんにお願いしなくてはならない。が、わたしのこびとさんは、相当引っ込み思案なのか、のんびりなのか、なかなか出てきません。最後になって出て来てくれるときもあるし、恐ろしいことに、出て来ないまま締め切りを迎えてしまうこともある。
わたしはまだ、こびとさんを確実に呼び出す術を知らない。
でも、追い込まれなければ絶対に出て来ない。
こびとさんが出てくるまでの作業は、無駄になるとわかっていても、
手を動かしはじめることなしには、こびとさんは出て来ない。
10日以上延々プレッシャーをかけて、
わたしのこびとさんは、今日になってやっと顔をのぞかせた。遅いよ…
ぎりぎりになって出てくるのはやめてほしいけど、どうしたらいいんだろう。
2009-10-07
台風が来るから、と、母屋の奥さんが声をかけてくださる。
台風対策なんてしたことがなかったら、
「なにしたら良いんでしょうかね?」と尋ねたら、
母屋は網戸をはずして、2階のベランダの植木鉢は部屋に入れた、とのこと。
そっか。
早速、部屋にブルーシートをひき、ベランダの鉢植えを部屋に運ぶ。
「寂しいとグリーンって増えるんだよね。」
と、何気なく言ったことがあるけれど、知らないあいだに鉢は15個に増えていた。
どうりでベランダが手狭なわけだ。
全部運び入れたら、部屋の一角がさながらジャングルのよう。
網戸をはずして、風で飛びそうなものは、ひととおり部屋の中に入れてしまう。
話しが終るころ、部屋中に散乱しているインクの染みのついた紙を見て、
母屋の奥さんが怪訝な顔。
「それなに?」
「あ、デザインに使おうと思って…。」
インクのしずく跡のイメージが必要で、ソフトをこねくりまわすよりも、実際のインクでつくったほうがリアルだろう、と思って、プリンタの替えインクを、紙にポツリポツリやっていたら、「バランスの良いしずく跡がほしいなぁ」が「もっと威勢の良いのが欲しい!」と、だんだん盛り上がって、ついには椅子に乗って高所から滴下。そうやって、インクを滴下しまくった紙を乾かしていたところに、母屋の奥さんはやってきた。そりゃ気持ち悪かったろうと思う。
なんでもかんでもPCで済ませようとすると、こじんまりしたものができあがってしまう、というのが最近の反省点。でも手でモノをいじると、必要以上に盛り上がってしまう。
2009-09-30
シルバーウィークの帰省にあわせ、実家にて前倒しでお誕生日会。
その数日後、両親が京都に来た折りに、あらためてランチでお祝い。
その翌日、エッちゃんとオヨシから少し気の早いハガキが届く。
深夜、妹にはじまり、朝にはエッちゃんとクニちゃん、そして母からお祝いのメールが。
午後はイマムラさんに映画に連れ出してもらい、楽しい時間と素敵なプレゼントをいただく。
帰ったら、ポストにはサワイちゃん一家からの家族総出の寄せ書きハガキが。
そして、東京のケイコさんから届いたお菓子とカードは母屋の奥さんが預かってくれていた。
34度目の誕生日をこんなにもたくさん祝ってもらって、
これ以上いったい何を望もう。
居場所のない思いをすること、
ふと、いなくなってしまいたくなることが、決して少なくはなかったけれど、
たくさんのあたたかい想いが、この世界にしっかりわたしをゆわえつけてくれている。
どうも、どうもありがとう。
2009-09-27
昨日書いた『塩一トンの読書』はエッセイ集、あるいは書評集のようではあるけれど、ところどころ、著者のしずかな社会批判が込められていて、それがあまりにしずかなので、見過ごしてしまわないように記しておこうと思う。
バイリングアルがよいなどと、人間を便利な機械に見たてたがる、無責任な意見が横行しているが、ものを書く人間にとって、また、自分のアイデンティティーを大切にする人間にとって、ふたつの異なった国語、あるいは言語をもつことは、ひとつの解放であるにせよ、同時に、分身、あるいは異名をつくりたくなるほどの、重荷になることもあるのではないか。
(『塩一トンの読書
』須賀敦子著 河出書房新社 2003 p40から抜粋)
これは、フェルナンド・ペソアという詩人について書かれた文章にさしはさまれていた。
在留外国人の子どもの教育支援に携わっている母から、母語ではないことばで教育を受けなければならない彼らの抱える困難を、折りにふれ聞いているから、この部分がいちばん気になった。
もちろん彼らの多くは「バイリングアルがよい」などという教育的配慮から、日本で教育を受けているわけではない。両親の仕事の都合でいたしかたなく、日本で教育を受けることになった者がほとんどだ。
母の話を聞いていて、あるいは、帰国子女である自分の経験と照らして、
彼らのその重荷を、教育者がどれだけ理解できているだろうか、と、
ときに思うことがある。そういうところと共鳴した。
あと、関川夏央さんの『砂のように眠る―むかし「戦後」という時代があった』という本について書かれている文章の最後のほう。
(中略)いったい、なにを忘れてきたのだろう、なにをないがしろにしてきたのだろうと、私たちは苦しい自問をくりかえしている。だが、答えは、たぶん、簡単にはみつからないだろう。強いていえば、この国では、手早い答えをみつけることが競争に勝つことだと、そんなくだらないことばかりに力を入れてきたのだから。
人が生きるのは、答をみつけるためでもないし、だれかと、なにかと、競争するためなどでは、けっしてありえない。ひたすらそれぞれが信じる方向にむけて、じぶんを充実させる、そのことを、私たちは根本のところで忘れて走ってきたのではないだろうか。(『砂のように眠る―むかし「戦後」という時代があった
』 関川夏央著 新潮社 1993 p157から抜粋)
これにいたっては、もうわたしが書き添えることなんて何もないと思う。
2009-09-26
楽しげな雰囲気が香りたつような表現で、いいな、と思ったのは、
須賀敦子さんの『塩一トンの読書』(河出書房新社 2003)。
仕事として書物に携わりながら、
でも、ときにこういうスタンスで本が読める、というのは、いいなぁ、と、心底思う。
サワイちゃんから「須賀敦子さん、翻訳家で、エッセイも良いんだよ。」とおすすめされていたので、作業のあいまの息抜きに『霧のむこうに住みたい』をひもといてみた。
情景の描写が重すぎも軽すぎもせず、風通しのよい文章だったから、二冊目を手にとった。
タイトルの塩一トンは、須賀さんが結婚したての頃、イタリア人の姑から、「ひとりの人を理解するまでには、すくなくとも、一トンの塩をいっしょに舐めなければだめなのよ」と言われたことに由来する。塩一トンをいっしょに舐めるというのは、苦楽をともに経験するという意味らしい。
どの分野にあっても、ひとつことに携わっていると、理想と現実との乖離だとか、苦悩や困難があったりするのだけれど、でも、最後のところで、どちらに転ぶか、は大事なことだと思う。
いろいろあるけれど、それでもやっぱり好き、
というところに転ぶほうが、そうでないよりずっと幸せだし、
それこそが継続してひとつことに携わっていくうえでの、強みではないかと思う。
塩一トンの読書でありながら、「おいしいおやつみたいにこの本を」と言えるこの幸福感が、読むわたしをも幸せなきもちにさせてくれる、と思った。
須賀さんは夙川から芦屋のあたりで育っているので、同郷の人だ。
そう思うと、イタリアの生活を綴ったエッセイでも、彼女の文体には、なにかあのあたり(いわゆる阪神間)の風土、風通しのよさみたいなものがあらわれているような気がするから不思議だ。
ほとんど現実と向き合うだけで精一杯で、かれこれ10年近く、小説、というものをほとんど読んでいなかったけれど、これを機会に、また小説、読んでみようかな。
そう思わせる一冊でした。
いざとなるとやっぱり、作業は夜にずれこむ。
26時、中京の郵便局に出かけた戻り、
この時期にしては星がたくさん見られたので、まわりみちをする。
輪郭はまだたよりないけれど、こまかい星までたくさん見える。
寒くなったら、もっとくっきり見えるんだろうな。
今年は蛍を見なかった。
夏の暑さもほどほどだった。
だからだろうか。
暮れに向かっている、という実感がまだ湧かない。
この数年は、季節のうつろいにすら、ひりひりしていたのに。
2009-09-22
アルバム、と言えば、リサちゃんを思い出す。
Bobbin Robbinのお客さんで、もうひとりリサちゃんがいて、
(向こうから見たら、わたしのほうがもうひとりのリサちゃんなんだけど…)
そのリサちゃんは写真家で、そのときちょうどギャラリーで個展を開いていた。
結婚式の写真をハンドメイドのアルバムにまとめたものを展示していたと記憶しているけれど、愛嬌のあるアルバムとは裏腹に、写真が鋭かったのが印象に残っている。
鋭く、それでいて、凛としたうつくしさの備わっている写真だった。
わたしがもし間違って結婚式をあげることにでもなったら、
迷うことなく彼女に撮影を頼むだろう。
自分もまた、撮った写真をアルバムに仕立てる依頼を受けたので、
ふと、彼女のことを思い出してしまった。
もうひとりのリサちゃんは、今ごろどうしているんだろう。
2009-09-21

昨日仕上がったアルバムに一晩重しをかけてプレスをしていました。
これでやっとアルバム完成。大きな瑕疵もなく仕上がったのでほっとしました。大きさは22cm正方くらい。

表紙はBobbinRobbinでひと目惚れした薔薇の刺繍の入った白い布でくるんでいます。見返しは濃いグリーンのタント。扉にはペールグリーンのトレーシングペーパーをあしらっています。グリーンにこだわるのは、写真の撮影場所がLe Vent Vert(緑の家)だったから。前日にノムラテーラーで買った草っぽい紐も無事栞として採用されました。栞の主張が強いので、花ぎれは抑えめにして白色のものを。

本文の厚みがあまりなかったので、表紙のボリュームと不釣り合いになるんじゃないかと少し不安だったけれど、サワイちゃんがうまく丸背にしてくれて、おさまりよくなりました。色が沈みすぎじゃないかと思っていた見返しの濃いグリーンも、白いボリュームの中にスッと差し色のように見えて◎
紙のT目、Y目もだいたい間違わずに判断できるようにもなっているし、細かい作法を忘れないうちに、もうひとつくらいつくらないと、教えてもらった技術が定着しないな、と思うので、目前に控えている仕事がひと段落したら、作品をまとめたものを製本することも考えておこう。(欲が出てきてる…)
スギモトさんの工房でのポイントレクチャーにはじまり、わたしのアルバムでも布の裏打ちからはじめて、丸二日、つきっきりで教えてくれたサワイちゃんに、深く感謝。どうもありがとう。
2009-09-20
Linnetとノムラテーラーをはしごして、明日の作業のための準備をする。

ノムラテーラーで草のようなおもしろい紐を見つける。
これ、栞になるのかな?
ソツなく上品に仕上げるつもりが、ちょっと遊びたくなってしまったのは、
しかけのあるブックデザインという本を見てしまったからだと思う。
あと、直前まで見ていた山名文夫さんの作品集からも影響を受けたかもしれない。
布や糸を使うから、どうしても手芸に材料を求めてしまうけれど、
手芸材料は気をつけないと、甘ったるい感じに仕上がってしまう。
持ち主がもう少し成長したときに気恥ずかしい思いをしないように、
かわいいけれど「甘ったるく」はならないようなさじ加減でゆきたい。
どうか、うまくいきますように。
2009-09-16
なんだかいやな感じ、だとか、なじめない感じ、だとか、
そういう齟齬としてとらえられた感覚が、
ずいぶんあとになって、他人や自分のことばに輪郭づけられることが多い。
ことばはいつも後から追いついてくる。
最近やっとそういうことがわかりかけてきた。
ことばで輪郭づけられるまでの、居心地の悪さのようなものは、
勘違い、くらいのことばで簡単に片付けられるものかもしれない。
でも、ことばにならなくても、そういうもやっとした感覚は、
もやっとしたまま大事にとっておいたほうがいいのだ。
0.01とか0.00023くらいの、
ともすれば、端数や誤差として削られて0にされちゃうくらいの微細なズレの感覚は、
ことばに出会って増幅され、確たる差異として認識されうるものかもしれないし、
簡単に切り捨ててしまってはならない。そういうことを考えた。
なんとなく気持ちがわるい、とか、
なんとなく居心地がわるい、とか、
なんとなくなじめない、とか、
そういう気分にはならないにこしたことはないけれど、
そういのをなかったことにし続けると、
知らないあいだに大きくなにかを損ねてしまう、気がする。
感じていることに気づかないふりをする、なんてことは、
絶対にしないほうがいい。
身体で感じることをあなどってはならないし、
ほかでもない自分が感じるところを、もっと信用してやろうよ、と、
なぜかそう、強く思った。
2009-09-14
今週末に控えている製本の日のために、こまかい材料を揃えはじめる。
淡いグリーンと白を基調にした仕上がりを想定しているので、美篶堂で、グリーン系の栞を、画箋堂で見返し用の紙を入手する。
(年頭にうかがったllenoのスギモトさんところのノートづくりではじめて「ミスズドウ(美篶堂)」という名前を知り、わたしの机上にある4年前にいただいたメモ立てが美篶堂の製品であることが発覚。それから半年するかしないかのうちに美篶堂の出している本づくりの本を読むことになり、ついに、実際に美篶堂の店舗に足を運ぶまでに至る…)
さて、製本は、まったくはじめてのことで、わからないことばかりだから、とりあえず、世の中の本を見てみようと思って、書店へ向かう。
書棚の本を、斜め上から見る。
花ぎれと栞の色がどんな風になっているか。
気になる本は、本を開いて、見返しの色をチェック。
もっと気になる本は、ちょっと失礼、表紙カバーを脱がしてみる。
ふだん本の表紙カバーを剥ぐことなんてほとんどなかったけれど、
剥いでみると、一見地味な本でも、表紙にエンボス加工が施されていたりして、
見えないところに趣向が凝らしてあることに驚かされる。
見返しにクラフト紙が使ってあるものとか、あとは、帯と見返しの色がそろえてあるのも、少し意外でおもしろかった。小口が染めてある本は想像以上にカッコよかった。
こんな風に本を見るのははじめてだったので、なんだか新鮮。
そして、小口と天地を染める、というプランが現実味を帯びてくる。
さっそく、作業場に戻って実験。
小口と天地に色をつけるために、スタンプ台を使うという手段があると聞いたので、シルバーのスタンプでテストをする。サンプルにペタペタしてみたが、これは失敗。色ムラが出るのと、乾かしたあとでも銀粉が手についてしまう。コツがあるのかな。
ネットで検索をしていると、パステル+フィクサチーフで小口を染めてあるのを見つける。どうやってやるんだろう…
と思っていたら、工作箱からマーブリングのセットが。わが家にはちゃんとミョウバンもある。すでに印刷済みの本文に加工するのだから、失敗は許されないけれど、小口のマーブル染めは、トライしてみたいところ。
あと、花ぎれも用意せねば。
水引なんかに布を巻きつけたら自作できるよ、とサワイちゃんが言ってたので、花ぎれはできれば自作でゆきたい。本文の厚みが1.2cmほど。せいぜい1.5cmの幅にどういうアプローチができるんだろうか。
いよいよ工作ウィークがはじまる。
本づくりのブームを、他人事のように思っていたけれど、いざ手を動かしはじめると、多くのひとが本づくりに魅かれる理由がわかる気がする。
2009-09-12
作品とはまた別で、まとまった量の写真を編集する機会をいただいた。
複数の写真が配置されることによってうみだされるリズム、とか、仮構される、時間性、空間性。作業をしているうちに、だんだんそういうことが気になってきた。
実際にはまったく脈絡のない写真でも、並べると、それぞれの文脈とはまったく別の、あたらしい意味がうまれたりする。
おもしろいのだけれど、おそろしい、とも思う。
先週末、メゾンドエルメスで開催されている名和晃平さんの「L_B_S」展を観に行った。
入り口のところで、監視員の方に、「作品にはお手を触れないでください」と注意される。わざわざ、こんなところまで足を運ぶような客に、わざわざ、そんな注意をせんといかんもんなのかなぁ…と思っていたら、その理由がすぐにわかった。
表面の質感に対する関心を強くひき起こす作品。注意されなかったら、つい触って確かめたくなってしまっていただろうな、と思う。
展覧会タイトルのL_B_Sの、LはLiquid、BはBeads、SはScumで、展覧会はその3群の作品から構成されている。
Beadsは、鹿の表面を覆うビーズによって中に入っている鹿の像は歪められている。ビーズで覆われた透明のボリューム。
Liquidは、グリッド状に発生しては消えてゆく泡。うまれては消えてゆくその白い泡の表面に、しばらく見とれていた。
わたしにはどちらも、とても映像的に見えた。
これらは、塊、ボリュームとして受けとめることもできるし、その表面に生起する映像として受けとめることもできる。Scumに関しては、触覚に訴えかける表面の質感が特徴的であり、ものの存在の多層性、ということを考えさせられた。
ドアマンと、店内の雰囲気にビビりながらも、勇気を出して観に行って良かったと思う。
2009-09-11
トーンカーブと格闘するうちに、夏が終わる。
写真は、撮った後が大変、ということがよくわかった。
色はほんとに難しい。相当色の偏った写真ばかりだったから、苦労したというのもあるけれど…
どうやったら、もっとスピードと精度、あがるんだろう…
言葉づかいに違和を感じることがある。
昔から気になっていたのは「家族サービス」。
たいせつな家族と一緒に過ごす時間を、サービスというビジネスのタームでしかとらえられないことが、なんとも寂しくていやだな、と思っていた。
そういう違和感に通じることが書いてあったので抜き出してみる。
書店にはビジネスコーナーがあり、「MBAに学ぶ企業戦略」だとか「ブランドエクイティ戦略」だとか「マネジメント戦略」といった「戦略本」が平積みとなって所狭しと並んでいます。わたしはいつも、ここはどんな「戦場」なのかといいたくなります。
いったい、いつからビジネスが「戦争」になったのでしょうか。わたしの経験からいっても、モノの交換から始まって高度消費資本主義の現在にいたるまでの「商取引」の原理からいっても、ビジネスはモノを媒介とする平和的なコミュニケーションであり、戦争のアナロジーで語れるようなものではないはずです。
(『反戦略的ビジネスのすすめ』平川克美著 洋泉社 より抜粋)
そういう好戦的な言葉づかいが蔓延することで、時代の風潮がつくりだされる、というようなことも書かれていた。
本屋さんに行ったときに、ビジネスコーナーで感じる「いやな雰囲気」だとか、ひとが、ビジネスのノウハウを語るときのその語り口に対する違和感だとか、そういったものの理由がわかった気がした。
戦略的に誰かを出し抜いても、そういう相手にはいずれ出し抜かれるし、結果として出し抜かれなかったとしても、出し抜かれるかもしれない、という不安や緊張のなかで競争するようにして仕事をするのは、必ずしも良いパフォーマンスを生むとは思えない。それよりは、協調して互いの利益を確保するほうが、長期的にはプラスとなるんじゃないの?ということは、漠然と感じていた。お客さんが相手でも、業者さんが相手でも、あるいは同業者が相手でも、それは同じことだと思う。
だから、そういう「刺すか刺されるか」みたいな殺伐とした雰囲気を、なんかしんどい、と感じていたところに、この本に出会って、少しほっとした。
戦争のアナロジーで語ることによって、ビジネスをもっとほかの枠組みでとらえる可能性が削がれている、というこの本の主張に、わたしは深く共感する。
こういうのはほんの一例で、メディアの、ひとの、言葉づかいに違和を感じることが日増しに多くなっていってる。その多くが、そういう言葉をつかうことで、あえて、生きることを貧しくしているんじゃないか、そう感じるような言葉づかい。
はたして、時代がかわったのか、自分がかわったのか。
2009-08-26
スピーディー、と言えば、聞こえはいいのかもしれないけれど、今年に入って、あまり自分のペースやなく動いてたんだろうな。ゆっくり考える、とか、感じる、とかやなかったように思う。
なんとなく、すべてが拙速。
目先のことばかりにとらわれている。
無心に手を動かしていると、それはそれで、しっかり充実もしているのだけれど、「考える」をおろそかにしたり、あとまわしにしとるし、このままやとあかんな、と、今日ふと気づいた。
いまのこの作業がひとだんらくついたら、少し考える時間をつくろう。
なにより、毎日がのっぺりつるんとしていて、感じる、の精度が危機的にさがってる。
2009-08-20

たぶん、この二匹は同じころに生まれたんだと思う。
左のほうは緑色の目をしていて、右のほうは黄色い目をしている。
ほんで識別するのに、GとY。
Gは積極的にえさをねだりにくるし、カメラを構えてもあまり警戒もしていないけれど、Yは自分からねだりもしないし、カメラを構えるととっさに逃げる。Yのほうが涼しげな顔立ちをしていて好みなんだけど…。
えさをもらうためなら、なりふりかまわないGに比べて、Yは「もらってやってもいいわよ」といった体。
猫好きでもないのに、毎日顔をあわせるもんだから、顔立ちで猫を識別できるようにしまった。
ま、ご近所さん、みたいなもんか。
2009-08-11
昨晩は来客があったので、久しぶりにぺルー料理をつくってみた。
ほんで、今日はその残りものがお昼ごはん。

手前の海鮮サラダのようなものが、セビッチェ(Cebiche)。奥がアヒー デ ガジナ(Ají de gallina)。セビッチェは白身魚をレモンでしめて、トマト、たまねぎなど生野菜と和えたもの。たまたま鯛が安かったので、今回は鯛でつくってみた。コリアンダーは嫌いなひともいるので、混ぜずにトッピング形式にしておく。
アヒー デ ガジナには、鶏のムネ肉をゆがいて割いたものが入っている。アヒー(とうがらし)が入っているので、もちろん辛い。カレーのようなとんがった辛さではなくて、くちあたりよくマイルドだけれどじわっとくる辛さ。来客ふたりは最後まで「カレー」と呼んでいた。
昨晩はこれにプラスじゃがいものビシソワーズ(ぺルー料理ではない)、という献立だったのだけれど、いちばんうまくできたのがビシソワーズというのが、なんとも複雑なところ。
ひとに食べてもらう、と思うと、料理って気合いが入るもんやね。
2009-08-09
7月末までに引越すはずだったのですが、引越していません。
紆余曲折の末、まだしばらく住んでいてもいい、ということになって、暑い、暑い、と言いながらも京町家に住み続けています。
結局、生活そのものもなんらかわることなく…。
わたし自身が、そう望んだのかもしれないんだけれど。

2009-07-31
年をおうごとに、ことばのレパートリーは増えているはずなのに、いざとなると、ほんとうに伝えたいことを、まっすぐ伝えることが、どんどん、難しくなっていく。
ことばがうわすべりするのが、自分でもよくわかっていて、
つらくなって、さらにことばを重ねて、撃沈。
ほんとうは、すごく感謝していることとか、
その真摯な姿にこころをゆさぶられたこととか、
そういうことを伝えたかったのに。
2009-07-28
もうどうしようもないタイミングで、どうしようもなくひとを好きになってしまうことって、あるんだな。
前からずっと、そのひとが濃やかな感受性をたずさえていること、気にはなっていたけれど、たわいのない話のなかでそのひとが口にした「夕陽が綺麗だったから」のひとことで、すっかり好きになってしまった。
どうしたものだか。
そのひとに会うことができるのは、もうあと2回。
あと2回。
2009-07-22
昨年撮ったのをいったん編集して、まわりの人に見せたら、「もっと夜景を見たい」と言われ、夏至のころ、再撮影。
撮影開始時間を1時間ほど遅らせる。
暗くなると露光時間が長くなるから、いろいろ問題が出てくる。
ライトをつけて容赦なくカメラの前を通り過ぎる自転車、とか。
いちゃつくカップルが増える、とか。
ほぼ50m間隔で三脚を立てて撮っているのだけれど、いいポジションには必ずはげしくいちゃつくカップルが居座っている。
一度撮ったものの仕上がりを見ながら、いろいろ検討中。
夜景は難しいわ。
2009-06-23
大事にされていない、と思う仕組みのなかで、一生懸命、周囲のひとをたいせつにしよう、と思って頑張ってみたけれど、もう限界かなぁ。大事にされていない、と感じ続けることは、少しずつ少しずつ、こころとからだを蝕んでゆく。
それでも幸せだと思うのは、大事にされていない、ということを明確な痛みとして感じられるくらい、わたしは、たいせつに育てられたこと。
大事にされていないことに慣れてしまったひとは、そのことに痛みは感じない。あるいは、痛みを感じていることに、気づいていないだけかもしれない。でも同時に、自分が他人を大事にしていないことにも、気づかない。
久しぶりに、ざっくり傷ついちゃったかな。
2年ぶりに縫製業者のおっちゃんに電話をかけると、「おぉ、リサちゃんか、最近どないしとるん?」と。
かんたんに近況を伝えると、
「あんたまだ結婚してへんのかいな?はよ結婚したらいいのに。あんたなら、なんぼでも寄ってくるオトコはおるやろに、よっとる(選り好みしてる)んちゃうか?」
と、厳しいコメント。
「そんなことないですよ。」とこたえると、
「なら、オトコに隙を見せへんのやろ?」とぐっさり。
あの…注文の電話なんですけど…
でも、久しぶりの発注にもかかわらず、快く仕事を引き受けてもらえて、
さらには、結婚の心配までしてもらって…
(以前発注したときは、食べていける仕事あるんか?と心配してくれてはった…)
つくづく、ありがたいご縁やと思う。
最初お目にかかったときは、とても気難しそうな印象だったけれど、いざおつきあいしてみるとほんまにあったかくて、繊細で、こういうご縁は大事にしたい、と心底思う。
注文の電話なのに、こころがほっこりあったかくなって、かたく閉じつつあったこころが、ほんの少しほころびました。
おっちゃん、ありがとうね。
2009-06-10
忙しいと、家が荒れる。
どうもわたしはそれが苦手。
どっと忙しいさなかには、
この忙しさがおさまれば、まず「家事をしたい」と思っている。
家事だけの毎日、というのはとても耐えられそうにもないけれど、自分の身のまわりのことや家事に丁寧に手間をかける、というのは、とても贅沢なことだし、なにより気分がいい。
目のはしで、階段のほこりや、取り入れっぱなしの洗濯物が目についていながら、「いまは仕事に専念、制作に専念」と、対応を先送りすると、「家事をする時間がほしい」という気持ちは、ほとんど熱望に近くなる。
冬用のラグを片付けて、散乱していた本をまとめて書架に戻し、洋服箪笥の中を整理して、探していたパジャマとスラックスを鞄の下から発見。古い謡本を片付け、段ボールの空き箱を解体して、しばってまとめる。トイレを掃除して、床に掃除機をかけて、洗濯物にアイロンをかけてしまう。
2時間ほど掃除をしていたら、汗びっしょりになる。
やれやれ、だいぶ片付いた。
2時間で済むような掃除なら、いつでもできるじゃないかと言う人がいるかも知れない。
毎日3時間も4時間も酒飲んで、バカ映画みてごろごろしているんだから、その時間にやればいいじゃないか、と。
そういうものではないのだよ。
それは家事というものを本気でしたことのない人の言葉である。
家事というのは、明窓浄机に端座し、懸腕直筆、穂先を純白の紙に落とすときのような「明鏡止水」「安定打座」の心持ちにないとなかなかできないものなのである。
お昼から出かける用事がある、というような「ケツカッチン」状態では、仮に時間的余裕がそれまでに2、3時間あっても、「家事の心」に入り込むことができないのである。
というのは家事というのは「無限」だからである。
絶えず増大してゆくエントロピーに向かって、非力な抵抗を試み、わずかばかりの空隙に一時的な「秩序」を生成する(それも、一定時間が経過すれば必ず崩れる)のが家事である。
どれほど掃除しても床にはすぐに埃がたまり、ガラスは曇り、お茶碗には茶渋が付き、排水溝には髪の毛がこびりつき、新聞紙は積み重なり、汚れ物は増え続ける。
家事労働というのは「シシュフォスの神話」みたいなものなのである。
(内田樹のブログより抜粋)
内田樹さんの書いた、
お昼から出かける用事がある、というような「ケツカッチン」状態では、仮に時間的余裕がそれまでに2、3時間あっても、「家事の心」に入り込むことができないのである。
というのは、家事に対してというよりむしろ、制作に対して感じている。
単純に作業時間と成果が連動する世界ではないから、2時間を実りあるものにするためには、実際はその倍以上の時間的余裕と、心理的余裕が必要だと思う。
いかがでしょう。
今年の春先からか。腸の調子がすこぶる悪い。
いまはやりの過敏性腸症候群だ。
週末はついに、胃までしんどくなって、早朝5時に胃痛で目覚める。
だめな一日…と思いながら、からだを引きずるようにして撮影に出かける。
本調子でない分、動きも緩慢になっていたのだけれど、かえって、世界の肌理を近くに感じた。
最近、忙しくしていたせいで、しっかりものを見るペースで生きてなかったのかもしれない。
ものをつくるのには、調子が悪いくらいがちょうどいい、というのは、たしか仲條正義さんの言。
絶好調で全速力、では見えないものもあるんだな。
2009-06-05
母屋の軒先に、鮮やかなマゼンタの花。
艶っぽいなぁとしばらく眺めていた。
あとから、母屋の奥さんに、それがクジャクサボテンという名前だということと、2〜3日しか咲かない、ということを教えてもらった。
なにげなく目にしたものが、実は貴重な体験だったりするんだな。
ここのところ、慢性的な苛立ちを抱えていて、あたりまえのようにあるもののありがたみ、忘れかけていたかもしれない。
ダメダメや。
古い町家に引越して、大家さんから最初に手渡されたのが、家賃帳。1年分の家賃の領収書を一冊にまとめてあるもので、レトロな風情がなかなか、好い。
毎月5日までに、家賃とその家賃帳と、光熱水道費を大家さんに届けるのが、ルール。
光熱水道費は、母屋の方がまとめて支払ってくださっているので、はなれだけの子メーターを、自分で検針して、はなれの使用量を、電気・ガス、それぞれ計算してお届けする。
わたしの住んでいるはなれは、もともと1階と2階をわけて間貸ししていたものだから、子メーターもそれぞれ2つずつついている。
1階分と2階分、ガス2つ、電気2つ、都合4つの子メーターをそれぞれ検針し料金を算出する。最初は、面倒だなぁと思っていたこの計算も、もう残すところあと2回、と思うと、寂しくなる。
住めば都、とはよくゆうたものだ。
2009-05-17
ずいぶん長い間、書きそびれているな、と思っていたら、2ヶ月もあいてたのか…。
作業内容をノートにメモするようにしたら、それでことたりてしまっていた。
つないだ写真のラフを出力して、何の気なしに、蛇腹折りにして、手のひらサイズにしてみたら、これが意外とよい感じだったので、工作にのめりこむ。
PCで作業するより、実際モノを触っているほうが楽しいな。
晴れの日は撮影に出るほうが気分いいし、PCでの作業は、実際のところ、工程のなかでいちばんストレスフルなのだろう(いちばん重要だけど)。
そうはいっても、製本の目処がたったら、PC作業に戻らないといけない。
明日は、友人と一緒に杉本博司の展覧会を見て、場所を四ツ橋に移して、別の友人の展示を見て、東急ハンズに製本の道具を探しに行って、帰りに紙も選んでくる。
あと、できれば道頓堀の《とんぼりリバーウォーク》も見てみる。
土、日、と雨が続いたら、月曜の朝の光は綺麗だろうな。あまり欲張らずに早めに帰宅しよう。
大切なひとを亡くし、しばらくぼんやりしとったん。
熱いものを触ってギャーっと叫ぶような、そういう生理的な反応が続いていたんだと思う。
そういうこころのありようで過ごしていたから、ましてや、ことばを綴るような状態、ではなく。
ただ、わたしがのんきに彼岸なんてタイトルで文章を書いているときに、そのひとは病と闘い、そして、まさしく彼岸に行ってしまった。
葬儀に向かう夜行バスで、不意に目が覚めたのが朝の5時。
オレンジがかった朝の光で満たされた世界。
空に向かってぬくっと存在を示しているのは、富士やったんやろうか。
見たことのない美しい時間やった。
2009-04-15
歴史は苦手科目だったのだけれど、昨年あたりに出会った網野善彦の著書がおもしろくて、時間を見つけては、読み進めている。
川岸を撮っていることもあって、気になって読んでみたのが、『河原にできた中世の町―へんれきする人びとの集まるところ (歴史を旅する絵本)』(網野善彦著 司修絵 岩波書店 1988)。これは、児童書にしてはとても深く難しい内容を扱っている。
ふるくから、川べり、山べりなどの、自然とひとの生活の営まれる世界との境目が、あの世とこの世の境だと考えられていた。だから、向こう岸(彼岸)は、そのまま彼岸なのだ。ここ数週間スキャンしていたフィルムは、彼岸の写真だ。
写真家の中には、人の営みと自然との境がおもしろい、という人がけっこう多いのだけれど、そういう境に魅かれる気持ちの奥底には、本人も自覚しないかたちで、生と死に対する関心が横たわっているのかもしれない、などと思う。
さらに、そういう境の場所は、人の力のおよばぬ神仏の世界に近いので、人と人のこの世での関係もおよばないところとされ、物と物、物と銭を交換しても、あとぐされがない、ということで、商いをする場所として、発展した。
おもしろいのが、もし人びとの生活の中で物の交換が行われ、物を贈ったり、お返しをしたりすれば、人と人との個人的な結びつきが強くなってしまい売買にはならない、という理由で、ものの交換や売買を行う場所として、この世の縁とは無関係な場所が選ばれた、といういきさつ。
そういう、ひとの生活意識をベースに、社会がどう構成されていったか、という描写がとてもおもしろい。
今村仁の著書にある、貨幣と死の関係が、どうしても実感として理解できなかったけれど、これを機にもう一度読み直してみようかな。
2009-03-29
さきおととい、夢のなかのわたしはあまりに幸せだった。
夢の中に置いてこればよかったものを、
幸せをぎゅっとつかんだまま目覚めたものだから、
かえって朝がつらかった。
今年いちばんの底にいる。
いつもの交差点で、信号の赤をぼんやり見上げながら、
決して言語化してはならない気もちに、4つの文字をあてがった。
もう思春期でもないんだから、と自分を諌めてみたけれど、
どうにも気もちが持ち上がらない。
こういうときは、歩くに限る。
撮影と称して歩くことで、
わたしはどれだけ救われてきたことか。
今年いちばんの底にいる。
2009-03-27
静かな、それでいて、ある強度をたずさえた光。
狂おしいほど、の光に、
ひきずられるようにして、家を出る。
2009-03-07
早朝の撮影。
いちにちの始まりは、まず青から順に届けられる。
そのあとミドリが。黄色が。
そうして最後にやっと赤が。
まだまだ低すぎる露出とにらみあい、
かじかむ手を缶コーヒーであたためながら、
世界のことを少し知った。
2009-03-05
ちまたには、時間を管理する本がたくさん出まわっているけれど、わたしは、細かく時間をきざんで、管理するのも、また、されるのも、きらいだ。
この気質は、学者の家庭に育ったことに因るものかもしれない。
ひとつのことを数十年と考え続ける人間が家族にあって、また、そうすることでしかたどりつけない境地があるということを、間近で見知っている。
締め切り間際に発揮される集中力もあれば、時間から解放されたのびやかな状態でしか発揮されない集中力もある。
わたしはもっぱら後者のほうで、ならその種の集中力を活かして仕事をする方法を考えなければならない。わたしが、わたしのなかに持っている時計は、とてもゆるやかな時を刻む時計で、のんびりしてるんだと思う。
それはこの時代にはそぐわないけれど、そぐわないなりに生きて、
そして死ぬまでの時間をかけて、
もう少し濃やかにこの世界の手触りを確かめたい、と思う。
2009-02-18
内田樹さんのブログにあった、村上春樹のエルサレム賞の受賞スピーチ。
からだの芯にずっしりきた。
Between a high solid wall and a small egg that breaks against it, I will always stand on the side of the egg. Yes, no matter how right the wall may be, how wrong the egg, I will be standing with that egg.
「高く堅牢な壁とそれにぶつかって砕ける卵の間で、私はどんな場合でも卵の側につきます。そうです。壁がどれほど正しくても、卵がどれほど間違っていても、私は卵の味方です。」
このスピーチが興味深いのは「私は弱いものの味方である。なぜなら弱いものは正しいからだ」と言っていないことである。
たとえ間違っていても私は弱いものの側につく、村上春樹はそう言う。
こういう言葉は左翼的な「政治的正しさ」にしがみつく人間の口からは決して出てくることがない。
彼らは必ず「弱いものは正しい」と言う。
しかし、弱いものがつねに正しいわけではない。
経験的に言って、人間はしばしば弱く、かつ間違っている。
そして、間違っているがゆえに弱く、弱いせいでさらに間違いを犯すという出口のないループのうちに絡め取られている。
それが「本態的に弱い」ということである。
村上春樹が語っているのは、「正しさ」についてではなく、人間を蝕む「本態的な弱さ」についてである。
それは政治学の用語や哲学の用語では語ることができない。
「物語」だけが、それをかろうじて語ることができる。
弱さは文学だけが扱うことのできる特権的な主題である。
そして、村上春樹は間違いなく人間の「本態的な弱さ」を、あらゆる作品で、執拗なまでに書き続けてきた作家である。
(内田樹の研究室 2009/2/18 「壁と卵」より抜粋)
自分のものであっても、他人のものであっても、「弱さ」によりそいたい。
そう思ってはきたが、
「たとえ間違っていても私は弱いものの側につく」
果たして自分は、ここまで言いきれるだろうか。
2009-02-15
昨日の挙式でのこと。
親族代表として挨拶をされた新郎の父が、挨拶のことばに詰まったときに、そうおっしゃった。
ことばが、乱れました。
こころが、ととのいません。
ゆっくりと、ひとこと、ひとこと、ていねいに紡ぎ出されることば。
思わずシャッターを押す手がとまった。
たったひとことに、ひっぱられた。
誰もがだいたい、こらえたり、誤摩化したり、あるいは、そのまま通り過ぎるところを、まっすぐ自分のこころのあり様を見つめ、そのままことばにされたことに、驚いた。
そして、新しく家族に迎えるお嫁さんを、「家族をあげて、いや、親族をあげて、お守りします。」とおっしゃるところにいたっては、他人の家族のことなのに、涙が出そうになった。
ひさしぶりに、こころの深いところにことばが触れた。
こんなにまっすぐ届くことばがあるんだな、と驚くのと同時に、
わたしたちが普段、どれだけことばをぞんざいに扱っているか、ということを身につまされもした。
きっと死ぬまで忘れることはないであろうそのことばは、
わたしの中で、今も疼くようにしてある。
2009-02-04
ひとは、自分を被害者だと思い込むときがいちばん、加害者になりうる危険性が高い。
「外部から邪悪なものが立ち現れて、無垢な自分(たち)を傷つける」という構図のもとに大虐殺が正当化されていた、という文章を、前に多く読んでいたのに、実際に自分の過去にあてはめてみるまで、実感として理解できなかった。
わたしは、わたしがしてきたことを、「やむにやまれず」なんてことばで、知らず知らずのうちに正当化してきた。こわいのは、その自分のこころのうごきに「正当化」ということばすらあてはめることなく、「正当化」なんてことばは、今はじめて発見したというくらい周到に、無意識下で正当化していた、ということ。
自分のことを被害者だと思っているうちは、自分のしたことによってたいせつな人がどれほど傷ついたのか、気づくことも、想像することも、できなかった。あるいは、被害者だと強く思い込むことによって、気づかないようにしていたのかもしれない。
ほんとうに長いあいだ、気づかなかった。
だから、これからは、そのこわさに気をつけながら、ひとのあいだにあって、おだやかに生きてゆきたい。
2009-01-25
神式の挙式には参列したことがないので、いちど式の流れを見ておきたい、と思って、大安だったし、護王神社に二度目の下見に向かう。
建物の構造的に正面から新郎新婦を撮るのが難しいこととか、蛍光灯と外光のミックス光だとか、どのあたりにポジショニングすれば、儀式の邪魔にならないかとか、そういうことをひととおり確認。
わたしと並んで挙式を見ていた参拝客の方と「シロムクって良いですね。この神社も落ち着いていて良いですよね。」という話をしていると、「じゃぁ、あなたもここで式を挙げたらいいじゃない。わたし見にくるわ。」と言われてしまった。
ひゃぁ…。
もともと落ち着いた雰囲気の神社だったからかもしれないけれど、商業の匂いがプンプンしていたり、うわっつらにたくさんのイメージ(やイデオロギー)をかぶせて甘くコーティングした、カタカナのブライダルやウエディング、とは違う、まっとうな儀式としての結婚式だった。
お宮参りの延長としてとらえたら、幼い頃から見守ってもらっている神様の前で、婚姻の儀式を執り行うというのは、人間の成長のなかで都度神様と関わりゆく、長い時間軸のなかのひとつのステップとしての経験であり、それは、ことさらに「トクベツな瞬間」を強調するブライダル産業のありようとは、一線を画しているように思う。
まっとうな記録写真を撮ります。
2009-01-21
先日、大学時代の恩師から連絡をいただいた。
学生時代、カミナリ研究の第一人者であるその先生は、まったく不出来なわたしくしたち(仮進級女子3名)の、不出来っぷりをあたたかく見守ってくださっていた(と勝手に思っている)。
久しぶりのメールには、まいど一号の打ち上げに携わっていることが書かれており、気になっていた「まいど一号」、ここにきていっそう気になりはじめた。
本日予定していた打ち上げは延期になったそうだけれど、無事打ち上げられるといいなぁ。
ご紹介いただいた先生の著書『雷に魅せられて』をアマゾンで調べたら、著者みずからレビューを書かれているうえ、☆3つで評価の平均を下げておられる。なんとも先生らしくて、笑ってしまった。
学生時代には知る由もなかった恩師のいろんな側面を、10年の時を経て、ブログ(風塵雷人ブログ)を介して知ることになるなんて。(そもそも、こまめにブログを書くような方だとは思いもしなかったので…)
大学を卒業した1998年は、自宅ではまだ電話回線のダイアルアップでインターネットに接続していたし、インターネットにつないでいる家庭も、そう多くはなかった。だから、10年越しに、恩師とこんなかたちで出会い直すなんて、想像だにしなかった。つくづく、ご縁とは不思議なものだなぁと思う。
2009-01-09
年賀状が届く。
うれしいのは、業者さんや、仕事で個人的にお世話になった方々から、あたたかいエールが届くこと。
なにかを仕事をするときに、必ず力になってくれる方々があって、そしてそういう方々と、あたたかい関係がとりむすべていることは、ほとんど奇跡のようなことだと思う。
だから、2009のこの年は、感謝のきもちからはじめよう。
2008-12-14
ひどかった鼻風邪がおさまってきたので、パンクの修理に自転車やさんに行く。
もうタイヤ自体がバーストしとるし、タイヤ交換の時期がきている。後輪のタイヤ交換は自信がないので、一度やり方を見せてもらおう、と。(ちなみに、前輪は自分で修理した)
「すいません、修理しているところ、見せてもらえませんか?今度自分で修理したいので。」とお願いしたら、「じゃぁ、教えますから、自分でタイヤ交換されますか?」と店員さん。
願ってもない。
そして、店員さんの指導のもと、およそ1時間ほどで、後輪のタイヤ交換をひととおり終える。細かいノウハウがあるのと、どこがどうなってどう動作するかというしくみを教えてもらえたので、やっぱり自分ひとりでやらんでよかったな、と思う。そもそも、工具が足らんかった。
作業を終えた後、「奥で手を洗ってもらってかまいません。」と言ってもらったので、店内奥まで進むと、店員さんがみなさん揃ってお昼休み。
真っ黒になった手を謎の洗剤でごしごし洗っていると、店長さんに「これ、飲みな。暖まるよ。」と、スープをすすめられる。
おぉ…コンソメスープ。
この荒々しさ、まさしく男の手料理☆
そして、すっかり《自転車屋の店長さんのまかない》をごちそうになって、店員4人と一緒に、世間話なんかしながら、まったり。
おっと。あやうく、立場を忘れるところやった。
修理代をまけてもらった上に、まかないまでごちそうになってしまったので、さすがに恐縮で、簡単に洗いものだけして、店を後にする。その足で、護王神社に寄って撮影現場の下見をしたあと、やっとこさ家に帰りつく頃には、1時間かけて覚えたはずの修理方法は、すっかり食べものの記憶にすりかわっていた。流行りの脳科学がどういうかは知らんけど、記憶なんて所詮そんなもんね。
とにもかくにも、自転車やさん、ありがとう。
そして、食べものの神様に今日も、感謝。
2008-12-08
ここ数年、制作時間の確保に固執していたところがあって、ひとと会うことに対しては、積極的に「消極的な態度」をとっていたのだけれど、それではまずい、ということに気づきはじめて、一旦、他者と時間や経験を共有することに寛容になろうと決めた。(「積極的」と言いきれないあたりが、潔くないのだけれど…)
その途端に、さまざまな方面のしばらくぶりのひと(びと)からお声がかかった。もちろん、自分からそんなアナウンスはしていない。
水流を塞き止めていた石をどかしたら、急に水が流れ込んで来たかのよう。ひととのご縁とは、不思議なものだと思う。
ここ数週間にわたって、たてつづけに、しばらくぶりのひとと会っていた。そして、おそらくそれは、旧くからの友人と新しく出会い直す作業でもあった。
まともに話すのは数年ぶりだし、まったく違うフィールドで生きているにも関わらず、お互いが問題意識を持っていることについて、深く話せることに驚いた。彼女が教育現場で日々考えていることが、わたしが制作の中で感じたり考えていることと、深いところでつながっているということもうれしかった。
「あるレベルに到達した人々が言うことは、それがどんな分野のひとでも、案外同じなんだよ。」という友人のひとことが印象的だった。わたしたちのどちらも、途上のひとではあるけれど、いま時点での、お互いのいる場所から見えている景色も、そう大きくは違わないのかもしれないし、そもそも思っているほど遠くにいるわけではないのかもしれない、と思った。
結局、他者によってしか自分を知ることができない、ということも、あわせて実感。ひとは他者からの期待によって成長することとか、他者との対話の中にあってはじめて新しいものを見つけるとか、そういうことを、わたしはあまりに過小評価していたのだと思う。
1ヶ月弱くらいのあいだ、集中的に内田樹の文章(著書とBlog)を読んでいた。彼の明快な文章によって、いままで自分が感じていた齟齬や違和感に、くっきりとした輪郭が与えられるような感じだった。しばらくはその快楽に浸っていたというのもあるけれど、そういう時期は、彼のことばに自分のことばを絡めようとしても、どうしても自分の文章にならなかった。
どうも、咀嚼には時間がかかるようだ。身体論から社会分析まで、あまりに広範にわたる内容の、それも濃い内容の文章を大量にinputしたのだから、無理もない。
いまから少しずつ咀嚼して、自分の経験にからめて書けたらいいなと思う。
武道論から派生する人間の身体運用についての記述がとりわけおもしろくて、着物では、背面の見えない位置に一家のアイデンティティたる家紋を背負っていることになり、その身体運用においては、「見る」意識が、自分の後方にも回り込んでいる、という。
ひとの「見る」が、そのような複雑な経験として成立しているのだとすれば、写真で表現、あるいは再現できる視覚経験というのは、とても限定的なものかもしれない。どうしても、写真の「可能性」より「不可能性」に魅かれるな、と思いながら、冬空の下、撮影を続ける。
2008-11-30
言葉が相手に届き、理解されるためには、まず相手の身体に「響く」必要がある。そして、言語における「響き」を担保するのは、さしあたり意味性よりはむしろ身体性なのである。(p63)
作家的直観によって村上は「人の心に入り込む物語」と「入り込まない物語」の違いが、言葉の身体性に存することを見抜いている。「倍音」とは「耳には聴き取れないが、身体に入る」音のことである。倍音を響かせることばは、「何を語っているか」という意味性のレベルにおいてではなく、「どのように語っているか」というフィジカルなレベルにおいて、おそらくは聴き手に「響き」を伝えるのである。(p64)
(中略)テクストを黙読しているときにも、私たちは「無声の声」で音読している。そして、「単音」しか出せないテクストと、「和音」を響かせているテクストの違いを聴き取っている。現に、同じような政治的主張を、同じような論拠で展開しているテクストなおに、こちらのテクストは「薄っぺら」で、こちらのテクストは「深い」という印象を与えることがある。「深い」言葉はどれほど簡単な主張を告げていても、確実に身体にしみこんでくる。(p77)
(いずれも『態度が悪くてすみません―内なる「他者」との出会い (角川oneテーマ21)
』 内田樹著 角川書店 2006 より抜粋)
響くことば、響かないことば。
そういうの、すごくよくわかる。
最近は、いっときほど、自分のことばが響いてないな、と感じることも。そういうのは、文章の内容ではなくて、切迫感のようなものだと思う。ことばが、このわたしに向かって迫ってきているような感覚。
さて、他人の文体についてだけれど、わたしの場合、なじむ、なじまない、というのが極端で、文体になじめない、ことが多い。目新しい内容でおもしろいはずの文章が、その文体になじめないと、おもしろく読めなかったりする。
文体に限らず、わたしは、なにかと判断を、「なじむ、なじまない」という生理的な感覚にゆだねているところが大きい、と思う。
霊感はまったくないけれど、土地や建物に「いやな感じ」を受けることは多いし、なるべくそういう場所は避けて暮らしている。確かに、OL時代の社員寮は「いやな感じ」で充満していたし、そこに住んでいるときは、夜中に金縛りにあうことが多かった。(人生のなかで金縛りにあったのはその時期だけだ。)
良い「気」の土地と悪い「気」の土地がある、ということを、同じ内田樹さんが別の著書に記していた。
一見合理的な考え方や、世間の論調にも、なじめないことが多い。自分自身の身の処し方にすら、なじめないと感じることがある。
違和感や齟齬がたとえ言語化できなくても、「なじめない」と感じた事実を、見過ごしてはならないと思いはじめたのは、作品をつくるようになってからだ。そして、デザインを組み立てるとき、写真に関わるときこそ、いちばん「なじむ、なじまない」の感覚に判断をゆだねているのだと思う。
理屈では問題なくても、どうしても、自分のきもちが「なじめない」ときは、ダメなんだと思う。どんなに根拠がなくても。そうやって身体に判断をゆだね続けていると、だんだんとその判断は厳しくなる一方だし、「なじむ」の条件が厳しくなると、「なじまない」=不快なものは増大していく。
ことばにならない違和感やら齟齬やらが、増大し続けているのだから、それは決して幸せな作業ではない。そう思いながら、でも、その後もどりできない道を、ひたすら全力で進んでいる。
響くことばから、ずいぶん話がそれてしまった。
昔の同僚が、ともだちを連れて紅葉の京都に来るということで、昨夜から一泊された。同僚が連れて来たのは、ベトナムの女性。素朴で遠慮深く、わたしより10歳ほど年若い彼女は、大学で専門に学んでいたこともあって、日本語が流暢。
盛り上がったのは、日本のアニメの話。
ベトナムでクレヨンしんちゃんが禁止になった話では、その背景に子どもたちがこぞってしんちゃんの真似をしていたという状況があったらしく、国境を越えたところでも、子どもの反応は同じなんだなぁとつくづく。
そして、ドラえもんは、ベトナムではドレえもんなんです、と言うので、
「ドレえもんって、まるで奴隷みたいやん。」と返したら、
「のび太の奴隷です。」と彼女。
鋭い。
日本に来て、まず食べたかったのが「ドラ焼き」と言ってたのには、さすがに、ジャパニメーションのパワーを思い知らされた。
成長する時期に同じ文化を共有していたことに、なんだかお互いとてもほっこり。こたつで自家製のおでんをつつきながら、国際交流。
2008-11-08
ふだんあまり映画は観ないほうなのだけれど、ふらっと立ち寄った三月書房で、その挑発的な「まえがき」にそそられて思わず買ってしまった一冊『映画の構造分析』(内田樹著 晶文社 2003)。5年前の大学院の講義ではわからなかった映画のナニが、これですっきり。
無知というのは、何かを「うっかり見落とす」ことではなく、何かを「見つめ過ぎて」いるせいで、それ以外のものを見ない状態のことです。それは不注意ではなく、むしろ過度の集中と固執の効果なのです。
視線について、欲望について、そして、作品構造の重層的な分析、映画の構造のあまりの深さに恐れ入った、というのが正直なところ。
それにひきかえ、大多数の写真とそれにまつわる言説はあまりに素朴すぎやしないだろうか?
私たちが隠れている何かを組織的に見落とすのは、抑圧の効果なのです。
ですから、抑圧の効果を免れるただ一つの方法は、自分の眼に「ありのままの現実」として映現する風景は、私たちが何かから組織的に眼を逸らしていることによって成立しているという事実をいついかなるときも忘れないこと、それだけです。
写真が、組織的に見落としているもの、眼を逸らしているものって何だろうな。
2008-10-27
大学院を卒業したての頃、「仕事」に対するスタンスを決めかねている時期があって、今村仁さんの著書を読み漁っていたと思う。
そして、そろそろ、会社でのポジションが上がってくる同年代のともだちから、部下や被雇用者のモチベーションが低いという事態にどう対処したら良いのか、という相談を(なぜかわたしが)受けることが多くなった。そういう事情もあって「労働」に対する関心がずっと横たわっていたのだけれど、先般、内田樹さんのblogにおもしろい文章を見つけた。
仕事の苦楽は仕事そのものによって決められるのではない。
その仕事を「やらされている」のか、「やらせていただいている」のマインドの違いによって決される。
私はいつも仕事は「やらせていただいている」というふうに考えている。
そういうふうに考えるのは当世風ではない。
当今の方々は「労働」と「報酬」が等価交換されるという図式で労働を捉えている。
ならば、雇用する側は「どうやって報酬を引き下げるか」を考えるし、雇用される側は「どうやって苦役を軽減するか」を考える。
そうなるほかない。
そういうつもりの人間たちが集まって仕事をしても、ぜんぜん楽しくない。
「働くモチベーションが下がる」のは当たり前である。労働と報酬は「相関すべきである」というのは表面的にはきわめて整合的な主張のように見えるが、実際には前件の立て方が間違っている。
等価交換論の前件は「労働者はできるだけ少ない労働で多くの報酬を得ようとし、雇用者はできるだけ少ない報酬で多くの労働力を買おうとする」というものである。
そんなの常識ではないかと言う方がおられるかもしれない。
あのね、そんなの少しも常識ではないのだよ。
もしそうなら、人類の生産力と生産関係は新石器時代で停止しているはずだからである。
とりあえずそこらへんの木の実を拾ったり、魚を釣ったり、小動物を狩ったりして飢えが満たされるのなら、誰が分業だの企業だの資本だのというめんどうな制度を作り出すであろう。
労働は「オーバーアチーブ」を志向する。
飢えが満たされても満たされないのである。
もっと働きたいのである。
そういう怪しげな趨向性を刻印された霊長類の一部が生産関係をエンドレスで巨大化複雑化するプロセスに身を投じたのである。
どうして「そんなこと」を始めたのか、私は知らない(たぶんマルクスも知らない)。
とにかく、そういうことになった。
だから、労働と報酬の等価交換が成り立つべきだという「整合的な」理説で労働を説明することはできない。
( 以上、内田樹氏のblog http://blog.tatsuru.com/から抜粋 )
デザインや、写真、さらに作品となると、価値づけが非常に難しく、「等価交換」なんて厳密には不可能なので、「労働と報酬の等価交換が成り立つべき」などという前提は、一旦脇に置いているつもりだったけれど、というより、その前提を脇に置かないことには、(コストパフォーマンスに拘泥していると)自分自身の進歩が望めないということに、徐々に気づきはじめていたのだけれど、完全に無視はできなかったし、無意識のうちに寄りかかっていっていたのかもしれない。
こう潔く否定されると、すっきりするな。その前提を完全に取り除いたら、あたらしく視界がひらけるかもしれない。
2008-10-26
偶然看板を見かけたので、用事を済ませたあとで、内田樹さんと釈徹宗さんの講演会「呪詛と祝福」の最後のほうだけ、ちょこっとのぞいてみた。
釈さんのほうが話していたと思うけれど、「単純に、人間のこの身体を80年保ち続けるのには、人間はエネルギーを持ちすぎている。だから過剰なエネルギーを、分配、贈与というかたちで放出しないと、そのエネルギーが呪詛へと向かってしまう。」というようなことを言っていた。
なるほど、と思う。
制作に向かう時間と労力を確保するため意図的に「閉じていた」この数年を振り返って、反省するところが多い。そして、少し方向を変えてみようと考えはじめた矢先に、こういう言葉と出会う。
自分のエネルギーを自分のためだけに囲うのではなく、他者に分配・贈与することによって、少なくとも自分が他人に呪詛をかける(他人の不幸を喜ぶ)ような事態は避けられるのかもしれない。
昔、ともだちが賞をもらったときに、周囲があまりそのことに好意的ではなかったこと、わたしはその事態にショックを受けた。
どうして素直に祝福できないのか。
そのときから、身近なひとの幸福を祝福できなくなるくらい余裕を失ったらあかんやろ、という危機感を強くもって、祝福するべきタイミングには、大いに祝福するよう努めてきたのだけれど、この講演会で、「呪詛を解くのには祝福しかない」と聞き、わたしは、知らず知らずのうちに呪詛から逃れて来られたんやな、と思った。
そして、今年になってようやく、我が家には祝福の季節が訪れ、ふたつの結婚と、ひとつの生命の誕生が約束された。
弟の結婚式で賛美歌を歌いながら、3年前のいまごろ、家族がいちばん危機的な状況であったことを思い出し、その頃のわたしたちには決して想像もできなかったこの幸せな事態に、胸が詰まった。
この日の祝福と感謝の気もちを、いつまでも忘れぬように。
2008-10-13
夏場、あまりの暑さに出歩くのを躊躇していたせいで、すっかり身体がなまってしまった。
ということで、先月から水泳をはじめた。
小学校高学年まで、スイミングスクールに通っていたから、泳ぐことにはほとんど抵抗がない。スイミングスクールでは、クロール25m、10秒間隔、30秒もち10本、とか言われて、機械的にせっせと泳いでいたな、と思う。
しんどいとかしのごの考える前に、顔を水につけてさえしまえば、あとはなんとか最後まで泳ぎきれるのだということを身体が覚えているから、さくっとそれなりの距離を泳いでいると思う。
水泳に限らず、しのごの考える前に、カメラを持って外に出れば良いのだし、しのごの考える前に、手を動かしてアイデアを練ればいいのだ。とりあえず、初動をかけてみること。
2008-10-11
晴れてはいたものの、かなり霞んでいたから、撮影は早い段階で断念し、もう一度見ておこうと思った、入江マキさんの個展に向かう。グリーンから青を通り越して紫までの色が印象に残る。
見たそばからはかなく消えゆく夢をたぐりよせるようなこと。
つじつまをあわせたり、輪郭を確定したとたんに崩壊するような世界を、そのまますくうようなこと。
そのあと、芸術センターで開催されているdual pointで、はじめてまともに高木正勝さんの映像を見て、しばらく動けなくなった。何ループくらい見ていただろう。映像でしかつくれない質感。
それから、cococn karasumaで開催されているNY TDC展まで足を運んでみたものの、作品の良し悪しより、展示物の状態の悪さが、気にかかった。
烏丸通り1ブロック分のこと。
2008-10-10
中心からの偏差を測るような、
そういう無益な作業をぐるぐるぐるぐる、繰り返して、
まともに世界と関わっていたのは、
カメラを構えているときだけだったのかもしれない。
3年も先送りしていたことが、ある日突然、
他人によって、とてもシンプルに片付けられた。
そして、わたしは、
空っぽになった、
のではなくて、空っぽだった、
ことに気がつく。
不思議と少し気持ちは軽くなっている。
自分をいちばん縛っていたものは、
他ならぬ己の執着だったりするのだな、と、静かに思う。
思い出さずに済むのなら済ませたい映像を、
それでも擦り切れるくらい反芻するのは、
忘れるための機構が正常に働いているからなのかもしれない。
もう同じシーンを100回くらい見た。
昨晩、ノーベル文学賞の発表を受けて、
久しぶりにル・クレジオの『歌の祭り』をひもといてみた。
なぜなら、あるものは、失くすことによってはじめて得られるのだから。
その一節が、風のように、さらっとわたしのこころを撫ぜた。
2008-10-09
気をつけたいことは、知らず知らずのうちの、不遜、そして、傲慢。デザイナーの義妹と話していて、彼女のデザインに対する真摯な態度に、自分が恥ずかしくなった。あるいは、デザインに対して真剣に向き合っていないことに、自分の傲慢さを感じた。究極的には、デザイナーではありえないのだけれど、そこに携わる以上は、謙虚に研鑽を積まなければ失礼だ。
せめて、知識と研鑽の積み重ねで、良質のデザインを世に出すことができるようになるのかもしれない、と思って、まっさらな気持ちでデザインの勉強をやり直すことにした。少しずつでも、本質的なところに向かえるように。
いま携わっている仕事はちょうど貿易関係の販促物なので、どうしたら欧文をうつくしく組めるのだろう?という素朴な疑問から出発する。
海外の空港の案内板でみる欧文はとてもうつくしいのに、国内でうつくしい欧文を見ることは少ないし、自分でもなかなか、気持ちよくデザインできたと実感できることが少ない。
ということで手にとった、小林章さんという書体デザイナーの方の著書がすぐれて良い。
欧文書体―その背景と使い方 (新デザインガイド)
(小林章著 株式会社美術出版社 2005)
海外で見かける和文の組版が「どこかヘン」と感じるように、きっと日本人の組む欧文の組版も、海外のひとには「なんだかヘン」に映るのかもしれない、という危機感があったのだけれど、
まったく同じことを、最初の章に書かれているのが可笑しかった。
そして、例文がまたうつくしい。
Letters are symbols which turn matter into spirit.
文字は単なる物事を精神にまで高める
2008-10-01
ここに来て、少し風向きがかわったのかな。
変わらないことに、幾分固執していたところもあったのだけれど、環境も自分も変わりうる可能性に、前向きに身をひらこうと思う。
厄年を通り抜けたところで、ふと思ったのは、変化を恐れないでおこう、ということ。
2008-09-25
いま時分の光を、なんとなくそう感じる。
それでも、午後をすぎてしばらくすると、
驚くほどはやく、その勢いが削がれているのに、
秋の到来を見たり。
ベストシーズンの到来。
2008-09-23
撮った写真のうちどのくらいが、作品になるのですか?という問いに、
0.5%くらいかな
とそのひとが答えたことを思い出した。
ネガチェックをしてみて、実際そんなもんなんだなぁ、という実感があって、全然、撮り足りていない、ということもよくわかった。
そのものがなんであるか、ということよりも、
もののたたずまい、に興味があるということもわかったし、
狭い地域で撮ることの限界もはっきり見えてきている。
ここで、いったん総括したことは、その先を考えるうえで良かったのだと思う。
ということで、今日も路上へ。
帰りに六本木に立ち寄った。混雑がひどかったために森美術館の展示は見送って、ミッドタウンに足を運ぶ。
少し歩いただけでだいたいのところがわかったので、その界隈までフラフラと足をのばすと、どこからともなく、太鼓の音がきこえてきた。
音の出どころは、少し遅めの盆踊りだった。ミッドタウンから、ほんの一筋入ったところ。飲食店やら商店の並ぶ街路の一角で、地元のひとがたくさん、浴衣で踊っていた。
そのにぎわいにほっとしたのと同時に、文化っていったい何だろうな、ということを考えさせられた。
商業と抱き合わせの文化施設と、地域の生活に根ざした祭りと。ほんの一筋道を隔てただけの場所で”文化”と呼ばれうるものの両端に接し、そのコントラストに目眩を覚える。
文化っていったい何だろうな
2008-09-18
怒りの矛先をそこに向けるのは、理不尽なことだとはわかっているのだけれど。
ついに被害が出た。
木の扉の向こうに置いてあった、粉モンの袋が、のきなみ全部、ねずみにヤられている。
口惜しいのは、全部きれいに食べきってくれたら良いものの、袋をひきちぎられた程度のものでも、衛生上の不安から廃棄せざるを得ないこと。小麦粉も、パン粉も、パスタも、米も、ライスペーパーも、コーンスターチも、かつおぶしもヤられている。
あぁ、口惜しい。
その傍らのネコたちと言えば、
いやらしい鳴き声を上げて求愛中。
恋にうつつをぬかして、
ねずみを捕ろうともしないネコたちに、
しぜんと怒りの矛先が向く。
ねずみも捕れないなんて、ネコ失格やん!
2008-09-12
天井の物音に気づいたのは一週間ほど前のこと。
姿こそ見えないものの、
どうも、お向かいの家の解体を機に、
ねずみ一家が引越してきた様子。
母に相談すると、
「家ねずみだったら、家の守り神。古い家にはつきものだから。」
と言われ、とりあえず、様子をうかがいながら暮らしている。
が、このねずみたち、深夜になると大運動会をはじめるのだ。
どたん、とととととと。どたん、どたん。
古い家だけに、天井板も薄く、足音もツツヌケ。
寝入りばなにやられたらたまったものではなく、
この数日でまったく不眠気味になってしまった。
野良猫もウロウロしてるし、そのうえねずみまで…。
「動物も住めないような町はあかん」と、大家さんは言うけれど、
いざ、わがこととなると、「共存共生」がいかに難しいか。
深夜の大運動会さえやめてくれたら、仲良くするのになぁ…。
最近ずっと、家で作業をしていることもあって、
だいたい、常連ネコの顔ぶれもわかってきた。
ある日、キツネ色の立派な体格(デブ)のネコが、
執拗に、細身の色白ネコに迫っているところに出くわす。
あの奇妙なトーンの声で、デブが迫っていくと、
最初は同調していた色白も、
最後にはさっと身をかわして、軒の下に逃げ込む。
逃げられて、残念な面持ちのデブは、
有刺鉄線に毛をすりつけながら、
チラチラ、色白の様子をうかがったりして、
傍目に見ていて、ちょっと未練がましい。
ネコ模様もなかなか複雑なようで、
休憩がてら、観察するのがおもしろい。
尾の長い流星を見た。
ゼラニウムの苗をもらった。
のに、
うつりかわる季節に、かんたんに気分を弄ばれて、
ほんの少し、弱っているのかもしれない。
あるいは、ひとあたり、したのか。
2008-09-10
とりあえず、2006-2008、3年分のネガチェックを終える。
結局、数千カットあったスナップのうち、見るに耐えうるものなんていくつもない。
質に対する意識が量を押し上げ、量が質を押し上げる、
という言葉の意味が、痛いほどわかる。
けっこう数を撮っていたつもりで、全然足りていない、ということも、よくわかった。
道のりは、まだまだ長い。
2008-09-03
ロン・ミュエック展のことをしばらく引きずっている。
あれらの作品で、わたしにとっていちばん辛辣に感じられたのは、
いままでの彫刻作品がいかに抽象化され理想化されたものであったか、
ということを暴いたこと。
同じことを写真にあてはめて、
世に流通する写真群がいかに抽象化され、理想化されているか、
ということを考えさせられている。
2008-08-28
知らないでいい
そんな風には思わないでおこう、と、
つとめて自分に言い聞かせている。
けっこう長い間、経済のこと、政治のこと、もろもろ、
自分で勝手に「知らないでいいこと」に分類して、
目をつむり、耳を塞いできた。
たくさんあふれる情報のうちから何を摂取するか、
選んでいるつもりだったのかもしれない。
でも、すこし知ろうとするだけでも、
世界はいままでと違った相貌を見せるし、
理由もなく「知らないでいい」なんて決めつけると、
なにより自分が損をする。
難しいことだけれど、
「知らないでいい」という内なる声が聞こえたら、
せめて「知っててもいいんじゃない」と思い直す。
まずは知らずしらずのうちに下している
「知らないでいい」という判断そのものに気づくように、
注意深く耳を澄ませる。
うまくいくかなぁ。
意外と「知らないでいい」と遮断してしまっていることって、多い。
おじょうちゃん、
見知らぬわたしのことを、
娘さんでも、お嬢さんでもなく、おじょうちゃんと呼ぶ哲学者から、
わたし宛に二冊の献本をいただいていると、実家から連絡があった。
作業に入って、ひたすら画面と向き合う日々が延々と続くと、
どうしても、自分ひとりで闘っているような気持ちになってしまう。
画面に現れる一枚一枚の画像に、浮いたり沈んだり。
そういった矢先のことだったから、
ものをいただいたということより、気にかけてくださったという事実が、
胸の深いところを衝く。
かつて、その哲学者が父に、
「おじょうちゃんはまだ京都でがんばっているのですか?」
と問うたことを思い出す。
まだ京都でがんばっている
何気ないそのひとことに、
含まれていることがらがあまりに多すぎて、胸が詰まった。
そして、くじけそうになるたびに、流されそうになるたびに、
そのひとことを思い出して、とりあえず前を向こう、と思い直す。
この3年はそういう3年だった。
まみえること、あるいは不純、
あるいは、整理されていないこと。
過剰なほど潔癖な写真を見ていて思ったこと。
2008-08-15
今朝起きると、朝顔の花が開いていた。
15年前に亡くなった祖父がおとりおきしていた朝顔の種を、
咲くかどうかもわからず蒔いたもの。
芽が出たあとも、
陽当たりの悪いこのベランダではまさか咲くまいと思いながら育てていたから、
感慨もひとしお。
淡い藤色の花は、祖父らしい上品な色あい。
お盆だし、じいちゃん、帰ってきたんだね。
開くところを見たいから、明日はもう少しはやく起きよう。
2008-08-10
やけに輪郭のはっきり見える光だったので、海にでかける。
須磨の海岸は、ワカモノであふれかえっていて、
地元の海、というより、大阪の繁華街みたいで、
気分が悪くなってすぐに引き返す。
空と海の広さに、
ゆったりと身を預けたい、なんてのぞみは、
とうていかなえられるような場所じゃなかった。
子どものころ家族で遊びに来たこの海は、
にぎやかだったけど、もっとおおらかで落ち着いていた。
もうあのころとは違うんだ。
2008-08-09
年をおうごとに、毒づく母。
しばらく母からのメールには、面倒がって文字なし絵文字(表情)のみのメールしか返さなかったのだけれど、昨日ちゃんとした文章を送ったところ、母から返ってきたメールは、
おお、朝顔を愛でる姫より文あり、恙無きや。
「文あり」というおおげさな表現に、最近のつれない絵文字のみのメールに対する非難が。
「朝顔を愛でる」のくだりは、ここのところ「帰って朝顔に水をやらなきゃ」と言っては早々に実家をあとにするわたくしに対する揶揄が。
三十すぎの娘をわざわざ「姫」と呼ぶところには、ほとんど悪意が。
ひしひしと感じられる。
母よ、腕を上げたな。
互いに侵食しあいながら、それでも共に在るさま。
ネガチェックを続けながら、気になるコマを拾っていると、光や影、物の「せめぎあい」に惹かれているんだと思う。それが写真として成功しているかどうかは、別としても、関心があるのは、共存とか、混在とか、そういうこと。
画面から都合の悪いものを引いて成立するのではなくて、
そこにあるもの全てで成立すること、とか。
削いで削いで純化する、というのではなくて、
不純のままに見えてくるもの、をじっと見ること。
2008-08-04
海が見たい。
ちがう、見たいんじゃない。厳密には。
海のそばにおっとりたい、ぼんやりと。
昨年は、撮影で訪れた舞子の海に、
ほんのすこし救われた、気がした。
かつて、好きになったのは、
おおらかで、広い海のようなひとだった。
海に近い土地の陽射しが好き。
内陸の陽射しは、逃げ場のない感じがして辛い。
海のこと、すこし、
想っているうちに、
やわらかい風がふく。
夕涼み、散歩に出かけよう。
最近のキーワード。
2008-08-01
ものがみえるのは光の放射速度がものの表面に効果をおよぼすからにほかならない。また物体は速く移動すればそれだけはっきりと知覚することができなくなる。だからつぎのような自明の理をうけいれざるをえない。すなわち視野のなかにはいるものはすべて加速や減速という現象をとおしてみられている。速度の大きさはあらゆる面で照明の強さと同一の効果をもつ。速度は光であり、世界中の光のすべてである。だから外見とは運動にほかならず、外観(アパランス)とは瞬間的かつ欺瞞的透明さ(トランスパランス)にほかならない。移動する視線、場所であり目でもある視線によって事物が一瞬にとらえられてはすぐに後方に消えさっていくのとおなじように、空間的次元それ自身もうつろいやすいつかの間の現象にすぎないからである。
それ故、速度の源泉(発電機やモーター)は光の源泉であり、映像の源泉である。世界の次元に話をかぎれば、速度の源泉とは世界の映像の源泉なのである。
(『ネガティヴ・ホライズン―速度と知覚の変容
』 ポール・ヴィリリオ 丸岡高弘訳 産業図書 2003 p155,156から抜粋)
数年前、車窓から見る風景がとても映像的だと感じて、テストをしていたことを思い出す。
車窓から見る風景が質感を欠いて見えることとか、実際手で触れられないこととか、そういうことを考えていたと思う。出発のときの、ある場所から引きはがされる感じだとか、停車時、速度がゆるむにつれて、見えるもののリアリティが徐々に取り戻されるような感じとか。速度は光、と断言されると、少し戸惑うけれど、そういう実感とリンクするのでとてもひっかかりを覚える文章。
2008-07-31
ぼんやりと、5年くらい先のことを考えながら夜道を歩いていたら、
光の筋がのびやかに頭上を通り過ぎる。
あまりにゆったりとしていたせいもあって、
流星だと思いあたるのは、少し経ってからのことだったけれど、
そのタイミングなら、そのとき想像していたことは、
いくぶん、叶うのかもしれない。
つい卑近なところに目線が下がってしまうこともあるのだけれど、
いただきを見失わないように
足下を見くびらないように
2008-07-24
ほんの少し、会計の勉強をはじめただけなのに、
けっこう経済のトピックスに敏感になるもので、
長銀の粉飾決算とか、サブプライムローンとか、
それがどういったことなのかを
積極的に知ろうと思うようになった。
とっかかりができると、ぐっと理解しやすくなるのは、
不思議なもんだな、と思う。
テレビも、最近見るのは、
社会問題を扱ったドキュメンタリーや、経済の番組ばかりだし、
自分の身のまわりのことで精一杯だった20代にくらべて、
30代になって、少しずつ視野が広がっていると思う。
「いい年」になって、他国の紛争の経緯や、経済の仕組み、搾取の構造を、
何も知らないでいることは恥ずかしい、という意識が、根底にある。
2008-07-19
山田真哉さんの著された入門書を片手に、
3日間かけて、複式簿記による帳簿つけを終える。
料理が、
作りながら覚えるのがいちばん効率が良いのと同じで、
簿記も、実際の数字を扱いながら覚えるほうが早いやろうな、
という読みは、当たっていたように思う。
カリカタカシカタにも少し慣れたし、
概要はつかんだし、仕訳の細かいことは、
ネットを検索すればだいたいのところは解決できることもわかった。
これで、いったん終了。
想像していたよりは、早いことカタがついた。
話は少しそれるけれど、
簿記のできるともだちに、SKYPEをつないで質問したら、
会話をしながら、仕訳のエクセルファイルが送られてきたのに、驚く。
お互いPCの前に座っているのが前提から、情報のやりとりがスムーズで、
SKYPEは打ち合わせに使えるツールなんだ、と思う。
便利な時代になったものだ。
WEBカメラをONにして、
お互いの様子をビデオで見ながら話をすると、
自室の空間が拡張された不思議な感じがすること。
画面を見ながら話すのだけれど、
カメラの位置≠画面の位置だから、
お互いが画面に映る相手の顔を見ていても、微妙に視線があわないこと。
ツールに媒介されるコミュニケーションの、
ちょっとしたズレが新鮮だった。
映像、音声、テキスト、ファイル送信、
さまざまなチャネルでコミュニケートできるのは、
便利な反面、無防備な感じもして、
通話相手を選ばないとコワいツールだ、と思う。
2008-07-17
暑さで、長時間、撮影に出ることもできず、
なら、時間に余裕があるうちにやっておこうと、
実際に帳簿をつけながら複式簿記の勉強をはじめる。
複式簿記は、ゲーテが最高の芸術と言ってるくらいだから、
理解すればものごっつおもしろいんだろうな。
けっこう難解…。
毎年、夏に蓄えた力は、
ちゃんと翌年以降の仕事につながっていくもので、
できるときに、できることを、きちんとやる、
ということは、大事なんだと思う。
多少積極性には欠けるけれど。
風水はあまり信じていないのだけれど、
作業場を一階におろしてから、
何かとひととのつながりが活性化している。
部屋割りをかえて、
気持ちが少しオープンになったということも一因かもしれない。
実際、気の流れもかわったようで、けっこう不思議。
世の中のものごとは、
所詮、ひととのつながりをベースに動いているのだから、
つながりが活性化すると、”いいこと”もふえる。
2008-07-16
ふだんはほとんど電話で会話をすることがないんだけど、
ここのところ、ともだちからまめに連絡があったので、
SKYPEをインストールしてみた。
すごい。
使い方を間違えるとすごく怖いツールだな、と思いながら、
おそるおそるの会話。
お互い、コレ切りドキがわからんな、と言いながら、
いちおう要件らしきものを伝えて切断。
まだ、機能をあまり把握していないので、
チャットやSMSにどのくらいの情報がOPENになっているのか、
ということと、傍受の可能性に対して、警戒心を抱いている。
とりあえず、安全に使えるように、
機能と仕組みをちゃんと把握しないとあかんな。
2008-07-06
少し前に読んだ、スタフォードの『ヴィジュアル・アナロジー』が読解不能だったことで、(なかば自信を失い)読書からずいぶん遠のいてしまっていた。
暑すぎる夏の夜は、読書にかぎる。
そばにあるのはポール・ヴィリリオの『ネガティヴ・ホライズン―速度と知覚の変容』。
速度と知覚の変容、という副題にひっぱられた。
まだ読みはじめたばかりだけれど、第一章の前の『緒言 外観をめぐる企て』からすでに、おもしろい予感がする。
こんな風にして絵画について何年もかんがえていたあるとき、わたしのものの見方にとつぜん変化がおこった。特別な価値のない物体にむかっていたわたしの視線がその傍らにあるもの、そのすぐ横にあるものに移ったのだ。平凡な物体が特別な物体に変化したということではない。「変容」がおこったわけではない。もっと重要ななにかがおこったのだ。とつぜん、わたしの眼前にあたらしいオブジェが出現した。切りとられ、切りこみをいれられた奇妙な形象の構成の全体がとつぜん目にみえるようになった。あたらしく観察されたオブジェはもはや平凡なもの、どうでもよいもの、無意味なものではなかった。それはまったく逆に、極度に多様であった。それはいたるところに存在していた。すべての空間、すべての世界があたらしい形象で充満した。(中略)卑小な幾何学になれてしまっていたために、あきらかに存在するにもかかわらず、われわれにはみえていなかった形態が出現した。われわれは円や球や立方体や四角形は完全に知覚することができるが、事物や人間の間の間隙やすきまを知覚するにはずっとおおくの困難をかんじる。物体によって切りとられ、形態によって型どりされた間隙というこの輪郭の存在にわれわれは気がつかない…。
(『ネガティヴ・ホライズン―速度と知覚の変容
』 ポール・ヴィリリオ著 丸岡高弘訳 産業図書 2003 p11から抜粋)
のっけから強烈に気になる一節で、間隙を知覚できるようになったら、いったい何が見えるんだろう。その知覚のなかではどんな価値観の軸が出現するのだろう。ということが、気になってしかたがない。
2008-07-05
どうも1階と2階で気温が違うな、と思っていたら、
その気温差、実に5度。
2階が亜熱帯だとしたら、1階は温暖湿潤気候。
2階を作業場、1階を寝室にしていたのだけれど、
「古い家屋は危ないから二階で寝ろ!」という忠告の多さと、
この数日の蒸し風呂のような暑さで、ついに入れ替えに踏み切った。
夜しか使わない寝室は2階。日中作業をする作業場は1階。
外気温が33〜35度くらいでも、
1階は扇風機だけで過ごせるくらいひんやりしている。
こわいくらい、ひんやりしている。
2008-06-28
週末に撮影を予定していたものの、雨マーク。
ちょうど昼過ぎくらいからうす曇りで、今日なら逆光を気にせず撮影できるな、と思って、5時すぎスタートで撮影をはじめる。
想像よりも時間がかかるな、と思いながら撮り進めると、四条のあたりから、赤いコーンで通行規制がされており、?と思いながら、撮り進める。
結局、御池→二条間が完全に侵入禁止にされていて、二条まで行くつもりが御池までしか撮れないことに。
そのうえラストのカットには、赤いランプのついた、警察車両がバッチリ。
警備にあたっている警察官に、
「ごめんなさい、せっかくの景色がだいなしですよね。明日までですから。」と言われたけれど…
まぁ、うつくしい絵が欲しいわけじゃないし、それはそれで今日この日のドキュメントとしてはけっこうなことなんだけれど、最後のカットの警察車両が意味ありげに見えてしまうかもしれない。
自宅に帰ってから調べてわかったのだけれど、京都でG8が開催されていたのね。
2008-06-26
デジカメで露出をかえずに撮ったのものでラフをつくってみる。

途中で電池切れになったので40カット分のみだけれど、思ったより急激に暗くなる。
これでも、最後のほうのコマが暗すぎるので、トーンを上げているくらい。
逆光だし、実際の撮影では、これよりずっと遅いペースでしか撮れないから、かなり難しい。
ついつい、スクロールバーを右へ左へと動かしてしまって思ったのは、水平方向の移動で時間軸が展開するものの原体験って、小学校の頃に夢中で遊んだ、スーパーマリオブラザーズやん。
2008-06-25
しかし、よくひとに声をかけられる。それも撮影中に。
今日もデータをとるために、川を南下していたら、橋の下のホームレスのおっちゃんに声をかけられた。
「自分、写真とってるんか?」
「はい」
「ほんじゃ、おっちゃんを撮らしたるわ。ホームレスやで。」
「え…」
「ほら、こんなポーズどうや?」
路上でひとは撮らないんだけど、わざわざ申し出ていただいたのを断る理由もなく、かんたんに二枚撮らせてもらった。
礼を言ったら。「おっちゃんに惚れるなよ」と返される。
うーん、それはたぶん大丈夫。
さて、データをとってみると、30秒、1分で時々刻々露出が変わる。
速いときは1分で1段くらい下がる。
撮影は思っているよりもずっと難しいかもしれない。
最近、この近辺にはえらくたくさん警官が出ていて、露出計とデジカメを持ってメモをとりながら歩いていたし、多少不審に思われたかも。
2008-06-20
いろいろとかわったお茶をもらうことがあるのだけれど、
飲みやすいものから手をつけると、
自然とクセのあるお茶ばかりが手もとに残って、
変なお茶コレクションが形成される。
今、メインで手もとにあるのが、
高麗人参茶
mate de coca (コカ茶)、
una de gato(キャッツクロー)。
高麗人参茶は、
冬場、からだをあたためるのに重宝するので置いておく。
アイスティーの時期なので、
やっかいなmate de cocaとuna de gatoのアイスに挑戦。
コカ茶はコカインのコカなんだけれど、
お茶それ自体は怪しいものではなく、
ペルーでは、高山都市に行ったときに、
高山病をやわらげるために、飲んでいた。
久しぶりに飲んだけれど、警戒していたほどのクセはなく、
たぶん、飲みやすいほう。
一方のuna de gatoは、耐え難い苦み。
甘くしたら飲めるんだろうか。。。
今月の新入荷は、カナダからのアイスワインティー。
ワインの香りがする。
2008-06-12
頭もはたらくものなのなんだな、と思った。
突然、とても具体的なプランが思い浮かぶ。
するするっとからまった糸のほどけるような感触。
自分自身がすっきりと納得するところまでたどりついたら、あとは段取りの問題だけや。おもしろくなるよ。
2008-06-10
インターネットラジオのラテンチャンネルをずっと流していたからだろうか。
急に、リマの記憶が鮮明な映像としてあふれだした。
タクシーの黒い合皮のシートの質感とか、
排気ガスの臭気にあたってぐったりしながら、
見上げた位置に流れる街の景色。
たぶん、5,6歳の頃の記憶。
なのに、妙に生々しくて懐しくて。
南米で暮らしたその時間は、生も死もはるかに近くて、
幼いわたしにもわかるくらい、色気に満ちていた。
丸3日かけてラフをつくる。
建物が写っていないと、水平垂直の基準がとりにくくて、作業に時間がかかるということがわかる。
ラフでは、標高差があったり、被写体との距離にゆらぎがあって、トリミングが難しいことがわかる。
何かを選ぶと、ほかの何かを犠牲にしないといけない。
2008-06-08
結局、紙はマットではなくセミ光沢というところで落ち着く。紙は厚すぎるとめくりにくい、ということもわかる。
細かい設定を決めるために、段階的に数値をかえてテストを行う。
昔、理科の実験でやっていたようなことをやっているな、と思う。
結果によっておのずと決まることもあるのだけれど、細かいことをひとつひとつ決めていくここらへんの作業が、案外しんどかったりもする。
2008-06-06

母屋の奥さんから紫陽花をいただく。うれしい。
こもってひとりで黙々と作業をすることが破綻しないで済んでいるのは、母屋にひとの気配があるからかもしれない、と最近は思う。
あるはずのないところに気配があるのはすごくコワいことだけれど、誰のものか特定できる気配は、ないよりはあるほうが気持ちが落ち着く。
実家の薄い色の紫陽花に比べて、濃い色の紫陽花たちはにぎやか。
やっぱり女ですからね。お花をもらうとすごくうれしいのです。ふふふ。
トリミングの幅と、大きさを検討していた。
冊子を手に持ったときの距離で、細部がどう見えてくるか、ということと、画面の大きさによる距離感。
見る人がぐっと画面に近づいて見たくなる、塩梅、というのは、とても難しい。
今のところ、インクジェットプリントで、ツインループ製本のラフな仕上げで十分。
パラパラっと気楽に見られるほうが良いやん。
ラフな感じ、がいい。
3mmや5mmの差でずいぶん印象がかわる。
それは、距離感にも関係するから、何度も試作をつくっては、ああでもない、こうでもない、をする。
白フチがないほうが、近しい感じがして好ましいことが分かる。距離感と、あと、親近感の問題もあると思った。
寄って見たくなるかどうかは、写真の内容とか精度だけではなくて、心理的なものも絡んでいる、と思う。手に持ったときの重さ、とかも含めて。
自分が手に持ってどう感じるかを、何度も確認。
フォーマットはほぼ決定。
けっこうコンパクトな大きさ。
光沢があるよりマットなほうが色の落ち着きが良い。
あと、マットなほうが、めくるときに、手で画面を触ってしまうことに対する心理的な抵抗が、少なくて済む、気がした。
発色の良い紙に出会えるかな。
2008-06-05
およそ二日と半日。130コマ弱のスキャニングを終える。
端を切り落とすのがもったいないくらい、たくさん「ひと」が写っている。
画面に写るひとびとが、それぞれがそれぞれに、それぞれの時間を生きていて、それらが「ひとつ」に集約されずに、まんまばらばらな感じ、が好きなん。
現場では時間との勝負だから、ミスのないようにと淡々と撮影を進めているのだけれど、たまに‘瞬間’を感じさせるコマに出会うのが面白い。
たぶん、これから後の手を動かす作業のなかで写真と向き合いながら、自分自身がいちばん多くを学ぶのだと思う。
2008-06-03
あなたの抱える痛みを厳密に特定するために、
たくさんの言葉を重ねるよりも、
いま自分の感じているところを信じて、
ただ受けとめようと思いました。
悲しみの輪郭を確かめるための所作がかえって、
当事者であるあなたと、わたしとの距離を際立たせる、
そのことがとても暴力的に思えたのです。
2008-06-02
2週間強の期限をきった作業に入る。scaningはルーティンワークだから、意識が手先と別のところを彷徨う。
先日、液晶絵画という展覧会を見たことも手伝って、《時間軸》ということをぼんやり考えていた。stillとmovieの境界線上にあって、その両者の差異を意識させる作品がおもしろかった。
2008-05-23
この数日で、グリーンアイスのつぼみがつぎつぎとひらく。
今日はともだちの命日。
前に、お線香をあげにいったときに、
その家のベランダにも可憐なグリーンアイスが咲いていて、
彼のお母さんと話がもりあがった。
だから、
今朝はなんだか戻って来ているような気がしたのよ。
お盆でもないんだけど。
記憶のなかの彼を思い起こすとき、
かわらぬ笑顔の彼は、なぜか自分と同じように年をとっていて、
人間の想像力は、なんて身勝手なんだろう、と苦笑する。
年を重ね、自分が18歳から遠ざかれば遠ざかるほど、
たった18でその生命を絶たれるということが、
どれほど残酷であるか、ということを思い知らされる。
写真の意味、というのは、撮影者本人より、むしろ周囲が見いだしたがるものなんだな。
「森山さんは自写像を多く撮りますが、意味があるのでしょうか?」と、問われた氏は直接展示されている写真を指して、「これ、影がうつってないより、あるほうがいいじゃん。」
ほんとだ。
そういう、意味を探る質問が多かったと思う。
必死でひとの写真に意味を見いだしたがっている若者たちは、きっと、自分が撮影するときも、意味を見いだそうとしているんだろうな。
でも、写真に意味がある、と、盲目的に前提しているところに違和を感じた。
2008-05-21
グリーンアイスがつぼみをほころばせている。
そのおすそわけだろうか。
今朝はわたしのこころも、ほんのすこし、ほころんだよう。
朝方の夢は、おだやかであたたかな時間、そのものでした。
「昔から、こうと言ったらきかないからね。頑固だから。」
と、まえに幼なじみに言われたことを思い出しました。
その一点に関しては、
自分の意志でもどうにもならないくらい頑で、
すでにもう、どうにかすることを諦めているのですが、
不毛で不動の一点から差し込んだ、淡い光のような夢は、
はかなくも、幸せな時間でした。
夕刻の空のいろは、極上のやさしさ。
一日の終わり、
とにかく感謝をしたい気持ちになったのは、
ずいぶん久しぶりかもしれない。
最近夜空を見上げていない。
月曜日に聞いた森山大道さんのことばが耳に残っていて、用事のついでと言いつつも、ずいぶん大阪の街を歩いたと思う。
大阪は地下鉄でしか移動しなかったから、地上を歩くと、案外コンパクトな街なのね。京都にない情景に触発されて、気がついたらけっこうシャッターを切っていた。
大阪が京都と違うのは、変化もまたしゃあないと受け入れる、あっけらかんとした空気が街から感じられることかな。京都は、かわらないことの価値を知りすぎている、と思う。
一足に転地とはいかなくても、撮る街をかえてみたら、あたらしいことが見えるかもしれない。
2008-05-17
目の前に見えるのは赤い花だった。
そのあと息を吸ったとき、
視界がむらさきの花でいっぱいで、
むらさきを吸い込んでしまうと思って、おそろしくて、
とっさに息をとめる。
2008-05-16
スナップがある程度、固定化してきていて、やっぱりそれは、当然打破しなければならず、いったん、いままで撮ったものを総括をせんと、前にもうしろにも進めんという、切羽詰まった状況にある。
吐き出してしまいたい、という得体のしれない欲動。
数年分のネガをずらっと見通して、その遅々たる歩みに対する焦り。
スナップなんだから、もっと軽やかでいいはずなのに。総括で済まなければ、転地かな。
2008-05-09
撮影するこのわたしが光のただなかにあるということ。
透明な存在としてではなく、光のただなかにこの身を持って存在することは、単に視神経が刺激されるのとはまったく違う経験なのだと思う。
光にくるまれるような経験を、四角く区切った平面にどれだけ写しとることができるのだろう。
執拗に光と影を追ったスナップを見ながら、つくづく。
2008-04-24
というのは、スナップにおいては、あまり本質的ではないんじゃないか、と思う。
編集の力で何らかのテーマを「描き出す」ことはできても、スナップそのもので「描き出す」というのは、違うんじゃないかな、と。描き出すというより、結果として浮かび上がる、のほうが正しい気がする。
スナップにテーマだてをすることに違和感を感じているのは、そういったところ。
その場その場で被写体ととり結ぶ関係によって、アドリブで対応し続けることが、スナップの醍醐味だと思っている。
被写体や光との出会いによって、自分自身のものの見方そのものが更新されていくのが、ここちよい。そういう可能性に対して最大限身をひらきながらスナップを撮り続けるには、先にテーマだてをすることは無理なのだと思う。
絵画とか、美術作品の制作とは、根本的に方法論が違うんじゃないか、ということを考えていました。
2008-04-23
ハトを握り殺す夢を見る。
目覚めたあとですら、
そのぬくもりやら量感やらが残っていて、
罪悪感の隙間にいくばくかの性的なニュアンス。
新緑の過剰なるは毒々しく。
それは悪夢のつづき
おじいちゃんのおとりおきしていたアサガオの種を植えてみた。
陽当たりの悪いベランダだし、期待はしていなかったけれど、
今朝見ると、心配になるくらい色白の芽が出ていた。
半年ほどのあいだ、こぶりなクローバーが一輪、葉を広げていた。
ふゆの寒さも陽当たりの悪さも乗りこえて、たった一輪、生き続けるその頑な姿に、
ほんとうは、毎朝、励まされていた。
さすがに、葉に穴があいてきて、もうそろそろ引退かな、と思った矢先、
バトンタッチ、新しいクローバーが芽を出した。
小さい鉢のなか、いのちがくるくるめぐる。
2008-04-17
scanの作業をしていて、走査、ということを考える。カメラを水平方向にスライドさせるRIVERSIDEの撮影は、走査なんだと思う。
なんとなく、まとまったひとつの大きなものを構成するというスタンスではない、というところが、立ち止まっているところでもあって、あぁ、わたしは風景をscanしているんだな、と思った。
展覧会でも写真集でもなく、webで写真を見せるとはどういうことか、ということをずっと考えていて。展覧会の告知や作品カタログのようなかたちではなく、webで何ができるんだろうか、と。webで見せること自体が作品であるにはどうしたらいいのか、と。
写真集も展覧会も、配置や点数の制約があって、それゆえそのなかでどう見せるか、という編集が見せどころでもあったりするのだけれど、そして、編集というのはとても魅惑的な作業なのだけれど、一旦、その編集の0度、写真そのものから何が見えるのか、というのを見てみたい、と思ってもいて。
いっそ、表示順序もランダムにして、総体としての「まとまり」を把握しにくいかたちで見せるのはどうだろうか、と思いはじめ、実験的ではあるけれどsnapをランダムに見せるscriptを組みはじめました。
編集というのはほんとうに”力”があって、写真そのもの、というよりも編集で見せてるんじゃないの??ということを考えたりして、シリーズとしてまとめることに、いまはまだ納得がいかなくて、写真点数をだんだん増やしていったら、輪郭があやふやなまま、育つような感じ。
コントロールすることを一旦放棄して、編集から自由になったところで、何が見えるのか。
何も見えないかもしれないし、しょうもないかもしれないけれど、見てみたい、と思うことはやってみようと思う。曖昧な表現でごめんなさい。違和感、とか齟齬とかは、ほんとうに、ことばにしにくい。
2008-04-10
松岡正剛の書評(千夜千冊)に良寛全集についての書評があったので読んでいたところ、せつない、ということばについて書かれたところで、立ち往生。
こうして、良寛はどんなときも、一番「せつないこと」だけを表現し、語りあおうとした。「せつない」とは古語では、人や物を大切に思うということなのである。そのために、そのことが悲しくも淋しくも恋しくもなることなのだ。それで、やるせなくもなる。
しかし、切実を切り出さずして、何が思想であろうか。切実に向わずして、何が生活であろうか。切実に突入することがなくて、何が恋情であろうか。切実を引き受けずして、いったい何が編集であろうか。
(松岡正剛 千夜千冊 第千夜から抜粋)
ある頃からほとんど小説を読まなくなり、
かわりに思想書、哲学書を読むようになったのは、
そこに哲学者の、思想家の、切実、が垣間見えることがあるから。
その切実にふれて、こころが震えるから。
そして、せつない、がもともと人や物を大切に思うことを意味していた、
という解説に納得した。
年を重ねるほどに、せつないと感じることが増えているのは、
きっと、たいせつに思う関係が増えているのだ。
たいせつに思う関係が時間を重ねることによって築かれるものであれば、
生きた時間のぶんだけ、せつなさは増えて当然なのかもしれない。
そして、彼のことばを借りれば、
切実にこの世界に触れることなしに、なにが写真家であろうか。
「びは乱調にありは瀬戸内寂聴。貴女にとってびとは?」
唐突なメールをよこしてきたのは、おかん。
び→美くらい、ちゃんと変換せえよ…。
「ゆらぎ そして、きわ」
と返す。
その返答には納得した様子だけれど、
たまに、こういう問いを携帯メールで送ってくるから、油断ならない。
つけたすとすれば、あたかも写真が全能であるかのように錯覚させるような見せ方に、危機感を抱いている、ということ。
もっときちんと自分のなかで整理しないといけない。意図と方法論との結びつき、とか。
2008-04-09
パノラマ写真、を辞書で調べた。
「広大な光景を一目で見られるようにした写真。」とあった。
わたしの作品は、パノラマ、ではない。
一目で見られるなんてこととは正反対だから。
それぞれがそれぞれ、それぞれの時間のなかに在って、無関係で、それらを撮影者を中心に据えて簡単に組織化なんてできないこと、とか、都合良くひとつにまとめあげたりなんかできないこと、とか、否定形でしか書くことのできない、そういうことをたいせつに思っている。
できること、よりも、できないこと、不可能性のほうに、ずっときもちが引きずられている。
題材が何であっても、撮り方がどうであっても、根本的にひっかかっているのは、そういうことなんだと思う。
ここのところ、いやというほど撮り歩いて、歩いて、歩きながら考えたのは結局そういうこと。
2008-04-08
なんとなく、最近、若いひとから
別れぎわ、そでをつかまれるような感じがしているのは、
きっと良いこと、なんだと思う。
たとえば、映画監督を志す芸大の卒業生だったり、
仕事先のデザイナーだったり。
いずれもプライドも志も高い。
何もなければその場限りであったであろうに、
最後の瞬間にそっと名刺を渡されたり、
連絡先をこまめに伝えてくださったり。
つながる可能性をきちんと置いていく。
いままでは、年上の方々から、さんざんかわいがってもらってきたけれど、
志ある若者からご縁をいただく、というんだろうか。
今すぐ深くつきあうわけでもないのだけれど、
いただいたご縁は、たいせつにしまっておこう。
2008-04-07

昨日、RIVERSIDEの続編を撮る。
ちょうど、まえに撮った川の上流に川幅が一定で撮れそうな範囲があったのだけれど、景観自体の印象が薄く、保留にしてありました。桜がうわっているようだということはわかっていたので、ロケハンをし、けっこう長いスパンにわたって桜が植わっていることがわかったので、撮影候補に上がってきました。
4月に入ってから、桜の開花とともにテスト撮影をしてみると、点景として写るひとの往来がおもしろく、今回は景観よりもひとやひとの営みを中心に構成しようと考えています。
前作を顧みて、つなぐことによって生まれる時間的な要素と、景観的特徴と、ひとの営みという風俗的要素が、作品を支える柱になっているんじゃないかな、と思っています。今作からは、それぞれの要素を意識的にとらえていこうと思っていて、今回は、風俗的要素に重心を置いて撮ってみました。
もう少し日が長くなると、日が暮れて、街をくるむ色がどんどんかわっていく様子を撮ってみたいな、と思っています。
体力に少し不安があったので、4年ぶりの本番撮影を終えて少しほっとしている、というのが本音。
ひとり屋台は、孤独であるという点で、
あるしんどさを背負ってはいるけれど、組織に属さない気楽さがある。
逆に言えば、組織のなかでひとに揉まれて学ぶことが、学べていない。
ひとと一緒に仕事をすることがあって、強く感じた。
そうとう自覚的でないと、あたまでっかちのまま、
自分ひとりのことしか考えない人間になってしまう。
教職に就いている友人がかつて言っていたこと。
狭い世界で「センセイ」と呼ばれ続けて、意識的でなければ、
長い教師生活のなかで自分は偉いのだと勘違いしてしまう、
そういう先生がたくさんいる、と。
それぞれの立場で内容は違うけれど、
危機感を抱いておかなければならないことがらはあるのだと思う。
わたしの場合は、組織に属していないことで、
ひとから学ぶ機会を損なっているということを、
肝に銘じておかなければならない、と思う。
2008-04-04

母屋とはなれをつなぐ屋根のうえに、
1,2,3,4,5,6,7,8…8匹やん…。
住みついてるのは6匹やと思ってた。
家族団欒なんやろか…。
そりゃこんだけおったら、悪さするやつもおるわな。
2008-04-02
最近、関係が悪化していると思う。
わがネコ屋敷のネコさんたち、
今まで、ゴミをあさる気配はあったものの、
実際に荒らしたことはなかったのに、
先日の朝、ゴミが散乱していた。
そして、今朝は、
中庭に置いてある洗濯機横のかごに入れてたブラックジーンズに、
足跡、足跡、足跡。そして、大量のネコ毛が付着。。。。
ちょっと、ネコさん、どうゆうこと?
わたしのジーンズで、何しはったん??
それとも、今まで気づかなかっただけなんやろか。
うーん。。。
2008-03-23
ともだちから借りた、勝間和代さんの金融リテラシーについて書かれた本が、
案外おもしろかったので、この方のblogを読んでみると、
タイトルにある記述があった。
過食、喫煙、などの行為を続けるのは、
将来の健康とひきかえに現在の享楽を優先する健康負債で、
遺伝的な疾患を別として、過体重のひとには、
実に、借金体質のひとが多い、とのこと。
経済という切り口で、
過体重という現象をとらえているところがおもしろい。
ふだん撮影でひと一倍歩いてるからいいや、と思っていたけれど、
おやつ、やめます!
2008-03-14
春霞、あるいは、黄砂の舞うなかの撮影。
遠景があまりにぼやけて、つまらない、と思ったときに気がついた。
その写真が、具体的であるかどうかということが、自分にとっては、すごく重要だということ。
霧の街の写真を見た恩師が、「ものは抽象的になると、美しく見えるからね」と言っていたのを思い出し、そうか、その写真が具体的かどうか、ということが、わたしにとっての、ひとつの判断の軸なんだ、と思った。
なんでも言語化すればいいものではないけれど、言語化することによって、いくぶん視界がクリアになった。
2008-03-03
“Vol de Nuit”
おみやげにいただいたのは、夜間飛行という名の香水。
その香りを纏って眠りについたら、
ずっとずっと、遠くにいけるのかもしれない。
ここではないどこか、に。
2008-03-02
まったく安寧な場所に在って、なにひとつ賭すところのないひとのありよう、が、ほんとうにつまらない、と感じることがあって、それは、他人のフリ見て、我がフリ直せという意味で深く考えさせられている。
重々しい雰囲気とか、深刻すぎるものは、はなから苦手で、しぜん、気持ちは軽やかなものに向かうのだけれど、ただ、その軽やかさのなかにも、なにか賭されたものがなければ、と、思うようになった。
たとえ技巧的には稚拙であっても、ぎりぎりのところまで賭されたものには、切迫感がある。むかし友人の作品に、そういうものを見た。
作品の内容を安全なところから評価できないくらい、巻き込まれてしまうということ。つくり手の、もうどうにもならないこころのありようが、言葉や意味を介さないところで作用して、見る者のこころをゆさぶる、ということ。
その一回のシャッターに、一本の線に、ひと色に、どれだけのものが賭されているか。最近、そういうことをすごく意識するようになった。
ゆっくりと漕ぎ出すように、
朝のおくゆかしい光のなか、撮影に出かける。
ある頃から、錆びたトタンに無数の色を見るようになった。
それからは、
世界のいろいろなものがすべて、いちいち、具体的。
軽い目眩に陥っているような状態が続く。
スナップをあまり長時間続けられなくなっているのは、
集中力や体力が落ちているのではなくて、
あまりに、それぞれが具体的になりすぎて、
その重みを受け止めきれなくなっているのかもしれない。
2008-03-01
なんで、この色とこの色が一緒やとうわぁ好きな感じになるんか、
そういうことを知りたかってん。
美学の話をしていたときに、同年に卒業したともだちが、
大学に入った理由のひとつ、として言っていたこと。
それが、このところ、ずっとこころにひっかかっている。
優美だと感じさせる曲線、と、そうでない曲線。
綺麗だと思わせる色あわせと、そうでない、色あわせ。
幼いころ、クーピーを並び替えて遊ぶのが好きだった。
(もしかしたら絵を描くことよりも…)
並べ方によって、きれいに見えたり見えなかったりしたことが不思議だった。
日々の生活のなかでも、
自分の目が喜んでいると感じること、と、そうでないこと、があって。
美の体験、ってなんなんだろう?と今さら気になりはじめた。
小学校高学年以降は、
一本の補助線を引くだけで、するするっと謎が解ける、
図形の問題にとり組むのがとても好きだった。
一本の線の持つ力に、ドキドキしていた。
見た目の美しさとは違う次元だけれど、
謎を解く補助線の機能を、美しいと感じていた。
線ってなんなんだろう。色ってなんなんだろう。
それらに接して、
わたしの目が喜んだり、喜ばなかったりするのは、
なんでなんだろう。
2008-02-28
近所に、長谷食品という小さなスーパーがある。
けっして割安ではないそのお店。
でも、わたしは好んで足を運ぶ。
わたしのうしろに並ぶお年寄りの女性に、店員さんが話しかけている。
「さっき、娘さんが牛乳2パック買って行きはったよ。それ知ってはる?」
「いや、知らん。」
「ほんじゃ、牛乳、カブるんじゃない?」
「せやな。戻しとこか。」
そういうやりとり、今まで何度も見かけた。
レジで小銭を一生懸命探すお年寄りを、けっしてせかさない。
お年寄りのお客さんが多く出しすぎたら、大きめの声できちんと金額を説明して、
出しすぎたお金を財布に戻してあげている。
手が空く時間は、話あいてにもなっている様子。
それが、御所南、京都のド真ん中にある。
お年寄りの生活をそっと見守るこのお店には、
「サービス」や「顧客満足」なんて薄っぺらなことばは似合わない。
ひととひととが思いやり、いたわりあって生きる、ただそれだけのこと。
サービスなんかじゃない。
マニュアル化されたサービスで埋め尽くされた店にはない安心感が、そのお店には、ある。
2008-02-22
表紙の写真からおもしろくて、つい手にとってしまった。
写真がおもしろくて見ていたのだけれど、この方、写真家、ではない。だから、かえっておもしろいのかもしれない。
最初、切ったり貼ったりしているのは、写真なんだと思って見ていて、それだけでも充分おもしろかったのだけれど、途中で、それが実際に建築物をぶった切ってるとわかって、さらに、おもしろくなってきた。
届いたばかりで、まだなにも咀嚼できてないので、これからゆっくり向き合います。ワクワク。
まるでキツネのしっぽ。
御池の角から見上げた空に、
みごとにふさふさのひこうき雲。
空を舞うfox tail。
ビルのうえを、軽やかにまたいでいるのが、
わたしには、そうとう小気味良かった。
あろうことか、このわたしにレンアイの相談をしたいとのこと。
久しぶりに、大阪で大学時代のともだちと飲んでいた。
コイバナなのに…。
たしかに、理系やったけど、
なんで、恋愛の緊張関係をエネルギーバンドで例えるのか…。
なんで、「量子化」とか「励起」とかいうことばが飛び交うのか。
話しているふたりとも、大学での成績は最悪だったから、
ことばの意味をわかったうえで使っているんじゃなくて、
子どもが覚えたてのことばを使いたがるようなもの。
電気系180名のうちたった6名しかいない女子。
6名がすべて仲が良いというわけでもなかったから、恋愛相談と、
マニアックな電気系タームの両方でつながる相手なんて、そうはいない。
単純に、その二極にあることばを共有できる連帯感がここちよかった。
落ち込んでいた彼女も、だんだんお酒がまわってきて、途中から悪ノリ。
「どっちも含み込むような、でっかいバンドをつくれっちゅうねん。」
「二次元や三次元で考えんと、八次元くらいで考えてくれっちゅうねん。」
くだの巻きかたがマニアックで、おもろすぎ…。
だから、言わんこっちゃない。
わたしに恋愛の相談役はムリやっちゅうねん。
2008-02-18
ひとと話していて、ふと口をついて出た。
「5年後、自分のシャツを自分で作れるようになっていたい。」
毎年、冬になると布が恋しくなり、針仕事にハマるのだけれど、
今年は、少しチャレンジも兼ねて、譲ってもらったコートの丈を30cm詰めたり、
シャツの襟を外したりと、いろいろ、リメイクじみたことをしている。
布の扱いに慣れてもきたし、
丁寧に作業すれば、ある程度のことはできるんじゃない?
という自信も生まれてきたのだと思う。
そろそろ、自分で1から作りたくなってきた。
シャツだけだし、いまから5年くらいかけてゆっくりみっちりやったら、
自分のシャツ、自分で作れるようになるんちゃうかなぁって。
きちんと身丈にあってパリっとした白いシャツ。
凛として、気持ちを引き立てるだけの力のあるシャツ。
ずっと憧れているんだよね。
2008-02-15
雪と雪のあいまの晴れ間に、外に出る。
最近、自転車に乗らなくなった。
撮影をするのに、自転車のスピードは速すぎる、と気づいてから、
用があって遠くに行くとき、重いものを運ぶとき以外は自転車には乗らない。
市内で片道1時間半くらいまでの距離は徒歩圏になった。
そのうえ、撮影に出かけるときは、ものをつぶさに見ながら歩くから、
その歩くスピードすら遅くなっている。
だから、何時にどこかに着かなければならないと思いながら歩く、
その速さとこころもちでは、まったく撮影にならない。
雲の端から太陽が顔をのぞかせるまで、
じっと待てるだけのゆとりがないと。
わたしが、写真によって手に入れたのは、この遅さ、なんだと思う。
そして、その遅さは、この時代に対するささやかな抵抗なのかもしれない。
2008-02-14
Joachim Schmid: Photoworks 1982-2007
Gordon Mcdonald, John S. Weber, Joachim Schmid
中身を見ずに写真集を買うことはほとんどないけれど、京都で洋書を扱う書店をいくつかまわってみてもなかったので、思いきって買ってみた。
写真を、とてもアナログっぽく継いでいるのが、気になって。似たような写真を複数並べたり、違うひとの顔をわざと継ぎ目がわかるようにつないだり。
アタマで、継いでるとわかっていても、つい、ひとつのものとして見てしまう、まるで、わたしたちの眼のありよう、脳のありようを試されているよう。
写真を切ったり貼ったり、複数組み合わせたり、編集することによって何が見せられるかということの可能性、おもしろい。
このひとの情報はあまり(日本語では)見あたらないし、英語の解説ちゃんと読んでみようかな。
2008-02-11
「ほんとうに雪はしんしんと降るのか?」
耳を澄ませて雪の音を聴いてみる。
舞い降りる瞬間の音は、スチャッ、スチャッ。
少し雨まじりだから、湿った音がする。
きっともっと細かい雪でも、
いちばんリアルな音は顔やからだにふりかかる音だし、
雪の降るなかにあるひとにとって、雪の音は、もっと具体的。
しんしん、ではない。
あとから気づいたけれど、きらきらと星が輝く、のきらきらは擬態語。
ゆらゆら揺れるの、ゆらゆらも擬態語。
同じように、しんしんも、擬音語じゃなくて、擬態語。
きらきらは煌めき、ゆらゆらは揺れる、ということばからも類推されるけれど、
しんしん、はどこから来るんだろう。
ひとつ言えるのは、そんな上品な表現は、
窓から外の雪を眺めているひとにとっての音景なんじゃないかということ。
今日も帰り道、雪にふられたけれど、雪の最中にあったら、
擬態語だとしても、きっと、「しんしんと」は使わないなと思う。
さて、長くなったけれど、
最中にあるひとと、それを傍観するひととでは、
表現に差があるということを考えていたのです。
ひとがどのポジションに身を置いているかは、
その表現のなかで、あからさまに露呈する。
よくも、わるくも。
母は映画が好き。
BSで放映されている辺境の地の映画をもっぱら好んで観ている。
居間で一緒にゴロゴロしながら映画を観ていると、彼女が言う。
「(映画って)すごいわよね。それこそ幾千のディテイルの積みかさねじゃない。」
おっと、おかん。ええこと言うやん。
「幾千のディテイルの積みかさね」
素敵なフレーズや。どこからパクってきたんやろ…。
そんな母に、
「深夜、寝しなにテレビつけたら、ニューシネマパラダイスやっとってん。」
と言うと、「あら、そんなん寝られないじゃない。」と。
まったくその通りだったのが可笑しかった。
翌朝早くに用事があるのがわかっていながら、
〜早朝4時の放映を最後まで観てしまった。
4度目なのに、泣きながら。
2008-02-05
寺町を自転車で通り過ぎようとしていたところ、坂井さんとすれ違う。
一見の客なんて覚えてないだろう、と思ったら、
すぐにわかったようで、声をかけてくださった。
そりゃそうだ。
わたし、そのとき、彼のつくったふくを着ていたのだもの。
自分のつくったふくを着ているひととすれ違ったら、そりゃ、わかるやろ…。
お店の外で、着ているふくをつくったご本人と対面するという状況は
ちょっと気恥ずかしい。
追い打ち。
新しい店舗がガラス張りなのを良いことに、
外からうっとりふくを眺めているところを、目撃されていたそうな。
メンズラインばかりだし、
クールな店内にはなかなか入る勇気がなかったの。と、こたえたら、
「僕のいるときに来たらいいよ。」
と、やさしく微笑む。
頑固で筋のとおったふくづくりをされていて、相当気難しいであろうそのひとが、
やさしく微笑んでくれるのが、ちょっと、いや、すごく嬉しかった。
男物で、そのうえかなりハードなのに、
つい、お店の前でぼうっとしてしまうくらい、吊られているふくが美しい。
吊られた状態の造形が美しいと思うふくは、そうは多くない。
ふだんはそんなこと思わないのだけれど、
このときばかりは、男に生まれたかったと思う。
2008-02-03
この日一日、ひとつも明るくならなかったこと、
悪びれる様子もなく、なにくわぬ顔でいつもどおり日が暮れたこと。
口惜しい。
明るくなるのをずっと待っていたのに。
ちょっと、神戸のパンを食べたいきもちになったので、
大丸のDONQに寄ってみたら「パネトーネ」が並んでいた。
このお菓子、もともとはイタリアのものらしいけれど、
ペルーでは「パネトン」と少し歯切れの良い音で呼ばれ、
クリスマスのころに食べていた。
懐かしくて、試しに買って帰ったら、見事にハマる。
オレンジのほのかな香りが食欲をそそり、
ほんのり甘いくらいの優しい味なので、朝食にも◎
少しトーストしてバターを添えて食べています。
それほど特別なものではないのだけれど、
クリスマスの記憶とゆわえられてるから、そのぶん余計に美味しい。
リーガのパネトーネも買ってみたけれど、DONQのほうがふんわりしている。
けっこう手間がかかるようだけど、自分でつくれるようになりたいな。
2008-01-29
スタイルはすでに思想である。ある思想を学ぶ(まねぶ)というのは、まずはある思想が世界を見る、世界に触れるそのスタイルに感応するということである。もうそういうアクセスの仕方しかできなくなるということである。その意味で、哲学はその語り口、その文体をないがしろにしてはいけないと、つよくおもう。
(『思考のエシックス―反・方法主義論
』鷲田清一著 ナカニシヤ出版 2007年 p88から抜粋)
うえの文章は、語り口、文体について書かれたものだけれど、「もうそういうアクセスの仕方しかできなくなる」というところに、ドキっとした。
ある撮影スタイルに固定化することで、なにか可能性を逃してしまうような危機感を、うっすら感じていた。わたしが怖がっていたのはそういうことなのかもしれない。
「もうそういう見かたでしか、世界を見ることができなくなる」と。
ただ、最近はこうも思うようになった。
固定化せずに、更新し続ければいいのだ、と。
ある時点、ある時点で何らかのスタイルに着地したとしても、そこに留まらなかったらいい。
スタイルが固定化することを怖がってoutputを出せずにいるよりも、一旦、着地して、outputを出してみて、そこからまたあたらしく踏み出せばいい、と。
ここ数年の我が身をふりかえって、臆病にもほどがある、と思った。
2008-01-27
ぼんやりテレビを見ていると、大阪府知事選の開票速報が流れていた。
あいかわらず、大阪のひとはタレント好きやなぁとか思っていたら、
落選した候補者のインタビューもあって、熊谷さだとしさんが質問を受けていた。
このひとどこかで見たことあるなぁ…と思ったら、
アナウンサー曰く、元大阪大学教授とのこと。
たしかにクマガイ先生っていたなぁ…と。
もしかして…。
そうやん。わたしが学生やったころの電気の学科長さんで、
就職のときの推薦状、この先生に書いてもらったんや…。
うちの在籍していた研究室の真上に、クマガイ研があった。
でもまだあまり自分の記憶に自信が持てないので、
同級生にぐるっとメールをまわしてみると、
「そうやで。単位とれん授業やった。」と返事が届く。
線形システム論。
わたしにはどうしても日本語に聞こえなかった講義。
そして、クマガイ先生はとても穏やかな良い先生やったと記憶している。
2008-01-25
悪天候のおかげで、調整する時間を得て、ようやく、暗部のツブれなくscanができるようになった。
2006年11月頃のスナップ。画面全体がゆるい感じ。
カメラのせいなのか、意識のせいなのか。
2005年から、途方に暮れた時期が1年半ほど続いて、2006年の晩夏ごろからやっと外に撮りに出かけられるようになったから、2006年11月は、スナップを撮り直しはじめた頃。ちょうど気候も良くて、毎日、出勤前の2時間、撮影に出ていた。
つたないけれど、それでも救われたのは、少なくとも、それらの写真を撮るときの動機は、写真からうかがえる。
2008-01-24
最近、子どものころのことを思い出すことが多い。
わたしは、幼い頃のなりたいものは絵描きさんだった。
そのあと小学校高学年のころには小説家にかわったけれど。
近所のYちゃんは、お花やさんか、ケーキやさんになりたい、と言っていた。
そんなYちゃんは、短大の卒業後、アパレルの会社に勤めたと思ったら、さっさと辞めてドイツに行き、パティシエになって帰ってきた。
小学校の頃、全員の絵を黒板に貼り、好きな絵に挙手しましょうという心ない教師の提案で、わたしの描いた絵は一人の挙手も得られず、ひどく落ち込み、中学の美術教師とは折り合いが悪く、寒い廊下で補習を受けさせられた頃には、もう美術なんて大嫌いで、高校では選択すらしなかった。のに、なぜかいま、こんなところにおる。
だから、けっこうひとの人生なんてものは、
幼い頃の無心の選択に集約されてるんじゃないか、と思う。
そういえば、ものごとを習得するのが、ひとより遅いということを思い出した。
逆上がりも、修学旅行のスキーも、みなが習得できたころ、わたしはまだ四苦八苦していた。でも、そういうときでもじっと粘って必ず習得したし、ひと一倍苦労して習得したものは、結果的に、ほかのひとより上手くなった。
だからね、あわてんとこうと思うん。
ひとよりペースが遅いことを受け入れたら、少しだけ、気が楽になったよ。
しかし、それにしても「事象そのものへ」というザッハリッヒな探求、あるいは芸術の自律性の探求は、なぜ純粋な領域を要請するのか。なぜ、領域の固有性、あるいはその形式性、透明性を要請したのか。諸学問、諸芸術のそれぞれが自己に固有の領域へと閉じこもること、そのことがさまざまの知的・美的領域で並行現象として発生したこと、そういうことを可能にするトポスとは何であったのか。そういうトポスへの問いは、当然のこととして、そのトポスが閉じた系、閉じた回路として成立していることを前提とするが、ほんとうにそういう閉じた関係の世界というものは可能なのだろうか。
(『思考のエシックス―反・方法主義論
』鷲田清一著 ナカニシヤ出版 2007年 p34から抜粋)
単純に「ファインアート」ってなんなんだろう?という問いがずっとあって、「ファイン」ということばで、ある表現領域を囲わないといけない理由とか、そういうことを知りたい。
そういう「囲いこみ」が表現としての閉塞感とか、制度としての閉塞感に、つながっているんじゃないの??という漠然とした感触とか。論理的に説明はできないけれど、感覚的に、ひっかかりを覚えていること。
※ザッハリッヒ:即物的 トポス:場所
2008-01-23
少しずつつみ重ねる、ということを意識しだしたのは去年あたりからか。
30代、40代、50代、で、ひととなり、にどんどん差が出てくる。
それはきっと、本人も意識しないようなささやかな日々のつみ重ねが、
10年、20年、30年、経つうちに、大きな差異になってしまうのだと思う。
そうやってできあがってしまったものって、簡単には変えられないんだ。
だから、ひといきに何かを変えようとせずに、
少しずつ、日々のなかにささやかな工夫と進展を、と思うようになった。
実際のところ、無理が利かなくなってきた、というのもあると思う。
重い段ボールを階下に運ぶのに、なかみを出して、
用事があるたびに、少しずつ持って降りる、とか。
薬に頼りすぎると、だんだん身体の免疫機能が働きにくくなる、ときいて、
即効性のある薬は飲まずに、からだを温める食べ物をとってゆっくり休んで、
からだの免疫力で風邪を治す、とか。
制作にしても、昨日のわたしより、今日のわたしのほうが、
去年のわたしより、今年のわたしのほうが、
少しずつでも進歩してたら、ええかな、と思うようになった。
ひといきに解決しようとせずに、少しずつ前に進む、という時間感覚、
20代のころは持ち合わせていなかった。
いままでは次の一歩のことしか考えてなかったけれど、
三歩くらい先を見渡せる余裕ができてきたのかもしれない。
いよいよ30代らしくなってきたかな。
先日、読んだ『ひきこもれ』(吉本隆明著 だいわ文庫 2002)に、10年の持続という話があった。
持続ということは大事です。持続的に何かをして、その中で経験を積んでいくことが必要ないような職業は存在しません。ある日突然、何ものかになれるということはないということは、知っておいたほうがいい。(中略)
たとえば物書きというのは虚業で、政治家の次くらいにくだらない職業ですが、それでも持続ということが大事であることは変わらない。才能がどうこう言っても、十年続けないと一人前にはなれません。
逆に言うと、十年続ければどんな物書きでも何とかなります。毎日毎日、五分でも十分でもいいから机に向かって原稿用紙を広げる。そして書く。何も書けなかったとしても、とにかく原稿用紙の前に座ることはやる。
まるで朝礼の校長先生のお話みたいやな、と思いながら、読んだのだけれど、「何も書けなかったとしても、とにかく原稿用紙の前に座ることはやる。」というくだりに救われたんだと思う。
スナップを撮りに出かけて行って、一枚も撮れずに帰ってくる、というのがたまにある。それを「無駄足」と思って落ち込んだりもするから。
スナップについては、実に10年どころではなく、30年、50年くらいのスパンじゃないと勝負にならない、と思いはじめている。
日々、経験を更新しながら、撮り続けること。
それが当面のわたしの課題だと思っている。
ある日突然、すごい写真が撮れるようになるわけではないけれど、続けているうちに、かならず機が熟す。
2008-01-18
京大周辺の古本屋をつたっているうちに、
思い立って、久しぶりにガケ書房に立ち寄る。
当初の目的は九鬼周造の著書を探すことだったのに。
『ひきこもれ』
いささか乱暴なタイトルだな、と思いながら手に取ったのは、吉本隆明の著書。
このひとの本、何度も読もうとして、挫折してる…と、少し躊躇もあったのだけれど。
いざ開いてみると、ずいぶんやさしい文章で綴られている。
たぶん、不登校やひきこもりまっただなかの若者に向けて書かれたものなのだろう。
ほとんど家にこもり机に向かって仕事をする父親を見て育ったから、
下に抜粋するひきこもりについての記述は、わたしにとっては自明のことなんだけど。
世の中の職業の大部分は、ひきこもって仕事をするものや、一度はひきこもって技術や知識を身につけないと一人前になれない種類のものです。
(『ひきこもれ―ひとりの時間をもつということ (だいわ文庫)
』吉本隆明 だいわ文庫 2002から抜粋)
そこから、話は「子どもの時間を分断しないようにする」と展開する。
「分断されない、ひとまとまりの時間」をもつことが、どんな職業にもかならず必要なのだとぼくは思います。
という視点から、親の立場として書かれている文章を抜き出してみると…
(中略)くだらない用事や何かを言いつけて子どもの時間をこま切れにすることだけはやるまいと思っていました。
勉強している間は邪魔してはいけない、というのではない。遊んでいても、ただボーッとしているのであっても、まとまった時間を子どもにもたせることは大事なのです。一人でこもって過ごす時間こそが「価値」を生むからです。
ぼくは子どもの頃、親に用事を言いつけられると、たいてい「おれ、知らないよ」と言って逃げていました。そうして表に遊びに行って、夕方まで帰らない。悪ガキでしたから、その手に限ると思っていました。
そうするとどうなるかというと、親はぼくの姉にその用事を言いつける。姉はいつも文句も言わずに従っていました。
いま思っても、あれはよくなかったなあと反省します。つもり、女の子のほうが親は用事を言いつけやすい。姉本人もそういうものだと思って、あまり疑問をもたずに用足しに行ったりするわけです。
そういったことを当時のぼくはよくわかっていた。そして、うまく逃げながらも「自分が親になったら、これはちょっとやりたくないな」と思っていたのです。
ぼくの子どもは二人とも女の子です。女の子が育っていく時に一番大きいハンデは「時間を分断されやすい」、つまり「まとまった時間をもちにくい」ということなのではないかと思うのです。それ以外のことは、女の子でもやれば何とかなる気がするのですが、これだけは絶対に不利です。
この文章を読んでやっと、幼いころ抱えていた怒りの正体がわかった気がした。わたしは用事を言いつけられると、「いや」と言ってまっこうから母親と喧嘩して育ったほう。ずっと手伝いが嫌いなのかと思っていたけれど、いま思えば、それは手伝いがしたくないのではなくて、集中して何かをやっている最中に腰を折られることに腹を立てていたのだと思う。そういう意味では、母はとてもどんくさく、わざといやがらせをしているのか、相当無神経なのか、ことごとく言いつけるタイミングをはずし、なんでいまやっていることが終るまで待ってから声をかけてくれないのだろう?と、毎日怒っていた。
そのせいで、わたしは自分が家事が好きであるということに、ながいあいだ気づかずにいた。
いまさら、親のことをとやかく言うつもりはないけれど、自分がされていやだったことは、自分の子どもには絶対にしないでおこう、と思う。もし子どもを持つことがあれば。
そして、いま自分のこととしては、制作のための時間をまとめて持てるように、もう少し工夫しよう。ここのところ、人から頼まれた用事にふりまわされすぎている。
2008-01-15
先週末、神戸の映画資料館で上映していたので、観に行った。
映画館のせいなのか、編集が原因なのか、音がとても酷かったのが残念だったし、技術的に拙い感じは否めないけれど、数年前に見た「きわめてよいふうけい」よりも、見るべきところは多かったように思う。
特に沖縄の講演会のシーン。
講演会のタイトルのなかで使われている「創造」ということばに対して、「写真はクリエイションじゃない、ドキュメントだ」と言っているところとか。
中平さんの写真には、まなざしに余計なものが混じってなくて、ものがただそこにあることだけが定着されて、成立している。やっぱりすごいなぁ、と思う。
撮影しているとき、楽しそうなのが印象的やった。
2008-01-09
数時間じっとしているのが苦手で、
ほとんど劇場に行かないし、あまり映画は観ないほうですが。
何年かにひとつくらい、これは観とかないとと思う映画があって、
「いのちの食べかた」
京都みなみ会館で上映中だったので、さっそく観に行く。
ドキュメンタリーになるのかな。
音楽もナレーションもなく、淡々と、動物が、植物が、食料化されていく工程と、
職員がご飯を食べる姿が交互に続くだけ。
牛や豚、鳥や魚が生きものから「肉」になるということがどういうことなのか。
人工交配がどういうことなのか。
知らなかったわけじゃないけれど、知識として知っているだけで、
実体験としてはなにも知らない。
そういうことを、目の当たりにさせられます。
ふつうにグロテスク。
しばらく緊張でからだが萎縮するほどに。
でも、食品加工におけるグロテスク、を隠蔽したり、
あるいは、誰かにそのグロテスクな作業を負わせているのに、
涼しい顔で知らないでいることは、もっとグロテスク。
まるで工業製品を扱うかのような無情さで、淡々と加工される動物・植物。
知らなかったわけじゃないけれど、でもどこかで、
せめて食品くらいは、人の手を介したあたたかいものだと思いたがっていたんやろな。
冷や水をあびせられたような気持ちになりました。
飲食業を営むUさんご一行と出くわして並んで一緒に観ましたが、
途中から、みなおかしを食べる手がとまってしまっていたのが印象的でした。
わたしは、帰り道も想像力のスイッチが入りっぱなし。
「海鮮かきあげ丼」の看板を見ては、生きたまま魚が腹を切り裂かれるシーン、
「焼き鳥」を見ては、鶏が首なしでコンベアで運ばれるシーン、
「牛丼」では、おびえる牛に高圧電流を流すシーン、
が頭をよぎって、なかなか、食欲が戻りません。
2008-01-07
なりゆきで深夜のドライブデート。
今出川より北、
お互いの思い出をなぞるように、
なつかしすぎて甘ずっぱい場所をうろうろ、と。
どんどん空が広くなって、漆黒の空にとびきりの星。
運転席のそのひとが「ヘラクレス座の…」と、それらしく言うから、
真剣に見上げると、「うそ言うた。テキトー。」とかわされて。
目的のないドライブだったし、
共通の友人のたちあげたNPOの建物をのぞきに行ったり、
クルマに乗らなきゃできないこと、
たとえば、スタバのドライブスルーでラテを頼む、
なんてことを、ひとつずつ、叶えていった。
新年早々、の、うれしい夜。
2008-01-06
歯にトラブルを抱え、またいだ新年。
今年の目標は、脱力の作法を身につけること。
力を入れるより、抜くほうがよっぽど難しい。
まずは、力みすぎないこと。
いま、実践しているのは深呼吸。
そう意識しはじめると、日中の活動時間帯、
びっくりするくらい呼吸が浅くなっていることに気づく。
もうひとつは、短期決戦に持ち込まずに、
中長期で着実に実現する、くじけない意志を育てること。
ささやかな進化を日々重ねるほうが、
いっそくとびにものごとを変化させるより大事。
あと、年末に「ことばを大切にしないと、あかん。」と言われたから、
自分から発することば、文字に責任をもつこと。
のぞみは、やっぱりたくさんのすばらしいものに出会いたい。
「見たい」の欲望がいちばん強い。
そして、それらをきちんと写真に定着していけたら良いな、と思う。
今年もよろしくお願いします。
2007-12-28
Tessarのレンズテスト。
これで、中判2機と、35mmのレンズのテストがほぼ終了。
摩耶山からの撮影では、被写体が遠すぎて、比較ができなかった。
今回、京都駅から街を撮影したくらいの中〜遠景くらいが、いちばん解像力の差が出て良かったと思う。
今回のフィルムを見た限りF11がピークのもよう。
ついこないだまで秋めいていたのに、気がついたら、街が冬の色にさまがわりしていて、びっくりした。もう年の瀬だものね。
週末から、もう一段、気温が下がるようだけれど、また少し、光もかわるのかな。
2007-12-25
マサキは緑が好き。
春は緑色の服をたくさん着てくる。
緑色の帽子も持っている。
緑のお兄さん。
秋になると、ちゃんとそれが茶色くなる。
そんな彼はダンサーで、なかなか美しい筋肉を備えている。
そして、なぜかわたしに筋トレの方法を教えてくれる。丁寧に。
そのマサキが最近すごい。
わたしの視界に入った途端、挨拶がわりに新作のダンスを披露してくれる。
それも、毎回、振り付けが違う。
そこまでされて気づかないのは野暮だから、どんなに遠くても、どんなに見切れていても、ちゃんと「気づいてんで」の視線を送り返す。それはかなりの真剣勝負。
画面端の阿部サダヲくらい油断のならない存在。
そして、それはスリリングな関係。
2007-12-21
なんてこった。
一日一本ずつ神経を抜いていたのですが、
今日ほぼ原因の歯を特定できました。
食いしばりの加圧によって、歯に縦にヒビが入り、
そこから水やお湯が入り込んで、神経を直に刺激していたようで。
歯の中で神経が炎症を起こしてはった。
原因は、かなりきつい食いしばりなので、
これ以上歯を痛めないように、マウスピースをつくることになりました。
正直、マウスピースなんて色気ないなぁ…とげんなりしているんだけど、
まるでアスリート!と、テンション上げて、渋々、型どり。
しかし、長年の生活態度や習慣が、
モロに身体に出てくる年になったということに、率直に驚いています。
なんせ今年は本厄やしね。
なんだかんだ、この数年、ずっと気を張ってたんかも。
うまく脱力する方法を身につけないと、ね。
2007-12-18
が低いということは、重々承知していたが…。
先日から、歯の激痛に見舞われています。
歯みがきで激痛、熱かったり冷たかったりする食べ物でも激痛。
日に日にひどくなるので、歯科に行くと、
「あなたは食いしばりがひどいけれど、ストレスためてる?」
と訊かれた。
おおいに。
食いしばり(噛みしめ)がひどくて、歯が硬いひとは、
食いしばり(噛みしめ)の圧力で歯がしならずに、割れるんだと。
もしかしたら、犬歯に断裂が入っているかもしれない…と。
そして、いまはまだ初期段階だけれど、これが本格的に割れると、
いまの痛みどころじゃない、とのこと。
とりあえず経過観察で、麻酔と痛み止め。
昨日は頓服飲んで痛み抑えて、嵯峨芸の学生さんとご飯を食べたけれど、
もう今日は麻酔で口半開き。
ストレスが、こんなところに発現するなんて、きっついわ。
そこで登場したのが、歯医者さんにもらった食いしばり(歯ぎしり・噛みしめ)を改善するプリント。
たとえば、前準備。
「布団に入ったら何も考えないようにしてください。もし、どうしても考えることがあれば、もう一度、布団から出て考えてください。布団の中は眠るだけの所と決めて下さい。あるいは、朝目覚めてから布団の中で考える習慣をつけると良い考えがでてきます。」
と、この調子で延々、A4 2枚両面。
この季節、一旦入った布団から出るのは寒いし、
布団を「眠るだけの所」と決意するくらい几帳面なひとは、きっと食いしばっちゃうよ。
「あるいは、朝目覚めてから布団の中で考える習慣をつけると良い考えがでてきます。」
と言いきっているのも不自然だし…。
痛いのは深刻なんだけど、親切すぎるA4プリントはつっこみどころ満載。
歯医者さんの言う
「南の島に行くとか、温泉でゆっくりするとか」というのが、
いちばん良いんだろうけどね。
でも、いまこの苦境をどう打破するかだよ。
あ、また食いしばってる。
2007-12-16
まだ夜も早い時間、低い空に見えるのは、
ひとつ星の欠けたオリオン座。
星座を知っている、ただそれだけで、
見えないけれど、もうひとつの星の存在を、
そしてそれがまだ地平線のしたにあることを、想像することができる。
見えないものを想像すること。
そうすると、すこし意識がゆさぶられて、
ただ、目の前にあるものを受け入れるだけじゃなく、
自分とその周辺がもっと大きな宇宙の営みのなかにあることが感じられる。
覚えるのが苦手だったから、
星の名前も、星座もほとんど覚えていないけれど、
ひとつ星座を知るだけで、世界の様相ががらりとかわる。
世界がぐんと広くなるスイッチ。
知識って、きっとそういうものなんだと思う。

前のすまいのときは、よくここの交番の警察官が巡回に来ていました。あやしいたたずまいの堀川マ●ションをぶっそうだと思ったらしく、「こんなところに住んでいたらいけない。」としょっちゅう言われていました。なつかしい。
さて、この交番の前を通るたびに、ええ仕事しとるなぁ…と思っていたのね。
写メなのでわかりにくいかもしれませんが、写真中央、警察署のマークが切り絵です。
画面のなかにヒエラルキーをつくらないこと、とか。
すでに価値づけをされているものの、その価値づけに加担するような写真を撮らないこと、とか。
そういうこと。
悪趣味な写真を大量に見てしまったのと、悪趣味な提案をさしむけられたのと、で、再認識。
2007-12-15
あいだにお金を介在させると、いろんなことが狂うな、と、最近思う。
本来は、お願いするひとが相手のところにうかがうのが筋だ。
世間の通例と違っても、それが筋だとわたしは思っている。
だから、わたしはお願いする相手のところにわが身を運ぶ。
そういうこと。
お金を払う側だから、来てもらって当然、という気持ちが、
金銭への隷属の第一歩。
自分の払う金にどれだけの価値を見ているのか。
それはむしろ、お金をもらう側ではなく、払う側である場合にこそ、
気をつけなければならないこと。
大事なことは、お願いしたりお願いされたりする関係を、
いかに良好に築くかということだと思う。
さいごのさいご、ほんとうの意味でひとを動かすのは、お金じゃない。
相手への敬意だとか、感謝だとか、志の高さだとか、礼儀の正しさだとか、
このひとと一緒に仕事をしたいという気持ち、そういうものだと思う。
それは、資金力のないなかで、
なんとかものをつくってもらってきたからこそ、学べたこと。
ひとにお願いしてものをつくってもらうんだよ。
ひとも業者も「使う」もんじゃない。
あるひとが「業者を使う」という表現をつかったときに、感じた違和感。
業者さんとわたしの関係は「使う-使われる」の関係じゃない。
「うちが使っている業者、紹介します。」とそのひとは言う。
「うちがお願いしている業者さんも紹介しますよ。」とわたしは返す。
つい「人づかいが荒い」なんて言ってしまうけど、
ひとに対して「使う」ということばを絶対に使うまいと思う。
2007-12-04
つい先日、手もとに届きました。初版発行が12月20日になっているので、もうすぐ店頭に並ぶのでしょうか。
恩師のお声かけで、ほんの少し執筆しています。どこかで見かけたら、チラとのぞいてみてくださいな。表紙は松村康平さんのデザインです。『芸術展示の現象学』(太田喬夫・三木順子編 晃洋書房)
分厚い本だから、しばらく開いてみる勇気がなかったのだけれど、スキャンの待ち時間のあいだに読みはじめたら、ぐんぐんひきこまれてしまった。制作者の生のことばだけに、問題意識を共有しやすかった。
いくつも、とりあげるべき箇所はあるのだけれど、気になったところからひとつ。
睡眠薬を常用し続けることによる知覚異常の話のところで、距離感を喪失する幻覚を見るという記述。抜き出してみよう。
幻覚といってもありもしない幻を見るのではなく、つまりそれはこの距離感の崩壊であり、事物と私との間に保たれているはずのバランスを喪失することであった。たとえば、テーブルの上にコップが置いてあるとする。だが自分にはコップをコップとして認識することができず、私とコップとの関係を正常に知覚することができないのだ。
ふるくからの友人が、幼いころ、ものがだんだん、小さくなっていくように見えることがあったと言っていたことを思い出す。家族の問題に端を発したその症状は、家族関係の改善とともに、なくなっていったのだそう。
ものの大きさの見え、は、隔たりや距離感と密接にかかわり、それが崩壊するというのは、単なる知覚のエラーという以上の意味を持ち、心理的な危機とも深くかかわっているのだと思う。
中平卓馬さんの近作にひっかかりを覚えていて、それが何なんだろう、と、ずっと考えていたのだけれど、最近ようやく、それは、ものとの距離感、隔たりにあるのではないか、と思いはじめた。身体距離を侵されたときの居心地の悪さに似たなにか。
先日、自分の書いた文章を読み直してみることがあって、あらためて自分が「隔たり」に強い関心を持っていることに気がつく。被写体との距離感。
2007-12-03
18時の星がもうすでにくっきり。
つい目を離せず、星を追って歩くみち。
街路を彩る金色の落ち葉。
いちょうの木がこんなにたくさんの葉っぱでくるまれていたなんて。
ささやかだけど、たいせつなこと。
そういうもののつみかさねで、人生をまっとうできたら良いな、と思う。
多くは望まないと決めたけど、
きちんと贅沢に生きているのかもしれない。
2007-11-26
タイトルがあやふやだけれど、
親戚の家で猪熊弦一郎の、ARIZONA AND CACCINA DOLLSという画集を見せてもらった。
少し古いものだと思うけれど、装丁も遊び心にあふれていて、
作品も、とてものびのびと楽しいものだった。
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館の常設で見る額装された作品は、均整がとれていてちょっとストイック。それよりも、この画集の線は奔放で、見ていて楽しい。
子どものころ、無心に絵を描いていたころの楽しさを彷彿とさせる。
それと、原美術館で開催中のピピロッティリスト展。
素晴らしい作品に出会ったときはいつも「自由でいいんだ」ということを思い知らされる。
知らず知らずのうちに、既成の枠のなかにはまっていることに気づかされる。
自分を不自由にしているのは、ほかならぬ自分自身なのだけれど。
2007-11-23
怠慢だと思った。
2年分、ほとんど未チェックのまま放置しているネガ。
スキャナの色再現が良くないせいにして、チェックを先延ばしにしていた。
撮ったものを、きちんと見ないでどうする。
そういう、ごく当たり前のことを、当たり前にできていないから、見えるものも、見えんのや。
2007-11-19
まだ二十歳すぎのころ、
それまでの人生のこと、ぽつりぽつり話したことがある。
その時点で、自分がやってきたことはすべて、やむにやまれずのことだと思っていた。
そのひとは言った。
「でも、あなたは、そうしたかったんでしょう。あなたはそれをやりたかったのよ。やりたいことを全部やったのよ。」
そう言われて、最初はきょとん、としていたのだけれど、
「わたしは、それをしたかった。」
と何度か反芻しているうちに、視界が晴れてきた。
それは、「やむにやまれず」なんてことばで、他者や環境のせいにしていたことを、
すべて、自分の選択として引き受けることだった。
自分がやったことはすべて、自分のせいだ。
やむにやまれず、という言い訳をしながら生きるよりも、
自分がしたくてしたことだ、と腹をくくって生きる方が、性にあっている。
その時点でやっと、わたしは自分の人生を引き受けたのだと思う。
自分の手もとにぐっと人生が引き寄せられた瞬間だった。
そこがターニングポイント、だったと思う。
それからは、願っても叶わないことがあれば、
自分の努力が足りないせいだ、と思うようになった。
どんな苦境にあっても、絶対に、他者のせい、環境のせいには、しない。
言い訳はしない。
そうわたしに教えてくれたひとが興した企業が25周年を迎える。
明日はその記念のパーティー。
きっとわたしが今まで立ち会って来たなかで、
いちばん晴れやかな場になることが予想される。
ささやかではあるけれど、感謝の気持ちを込めて、
明日は、祖母のうつくしい紫の絞りの訪問着と、金地の帯を纏おう。
2007-11-16
ひとと話しているとき、
一人称に、そのひとの自己認識を垣間見るのがおもしろい。
一見おとなしそうなひとが、俺と言うのに驚いたり、
会社の社長さんが、僕と言っているのを素朴に感じたり、
おいら、なんて、かわいらしい表現をするひともいる。
あと、学者御用達の「小生」。
ふるくからの友人には、わしとかオレと言う女性もあるから、
一人称が豊富な日本語って本当におもしろい。
わたしは、わたし、か、うち、を使う。
そして、俺ということばの屹立した感じ、どうもなじめなくて、
どうしても、僕、わたし、を使うひとのほうを親しく感じてしまう。
ことばってほんまに不思議やね。
語られてかたに時代のスタイルのあることとか、実は感想文程度でしかない文章が横行していること、とか、敢えて言うなら、2000年以降になって、やっとまともな論評が出てきたということを、確認できたのがおもしろかった。
批評の不在という、かの写真批評家のことばの意味がよくわかる一冊。
2007-11-14
ひどく暗部のつぶれるスキャナに辟易しながら、ネガスキャンをぼつぼつはじめる。イチョウが写ってるから、ちょうど去年の今頃のスナップ。
たまに、オーバーでスキャンしてしまうと、イマドキの写真っぽくなるから、おもしろい。
スロウライフ系の雑誌には、「光にあふれた」写真がたくさん出まわってるんやなぁ…とつくづく思う。
わたしには、世界はそんなに淡くない。甘くもない。
バランスの良い光やったんやと思う。
うす曇りのわりに、青に寄ってもいなかった。
光と影のコントラスト邪魔されずに、色がきちんと目に入ってきたから、いつもと違ったチャンネルで反応していた。その前の日と、まったく違うフレーミングでまったく違うものを撮ってる。
フレーミングすること、選択することによって、写真はいとも簡単にものを、被写体をトクベツなものしてしまう。その威力には十分慎重にならんといかん。意図があるならともかく、不用意に被写体に偏りがあるのはよくない、と思っている。
いつも、好んで細い路地に入りこむから、至近距離のスナップばかり撮ってしまうこと。見知らぬひとを撮るのが心理的に負担なこと。撮りたくなるもの、の、パターンが固定化してきていること。これらが、最近スナップのとき気にしていること。
中庸(?)な光のおかげで感じ方の軸がゆさぶられて、良かった。
あと50年生きれたとしても、あと何回、ゆさぶられるような光と出会うかわからない。
ほんとうに、ほんとうに、時間が足りない。
2007-11-13
最近、スナップを撮っていて、縦に構えることが多くなった。
縦にものを見ているというよりも、被写体によっては、35mmのフォーマット、横の長さを冗長に感じてしまう。
だからと言って、正方形は特殊すぎる。
縦位置/横位置、順光/逆光、比較のために撮ってみる。
順光と逆光の印象の違い、とか。
縦で撮る理由、横で撮る理由。
感覚だけではなくて、比較するなかで見えてくるものがあるのではないか。
そうはいっても、横殴りの光。軽い目眩の連続。
理性を手放さぬようぎゅっと。
2007-11-10
まる一日、歩いて歩いて、撮影すると、
それなりにいろんな光景との出会いがあって、
やっぱり、出ていかないと、出会わないと、あかんな、と思う。
たぶん、同じこと、が、人間関係にもあてはまるんやろうな。
わかってても、なかなか難しいんだけどね。
2007-11-09
と、言われた。本日、三度も。
唐突なことで、わがこととは考えづらい。
だってわたし、カメラマンよ。
日々を生きるので精一杯なのに。
でも、高額受注の仕事、納品したら、
「あんた商売っ気あらへんから儲かってへんやろ。」
と、謝礼をいただいてしまった。
この調子やったら、お金持ちになれるんかもしれへんけど。
我が家の家訓が
「ほんとうのお金持ちはひとのために(活きた)お金を使えるひと」
やから、いただいた謝礼は、この夏の撮影でお世話になった両親へのお礼に。
って、ほら、もらっても手元に残らへん。
こりゃ、あかんやろ。。。
2007-11-02
家にひとがいるから。
家にひとがいないから。
そのどちらの理由でも、家に帰りたくないと思うことがあった。
唐突にそんなことを思い出したのは、今日は日暮れまで家に帰りたくなかったから。
平成の大改修。
築年数不詳の住まい、早朝から大工さんが出入りして瓦をふきかえている。電ノコの容赦のない音が、リアルタイムで通っている歯医者の処置を思わせて、音だけで歯がいたい。
そんな事情で、家に帰りそびれているときに、そのひとのことばを思い出す。
家にいるのがいやでよく旅に出ていた。
それを聞いたとき、わたしはことばに詰まってしまった。
帰るのがいや、ではなく、いるのがいや、なんて、あまりに切ない。
2007-11-01
現物は見てないのですが、本日、無事、納品を終えました。
やっぱりどこか、ずっと緊張してたのね。肩の荷が降りました。
そして、長い夏やった。
方法論ばかり追いかけてると、本質的なことに目が向かない…という危機感もあって、
しばらくじっくりスナップ撮るの。そして、落ち着いて本を読みたい。
明日は晴れ◎
晴れやかな気持ちで写真が撮れる。
うれしい。すごくうれしい。
2007-10-30
ちょっとずつ、ちょっとずつ、
わりあい、増えていって、
もうあと戻りできないところまで、きちゃったのかな。
そろり、そろり、用心に用心をかさねていたのに。
最近、まったく、冷静じゃない。
2007-10-29
「家内が外気温より寒い。このままじゃ、自宅で凍死するよ。」
と、泣き言を言うと、
「晴明神社に行って、寒いさんに出て行ってもらうようにお願いせなあかんな。」
と、母。
ものは試しということで、撮影がてら晴明神社に。
これで、寒いさんが出てってくれたらええんやが。
雲間から、かすかに見え隠れする今朝の光は、
けっこう色っぽかったな。
2007-10-26
voice galleryで開催されている、現代美術二等兵のかに展。
「自由の毛蟹」って…。
と、あいかわらず笑える作品が並んでいます。
例年より、全体的に作品が小ぶりな感じがしますが、
ニヤニヤしながら見てきました。
同時開催(?)のたれ流しライフスタイル展の現実逃避という作品がいちばん好き。
ネガティブとポジティブと、二種類枕があるのん、むちゃおもろかった。
もう会期末間近。27日(土)までです。
今年は、射手座ではなく、voiceなので、おまちがいのないように。
2007-10-21
結局、深夜に外にでる口実ほしさ半分で、午前4時の再入稿。
寒くなると夜空が澄んで、
東の空のひときわ明るい星にこころを奪われながら、
なかば徒歩、なかば自転車の道程。
ひらけた場所で空を見上げる。
視界の端でとらえる流星。
流れたな、と思うのでせいいっぱい。
数年前の切羽詰まった気持ちはどこへやら。
いまは、叶ったらいいな、が、ほんの少し。
2007-10-17
午前2時の空。
星たちの確かな輪郭。もう冬は間近。
大学のころは、いつもこんなだったな、と思い出す。
作業自体は、それはそれは大変なんだけど、
深夜、天空に星を確認しながら、自転車で帰宅するの、けっこう好きだった。
目が覚めて、腕時計をしたまま寝てたことに気づく。
なんぼ忙しくても、それはないよね。
2007-10-15
2年前からずっと気になっていて、なかなかうかがう機会もなかったのだけれど。
今日はじめて、きちんとお話をした。
そのひとの、ものをつくる姿勢に、身の引き締まる思いがする。
昨日描けなかった線が今夜は迷いなく引けた。
彼の書いたもののなかから、見つけたことば。
誤摩化したり、言い訳したり、の、自分が恥ずかしくなる。
いいものをつくりたい、という気持ちを、誤摩化したら、あかん。
わたしは彼の志を纏う。
2007-10-10
連日のフォトレタッチ作業に、いささか食傷気味になっていたけれど、
テストプリントに入ってから、きた。
デジタルのデータが紙になったとたん、ぐんと楽しさアップ。
何度もテストプリントして、画面だけじゃわかりにくいバランスの微調整に入る。
暗室での作業は何時間でも大丈夫やのに、
PCでのフォトレタッチはありえないくらい苦痛なのはなんでやろ…と思っていたが、
やっぱり、素材との格闘がなけんとあかん。
PC作業ばっかの日が続くと、料理に凝るしね。
2007-10-07
ほどけてしまったんだ。
とっくに、気づいていたのよ。
ここでの余生を送るような気持ちは、ぬぐいようもなく。
いまはもう、さよなら、を受け入れている。
あたらしいお願いと、感謝と、さようなら、糺の森に伝えにいった。
かえりみちは、影絵の時刻。
木々の濃い輪郭をくるむ、太陽のわずかに残した橙、そして紺。
2007-10-04
たいせつなひと、目の前にたたずんでいるのに、まったく意思の疎通ができない。
わたしのそこに在ることすら、気づかない。
ことばを尽くしても、尽くしても、届かない悲しみ。
自分の存在をかき消されてしまったような孤独。
ぎゅっと気持ちが押しつぶされて、逃げるようにして目が覚める。
午前4時。
悲しみの質量を、そのまま胃が受けとめていた。
2007-09-30

ハルさんから誘いを受けて、かもめ食堂を観に行く。そのあとでご飯を食べて、「はい、プレゼント。」と渡された紙袋。
中には、茶色のショルダーバッグ。それも手づくり。裏地の布とか、さらにそのポケットの布とか、ずいぶん凝ってある。
そのバッグのなかには「Lisaちゃん お誕生日おめでとうございます」というカード。誕生日が近いから、わざわざ誘い出してくれたんだ、と彼女の心配りにやっと気がつく。そして、カードと一緒にしのばせてあったのが、この人形。
「それ、リサちゃん人形やで。」と言われて、思わずニマニマ。もじゃもじゃ頭がむちゃラブリー。そしてつい悪い癖。人形のスカートのなかを覗いてしまう。もうすぐ32になるひとのすることじゃ、ないよな…。
昨日は、今回の仕事のラスト、姫路城でのロケだった。
撮影地に近い実家で、早朝から支度をはじめていた。
出かける間際、台所の戸棚に、てるてるぼうずがくくりつけられているのに気づく。
16日の撮影が雨で延期になって、この29日、30日が最後のチャンス。
30日の雨は確実で、29日も天候が不安定なことが予想されていた。
多額の費用のかかるロケ、かなり切迫した状況で、決行の判断をくだしたことを、
きっと家族はわかっていたんだと思う。
すこし、じーんときて、
このかわいいてるてるぼうずを、そのまま車にのっけて姫路に向かう。
そして、途中パラっと小雨が降ったのものの、撮影は無事終了。
この無事は、運が良かったという種類のものでは決してない、とわたしは思う。
まわりのひとの「うまくいくといいね」という気持ち。
そういう気持ちがたくさんたくさんかさなってこその、無事、なんだ。
今回の仕事では、
見えるかたちでも、見えないかたちでも、多くのひとに支えられました。
深く感謝しています。
どうもありがとう。
2007-09-27
近景、中景のテストではわかりづらかったけれど、遠景でテストしてみて、ようやくレンズの解像力を観察することができた。
ハッセルのプラナー80mmよりPENTAX67のSMC105mmのほうが、解像力が高い。
数kmの道のりをかついで歩くには、華奢なハッセルのほうが良いのだけれど。機動性と解像力、どっちをとるか、悩むところやね。
実験と観察。この夏の収穫。
2007-09-26
仲秋の名月。
雨上がりの空は、しんと澄んでいて、
ひらけたところで月を見上げてから帰ろうと思っていたら、
ともだちが、おだんごを持って作業場に顔を出してくれた。
扉をあけたら、ちょうど良い位置に月がお目見え。
ベランダわきに腰をかけ、
すこしいびつな月の高らかに輝くさまを見上げて、お月見。
遠くの星のかすかなきらめきまで届いていたから、
これから転がり落ちるように、気温が下がる。
気がついたら、過ぎた季節をふりかえるところまで来ているんだ。
2007-09-18
舞子の海。
こういう撮影も悪くない、のかもね。
生まれてはじめて、海に陽が沈むのを見とどけた。
橋のうえでちょうど月が折り返す。
その傍にたたずむ赤い星。
海のうえ、広がる空のふところ。
夜の闇にこまかく隠れた星ぼし。
船が繁く行き交うさま。
潮風が肌にまとわりつく感触。
からだの調子も悪かったけれど、
それ以上にこころの調子が悪くて、
じくじくしたこころ、
海にすこし浚えてもらったのかもしれない。
なんでもなかったはずのことが、ある瞬間に突然、質量を持つ。
肩に感じるカメラの重み。月に寄り添う赤い星。
でも、決定的だったのは、突然の雨。
ささやかなことがたくさん、ふわりふわりかさなったら、
思いのほか、だった。
とびきりのひとり相撲。
グリーンアイスが、ひとつ、つぼみをほろこばせた。
夜景の撮影は、まず先に露出を決めておき、明るい時刻から待機して、その露出にあった暗さを待って撮るのが良いと聞き、早めの時間からポートアイランドで待機していた。
17時前後から暗くなりはじめ、18時半にはほぼ真っ暗。露光しているあいだにも、露出計の値は変化する。
あまりに日暮れのペースが速いので驚いたと母に言うと、「秋の日は釣瓶落とし、と言うのよ。」と、ごく当然のことのように返された。
秋に近づくと、日暮れの時刻が早くなっても、日暮れのペースがそこまで速くなるとは予想していなかった。あまりのショックに言葉を失う。
最初データをとった初夏の頃は、17時すぎから、暗くなりはじめて、完全に暗くなるのは20時を越えてからだった。
3時間強あれば、光の変化を細かく追えると思っていたのに、それが半分に短縮されてしまったら、さすがに厳しい。
ベストシーズンはやっぱり夏至のころか。
今週末に予定していた撮影は、来年に持ち越し決定やね。
仕事の忙しさでのばしのばしにしていたことが、
心底悔やまれる。
今年、とれるだけのデータをとっておこう。
2007-09-14
朝夕が涼しくなって、
夏の暑さに奪われていたこまやかな感覚を、
少しずつ、少しずつ、とり戻してゆく。
わたしの好きな季節。
今年、3台目のカメラを購入。
カメラに限らず、多くものを持つことは好きではないのだけれど、数十万円の費用をかけるロケに失敗は許されない。中判のサブ機はやっぱり仕事に必要、と、苦渋の決断。
おおいに悩んだあげく、学生のころから使い慣れた機種を購入。
ファインダーからのぞく世界、けっこう良い感触。
早速、レンズのテスト。
ハッセルがやきもちをやかなければ良いのだけれど…。
2007-09-11
今日は朝から太秦の映画村を探検。
というのも、お貸しいただく衣裳の確認をするため。
衣裳を拝見して、そのあと担当者とお茶をした。
実はすごく忙しくて、あと数週間、こちらの申し出が遅かったら断っていたとのこと。
本当はいろんな仕事を断っているのだけれど…とおっしゃっていた。
なんで、うちみたいな、一見の、それも何の後ろ盾もない個人事務所の仕事を引き受けてもらえたのか不思議に思って尋ねたら、今後につながりそうな予感、と、やたら値切らなかったから、とおっしゃった。
最初から値切りにかかるひと、自分たちの持っている衣裳や技術の価値をわからないひととは、ロケの現場でも絶対うまくいかない。そういうのは、先に断るか、断られる方向に持っていくのだと。いろいろ、テレビのロケも断っているなかで、今回の仕事、引き受けてもらっている。
うちは、モノをつくるひとの工賃をたたくようなことは絶対にしない、
というのが信条だから、それが通じたのかもしれない。
安くあげることばかりを考えたら、実現できることもできなくなるんやなぁ…と思った。
そして、衣裳や技術以外の部分で、経費削減の努力をしてもらっている。
新幹線での移動を、社用車利用に切り替えてもらったり。
ひとつのものをつくりあげるのに、金銭のやりとりによる不信のなかで仕事をするよりも、お互いが納得する利益を確保したなかで、どう合理的に経費を削れるか知恵を出し合うほうが、よっぽど、建設的だと思う。
それでもわたしは、世間知らずのお嬢さん、なんだろうか。
2007-09-05
「しっかりしなさい。」
部屋のなかには、母とわたししかいない。
え?…と思ってふり向くと、
母は扇風機に向かって話しかけてる。
しっかりしなさい。
聞けば、扇風機の首がぐにゃぐにゃして、落ち着きが悪い、とのこと。
自分のことかと思ってドキドキしたわ。
2007-08-30
どんなに頑張っても、
限られた時間内で慣れない着物をコーディネイトするのには限界がある、と思った。
行く先々の着物やさんで、相談する。
信頼できる、と思うお店でコーディネイトをおまかせする。
という方法に切り替えた。
何でも自分でしょいこまずに、
その道、その道のプロに相談して、まかせる。
OMOというそのお店に銘仙と小紋を持ち込んでみたら、
「こちらのほうがいい」と、祖母の小紋を選ばれた。
結局は、祖母に、祖母についている布の神様に、ずいぶん助けられてるんだと思う。
コーディネイト、仕上がりは月曜。
お正月のページを飾るモデルさんには、
華やかで上品なものを着せたい…という思いがあって、
撮影ぎりぎりまで衣装探しに奔走。
レンタルの振袖、うすっぺらでケバくて、ろくなものがない。
華やかと派手をはきちがえている。
見ていると吐き気がしそう…と思った。
現代のほんまにええ振袖は、到底手が出ない。
だから、アンティークの振袖。
運がよければ、状態が良くて、素敵なものがあるかもしれない。
そう思って、京都市内のアンティーク店はほとんどまわった。
目を皿にしてオークションも見てまわった。市にも行った。
それでも、お金を払ってまで欲しいと思えるものがなくて、万策尽きた…と思った矢先、
1万着以上、着物を持ってはるというコレクターの方を紹介してもらう。
聞けば、その方は映画SAYURIの衣装を全面的に提供されたのだそう。
京都ってやっぱり奥が深い。
予算と日程を伝えて、なんとかギリギリ、
黒地のとても可愛らしい振袖を貸していただく手はずが整う。
この2ヶ月、いろいろお店を見てまわったけれど、
華やかで嫌味がなく、心底可愛いなぁと思える着物なんて、
ほんまにひとにぎりしかない。
さいご、たった一着にYESを出すまで、
諦めずにずっとNOを言い続けた甲斐があったと思う。
めぐりあわせに感謝。
2007-08-29
「昔から好き嫌いがはっきりしていたからね。」
この夏久しぶりに会った幼なじみから言われて、しばらく考えていた。
自分のことを優柔不断で、何かを前向きに「選ぶ」ことがあまりない…と思っていたから、そう言われたのが意外だった。でもよく考えてみたら、なにかあるものを「選ばない」という方法で、別のものを選択しているのかもしれないということに思い当たる。
Aを積極的に選ぶ、のではなくて、
BとCとDとEとFを選ばない、ということによって、
Aを選んでる。
Aを選んだつもりはなくても、
最後にAが手もとに残る。
こうやって自分は、自覚もないまま「選ぶ」を繰り返してきた。
ちょっと恐いな、と思う。
自分はこんな人生を選んだつもりはないと思っていても、
それは別の人生を「選ばなかった」だけのことだ。
きっとそういうひと、多いんだと思う。
2007-08-28
結局さいごは、おかんが見かねて、
「ここをバイアスで使って、こう切って…」と、手伝ってくれた。
午前2時すぎまでかかったけれど、無事リボン制作は終了。
当日、赤いドレスを着たモデルさんが
「おもしろいのがいい。」と言いだし車の上にのっかっちゃったり、
岸壁での撮影を遊覧船からひやかされたり、
現場では思いがけないことがあるから、おもしろい。
今日は太秦の映画村からプロの鬘師に出張してもらって、鬘あわせ。
OLさんがオフィスで日本髪の鬘をかぶらされているのは、なかなかシュール。
その格好で電話応対してほしかった。
いろいろ、おもろい。おもろいわー。
2007-08-25
反物では、ワイヤーを入れてもリボンのふわっと感が出ないことが判明。
まずい…。
どうしても「できませんでした」とは言いたくなくて、
朝から布屋さんにかけこんで、相談してみた。
「車にリボンをつけたいんですけど…」
ひととおり説明を終えたら、店員さんはやっと納得された様子。
オーガンジーのような薄い透ける布で、リボンをつくる方法を教えてもらった。
帰りぎわの挨拶に、「お気張りやす。」と声をかけられ、
やっぱりここは京都なんだと思った。
荷物を持って、これから帰神。
2007-08-23
今朝知った。
都市公園、業としての撮影には使用許可申請と使用料が必要。
撮影は日曜。官公庁は平日しか開いていない。
蒼白になって、仮縫いのあと、その足で市役所にかけこむ。
公園管理課。はじめての訪問に、ドキドキ。
こういうとき、自分は恵まれているな、と思う。
困ったり切羽詰ったりしたときに、親切なひとにめぐりあう。
市役所の職員さん、右往左往しているわたしに、都市公園と市民公園の違い、と、
実は撮影予定地が全部、管轄がバラバラであること。
フィルムオフィスが一括して申請を代行してくれることを教えてくれた。
そのうえ、フィルムオフィスに紹介の電話まで入れてくれて、
バトンはフィルムオフィスに渡された。
状況を説明し、期限の短さに半ばあきれられながらも、
フィルムオフィスの担当者の尽力で、
ぎりぎり撮影の申請を通せる見通しがたった。
ほんの4時間ほどのあいだに、たくさんのひとのお世話になる。
明日はアサイチで申請書の提出。
関東で仕立ててもらったドレスは明日発送される。
車にかけるリボンにはワイヤーが必要。
いろんなことが動いて、いろんなひとに助けられてる。
撮影開始まであと2日。
2007-08-07
被写界深度の深さとピントそれ自体の質とは別ものだということを教えてもらい、朝から出かけて、35mmと中判のそれぞれ、レンズのテストを行う。
それってほぼ「ふりだし」っちゅうことやねんけど。かなりショックだったんだけど。
簡便なのが写真の良いところではあるが、道具の特性をきちんと知っておくほうが、何も知らないで使うより賢明だろう。
2007-08-06
うしろの席の子どもたちがにわかにさわがしくなる。
「ほら、赤いのが見えた。」
「わー、綺麗。」
なにごとかと思って窓のそとを見ると、
そう遠くはないところに花火があがっている。
あっと言う間に通り過ぎたこのときばかりは、
さすがに新幹線のその速さを疎ましくも思えたけれど、
しばらくしたら、反対の窓にも花火がチラリ。
この新幹線、花火のあいだをぬって走ってるんだ、と思ったら、
みじかい旅のさいご、ちょっとうれしくなった。
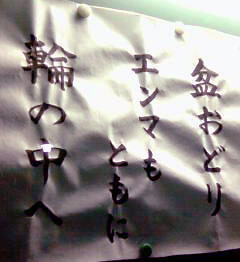
近所の願照寺の門前で発見。時季に即した文面。そして、このおおらかさ。素晴らしい。
日本は八百万の神さんが、みんなてんでバラバラにああだこうだ言うて、一神教に比べると、おおらかであると河合隼雄の著書に書いてあったと母が言う。
子ども同士で遊んでいても、あとから来た子に「入れたげない」という意地の悪い子と、「ええやん入れたげようや」というおおらかな子がいたなぁ。学年のさいご、けっきょく人望を集めるのは後者のほうやった。
「盆おどり エンマもともに 輪の中へ」
ほのぼのしとっていいよね。
2007-07-28
対談だしあまり気負って読まなくて良さそうだったので、手に取ってみた。森山さんの文章はけっこう読む機会が多いので、対談の内容はあまり目新しいことはなかったけれど、印象に残ったのは、「アメリカでは写真展のことを、ショーと言う」という話を、繰り返ししてはること。エキジビションとは言わないそうだ。
見世物なんだよね。
という森山さんのことばは、すとん、と納得できて、写真なんだから、そのくらい猥雑で軽やかで、ええやんって。
あとがきの「たかが写真であり、されど写真である。そのたかがをされどと言ってみたくって、ぼくは長年写真にこだわりつづけてきたような気がする。」というの、つくづく、うまいこと表現するなぁと思う。
「たかが写真」なんよ。本当に。たいそうなことやない。
でも、その「たかが」に、一生を賭けるひとが、賭けようとするひとが、少なからずおるんよね。
雨があがって、バタバタと動き回っていたけれど、朝のスナップ再開。
直接、作品につながらなかったとしても、わたしの軸はそこにある。
ただ、撮り終えたものをきちんと見る時間を持てていないところが最近の大きな問題。
スナップは、やっぱりネガからポジに戻そう。
夏の光は、コントラストがきつくて、どうも苦手。
外を出歩いて、ふだんより長時間粘っても、
ほとんどシャッターきらずに帰ってくる。
だからといって出歩くのをあきらめるのは、もうよそうと思う。
改善点ふたつ。
2007-07-23
訂正記号をいちいち父に尋ねながら、初校のゲラに朱入れ。
3ヶ月あけて読み直すと、文章のアラが目立つ。
「日本語は書き下しで、英語みたいに前に戻って読むことはないから、戻って読まないとわからないような文章はよくない。」
と教えられる。
なるほど。日本語ってリニアな構造なんだ。
2007-07-19
地下鉄、丸太町の構内に、特報の貼り紙。
「河合隼雄氏死去」
お体を悪くされていたことは知っていたけれど、亡くなってしまったんだ。
15歳の思春期まっただなか、
コントロールの効かない「気分」をどうにか理解したくて、
むさぼるように読んだのが、河合隼雄さんの臨床心理学の著書。
そのころ出ていた著書はほとんど全部読んでしまったんだと思う。
人生のいちばん不安定な季節を通り抜けると、読む機会も少なくなった。
それから10年後の25歳。
感じるということに対して関心を持って読んだのが、
鷲田清一さんの臨床哲学と現象学の著書。
そうやって、人生のある季節に集中して読む、ということがあるのだけれど、
河合隼雄さんの著書は、思春期のころに出会っただけに、
受けた影響も大きかったと思う。
10代で持て余していた「こころ」を、
やけにもならず、乱暴に切り上げも切り捨てもせず、
まんま、つきあい続けることができたのは河合隼雄さんの著書と出会ったおかげだったと思う。
感謝と、ご冥福をお祈りして。
2007-07-18
撮影用の衣裳。
自分用に自腹を切ってでも買いたいと思うものしか買わない…というのがひとつの基準。
最近の着物で、ほんまに上品でええもんを買おうと思ったら、おそろしく高価だし、
かといって、廉価で見た目に安っぽいものを買うわけにもいかず。
…と悩んでいたところ、お店のひとが出してくださったのが銘仙。
まえに通崎さんがテレビで紹介しているのを見たことがあって、
「メイセン」という音だけ、覚えていた。
昭和初期から1960年代くらいまでつくられていた、庶民の普段着用の着物なのだけれど、
柄がすごくモダン。正絹で、パリッとしているふうあいが新鮮だった。
さて、この水玉柄の銘仙。どうやって「現代着物」にしたてあげるか。。。
ここが腕の見せどころやろね。
2007-07-15
大雨のなか、春に書いた原稿の初校が戻って来た。
今まで、アルバイトで父の原稿のチェックをしたことはあったけれど、初校の見慣れない体裁に少し戸惑う。
大それた思惑のある作品をつくっているわけではないから、文章を書くこと、少し躊躇もあったのだけれど、活字になることで、少し遠くなって、これが本になったら、ずっと遠くなることは想像に難くない。
先日、雨のなか、先輩と話していた。
わたしは写真家はそもそもいかがわしいもので、ジャズメンのようなもんだと思う。そして、むしろいかがわしいほうが、おもしろいことができるんじゃないかと思っている。
野に放たれて、たくましく生き延びながら写真を撮らんと、撮り続けんとあかん。というのがわたしの勘。そして、わたしは自分の勘を信じている。
…布のかみさんのごりやく、やろうか。
(ふつうは見つからないと思うけれど)どこに行っても見つからなかった、
マリリンモンローの衣裳。
あつらえてくださるという方を紹介してもらえた。
パロディは、中途半端にやるとカッコ悪いと思っていたから、
あつらえられると、本当に助かる。
空にも、気持ちにも、少し、晴れ間が見えて来た。
雨のあいだ衣裳と撮影許可の手配ばかりで、
スナップもロケハンもテスト撮影もできなかったから、こころもからだもナマってる。
外を歩かない日が続くと相当にストレスフル。
今週から調子を戻そう。
2007-07-10
さめこもん。おおしま。どろおおしま。もんつき。しぼり。
まるおび。なごやおび。ふくろおび。
わたしが疎いだけなのかもしれないけれど、きき慣れない言葉をたくさん知る。
家族に吉報があり、昨晩は母と一緒に実家のタンスのそうざらえをしていた。
母のタンスと祖母のタンス。
大正生まれの祖母の着物だけでなく、曾祖母の明治の着物まで、たいせつに残されていた。
母は知らなかったのか、ふたりで大興奮。
祖母は、ええとこのお嬢さんだったらしく、
嫁入りのときの道具はすごかったと母からも親戚からも聞かされていたが、
祖母の着物、予想外にすごかった。
ひとり娘だった祖母のためにつくられた着物の数々を見た母は、
曾祖母がどれだけ祖母をたいせつにしていたか、つくづく実感している様子。
わたしのほうは、ええもんは、古くても、後代のひとにもええもんやと
ちゃんと伝わるねんなぁということをぼんやり考えていた。
わたしは着物のことはようわからんけど、
祖母の着物は、見ているわたしをドキドキさせる。
着物に興味なんてほとんどないけれど、着てみたいなぁと思わせる。
その時代の帯が、帆船の柄だったりして、
とにかくいまどきの着物なんか軽く飛び越えるくらいモダン。
祖母が母のためにこしらえた振り袖、
わたしが13のときに着せてもらったものを今また見たら、
とても繊細な色の刺繍が施されていて、ええもんやったんやなぁと実感。
わたしは、ばあちゃんには布の神様がついとると思っていたけれど、
彼女の着物を見て、ほんまに神様がついとる、と確信した。
そして、それはばあちゃんのお母さんが、自分の娘のためによんできた神様なんやと思う。
祖母の嫁入り道具の、
綺麗な赤の絞りの襦袢と、鮮やかなターコイズブルーの訪問着をあわせて着るハレの日を、愉しみに待つことにしよう。
2007-07-05
自分の制作ではない撮影のしごと、考えるところが多い。
写真の仕事は、ほかの仕事と違って、自分の作品に傷をつけたくないから、絶対に下手できないというプレッシャーが強い…ということを実感する。
自分が、これは作品、これはcommercial、と分けていても、ひとは、そうは見ない。
今回の仕事は、先方の社長さんが、わたしがcommercialの人間ではないことを承知のうえで、それでも依頼してくださった。
その気持ちに、真摯にこたえたい、と思う。
自分のなかでのいくばくかの葛藤を抱えながら、貴重な晴れ、ロケハンにでかける。
わたしはcommercialを否定はしない。受けたオーダーの中で自分の表現とのバランスをいかにとるか、というせめぎあいも経験してみようと思う。もしかしたら、商業写真ではない人間が、そのせめぎあいの中からなにかを探るほうが、おもしろいものが生まれるかもしれない。
この夏は、また川を撮ります。
忙しさにかまけてそこを譲ったら、うちは終わりや。
ふんばりどころやな。
2007-07-04

ひとつきほど前のこと。三条会を自転車で通っているときに、ふるい文房具店の軒先に置いてあるのを見つけた。
「はこでん」
なんとキュートな。。。そのうえ、ワンコイン。
で、息抜きにと、組み立てはじめたら、これがなかなか難しい。
子供の頃、雑誌のふろくの「やまおり」「たにおり」がようわからなくて、
ほとんどオトウトに組み立ててもらっとった…ことを、いまさら思い出した。
対象年齢3歳以上、15分ほどで組み立てられると書いてある。
今年で32になるわたしは、3時間近くかかったんだけど。
はこでんのすごいところは、ちゃんと、連結するんだよ。
で、引き出し式になっていて小物も入る。(←あまり必要じゃない機能やけどな…)
えらいぞ、はこでん!

ネットで調べたら、2年前くらいから販売していたらしい。仲間もたくさんおる。
こんなキュートなおもちゃを今まで知らなかったなんて。。。
やっぱ、蒸気機関車、つくりたいよなぁ。
→ はこでんのサイト
2007-07-03
今日は奉公、最終日。
助っ人的存在として関った大型サイトのリニューアル、
本日午前9時にオープンを迎えた。
10時に出社したら、
かわいらしいうす桃のふうとうに入ったカードがキーボードにさしてあった。
「染田さんへ」
と書かれたそのカードの裏には、小さなよつばのクローバーのシールがはってある。
開いたら、お礼のカードだった。
無事、リニューアルが済んだ報告と感謝のことば、
性格のにじみ出る几帳面な字で綴ってあって、
出社早々、泣きそうになった。
若い男性のADさんからの濃やかな気遣い。
たった一片の紙が、たった五行のことばが、
こわばったこころとからだをほどいてゆく。
ほんとうの、ねぎらい。
夜は、打ち上げ兼送別会。
手渡された花束に、思わず涙がこぼれる。
人生のほんの一瞬、ひとごみのなかですれ違うくらいのはかない出会いだったけれど、
この若いひとたちと一緒に仕事ができて、本当に良かった、と思う。
明日からはひとり屋台。気合いを入れてまいりましょう。
2007-07-02
R座、二度目の訪問。
一度訪れると、ハードルは低くなるもので、
日曜日の夜、みず知らずのひとと並んで映画を見るのが、楽しみになってきた。
サルサ!という映画、
タイトルのとおりのダンスムービーやけど、ダンスムービー特有のストーリーの安っぽさもなくて、気持ちよく見られた。フランス映画だし、少し、アフロアメリカンの描きかたに偏りを感じたけれど、青春恋愛映画としては、充分。ほんで、こんな機会がなければ、青春恋愛映画なんて、自分では絶対に見ないから、新鮮やった。オトも良い。
ところどころ、ききとれるスペイン語の響き。
キューバに行きたくなった。
日本はチマチマしてていややな、と、
ペルーから帰国したころから20年間ずっと思っていたから、
中南米、行ってしまったら、帰りたくなくなるだろうね。
35歳までに、メキシコとキューバと。
→ サルサ!
2007-06-29
実家に帰ると、いたるところに色とりどりのあじさいが飾ってある。
「おお、すごいな、あじさい。でも一部屋に花瓶三つはやりすぎやろ。」
と言うわたしに、母は切り返す。
「あじさい祭りやからな。」
そうか、祭りやったんか。。。
「でももうあじさい祭りも佳境やわ。」と母はすこし残念そう。
「あじさい祭りが終わったら、次は何まつりなん?」と尋ねると、
「そんなん、あんたんとこ(京都)の祇園祭やろ。」と。
あじさい祭り、祇園祭とタメはっとったんや。
2007-06-27
夕暮れどき、きちんと「いちにち」を見送ることができると、嬉しくなる。
気がつくとそとが暗くなっていたというのは、哀しい。
どんどん暗くなっていって、街に灯がともっていく、その時間のうつろいを、両の手のあいだに封じ込めたい。と、思うのです。
見てみたい。とか、つくりたいという、キラキラした気持ちがあるときは大丈夫。
で、想定しているのは、冊子。
美術手帖のインタビューでも、日本の作家の海外進出がすすまない理由として、作品が書籍になっていないということが挙げられていた。
ま、「進出」なんてどうでもええんやけど。
おもしろいもんをつくって、それを他人と共有するのに、冊子として流通するというのは、すごく良いと思うんだ。たいそうなもんとして、じゃなく、ひとの生活に入り込めるし。
あとは、めぐりあう機会の問題で、展覧会するのと、写真集をつくるのと、どちらが多くひとにめぐりあうやろか?ってところ。
ほんで、ひらく、めくる、とじる、もどる、といった操作が、
映像よりも自由なかたちで、見るひとにゆだねられてる。
「見る」方法を、ぽーんと相手にゆだねているというところが、おおらかでいいやん。
2007-06-23
晴れた!
早速、届いたカメラのテスト撮影に出かける。
35mmの目になってしまっているから、ロクロクのsquareフォーマットに違和感を覚える。
作品は合成前提だから、もとのフォーマットは無効化されるけれど、
問題はほかの撮影で使うときやなぁ。
squareのフォーマットは、たいした写真やなくても、それっぽく見える魔力があるからなぁ。
気をつけないと。
2007-06-22
しばらく雨マークが続くから、わずか1時間の昼休みに抜け出して強行でテスト撮影。ええあんばいに薄曇り。絞り22から2.8まで徐々にひらく。
撮り終えてから、気がつく。
本番で使うセットやないと意味ないやん…と。
気をとりなおして、ネットで公開されている、被写界深度の計算プログラムで計算してもらうと、40m離れた被写体にピントをあわせると、絞り2.8でも、19.360m〜∞までが被写界深度。ほんまなんかなぁ。
被写界深度の式、疲れていないときにちゃんと自分で計算してみよう。かなり理科や算数に近い。ま、数字じゃ納得できなくて、どうせ見てみないと気がすまないんだけど。
問題点は、水平垂直はええとしても、暗いなかで被写体に対して正面、がきちんと保てるのか…。思っていたよりずっと撮影条件が厳しい。
2007-06-20
きちんと暗くなった時点で、ISO800 / 絞り22 / 1/2s〜(場所によっては8s)
絞り、どこまで譲れるか、段階的に絞りをかえてテスト。できれば、明朝。スケジュールがきつい。
2007-06-19
天候のせいでテスト撮影が延びている。晴写雨読だ。
山の姿によって方位を知ることがなくても、そう、ビル群に視界を遮られた「巨大な密林」とでも言うべき東京にあっても、道に迷うことが少ないのは、目印の建造物から目的の場所まで移動してゆくその途中の光景をからだが憶えているからである。景観というのは、移動という運動のなかでのそういう光景のめくれというかたちで(あるいは、流れるように脇で眼に入っているらしい光景の断続というかたちで)身に刻まれるものであって、けっして正面に立ってこの景観はすばらしいというように感得されるものではないのである。
(『京都の平熱 哲学者の都市案内
』 鷲田清一著 2007 講談社 より抜粋)
最近、大通りを歩くとき、しっかりと対面にある景観を確かめるようにしている。
ふだんは進行方向を向いて脇に見るともなく見ている光景を、あらためて正面から直視すると、見知らぬ街にいるかと思うくらい、まったく印象が異なる。脇に見ることと、正面からじっくり見ることはまったく違う体験なんだと実感していたところだ。
正面に立ってこの絵はすばらしいというように感得する、美術の要請する「見る」作法はかなり特殊だと思うから、その正面に立ってじっと見るという作法を、日常の何に適用したら、いちばん違和感があっておもしろいやろう…と、ずっと長い間考えている。
なにか特別な場所から、完璧に全体を把握できる目になりきるのは、好きではない。その現場に身を置いていることとか、完結させずにおくこととか、すべてを見渡せないままにしておくこととか。画面の外につながっていく意識だとか。
そういうこと。大事なのは。きっと。
わざわざ、閉じない。
2007-06-17
何度も、何度も、暗室の赤い光の下で泣いとった。
わたし、いったい何してるんやろうって。
あのころのわたしにとって、暗室がいちばん安心して泣ける場所やった。
いまはもうそんなこともなくなったけれど、
それでも、周囲の環境に流されてブレてしまうことが、ある。
迷いだらけで、自分の位置すらわからなくなることも、ある。
でも、幸せなことに、わたしには夜空に輝く星のようなひとがある。
古のひとびとが、星をたよりに旅したように。
わたしはそのひとの背中をはるか遠くにたしかめながら、
自分のいま在るところを、進むべきところを、おぼろげながらも見定める。
NAVSTAR
見失いかけたかなと思った矢先、メールが届く。
ほとんど地球の裏側の、南米エクアドルの軌跡とともに。
「オポチュニティーの神様のひげをつかまなあかん。」
電話口で母がそう言う。
「オポチュニティーの神様にはひげがあって、そのひげを正面からぐっとつかまなあかん。」のだと。
「正面からじゃないとあかんの?」と聞き返すと、「うん」と母。
オポチュニティーの神様のひげ…。おかん、突然かわいらしく攻めてきたな…。
「誰が言ってたん?」と尋ねると、「昔、英語の先生が。」と。
おそるおそる尋ねてみる。
「(仕事先の)社長さんにもひげがあるけど…。」
「つかまなあかん。」
2007-06-14
特別なひと。
いちばん危うくそしてキラキラした時間を共有したひとというのは、
すごく特別で、何年経とうと、その手触りはふとした瞬間に戻ってくる。
ファインダー越し、追いかけて、
楽しげに演奏するその表情があまりに綺麗で、かっこよくて、
無防備にドキドキしている。同性なのに。
14年前からかわらず、ばかみたいにまっすぐで繊細なひと。
たとえばひきこもりという言葉。
安易に使っていたけれど、
本当にひきこもっているひとを支えているひとの前で不用意に使ってしまったこと。とか。
あるひととの会話、発話がかぶると、自分の話のほうを通してしまうこと。とか。
そういう心ないふるまいが、ここしばらく多かった。
今さら謝れないほどささやかで、蒸し返すほうがかえって不愉快で、
ささやかであるだけに決定的に酷いこと。ばかりだ。
相手の懐の深さにゆだねるしかないあれや、これや、が、
深くこころに沈殿している。
ごめんなさい。
2007-06-12
哲学の道に寄った帰り、自宅の斜向いの大家さん夫婦が、
娘さんらしき女性を送りだしているところに出くわす。
家族のたいせつな時間。なんとなく、邪魔したくなくて、
知らない人間のように声もかけずにそっと通り過ぎる。
角を曲がったところでしばらく待って、ころあいはかって引き返すと、
まだ奥さんが、遠ざかる娘さんの背中を心配そうに見守っていた。
歩きながらイヤホンを耳にさそうとしている娘さんとはうらはらに、
身を乗り出してじっと見守る奥さんのその姿があまりに切なくて、
挨拶もできずに家の前を通り過ぎる。これじゃまるで不審者だ。
二度目の立往生は、揺さぶられてしまったこころの後始末。
2007-06-11
結局、帰宅は深夜になって。
帰りみち、見上げた空の星の多さについ、
機材を一旦家に置いて、25時の散歩に出かける。
引越してから、夜空を見あげることが少なくなった。
街中は明るくて、暗いところを探すようにふらふら歩き、
銅駝のほうから鴨川に出ると、唐突にひらけた空に、大きく赤い月。
三日月ほどに欠けているのにどうして。
はじめてみる月のその風情に、狼狽。
この月に呼ばれたのかと思うと、こわくなった。
2007-06-07
ひとからよくものをもらう。
でも、今回もらったのは、アドバイス。
そして、迷っているわたしの背中を、最後に、ぽん、と押してくれた。
今回の仕事先の社長さん。わたしの迷いをすべて見透かしてはった。
大学に入り直してまで勉強したのだから、
コマーシャルのほうを向いていないことくらい、わかる。
芸術をやりたければ、やればいい。
でも、どのみちお金を稼がないと生きていけないのだから、
自分の技術でできる仕事を受けて、体裁もきちんと整えなさい。
個人事業主でも屋号をつけなさい。
屋号は長く使えるものにしなさい。ころころ変えるとお客さんつかなくなる。
そして、屋号をあたまに、代表 なにがしと名刺に載せなさい。
それだけであなたの立ち居振舞いも、気構えも、相手の扱いもかわるから。
そしたら、それなりに仕事が入ってくるものだから。
仕事が忙しくて、自分の好きなものをつくることができなくなりそうなら、
仕事を断わればいい。いやな相手と仕事しなくてもいいのだから。
気持ちよく仕事ができる相手とだけ仕事をすればいい。
あなたが、口先の営業に向いていないことも、したくないことも、よくわかる。
誠実できちんとしているから、いい仕事をすれば、必ず、お客さんは増える。
あなたはそれができるひとだ。
さいごには、
どんな値切っても、その値段でお願いすると決めたら、お金の支払いは、綺麗にしなさい。
でないと、支払いの不確かな仕事は誰もきちんと働いてくれないから。
だから、あなたに制作費を先払いします。と。
ほんまに、全部、全部、見透かされとった。
二十歳すぎたころから、出会う社長さん、社長さんに、本当にたいせつにしてもらってきた。自分の昔を思い出しながら、いろいろ、教えてくれはるん。なんでわたしなんかが?と思うくらい、格別の扱いも受けてきた。
「ひとのよろこぶことをすれば、お客さんは増える。簡単なことだよ。」
まったく別業種の二人の社長さんから教えてもらった。
ずいぶん遅くなったけど、決断するね。
嵐が来た。と、思う。
自分の立てた計画なんか、なしくずしになるくらい、めぐりあわせに翻弄される。
自分の力の及ばないなにか、が、どっと押し寄せて、
きっと拒むこともできるだろうに。
どうしてもほかの名前が見つからず、
2007年5月30日、惑星を屋号に冠し、開業しました。
母に「あなたがともだちとわいわい言いながら、仕事をしているところを夢に見た」と言われたことが、知人に「二年後くらいには、みんなと仕事やっているんじゃないですか?」と言われたことが、ほとんどそのまま実現し、チームを組んでまとまったボリュームの仕事を受けることになりました。チーム惑星。
このひとと一緒にしごとができたらいいのにな。
2年越しそう思っていたひとと一緒にしごとをします。
今年は本厄なのに。
この2年間、何より切実に求めていた、制作者としてのアイデンティティ。
それを、とても素敵なめぐりあわせによって授けられたこと。
調子の悪かったともだちが、元気になったこと。
そして、チーム惑星。
「そめちゃんには運がめっちゃあります。あるのです。全部望んでね!ゆずれないこと全部やでー。」
ともだちから届いた年賀状の文面を思い出す。
ほんまに、ゆっくり、でもたしかな手応えで、望んだことがひとつずつ、かなっていってる。
2007-06-03
正式な名称をしらない。
お寺の入り口の掲示板に書かれている「ひとこと説法」。
京都はお寺が多いのであちこちで目にするのだけれど、けっこうこれが興味深い。
なかには「?」なものもあるのだけれど。
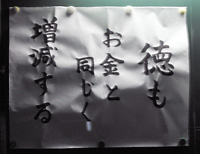
これは、願照寺の前にあったもの。「お金と同じく」というところに妙な説得力がある。徳の話をするのに、お金を引き合いに出すところがすごい。
毎日通る道には「わかっちゃいるけど、やめられない」というのもある。
タバコか?酒か?ギャンブルか?
そもそも誰に対する言い訳やねん。。。って、わたしはとても好きなんやけど。
あと、三条会に「茶のごとくもまれて味出る人間味」というのもあった。
なかなか個性的。
でも、こういうことばに見えないところで守られながら、
この町のひとは生きてきたのかもしれないな。
帰宅すると、はなれの玄関先にちょこんと鉢が置かれている。
棕櫚竹だったり、サボテンだったり。
いちど鉢植えの話でもりあがって以来、
母屋の奥さんが、いろいろ鉢を分けてくださるようになった。
「置いてある」というのが、なかなか好い。
こっそり家の前まで来て誕生日のプレゼントを置いて帰るともだちがいたけれど、
それに近い。
いただいた鉢のおかげで、ベランダがずいぶんにぎやかに。
花のおかあさんは最近、子だくさん。
お返しというほどでもないけれど、
小鉢で咲いた白いミニ薔薇を一輪、母屋から見えるところに飾っておく。
鷲田清一さんの「他人の視線をデコレートする」ということばを思い出した。
ちょうど薄曇りなので撮影ポイントにでかける。
晴天よりも俄然良い。
被写体を落ち着いてじっと見ることができる。絶対に逆光でしか撮れない被写体だから、拡散光のほうが◎なんだな。晴天だと、バックから射す光が邪魔になる。こういうのん、理屈でわかってても、実際見てみるまで納得できひんもんなのね。
細部の色を引き出すために、ビビッドカラーのフィルムを使うこと。あとは、感度400にするか800にするかを決めることと、タイムテーブルをつくること。中判カメラを調達すること。(←これがいちばん難儀だな)
今回は、ドキュメンタリーという要素を強く意識する。
あとは、やってみた感触に従うしかないでしょう。
たいせつなのは実験精神と「見てみたい!」という強いきもち。
失敗を恐れないこと。
2007-06-01
ほたるの季節。
忙しさにかまけていたら通り過ぎてしまうであろうささやかなこと。
今年も立ち止まれる境遇に、感謝。
2007-05-28
しくみを知りたい。なかがどうなっているのか知りたい。
と、思うことがたまにある。
ほんで、GPSってどういうしくみなんだろう…とずっと思っていたのね。
「あなたは今、どこどこにいますよ。」って衛星がわざわざ教えてくれるんか?
そんなこと、大勢の人にいっぺんにできるんか?
と思ってたら、さすがにそんなことはないんだ。
衛星が発信するのは、時刻と、衛星の衛星歴と軌道歴。
発信する側の時刻の情報を、受信機が受け取るその時間差から発信元の衛星と受信機との距離を計算する。でも、ひとつの衛星からの距離だけでは、受信機側は自分の位置が特定できないから、複数の衛星からの距離を割り出すことで、自分の位置を特定する。(昔、点aから3cm、点bから5cmの点cを求めなさいという問題をコンパスで交点つくる作図したのの3次元版やね)
位置を特定するための計算をするのは、受信機側のほうなんだ。
ひと昔もっと前の刑事もののドラマなんかで、お金がたくさん入ったスーツケースにつけてる追跡用の発信機とGPSのしくみは同じようなものだと思ってたのね。誰かに自分の位置情報を知られるのか…と、その点を危惧していたのだけれど、そりゃ違う。だって、受信機は「受信」機だもん。発信はしない。でも、携帯電話は、どの基地局の近くにおるか、特定されるから、ある程度、自分がどこにおるかをひとに知られる可能性がある。こちらのほうが恐い。
しくみがわかって、すっきり。
わたしの使っているGPSは衛星3機から受信した情報で測位しとるらしい。
なんで、3機も?と思っていたけれど、自分の位置情報を3次元(x,y,z)で特定するのには、変数が3つだから、衛星3機から情報を得ることが必要なのだと。3元連立方程式だね。
(ほんまは、受信機内の時計の誤差を補正するためにもう1機からの受信が必要らしいが。)
ほんで、電源をいれたあと、測位開始までに時間がかかるのが気になっていたけれど、電源を入れたあと、まず受信機は、24個以上も運用されている衛星の中から、自分の位置を特定するのに有効な衛星を選ぶところからはじめるらしい。受信した衛星歴からどの衛星の情報を利用するかを決め、選んだ衛星の軌道歴から、その衛星の正確な位置を把握する。なるほど、電源を入れてから測位開始までのあいだに、このGPSが何をしとるんかがよくわかった。
ほかには、GPSは、NAVSTAR/GPSが正式名称で、NAVSTARは、Navigation System With Time and Rangingからつくられた用語だけれど、「航法用の星」とも読めるだとか、GPS衛星は軍事目的のために開発されていたので、当初は、測位精度を劣化させる信号が電波に乗せられていて100m近い誤差があったという話だとか、いろいろおもしろい。
知らないことを知るのは愉しいものだね。
2007-05-27
テスト撮影をはじめる。
夕暮れどき、どのくらいのペースで露出がかわるのか、
17時前からスタンバイ。定点観測をはじめる。
いわゆる夕暮れの印象を受け始めるのは17時40分ころ。
18時45分から加速度的に光量が減る。
19時40分でもまだ日没方向の空は明るい。
今日の京都の日の入り時刻が19:02だから、日の入り時刻がイコール空が完全に暗くなる時刻じゃないんだ…ということに気づく。
空の明るさが劇的にうつりかわるのは、17時すぎから20時前の3時間弱くらい。で、思ったよりも長いというのが今日の収穫。
やってみないとわからないことが多い。
5分間隔、時計を気にしながらも太陽が水平線に対して没する侵入角度が浅いほうが、同じ時間間隔で撮影してもこまかく光の変化を追えるのかな…などと想像する。目の前の光景を撮りながらも、気持ちは太陽によりそう。
晴天の逆光で撮るのは無理があるので、薄曇りの日にもテストしてみよう。
逆光であることが気にならないくらい光が拡散されるといいのだけれど。
18時40分ころ、南東から東の空が見せる少し濃いめのグラデーションが好い。
ぼんやりしとった。
ARTZONEで開催されている、森山大道「記録7号」、今日までやったんやん。撮影の帰り際に寄ったカメラやさんで思い出したときは開場時間を過ぎていた。
まだ東京で会社勤めをしていた頃だから、1998年か99年のこと。
東京、渋谷のPARCOではじめて森山大道の写真展を見て、ショックを受けた。
それまでも、いくつか写真の展覧会は見てはいたけれど、こんな「ただならぬ」感を受ける写真を見たことはなかった。それまで写真に抱いていたイメージをばりっとはがされるような感じ。
そのうえ、名前に濁音が多いし、コントラストのきついバイクの写真が印象的で、マッチョでバイク乗り回しているようないかついニイサンだと思い込んでた。
その頃は新人OL(!)だったし、まさか自分が写真を撮るようになるとは思ってもいなかったのだけれど、その4年後には写真を撮りはじめるようになり、森山さんの本を読んだり、DVDを見たりしているうちに、まず「ニイサン」ではないことを知り、つぎにマッチョでバイクを乗り回しているようないかついひとではないことを知った。
先日のトークショウも開演に遅れて着いたら「満席です」と入場を断られ、あらためて写真展だけでも見に来ようと思っていたのに、ぼんやりしとった。
残念でならない。
2007-05-25
ここ数日ずっと寝しなにShinjukuとBuenos Aires
を見ている。
「近所で写真を撮って作品つくるのは作家の怠慢」
という写真家の厳しいことばがずっと頭にあって、どこか遠くに行くことを考えはじめたから、一人の作家のホームタウンで撮る写真と、アウェイで撮る写真とを比べて見てみたい思った。
同じ写真家が撮っているのに、ずいぶん違うものに思える。
被写体の違い、だけなんやろうか。
ShinjukuよりもBuenos Aires
のほうが作家のまなざしが自由になっている印象を受ける。
Buenos Airesは、特に見開き2ページの写真の組み合わせ方がおもしろい。
左ページのタンゴを踊る女性の網タイツが目をひけば、
右ページでは黒く濃く焼き付けられた橋脚の複雑な構造体が存在感を示している。
左右のページの被写体がまったく違っていても、どこか共振するところがあって、それがほどよい緊張感をもたらしているのだと思う。
1枚だけを見るのと、2枚を対で見るのは、2枚のたとえ片方を見ているつもりでも全然違う経験なんだと思う。
と、じいっと見ていると、寝そびれて起きそびれる。
明日は雨だから今夜はよふかしもいいかな。
2007-05-20
遠い異国の旗を思わせる、月と星の配列。
時々刻々、深まる蒼。
気づけたことに、ほんの少し安堵する。
空の色、花の香り、草木のあざやかさ、街のたたずまい、ほほをなぜる風、
こころが共振しないままカメラを持って歩いても、つらいだけだった。
時間を気にしながらの路上スナップは、かえって毒だ。
きちんと世界に感応できるだけの余裕を、わたしは死守しなければならない。
2007-05-17
母から電話がかかってきた。
母:鷲田先生の「京都の平熱」。
わたし:知ってるよ。最近出た本だよね。
母:リサさんへって。
わたし:?
しばらく、理解ができなかった。
母:リサさんへ献本が届いてる。
わたし:父ちゃんじゃなくって?
母:おじょうちゃんに…だそうよ。
今日はいくつかよつばのクローバーが開いて、
白いミニバラもつぼみをほころばせたから、
きっといい日になると思ったけれど、さすがにこんなサプライズは想像だにしなかった。
京都を題材にした著書で、写真も鈴木理策さんの写真だからということで、
父ではなくわたし宛に献本してくださったとすれば、その心遣いに目眩がしそう。
如月に届いた印画紙にはじまり、今年は、身にあまるできごとが多い。
実家に帰るのは明日の晩なのに、そわそわしている。
どうも今夜は眠れそうにない。
2007-05-12
チャリをパクられて困っていたら、
友人のお母さんが、引越し祝いに余っている自転車を下さるとのこと。
ご厚意に甘えて、いただくことにした。
「枚方から大学(京都市左京区)まで3時間で行けた!」と友人が言うので、
たぶんわたしでも大丈夫。枚方まで自転車をいただきにあがる。GPSを携行して。
ひきこもりがちだった気持ちにぐっとくる、
「外に出たくなるよ」という言葉にそそのかされたボーイのオモチャ、GPS。
(オトナのオモチャと言うともだちもいるけど…)
ナビとしてのGPSじゃなくて、移動記録としてのGPSだから、
知らない街に撮影に出かけたときに携帯すると、
帰宅してから、どのあたりで撮ってたのか経路が確認でき、
次の撮影の目処を立てやすくなった。
わたしの手もとでは実用で活躍している。
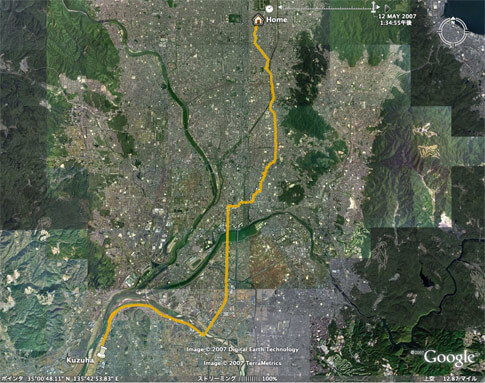
本日の走行距離は約25km。
川沿いや広い道路をまっすぐ走ったから、誤差の少ない綺麗なログがとれている。
実際自分が自転車で走りながら見たVIEWと、
帰宅してからGoogle Earthで見る、上空からのアングルで経路をたどったときのVIEWが
まったく違うのがおもしろい。ついつい、何度も再生。
陽射しもやわらかで、気持ちのいいcyclingでした。
2007-05-09
今週から、早朝の撮影を再開する。
ほんの30分でまったく光の調子がかわることに、あいも変わらず面食らう。
集中力が足らないのが自覚できるからもどかしい。
明日はうんと早くに起きようと思ったら降水確率60%。
連休に8時間ほど歩いただけで、ひどく消耗した。
体力も相当落ちているから、当面の目標は、まともに撮影できるだけの体力と集中力を取り戻すこと。
20時、食品売り場。
異様だった。
どこか身体の具合の悪そうな年配の女性たちが数名、
おのおのが半額になったお惣菜をじっと見つめて吟味している。
仕事帰りのOLやサラリーマンに混じって、
相当、年配の女性が普段着で、
そんな時間にスーパーの食品売り場にいるのが、
それも一人や二人じゃないのが異様だった。
お昼に買い物ができないくらい忙しいわけじゃない。
遅い時間に半額になるまで待って買いものに来ているんだと思う。
ほんとうに保護や補助が必要なはずのところが削られていることは明らかで、
それを目の当たりにして、いまさら、わたしはうろたえた。
しつこいかもしれないけれど、
いちばん立場の弱いひとに皺寄せをして、帳尻をあわあせるのは
最悪のシステムだ。
そんな国にしたのは、そんな政治を許したのは、
ほかでもない、わたしたちだ。
2007-04-28
どこの家でもおおかた、母親はその道数十年の家事のプロだと思う。でも、そんな母のノウハウを無視し、父はインターネットのレシピを見ながら料理をつくる。最初は不愉快に思っていた母も、最近はあきらめがついたらしい。
「彼は歴史家だから、書かれたものしか信用しないの」
ちょうど今読んでいる、網野善彦の『日本の歴史をよみなおす』(筑摩書房 1991)の中に、日本が律令国家を築くうえで文書主義を採用したことが書かれている。書かれたものしか信用しないのは、どうやら父ちゃん一人だけのことではないようだ。
あたりまえのように思っていたけれど、日本が、口頭のやりとりではなく、文書に重きを置いた国家であるということ。またそれによって、おなじ日本国内でも(各地の方言のように)口頭の世界が多様であるにもかかわらず、文書の世界の均質度が高かったというのがおもしろい。鹿児島のバス停で隣になったお年寄りの会話がまったく聞き取れないにもかかわらず、各地で見つかる木簡・書簡はどれもきちんと読めるという挿話に、なるほど。
『日本の歴史をよみなおす』(網野善彦著 ちくまプリマーブックス50 筑摩書房 1991)は、平易な文章で読みやすく、とてもおもしろい本。身近でありながら、知らずにいたことを知ると、生活にすこし深みが出ます。
おかん:面接何時から?
私:15時からだよ。
おかん:You will have a job interview at 3 o’clock. Do you think you will get a job?
私:Yes, of course.
おかん:あら。「あまり期待できないわ」っていうのは、It’s a long shot.って言うのよ。
2007-04-27
わがやは単身の引越しは家族総出でやっつけるのが通例だけれど、
今回は弟のガールフレンドや妹のボーイフレンドまで巻き込んで、
友人もふくめ総勢8名にお手伝いいただきました。
あまり人手が多いと収集がつかなくなりそうで、
お手伝いの申し出をおことわりした方も4名ほど。
お手伝いくださった方も、申し出ていただいた方も、
ほんまにありがとうございました!
件の冷蔵庫も奇跡的に町家の2階に鎮座しています。
築年数不詳の「新」居は、町家のはなれなので通りからは見えません。
携帯は圏外になります。
歩くと壁に寄っていくなと思っていたら、
明らかに家屋が南東に傾いています。
ふすまも引き戸も、一筋縄では開きません。
前の住まいは、玄関にインタホンがなかったけれど、
今度の住まいは、玄関にあるべきアレがありません。
隠れ家、と言えば聞こえは良いけれど、
エエ感じに浮世離れしてて、家から一歩も外に出ずに日々を過ごせます。
そう、魅惑のひきこもり物件!
2007-04-10
Mac OSXでもLinuxでもWinでも動くhuginというパノラマ作成ソフト、どのくらいの精度で「つなぐ」のか気になって試しはじめた頃に、原稿と高熱にまみれてしまった。
無事脱稿したし、今日はゆっくり取り組もう。最初は作業中に何度もおちてやる気も失せていたけれど、少しずつあんばいがわかってきた。
書き出し方は、心射方位/心射円筒/正距円筒と選べる。
心射方位で書き出すと、ひどく歪む。
下の図は、5枚の写真の合成で心射円筒法で書き出し。
(クリックすると大きい画像が表示されます。)

まだ設定方法がわかっていないけれど、露出補正までしてくれるみたい。
賢い。。。
2007-04-09
転居先を採寸する。
いちばんの問題は、
3年前、調子に乗って買ったエレクトロラックスの冷蔵庫。
冷蔵庫の幅は55cm。
玄関の間口が56cm。それも木枠が歪んでいるから怪しいところ。
はなれにたどりつくまでに、狭い土間を通さないといけない。
その冷蔵庫はバカでかく、ワインを寝かせて冷やせるくらいお洒落なのに、
冬は冷蔵が冷凍になり、夏は冷凍が冷蔵になる。
冷蔵庫としては、いまひとつだが、
フィルム保存庫、こめびつ、食器棚、と用途が広い。
買ったときも、ヤマトのニイサンが二人じゃ無理と応援呼んで、
クール便のニイサンも集って4人がかり、絶妙な角度で玄関を通した。
次の住まいに入れられるかどうか、よりもまず、
今の住まいから出せるのかどうか、やな。
ちなみに転居先、50平米超は、さすがに広い。
よく言えば、庭付き一戸建てやし。。。
シェア可です。いちおう。
小ぶりな冷蔵庫持ってる方。
2007-04-07
そのひとは一瞬たりとも目を逸らさなかった。
20分ほどのあいだ、
そのひとはずっとわたしの目から、目を逸らさなかった。
射抜かれるようなまなざしに、負けじとわたしも目を逸らさなかった。
あからさまにひとの目を見るのは「ぶしつけ」という文化がある。
だから、この文化圏にあって、一瞬たりとも目を逸らさない会話なんて、
生まれてはじめてのこと。
それは意外なほど、わたしのからだに緊張と負荷をかけたようで、
一晩たっても胃が痛い。
2007-03-22
2年前「そんなの書けないよ」と思いながら、締め切りに追われて提出した修了論文。齟齬を抱えたまま人前に出してしまった文章。
自分の作品についてのテキストを求められ、久しぶりに修了論文を読み返して、あのときの齟齬が何だったのかを知る。
論文として成立させるために削った部分こそ、制作の肝。
最初から最終形態が見えていたわけではなくて、試行錯誤をしながら、その都度なにかを感じ、取捨選択を行ったはずなのに、論文としてまとめると、あたかも最初からコンセプトが決まってて、最終形態も見えてて、それに向かっていちばん合理的な方法でつくったかのような文章になる。
それってまったくの嘘やん。
いちばんリアルなのは、ドキュメントとして、ひとつひとつの試行で何を知り、その都度何を考え、どう最終形態に結びつけたか。それを時系列で丁寧に書くことなんだと思う。
批評家でも研究者でもない、制作者があえて4000字も書く意味ってそういうところにあるんじゃないかな。
2007-03-21
万博周辺にむかし住んでいたマンションや通っていた小学校があるから、20年ぶり、そのあたりに寄り道してから、みんぱくに向かう。
当時はとても長く感じた駅からの道のりが、驚くほど短く感じられたり、広かったはずの駐車場がちっぽけに感じられたり、子供の頃の印象よりずっとコンパクトな古巣のたたずまいに、すこし混乱する。
ほんとにこんなんだったっけ?
スケール感というものは、自分のからだの大きさから切り離せないもんなんだ。
歩幅がかわるだけで、街のスケールがかわってしまう。
大きさとか距離といった単純なものではなく、街と自分のかかわりそのものがかわるから、それはそれは大変なこと。
撮影のたび、もうあと5cm背が高ければ…と切実に思うけれど、あと20cm背が高かったら、見える世界もスケール感もかわるから、きっと撮る写真も全然ちがうんだろうな。
2007-03-20
やっぱりdialogueって大事やと思った。
ひとつは、写真家とのメールのやりとりのなかで、やっと言語化できたこと。
「既知のものが、既知のものに見えなくなるときが、いちばんおもしろい」
もうひとつは、年下の先輩との会話において。
NPO宛に送られてきた写真展のDM。団地を大判カメラで真正面から撮ったと思われるそのハガキの写真を見ながら、「10年続けててここに辿り着いたんだったら、見に行こうかなぁと思うんだけれど、このひとの経歴を見ているとそうでもないみたい。」と彼は言う。10年、団地を撮り続けたひとにしかたどりつけないものがあるだろうと。
なるほど。時間の蓄積や、経験を積み重ねたひとにしか見えてこないものってあるから、それを見たいという気持ちはわたしにもよくわかった。継続が力となること、を客観的に理解する。
最終的には孤独な判断の積み重ねになるのだけれど、ひととことばを交わすことも大事。自分ひとりのあたまで考えることなんて、たかが知れてる。
2007-03-16
窓の隙間、電線のすずめと目があう。
出がけの空はひっかききずだらけ。
光の質量。
頂上だけの虹。
ミドリの色が前と違う、とか。
午前7時の東京に、はつゆき。
「見ておきたい。」
いままで何度も引越しをしてきたけれど、そんなことを言われるのは、はじめてのこと。転居するまえに、見ておきたいというひとが何人も。「あれは見ておいたほうがいいですよ。」という会話がわたしの知らないところで交わされているらしい。昼のホリカワを知らないひとのために、一枚だけ載せておこう。

ざっくり数えただけでも、生まれてから12軒目。わたし自身もいちばん愛着のある住まいだった。この部屋に、身もこころもくるんとくるまれていた。
この住まいの良さはすべて「ねえちゃんとこは、ばあちゃんちや。」という弟の一言に集約されていると思う。部屋のしきりの磨りガラス戸とか、鉄線の入った重い窓ガラスとか。お風呂場のタイルとか。小さすぎる洗面とか。屋上にあがれることとか。撮影にでかけるときに、上の階のおっちゃんが手を振ってくれることとか。なぜか引越し祝いと言ってごちそうしてくれる管理人さん、とか。
住むひとも住まいもあったかやった。
そして何よりも、部屋に射し込む光。
さいごに迎えたお客さんが「ちゃんと外のことがわかる部屋だね」と言い残す。光のこまやかな表情が部屋の中にいても伝わる、ソトとゆるくつながっている部屋。
もうあと少しでなくなります。
2007-03-14
子供絵画教室のチラシに使えそうな子供の描いた絵持ってない?と尋ねられ、わたしには子供がいないから、自分の思い出ボックスをひっくり返す。
あるある。ずいぶん、たくさん残っている。
子供のころって、こんなにたくさん絵を描くもんなんだと驚くくらい、ざくざくと。
うまいとかへたとかの評価にさらされず、ただひたすら無心に手を動かしていた頃のもの。見ているだけで楽しくなる。

切り絵だとか、ひっかき絵だとか、貼り絵だとか。いろんなもんが出てくる出てくる。
そして、そのどれもが「楽しかった」という記憶にきちんとゆわえられている。
結局その延長におるんやて。
2007-03-10
あるひとから、モノクロで写真を撮って欲しいという依頼があった。
「遺影」という言葉がチラリとよぎる。
話を聞いてみると、やはり遺影を撮ってほしいとのこと。
朝日新聞に遺影のシリーズがあって、そのプロジェクトに応募したが、応募が殺到して、無理だったと。それでもきちんと遺影を残しておきたいという気持ちはかわらないのでぜひ撮ってほしい、という。
かっこつけたりきばったりしない、ごく普通の表情が写っていればいいな…と思って、36枚ラフに撮りきる。きっと数枚は顔をくしゃくしゃにした笑顔で、ほとんどはカメラを向けられることに慣れていないひと特有のこわばった表情。でも、それが彼女のリアルだ。
遺影で思い出す。
18歳で亡くなった友人の実家。居間にある写真立てに、その友人が仲間と一緒に写っている写真が入れられていた。ある年、線香を上げにうかがうと、その写真の、仲間が写っている部分だけが、亡くなった友人の幼い頃の写真に差しかえられていた。
その不自然なコラージュを不思議そうに見ているわたしに、亡くなった友人の母が言う。
「ほかのみんなは生きているのに、失礼やと思って。」
しばらく言葉を失った。
こんなにせつない遺影を、わたしはほかに知らない。
2007-03-07

FireFox2.0が楽しい!と教えてもらい、週末、実家のマシンで遊んでみた。(おかん、ごめん。)
いろいろ、有用なアドオンが用意されているんだけれど、その中に「中止ボタンがしいたけに見えて困る」というアドオンがあって、つい入れてしまったんだな。しいたけ好きとしてはね、がまんできなかった。
なんとも言えん愛らしさやろ。
2007-03-06
夕方、家にたどりつく間際、空から雪が舞い降りる。
もう啓蟄だというのに。
肩に残るはかない雪の気配が
冬になりきれなかった冬の、最後に見せた意気地のようで、
わたしは少しせつなかった。
2007-03-05
きっと人酔いしただけだと思うのだけれど、とてもとても疲れて。
なぜか自分の手をあわせて「ああ、手のひらってやっぱりすごい…。」となかば夢うつつの状態で考えていたら、知らないあいだに眠っていた。
先日、NHKのプロフェッショナルという番組で専門看護士の北野愛子さんが、患者さんの手を握ることに対して、「手と手を触れ合わせることで、言葉でも表情でもないものが通じると思っている」というようなことを言っていた。
真偽のほどはわからないが、手をつないだほうが夫婦仲も良い、という話も聞く。
思い出したのは、いちばん不安だったとき、わたしはボーイフレンドの背中にやたら手のひらをくっつけていたこと。手のひらを相手のからだにくっつけるとびっくりするほど安心できること、そのころのわたしのちょっとした発見だった。
新年会の帰りみち、ひとりひとりの手を両手で握って別れの挨拶をする作家さんがいた。そのひとの両の手で自分の手が包まれたとき、じかに感情をさわられるような感覚にうろたえた。
根拠はないけれど、手のひらってやっぱりすごいんだと思う。
今度祖母に会うときは、そっとやさしく手を握ろう。
展覧会のあいまにお昼ご飯を…と、母と友人と一緒にJICAの食堂探検をする。
JICAだけあって、メニューの表示に英語も書いてある。
お食事を頼めば食後のコーヒーがついてくるとのことで、
セルフサービスのサーバでコーヒーを入れてほっと一息。
母はセルフサービスなのを良いことにおかわりに臨む。
「おかわり自由はbottomlessって言うのよ。」と得意気。
ニコニコしながら二杯目のコーヒーを飲んでいるけど、
bottomlessって、そんなんどこにも書いてへんよ。
2007-02-27
新しいカメラのフォーカシングスクリーンが肌にあわない。マイクロプリズムがうるさい。
マイクロプリズムの像を見ながらピントをあわせる操作をしているうちに、撮りたかったものの何がたいせつだったのかわからなくなる。
強制的にピントに意識を集中させられることで、撮る動機になったもの、場の持つニュアンスとかそういうものに対する意識がこぼれ落ちる。
思い返せば、写真を撮りはじめた最初の頃から、作品としての写真に対しては、画面の一部の「見せたいもの」にピントをあわせることに違和感があって、画面全体がくまなく大事だったりするものだとか、周縁にこそ意味があるものだとか、像そのものよりも画面から匂い立つ空気感とか距離感とか、に気持ちが向かっていた。わかりやすい視線の中心をつくることにも、全体で見ておさまり良い構図の一枚の絵をつくってしまうことにも「NO」という気持ちを抱き続けてきた。
しばらくこの拒絶反応と向き合ってみて、だめだったら、スクリーンをかえてみる。これだけ自分が拒絶していることがわかっただけでも良い経験だったと思おう。
2007-02-25
昨年12月発行とあるので、遅ればせながら。たぶん、「建築写真」というタイトルだけやったら縁遠く感じたけれど、巻頭がティルマンスの写真だったからつい手が伸びてしまった。頻繁に写真が特集で組まれたり、写真を扱う雑誌が増えているようだけれど、いまひとつ芯のあるものに出会えることはなく、この「建築写真
」は最近の雑誌のなかでいちばんおもしろかったと思う。
いわゆる「建築写真」と聞いて想像する写真とは違う写真の可能性が提示されている。建築にあまり興味がなくても、写真特集として充分読める内容を擁している。掲載されている写真もさることながら、伊藤俊治氏の20世紀建築写真史はさらっと読めるわりに情報量が多いし、清水穣氏のティルマンスについてのテキストも刺激的。
黒と白のコントラストのきついレイアウトが文字を追いづらくさせているのと、ノンブルが見つけにくいのが難点だけれど。
「建築」と「写真」のかかわり方の可能性。という切り口。
漫然とカタログ化してしまう写真特集や、甘い雰囲気ものの雑誌が増えるなかで、方向性がきっちりしている特集は気持ちがいい。
ひこうき雲が徐々にただれ、流されながらとけていく。
そういうゆったりとした時間は、もう明日には失われるんじゃないかという不安に突然襲われることがある。時間とのかかわり方の最終的な決定権は自分の手中にあるはずなのに。
しかし母は言う。
「わたしたち、年寄りが急くのはね、死ぬまでの残された時間を意識するからなのよ。あなたたち若い人は、まだいくらでも時間があると思ってる。」
親の世代がせわしないのは、ひとえに高度成長期を生き抜いてきた人々に特有の「ハヤさ」なんだと思っていたし、だからこそ、他人ごとで済ませていた。何かにつけ、両親からせかされ、うんざりしてきたというのもあると思う。
そう言われるまで、「残された時間」なんてことに思い及びもしなかった。
自分とは違う人生の季節を生きる親の目にうつるのは、自分とは違う景色なんだと思い知る。
もう少し寄り添って耳を傾けてみようかな。
新装開店のコーヒーショップでシンプルなエコバッグをもらったのをきっかけに、買い物の際は、そのバッグを持参し、なるだけポリ袋をもらわないようにしている。
さすがにこの寒くない冬に危機感を感じて、いままで「一人暮らしだし、少量だからいっか」と、あまり気にしていなかった牛乳パックもリサイクルにまわすようにしはじめた。
そうやって、少しずつでも具体的に社会にかかわりゆこうとすることで、自分の属する社会や、果ては地球にまで思い入れができてくる。
星の王子さまが、
あの一輪の花が、ぼくには、あんたたちみんなよりも、たいせつなんだ。だって、ぼくが水をかけた花なんだからね。覆いガラスもかけてやったんだからね…と言うくだりがある。
たいせつなものは、すでにたいせつなものとしてわたしの前に出現するのではなくて、たとえ最初はなんでもなかったものでも、たいせつに「する」というわたしからの積極的なかかわりによって、たいせつなものに「なっていく」のだということ。少し実感した。
2007-02-24
「ああ、迷ってるんやなぁと思った。」
とあるグループ展を見て来た y が、出展されていた友人の作品について言っていた。
迷いの時期、というのがあると思う。
この制作日誌を読み返していたら、この1年、(前の1年とあわせて2年)まさしく迷いに迷ってて、これを y が読んだら「迷いすぎちゃう?」と言うんだろうな…と思う。
でもバラバラに思えていた問題意識や関心が、あるときふっとひとつのかたちになりかけることがあって、それは迷い続けないとそこにはたどりつけない、とも思っている。
迷いながら考え続けること、待つこと、も大事よ。たぶん。
2007-02-22
先週の講演会で、美術作家と写真家の写真に対する態度の違いは”make”か”take”なんじゃないか、という話があった。
わたしは”take”のほうだと思う。
写真であるかぎり、出会わないと撮れない、ということ。
徒歩圏内の撮影にそろそろ限界を感じ、少し遠出をしてみる。
遠くに出かけたら、出かけたなりの出会いがあって、写真て、結局そういうことなんだと思う。
出会わないと撮れない。
部屋の中で「つくる」のとは違う。
きっとそれは究極的なこと。
すすんで出かけていこう、出会いにいこう。
ここのところ、その気持ち、強く強く。
ストリートの距離感に息苦しさを感じているのかもしれない。
最近、近距離のものしか撮っていないという反省があって、ぱっと視界のひらけるところに出かけたい。
てっとり早いのが川べりで、桂川を南下。
風景のなか、点景としての「ひと」の大きさ距離感に興味があって、距離を変えて試してみる。
視界が広くなると、ふだんとまったく違う写真を撮ってしまう。どんな場面でも同じまなざしで写真を撮ることができない。
2007-02-16
ぎゅっとそでをつかむようなこと。
わたしはそのひとのそでをつかんだ。
このまま縁が切れるのはあまりにも寂しすぎる、と。
自分がそんな衝動を持ち合わせていたことに驚くほどまっすぐ。
ここにきてやっと、今までの出会いのなかで、
わたしのそでをつかんでくれたひとびとの気持ちが少しわかった。
そして、最後の仕事でお世話になったひとに、
お世話になったのはこちらのほうなのに、ぜひ一緒に働きませんかと誘いを受けた。
そでをつかんでもらったこと、ありがたい。と思う。
その気持ちには応えられないから、そっと抱きしめるだけ。
ぎゅっとそでをつかむその衝動で、ひととひとはつながっていくのかもしれない。
2007-02-13
たとえば、メールが届いていることを期待して帰宅するなりパソコンを立ち上げてしまう、とか。そのひとのことを考えて一日中ウワノソラ、とか。しばらく連絡が途絶えるとやきもきする、とか。
まさか、そんなことになるなんて。
それは吹き抜ける春風のようにはかないものだったけれど、
落胆どころかうれしかった。
自分のこころが、ちゃんと、ふるえてくれたこと。
わたし、まだ、恋ができるんだ。
2007-02-12
かっこいい、と思った。
「100年の仕事だと思っているから。」ということば。
先日、松江泰治さんを迎えての講演会。自分の仕事は100年の仕事だと思っている。だから、そんなに急がなくてもいいと思っていた。デジタルに移行するタイミングについて答えるときに、そう言っていたと記憶する。「100年の仕事」というフレーズがひときわ印象的だった。
それは自分の視野が狭いなぁと反省させられるひとことでもあった。
100年というスパンで考えたときに、自分の仕事がどうあるべきか?という視点なんてまったく持ち合わせていなかった。目先どころか、自分の足下ばかり見ていた気がする。
技術的なことや写真の内容より、そのひとの写真に取り組む姿勢に多くを学んだ。
もうすぐ、チョコレイトの日が来る。
この数年、あげることよりも、もらうことのほうが多い。
今年はもうすでにもらってしまった。
それも、オトコノコから。
うれしいのと、うらやましいのと、はんぶん、はんぶん。
彼は知ってるのかもしれない。
チョコは、もらうよりも、あげるほうが100倍楽しいということを。
2007-02-03
いいことつづき。
どうしてもわたしに見せたい写真集があるから、と、
たいせつなともだちが会いに来てくれたこと。
好きな写真家が、送る荷物に印画紙をそっとしのばせてくれたこと。
同じそのひとが、わたしの作品を楽しいと言うてくれはったこと。
いいことは、どれもこれも写真つながり。
ほんまに幸せなことやと思う。
2007はのっけから、いいことつづき。
ありがとう。
制作展の搬入で忙しいことは予想できていた。
節分なのにバタバタ過ごすことになるんだろうなぁ…なんて思っていたら、
学生が「お昼ごはんにどうぞ」と。
差しだされたのは重箱。中には手作りの太巻とお稲荷さん。
感謝をとびこえて感激。
心底すごいなぁと思う。
展示の搬入日。ふつうは自分の作品のことで頭がいっぱいのはず。
他人さんに手作りのもん持参するなんて考えの及ばぬところ。
そして、きっとこれからも、わたしには絶対できないことだ。
節分にいただいたのは、美味しさと感激。尊敬と感謝。清々しさ。
ごちそうさま。
高校生の頃、わたしは不登校寸前だった。
毎朝、ふとんの中で葛藤しながら、
気配で、母が弁当をつくってくれていることを察知していた。
母が弁当をつくってくれている。
だから行かなくっちゃ。
しんどくても、つらくても、理不尽なことだらけでも。
最後の最後で背中を押してくれたのは、母のつくる弁当だった。
お弁当をつくってもらっているという毎朝の事実が、
かろうじてわたしを高校生活につなぎとめていた。
それがなかったら、わたしは高校を辞めていた。と、いまでも思う。
ずいぶん甘ったれた話やけれど。
だから、ひとの料理をいただくこと。ひとに料理を食べてもらうこと。
軽く考えたらいけないと思っている。
「食」を単なる栄養や効能に、手間や金銭、の話だけに還元したらいけない。
その営みがどれだけひとの「生きる」を支えているか。
打ち切りになった番組への批判が横行しているけれど、
栄養や効能でしか食をとらえられない「食」に対する自分たちの態度の貧しさに、そろそろ気づいたほうがいいんじゃないの。
2007-01-31
最初で最後なんだろうなと思って、学生と一緒に学食でごはんを食べた。
連絡先を教えてくださいと切羽詰まった様子で言われて、
きょとんとしていたら、「もう会えなくなるかと思った。」と彼女は言う。
わたしの勤務がもう残りわずかだということを知っていたらしい。
彼女、残りの会える回数を数えていた。それを知って胸がつまった。
「何しに来たん?」というリョウヘイに
「プロジェクタの調整。」と答えたら、
「それだけじゃなくて、俺に、会いに来たんだろ。」とニヤリ。
あいかわらずかわいいなぁ。
ちょうどわたしが二十歳すぎのころ、塾で小学生のクラスを担当していた。
その子たちの世代に10年ぶりに再会したようなもの。
またどこかで再会できると良いなぁ、と思う。
久しぶりに、寂しい、ということばの使いみちを見つけてしまった。
2007-01-29
あるいは、マーシャル・マクルーハンはこれを「感覚比率」という概念でとらえた。五感はつねにある比例関係のなかに置かれることで安定した現実感覚をかたちづくるが、いずれかの感官に新しいメディアが接続されることによってある単一の感覚だけがとりたてて活性化させられるとこの比例関係に歪みが生じ、それを回復するために別の感覚がみずからを暗示にかけるように刺激する。電話で長話をしていると指が知らないうちに脇の鉛筆を掴んで、眼の前の紙に三角や丸といった単純な図柄を書きはじめる。かなり強い筆圧でである。しだいにその形は増殖してゆき、気がつけばまるでシュールな絵のようなおぞましい図柄がそこにある。聴覚の不均衡な刺激が、視覚や触覚をおびき出したのである。そうして感覚の系はおのずから「感覚比率」の再編制を試みていたのだ。
(『感覚の幽(くら)い風景 (中公文庫)
』 鷲田清一著 紀伊国屋書店 2006 より抜粋)
おもしろいなぁと思った。
わたしの場合、時間とともにだんだん強く受話器を耳に押しつけて、受話器を置いたあと、耳と腕が痛い。なんでこんなに力むのだろう…と。だから電話で長時間話をするのは苦手。
よくよく考えたら、対面でひとと話すときは、相手の表情のうつろいにきわどく神経をはりつめている。不愉快なことを言っていないか。本当におもしろいと思っているか。不用意なことばで傷つけてはいないか。そして、自分の表情が「間違っていない」か。顔のこわばり、手の表情。身体の揺れ。
ひととの対話は本来、すごく多様な感覚のチャンネルを駆使するもののはずなのに、電話というメディアによって、それが音声だけに集約されたとたん、それ以外の使われないチャンネルが誤動作するのだろうか。電話は電話で妙な緊張が漂う。
電話よりメールが気楽になってしまった原因は、そこらへんなのかもしれない。
2024-01-23
このサイトでいちばんアクセスが多いのが「感覚比率」という2007年の投稿で、そこでは電話をしながらつい落書きをしてしまうという経験に触れたが、ちょうどいま読み終えた
『ハンズ 手の精神史』にも、会話と手の動きについての記述があったので抜粋しておこうと思う。
この本では、わたしたちがいかにせわしなく〝手を動かさずにはいられない〟存在であるかが描かれており、電話であろうとなかろうと会話と手の動きはそもそも切っても切れない関係にあるようだ。
第一世代の研究者たちは、手の使用がおおよそ二つのグループに分かれるという意見で一致していた。一方の「対象に焦点を当てる」手の運動は———特に、言葉を強調したり、区切りを入れたり、修飾したり、例示したりする際に———話し言葉と密接に関連していた。他方、引っ掻いたり、こすったりするような「身体に焦点を当てる」運動には、話し言葉との関連はみられなかった。対象に焦点を当てるジェスチャーは、発話のリズムにあわせて調整されており、その二つの同期のゆらぎが言語符号化における問題を直接的に示していると考えられた。発話と運動がうまく噛み合わない場合には、話者が何かを表現することに苦労している可能性がある、というわけだ。しかし、身体に焦点を当てる運動は、それとは異なったものであることがわかった。 それらの運動は、発話のリズムにはそれほど同期してはいなかったのである。そして、そうした運動は、分離や死別などの喪失の後にしばしば起こっていた。それはまるで、身体が痛みや悲嘆に反応して自分自身を刺激しているかのようであった。
あらゆる研究者によって確認されていたように、先の二つのグループの違いは、実際にはより複雑なものであった。古典修辞学者もそう考えていたように、「対象に焦点を当てる運動」が話すことと結びついていたことは確かである。だが、「身体に焦点を当てる運動」が言語から完全に切り離されているわけではない。後者の運動は、話すこと自体にはほとんど関係がなかったが、そういった運動はまさに「聴く」という経験に関係していたのである。私たちは、聴衆を説得しようとしたり、あるいは単に聴衆とコミュニケーションをとろうとしたりするときに、意図的であるかどうかにかかわらず、ジェスチャーを用いることがある。しかし聞き手の側にも、身体の関与が存在する。実際、他人から話しかけられているときに、手を動かさないままでいられる人がいるだろうか?
『ハンズ 手の精神史』(ダリアン・リーダー著 松本卓也・牧瀬英幹訳 左右社2020 pp.187−189より抜粋)
続く文章では、この問いに対して職業的に「聴く」ことが求められる精神分析家の例が挙げられている。
実際、現在までの精神分析の文献についての調査記録を読むと、話を聴いている精神分析家がもっとも頻繁に行っていることは、メモをとることではなく、編み物をすることだったようだ。
(同書 p190より抜粋)
そして、フロイトの娘のアンナが分析中に編み物をしていたこと。フロイト自身は、喫煙するために手をせわしなく動かしたり、宝石の指輪を舐めたり、古美術品の置物やお守りをひっかき回したり、なでたりしていたことが描かれ、
そのほかに分析家たちのあいだで頻繁に行われていたのは落書きで、それが話を聴くという経験と密接に関連しているのは間違いない。
(同書 p191より抜粋)
と括られている。
自分の経験に照らすと、対面だと話しづらいことも、作業だったりドライブしながらのほうが話しやすいことがある。養護教諭の友人は、わたしがなかなか話を切り出せないでいるとき、それを察して車のなかで運転しながら話を促してくれた。話しやすい場をつくってくれるってすごいな…と思った記憶がある。聞き手が手を動かしていることは聞き手自身の感覚のバランスをとっているだけでなく、話し手側の話しやすさにも影響を及ぼすのかもしれない。
さて、この本を読んだ直後、遺体科学の研究者である遠藤秀紀さんが、人間は木から下りて二足歩行になったことで、前足(手)が自由になり、重力によって喉のパーツが下にひっぱられて口に空間ができたことで音声言語を獲得したのではないか?とラジオで話されているのを聴いた。
もしその仮説が正しいとすれば、二足歩行によってもたらされたふたつのもの、自由な手(前足)と音声言語が切っても切れない関係にあるというのは興味深い。
つまるところ、わたしもまた自由になった前足を動かさずにはいられずに、この文章を綴っているのだ。
二足歩行についての話は52:17〜58:46まで。
2007-01-28
2月中旬。京都嵯峨芸術大学にて、現在活躍中のアーティストをまねいて車座シンポジウムが開催されます。
2月10日(土) 松江泰治さん
2月14日(水) 木村友紀さん
どちらも15時~17時30分。
前半1時間がアーティストの講演。後半が質疑応答による対話形式で進められます。
美術批評家の清水穣さんがナビゲーターをつとめます。
活発な対話が生まれることをめざしていますので、学外からの参加も大歓迎です。
2007-01-27
触れるというのはまさぐることだと、以前に書いた。触れるとは、身体の表面が物に接触するという偶発的な出来事を意味するのではなく、対象への能動的な関心をもって、触れるか触れないかのぎりぎりのところで物をまるで触診するかのように、愛撫するかのように探る行為だといった。が、これはなにも触覚にかぎられることではなかったのだ。触診、聴診のみならず、見ることもまたすぐれて世界をまさぐるという行為なのだろう。
(『感覚の幽い風景
』 鷲田清一著 紀伊国屋書店 2006 より抜粋)
「まさぐる」ということばがぴったりだと思った。
松江泰治氏の写真集『JP-22』。都市の見せる微細な表面を、わたしのまなざしはまさに「まさぐる」。潜るということばもどこかで聞いた気がする。細部にわけいるまなざし。そこから少し遠のいて全体を見るまなざし。細部に集中しているときは全体は見えていない。全体をまなざすときは、細部までは見られない。その視覚の不可能性や、往復運動はたしかに「潜る」行為に似ていると思った。
でも「まさぐる」もいい。
触覚的なニュアンスや、見る人の能動性をうまく表現している。
彼の写真はまさに、見るひとのまなざしが「まさぐる」ことを誘う。
わたしはそこがおもしろいと思う。
年末年始、暇つぶしにめくった青木雄二の著書に、なんぼうまくいかなくても倒産しても、いちばん弱いもの、従業員に皺寄せがいくかたちで倒産したらあかん、と書いてあった。
最近つくづく思う。
不具合を末端のひとに皺寄せすることで帳尻をあわせるシステムがどれほど多いことか。小泉改革なんてその最たるものじゃないかと思う。
そして、久しぶりに読んだ鷲田清一の著書のなかで、山本理顕の『細胞都市』からひいている一節が目に留まる。
「今の社会のシステムというのは、家族という最小単位が自明であるという前提ででき上がっている。そして、この最小単位にあらゆる負荷がかかるように、つまり社会の側のシステムを補強するように、さらに言えばもしシステムに不備があったとしたら、この不備をこの最小単位のところで調整するようにできているのである。だから、家族が社会の最小単位としての役割を果たせなくなっているのだとしたら、それは、社会の側のシステムの不備を調整することがもはやできないということなのである。」
システムの末端で起こっていることを、末端の責任として取りざたすることが多い。システムの不備は、いともかんたんに末端を担うひとの不備としてすりかえられる。
目先のことより少し大きな枠組みに目を向けること。
自明なことを疑うこと。
そして自分がどんな立場であれ、どんなにささやかなことであれ、どんな大義名分があるにしても、いちばん弱い者に皺寄せのいく仕組みにしないこと。
発言すること。
幼少のころ、ひとつふたつ年下のともだちを連れて、放課後の幼稚園に歩いていった。スクールバスで通っていたくらいだから、けっこうな道のりだったと思う。
一緒に行ったのに、わたしはその子をほったらかして帰ってきてしまった。
悪気はなかったのだけれど、自分が帰ろうとしたそのときに、年下のその子は帰ろうとしなかったんだと思う。ほんじゃお先に、くらいの軽い気持ちだった。
あとから知ったことだけれど、
うちの母はずいぶん、そのことでその子の親から嫌味を言われたらしい。
おさなごころに「責任」ということの意味を学んだんだと思う。
そのことばに出会う前に。
ふたつめ。
高校生の頃、ともだちと家出をしたことがあった。
夜の街を行くあてもなく歩いて、翌朝帰ったとき、ともだちの母から叱られた。
「本当のともだちなら、一緒に行くのではなくて、止めなさい。」
涙があふれた。
自分が巻き込んだことには責任を持つこと。
ともだちだからこそ、止めるべきときには止めるということ。
わたしがこころに誓ってきたこと、ふたつ。
特にいま、わたしの胸にずっしり重い。
2007-01-25
光線や視線、網膜といった概念を編んでいる〈線〉と〈膜〉という比喩、それがわたしたちの感覚に、なにがしかのバイヤスをかけてきたのだろう。二つの異なるもののあいだを走る線(矢印のように物に向かう視線、もしく彼方からこちらにやってくる光線)としての視覚、そして網膜というスクリーンに映る「像」としての視覚風景。ここでは視覚が、まるで知覚する主体と知覚される対象とのあいだの、眼球という媒体ないしは衝立を介して起こる出来事であるかのようにとらえられている。見るものが見られるものから隔離されているのだ。接触も摩擦も圧迫も浸透もない、距離を置いた関係として、である。「見え」とはしかし、そうした遠隔作用のなかで生まれるものだろうか。
考えてみれば、わたしたちがじっと頭部を固定して物を見るのは、顕微鏡をのぞくときくらいしかない。ほとんどのばあい、頚を回し、身体を動かしながら、わたしたちは物の「見え」にふれている。視覚とはつねに運動のなかに組み込まれているのであって、物を正確に見るというのも、カメラに三脚を装着して微動だにしないよう固定するということではなさそうだ。触れるということが、物との接触や衝突ではなく、まさぐりにゆくという身体の運動のなかで起こったように、見るということもまた、網膜への刺激の投影ではなく、何かに向かうという、環境への動的なかかわりゆきのなかで生まれると考えたほうがいいのではないか。
(『感覚の幽い風景
』 鷲田 清一著 紀伊国屋書店 2006 より抜粋)
「見る」とはどういうことか。視覚のモデルに対する懐疑。自分があまりに無批判でいたことに少しドキッとする。
ひとは見ようとして見るし、聞こうとして聞く。
たしかにそれは、動的で能動的。
やってみよう。
今、見えるもの。自分の部屋。少し離れたところにある展覧会のパンフレット。色鮮やかなので目をその方向に落ち着けて「見る」。もうその瞬間には、タイトルの文字をなぞっていて、さらにより細かい字を読もうと目を細める。また、少し視野を広げて、全体を見る。それから引用されている絵に目を移し、その裏に隠れている紙は何だろうと角度を変える…いざ「見る」となると、ひとところに留まることなく関心は移ろい続ける。なにか考えごとをしてぼうっとしていない限り、たしかに「見る」は動的だ。
展示現場での鑑賞者の「見る」をどう設計するかということに、以前から興味がある。考えるべきなのは、この方向かもしれない。
2007-01-24
「そのコップかわいいね。」と言うわたしにFはこたえる。
「これ、100均のコップやねん。」
つい、100均のわりにかわいいコップやろ、という話かと思ったら、
「小学生の弟がな、誕生日に買ってくれてん。小学生にとってはな、100円は大金やねん。」
その小さなガラスコップは歯みがきセットの受けになってて、いつも彼女はたいせつにそのコップを持って食後の歯みがきに行く。
「バレンタインデーに、女子からパーティーをしてもらったのはいいんですけどね、そのお返しにゴディバのチョコレイト、2個入りのんが800円もするの、6つ買ったら、お財布なくなりました。」
Mが言う。お財布の中身がなくなりました、ではなくて、お財布なくなりました、というあたりに実感がこもっている。
「あの日、ダムタイプのS/N見てレクチャー聴いて、ひとがひとを好きになることとかけっこういろいろ真剣に考えさせられたんですよ。でも、その帰り、電車乗るときに、藤原紀香と陣内の結婚の話をともだちから聞かされて、そのふたつの出来事のあいだで、僕どうしたらええんかわからんかった。あの日はそういう日だったんです。」
とはS。
いずれも学生の話で、ふとした機会に見せてくれるこまやかさや温かさ。
かわいいなぁの一言に縮約するには、あまりに彩りがあって。
そういうものに、わたしは少なからず救われていたんだと思う。
2007-01-22
ファインダー越し、恋をした。
40分のライブ。
たいせつなともだちと、
ともだちのたいせつなひととひと、に、わたしは束の間の恋をした。
2007-01-16
最近「感じる」がずいぶんおろそかになっている、と思って、ひさしぶりに鷲田清一さんの著書をひらく。『〈想像〉のレッスン』は、具体的に芸術作品をひいて書かれたもので、いくつか写真作品についても書かれている。
「みえてはいるが誰れもみていないものをみえるようにするのが、詩だ」。という、詩人のことばからはじまるこの著書のなかで、
アートもまた、わたしたちが住み込んでいるこの世界の、微細な変化や曖昧な感触を、曖昧なままに正確に色や音のかたちに定着させる技法だといえる。
(p18から抜粋)
とある。
最近、忘れがちだったかもしれない。
抽象的なコンセプトをああだこうだねりまわすより、自分の生活の中で感じたこと。どうしても無視できない齟齬。そういったものからスタートする、ということ。
「写真とはなにか」という問いは、もしかしたら写真をとりまくひとの間だけの問いでしかないかもしれない。「見る」とはどういうことか、という問いならもっと広く共有できる問いとなるのではないだろうか。
もう少し視野を広げてみよう。
そして、もう一度、問いのたてかたを考え直してみようと思う。
2007-01-14
「ひとをたいせつにする」ということを、
ひとからたいせつにされることによって学んだのは20代の最後の5年。
それを教えてくれたのは、かつてのひと、exだ。
今でも、そしてきっといつまでも、
たいせつにしてもらったことは清々しい感謝の気持ちとともに、思い出すのだろう。
それに比べてわたしは何もできなかったなぁ、と、
返しそびれていた「最後の荷物」を包みながら、つくづく思う。
2007-01-13
年末から年始にかけて立て続けに3人、ともだちが子供を産んだ。
ささやかだけれど、お祝いにと少し前からスタイをつくりはじめている。
いちばん最初に生まれた彩雪という名前の赤ちゃんに、雪の刺繍をしようと思って、刺繍糸を買いにでかける。
祝福、ということ。
わたしが生まれたときもきっと同じように祝福されたんだと思う。最近、実家で見つかったクレヨンは、美術家の親戚がわたしの幼い頃にくれたもの。当時、日本の子供向けのクレヨンは色数がすごく少なかった。でも、親戚にもらったそのクレヨンはびっくりするくらいたくさんの色が入った外国製のものだった。ほかにも、良質の絵本やらぬいぐるみやら、わたしは多くのひとから、祝福されて生まれ育った。
彩雪ちゃんの誕生がうれしいのは、たいせつなともだちの娘だから。
同じように、わたしが祝福されたのは、わたしの両親が周囲のひとからたいせつに思われていたからだ。たいせつに思われるためには、まずひとをたいせつにしないといけない。
わたしが祝福を多くうけて生まれ育ってこれたのは、わたしのひととなりうんぬんではなく、ひとえに、わたしの両親が周囲のひとをたいせつにしてきたからだ。それは、本当にありがたいこと。そんなシンプルなことにすら、三十余年気づかなかった。
祝福の連鎖を次の世代につなごうと思う。
おめでとう。
2007-01-12
元旦、午前0時の星空は明晰だった。
思いがけない瞬間に、ものごとの本質にさらっと触れるようなこと、めっきり少なくなった。日常の些事に埋没して、感覚が鈍ってきているのかもしれない、という危機感。
鋭利でありたい。
2007-01-09
CONTAX RTS2+Tessar45mm/F2.8。
路上のスナップ向けに最適なものをとセンパイに選んでもらった。
相当コンパクトだと思う。
フィルムの巻き取りミス。わたしの3日間の撮影は台なし。
慣れるまではそんなものかもしれない。
まだよくわからないでっぱりもある。
「きみのそのチョビはなんだ?」
「これはミラーアップですよ、リサさん。」
と、いまはまだお互いの自己紹介。
どうかイイ関係になれますように。

「撮ってください」と頼まれることと、撮りためたものの中から「ピックアップして、ください」と頼まれることと両方あるのだけれど、今回は後者のほうで、年明けからフィルム総ざらえ大会になっていた。
ねこじゃらしは、英語でfoxtailというのだそう。キツネのしっぽ。
オーダーにかなう写真じゃないけれど、一枚そっとしのばせた。
テレビを見るときと読書するとき以外は音楽を流していることが多い。ものの見えかたとか受け取めかたって、そのときかかっている音楽に影響を受けてしまう。次のお題はその逆で、曲を聴いて感じたイメージを写真にのっける。
まずは音を聴いてみる。
2007-01-04
最後の最後で負うた瑕。抱えたまままたいだ、年の瀬。
年明けのあたたかな陽射しで少し気持ちが上向いてきたのかな。
あけまして、おめでとう。
「そめちゃんには運がめっちゃあります。あるのです。全部望んでね!ゆずれないこと全部やでー。」
ともだちからの年賀状の唐突なエールに涙が出てしまった。
性懲りもなく、また張りつめたんかなぁ。
今年は逃げんとこうと思う。
目先のことからも、先のことからも。
「ゆずれない」自分の気持ちからも、かな。
2006-12-26
「ありがとう、助かりました。」
「お役に立てなくてごめんなさい。」
今年一年を振り返って、一番多く口にしたことば。
そのふたつのことばの間にゆるくはさまっていたんだと思う。
居心地、決して悪くはなかった。
でも、来年はもう一歩踏み出したいと思ったんだ。
2007年は「さようなら」から始まる。
2006-12-25
JBの逝去。
ヤフーのトピックスで知った。
ティーンエイジャーを卒業する頃のmyヘビーローテーションだった。
新宿タワレコのサイン会で、
脇に抱えた大きなクロッキー帳にサインをもらったとき、勇気をふり絞って
“Please, let me kiss.”
と英語で言ってみた。たどたどしかったけど。
JBは少し驚いたように笑ってから、
孫娘にするようなやさしいベシートをほっぺにくれた。
精力的なJBのほほが、
思っていた以上に”おじいちゃん”でびっくりしたことを思い出す。
クリスマスのニュースには、ちょっとつらいな。
「俺、おととい先生(名前を知らないからとりあえずわたしのことをそう呼ぶ)の夢見たよー。」
とリョウヘイ。なかなかカワイイことを言う。
どんな夢なのかと尋ねてみたら、
「何か返せって。何かわかんないけど。コップだったっけなぁ。追いかけてきてさ、マジこえーと思った。」
彼はなかなか機材を返さない。だから実習室で顔を見るたびに「ハンディカムを返せ、今すぐ返せ。」と言っている。だめもとで。それがかなり、彼の深層心理にひびいていたそうだ。夢の中で追いかけられるくらいに。
「いや、まじ、ストーカーみたいと思った。どこまで追いかけてくるん?って。こわかったー。」
ストーカーなんて失敬な!追いかけねーよ。
いつだって、カウンター越し、わたしをつかまえて延々おしゃべりするくせに。夢に出てくるって言うから、てっきりわたしのこと好きなんかと思ったじゃないか。
2006-12-18
制作展が迫ってきたからだろうか。学生から質問を受けることがにわかに多くなった。できる範囲でアドバイスはしてみるものの、だめもとでも「やってみたら、ええやん」というのが正直なところ。試行錯誤でしかモノはつくれんのやから。
失敗を恐れているのかな。
まわり道をする時間がもったいないのかな。
でも、自分自身の学生のころを思い出したら、
この「やってみたら、ええやん」というの、よう先生から言われていた。
そのころのわたしは、失敗、したくなかったんだ。
効率的にゴールにたどりつきたかったんだと思う。
ひとのことになるとよう見えて、それは我が身にそのまんまはね返ってくる。

星ってどうやったら撮れるんかなぁという学生からの質問に後押しされて「やってみたら、ええやん」の精神で星空を撮ってみた。やってみたら、欲が出てきて、ちゃんとフィルムで撮ってみたくなった。
この屋上から星を見上げることも、もうすぐできなくなるからね。
2006-12-11
実家で夕食を食べていると、母がex(エクス)ということばを教えてくれた。
元カレや元カノ、前妻や前夫を指すことばだそうな。
“She bumpt into her ex at Hakata station.”
(彼女は博多駅でばったり元カレに出会った。)
ご丁寧に例文までつくってくれて。。。
2006-12-07
昇天。
父から譲り受けたのが二十歳すぎのことだから、10年来わたしのそばにあって、いちばん近しい存在だった愛用のカメラ。少しずつ老い衰えていくように、最初に液晶が、そして巻き上げ部分が、最後にミラーまわりが動かなくなっていった。
予感はあったのかもしれない。
でも、決定的な最期を迎えたその朝は、よりによって光が良かった。
このカメラで撮ることができないんだと思うと、
哀しいということばにたどり着く前に、もう涙があふれていて。
ことばをつぎたせばたすほど、気持ちが昂るから、何も考えないように、
努めて光を見ないよう、感じないようにして、そうっとそうっと家に向かう。
それはずっとこころに突き刺さったまま。いまもまだ胸が痛い。
2006-12-06
さよならの準備を少しずつはじめる。
まず、自分の気持ちにけじめをつけて。
置いていくことばを選んでおこう。
起つ鳥あとを濁さぬよう。
今まで、そういうあたりまえのことができていなかったから。
今度こそ、感謝の気持ちを残せるように。
2006-11-29
来る12月5日、藤島啓子さんをお招きして現代音楽の演奏会を開催いたします。エリック・サティ、ジョン・ケージ、坂本龍一の作品を演奏する予定。ジョン・ケージのプリペアドピアノ、実際にセッティングするところをピアノのそばでご覧いただけます。学生と教員によるジョン・ケージのINLETS(ホラ貝とまつぼっくりをつかった例の…)の演奏もあり、気軽にお楽しみいただきながら、20世紀の現代音楽の流れをつかめる内容となっております。
12月5日(火) 16:00~18:00
京都嵯峨芸術大学 講堂(C棟4階)
予約不要、無料です。学外からのご来場も歓迎いたします。
学生がとても立派なまつぼっくりを入手してきました。先日のリハーサルで、水を入れたホラ貝の音も聴きましたが、味わい深い不思議な音でした。なかなか日常の生活の中では聴くことのない素敵な音との出会いがあると思います。ぜひお越しくださいませ。
2006-11-23

普通に銀塩で撮影をしているけれど、同時にコンパクトデジカメも持ち歩いている。デジカメで写真を撮るというよりは、もっぱら動物の動画を撮ることが多い。動画だと、映っているものが見切れるフレーミングがあって、それが写真だとあまりないことだから新鮮に感じる。
こういうフレーミングを見ると、写真は1枚で完結させてしまおうとするあまり、几帳面に画面を構成しすぎるんだなとつくづく思う。どうしても、すでにある文法に即して写真を撮ってしまうから、少しゆさぶりをかけています。
このちょっとした「おもろいかも」の種をどう育てるか。見切れている写真でもどんなんでもええわけじゃなくて、どういうのんが「おもしろいんかなぁ」、どこにそのおもしろさがあるんかなぁ…と考えています。それもただ新鮮というだけでなく、恒久的なおもしろさになりえるのかということも。種は育つかもしれないし、育たないまま終わるかもしれない。
今、もっぱらの関心事は「脱中心化」。なにか見せたいものを(意識の)中心に据えてそれ以外のものをぼかしたり、画面から排除するという画面のつくり方はいやだなぁって。
排除しなかったり、完結しなかったり、ということ。
いまの季節、南天ってとても美しい。名前もすごく好きで、まさか「南の天」じゃないよなぁなんて英語名を調べてみたらnandin。たまに、南天を見ていてふぅっと意識が遠のくようなことがある。こう、日常のささいなもののたたずまいに(宇宙と言ったら大げさだけれど)なにか大きなものを感じとること。木の落とす影が大きくビルを覆っているさまだとか、天体レベルのはかりしれない大きなものの営みの中に、自分たちがあるということを、日常のささやかなことから実感する。
重森三玲の仕事、たとえば東福寺の庭に、人為でそういうことを感じられるものがつくられている、ということにゾクっとする。ただの石が砂が苔がある様相を呈するとき、「小宇宙」と呼ばれるほど大きなものをひとに感じさせるということに。
ささやかなものであるにもかかわらず、とてつもなく大きなものを感じさせるということ。作品でそんなことができたらええんやけど、難しいよなぁ。
2006-11-20
妹はわたしのことを「ふとちゃん」と呼ぶ。
わたしは妹のことを「ちびちゃん」と呼ぶ。
先週は、粉モン天国ツカモトの数あるタコ焼き屋から、ちびちゃんイチオシのたこ焼きを買い集め「間宮兄弟」を借りて帰る。そう、その日は妹宅でのお泊まり会。母からの差し入れとたこ焼きをつまんで「やっぱロッキーのタコ焼きが一番だよ。」とタコ焼きの品評をしたあとで間宮兄弟の鑑賞。
でも間宮兄弟の
「だって間宮兄弟を見てごらんよ。いまだに一緒に遊んでるじゃん。」
ってコピーはそのまんま、自分たちにあてはまりそうで、ドキ。
雨があがり、カメラと一緒に外に出た。
強烈な黄色の光、夕暮れとともに押し寄せる青と不安定な混交。
あまりの振れ幅に、おどおどする。いつも通る道なのに。
2006-11-15
鴨川散歩のついでによく立ち寄る店がある。荒神口近くにある「はじかみ」というその雑貨店は友人から教えてもらったのがきっかけで、ことあるごとにのぞくようになる。商品のセレクトに店主の愛情がこもっている素敵なお店。
週末の散歩がてらふらっとのぞくと、来月中旬で閉店するとのこと。とても残念で、惜しむように、商品ごとにつけられている店主手書きの紹介カードを丁寧に読んでいたところ出西窯のカードで目がとまる。
「民芸、民芸と、貴族のような暮らしをしていたボンボンたちにもてはやされ…」民芸運動のこと。すごい辛辣な批判でびっくりした。近年、民芸運動に対する関心が高まり雑誌などのメディアにとりあげられることも多くなったけれど、どうかご自分の目で確かめて判断してくださいというふうに文章は続いていた。実際に窯を見学に行ったときの写真もさりげなく商品の横に添えられていた。
物事には多様な側面があって、なのに、わたしたちはあまりに無批判に民芸運動をすばらしかったと受け入れてはいないだろうか。久しぶりにドキッとしたのです。民芸運動そのものの評価、よりも、ものごとを無批判に受け入れている自分たちの姿勢に。お店で買い物をしていて、こんなにハッとさせられることってなかなかない。
なんとなく素敵そうなもの、手に入れれば生活がゆたかになると思わせぶりのものでごったがえした雑貨店は山ほどある。でも、はじかみは、店主のいいと思ったものだけを置いていて、あふれるほどのものに囲まれる生活が決して豊かではないことを知っていて、買い過ぎ防止のために、クレジットカードは扱わず取り置きも予約も受け付けない。
そんな信念を持ったお店がなくなってしまうのは、ほんとうに残念。
石けんを買いに立ち寄ったけれどその石けんは品切れ。そこで、石けんや洗剤のいらない布を購入した。「わたふ」というその布は、びわこの汚染が進んだときに、洗剤を使わなくても汚れを落とせるように作られた「びわこ」の姉妹品。
2006-11-09
数年前に友人がプレゼントしてくれた美術手帖、森山大道さんのインタビュー記事を読み返していた。
「一枚のタブロー化された作品というのは本質的な意味で写真ではないという、タブロー化への反感もあった。」
写真をばっちりと一枚の完成された「作品」に仕上げることに違和感を覚えていた。他人の作品を否定はしないけれど、自分は違うと思っている。そういうふうに理由もわからないまま、自分の直感を確信していることがいくつもある。理由がそれに追いつくのに数年かかることもある。
自分でも理由がわからないから、たまに同感できるものに出会うとほっとする。
ほっとする。けれど、理由はまだ見つかっていない。
ただシンプルに、写真は断片なのだから断片のままでいいのだと思っている。
「画家は絵筆を持たずに考えてはならない」
学生に特別に講義をするためにいらっしゃったフランス語の先生が紹介した誰だったかのことば。なるほど、と思う。
手を動かしているときに考えることは、ただ机の前でじっとして頭の中だけで考えていることとは違うから、とりあえず作りはじめたらどうだろう。という恩師のことばを思い出す。
毎朝、路上をふらふらしながら、「考え」ているんかなぁ。
2006-11-08
妹が、誕生日祝いにあたたかみのある素敵なポーチをくれた。
「化粧ポーチだけど、化粧道具入れないなら、フィルム入れにしてもいいかなぁって思って。」
ときに妹はかわいらしいことを言う。姉のことをよう見てるというか…。
ささやかな選択だけれど、ここで化粧道具を入れるか、フィルムを入れるか、というのはきっと、人生の大きな選択に通じている。このポーチに化粧道具を入れる人が歩む人生と、フィルムを入れちゃう人が歩む人生はきっと全然違ったものになる。
そう思ったら、ものおじ、どちらも選べなくて。
ぐずぐず、ぐずぐず。
うすもやのdefuse、印象そのものだった世界ははるか。
冬が来る。
くっきりとした空、なんと影の濃い。
暴力的なそのコントラストに、
不必要なほどはっきりした輪郭たちに、
目をそむけたくなるのをこらえて。
色も光もすべてが主張、主張、主張。雰囲気写真に逃げられない。
ハイコントラスト、目が痛くなるほどの乱暴なフィルムがあがるのは重々承知で、
わたしは外に出た。
どう撮ればいいのか。
どう受けとめればいいのか。
どう接すればいいのか。
光に試されている。日々、試されている。
2006-11-02
秋色に衣替えした紫陽花の葉。
朝帰りのホスト。
木切れをくわえた鳥。
枯れかけの赤いバラ。
今朝、見たもの。
うごかないすずめ。
おそるおそる、そして不謹慎なほど細部までじっと見つめて
あげくのはて自己嫌悪。
それは夕方のこと。
2006-11-01
快調に朝の撮影を続けていて、今日はええ感じと思っていたら、フィルムを装填していないことに気がつく。ありえない。初歩的なミス。
そういえば、大竹伸朗だったかがインタビューで若かりし頃のことを思い出して「フィルムが入ってなくてもいいくらいだった。」と答えていたように記憶する。
毎日、午前中の限られた時間の中で徒歩で撮れる範囲は限られている。自ずと同じ被写体を何度も撮ることになるけれど、それでも、フィルムが入ってなくてもいいくらいとは思えない。
明日もまた歩いて、同じように撮るけれど、それでもやっぱり痛い。
見たかったんだ、その写真を。
できるだけゆっくり『写真と日々』を読んでいた。クールでスピーディーな分析に追いつけずに、何度も反芻しゆっくり咀嚼しながら読み進むのが通例なのだけれど、突然、胸が詰まる思いがした。少し長いけれどその箇所を抜き出そう。
この時期の中平の文章の異様さは、「私」が、ある例外を除いて、格変化しないところからくる。格助詞を欠いた、いわば不定詞形の「私」。「思い出すことができない」「必要な文章を書く」「作り上げねばならない」という動詞の主語になりえずに、ただそのとなりにあるだけの「私」。あらゆる文脈に接続される以前の、内包を持たないまま宙に浮いた形式としての私は、しかし、「私が写真家で在る」という文章においてのみ、主語となる。「私は」ではない。「私が」なのだ。あなたは何ですか?私は写真家です。写真家はどなたですか?私が写真家です。「私」よりも「写真家」が先なのである。つまり、「写真家で在る」ということのみ、このたったひとつの絆を通じて、不定詞の「私」は世界に接続される。写真が、平凡であることの重みという、人の実存をつなぎ止めることがあるのだ。透明な形式にすぎなかった者が、現実性を獲得して色づく。「原点」とはこのことである。無名性はじつは問題ではない。私は中平卓馬だ、ではなく、中平卓馬が私だ、なのだ。
(『写真と日々』 清水穣著 現代思潮新社 2006 から抜粋)
記憶をまったく喪失してしまうということがどういうことなのか、わたしにはまったく想像もできていなかった。けれど、この文章を読んだとき、その凄まじさに触れて不覚にも泣いてしまった。
これだけ丁寧に説明されてやっと知りえるというのは、わたしが鈍感なだけかもしれない。でも、「私、ほとんど何事も思い出すことができず、…私ようやく必要な文章を書くことが、可能となりましたが…」という中平の文章から、彼の置かれている状況を濃やかに察する感受性。感受性にもいろいろあるけれど、言葉に対する感受性のすごいものに出会った気がした。
2006-10-31
先日のミソヒトモジたちとの会話の中で「写真の本質って何?」と訊かれ、まったくコメントできずにいた。そのことでひどく、ひどく悶々としている。
そういうことは、案外近すぎて見えていない。いちばんシンプルな回答は、「光の記録媒体」なんだと思う。レコードが音の記録媒体であるように。
それにしても写真にはいろいろとロマンティックな言説がつきまとう。
過去性や記憶というキーワードはよく耳にするけれど、はたしてそれが「写真」の本質なのか。写真にしか言えないことなのか。それとも記録媒体全般にあてはまるものなのか。そういうことを、寝しなにつらつら考えながら、そういえば、王家衛の『ブエノスアイレス』で、南米最南端の岬をめざすチャンが、ファイにさし向けたのはカメラではなくてテープレコーダーだったな、とか。映画のラストで、ファイが台北にあるチャンの実家でくすねたのはチャンの写真だったな、とか。
核心にはたどりつけずに、同心円上をぐるぐるまわっている。まだしばらく悶々としそうだ。
2006-10-19
第1弾のフィルムがあがってきて、スキャニング。スキャナの設定のせいかえらく黒がつぶれているのが気になる。色ひとつで写真の印象はまったく変わるから、色って大事やなぁと思う。
以前よりずいぶんラフに構えるようになってきている。でも、まだまだ、いろんなものを引きずっている。
スナップって誰にでも撮れてお手軽なぶんいちばん慎重にならんとあかん。その緊張感がええのかもしれない。あと、ものごとを権威づけるシステムというものが根っから嫌いなんだと思う。真っ白い箱の力を借りてただの写真を「作品」にしてしまうこととか齟齬があった。
展覧会をして、わざわざ遠いところから足を運んでもらって、写真を見てもらうことにも気後れがあった。写真なんて流通のしようはいくらでもあるのに、わざわざ展覧会の会場に来てもらうんだったら、その会場じゃないと得られない体験を提示しないといけないと思っていた。だから、作品は自然とインスタレーションのかたちを採ってきた。展覧会という作品発表の形式が最初にあって、そこからインスタレーションという作品形態が導きだされるのは、順序がおかしいんじゃないか。まず作品があって、それに適した発表形式を選ぶのがまっとうなんじゃないか。
わたしはスナップを撮るのがいちばんしっくりするし、スナップなら点数もたくさん見せたほうがいい。いまは冊子形態やweb媒体といったものに発表形式をシフトしようと思っている。だから展覧会をするつもりはまったくない。数年かけてスナップを撮って、それを適切な方法で見せる。中長期プラン。だから毎日少しずつ撮りためていっている。
わたしは美術からスタートしたのではなく、写真からスタートしたのだから、写真は写真のままでいいんだ思う。わざわざ白い箱に持ち込んで「作品」として見せることを意識しなくていい。さりげない方法ですばらしい視覚体験を提示できれば本望。
2006-10-14
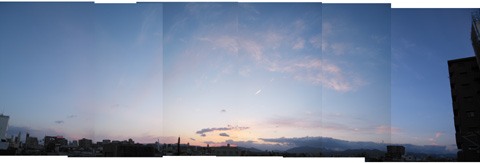
resetすると決めてからほぼ毎日、朝か晩は撮影に出かけている。
カメラを持った当初、なんやようわからんけど、妙にひっかかるという感覚だけをたよりに撮影をしていた。何を撮っているのかようわからへん写真ばっかりやった。数年撮っているうちに、フォトジェニックなものばかりを追うようになっていった。そして光や影に対するフェティッシュなまなざしも内面化してしまっている。
そういったものをすべてresetしたい。光や影も含め「もの」に対する関心を捨てて、その場から立ち上ぼるニュアンス(空気感という言葉は安直すぎて嫌いだけれど)に感覚を研ぎすませよう。たぶん、撮りはじめた頃の状態まで、いったん戻らないといけないと思う。それでもいい。
とある写真展で、技術に走ったおもしろくない写真と、つたなくても空気感をうまくとらえている写真とを同時に見たときに思った。写真に長く携わる人が陥る落とし穴にはまってはいけない、と。
手放す勇気。
2006-09-25
昨日の朝、コーヒーを淹れながらぼんやり考える。
被写体ではなくて、撮るものと撮られるものの「あいだにあるもの」、その関係をとらえたくてスナップを撮っているのだと思う。
「わたし」と「世界」との関係。
スナップについては、ずっと「何を撮っているのですか?」という問いに答え損じてきた。
なるべく特定の被写体ばかりを選ばないようにしてきた。
トクベツなものも撮らないようにしてきた。
被写体によってシリーズをまとめることに違和感を感じていた。
この数年、自分の興味が現象学のほうへと向かっていた。
そういうこと、すべてに合点がいった。
スナップによってとらえようとしているのは、被写体そのものではない。関係性なんだ。
それをきちんと言語化するのに4年もかかった。
そして、夜、むくんだ足が痛くて眠れないくらい、歩いて撮った。
まだまだ。まだまだ。
2006-09-22
少し光が秋めいて、喜びいさんだ午前7時。
世界はあまりに黄色く、想像以上に光はきつく。
まだ少しはやいのかもしれない。
影も長すぎる。
朝の光は思っていたほど素敵じゃない。叙情的すぎる。
焦って撮った数枚のせいで、自己嫌悪。
仕上がったフィルムを見て、また自己嫌悪に陥ることも想像に難くない。
撮るべきもののないときは絶対に撮らないこと。
2006-09-09

写っているものがなんであるかを把握するまでの時間。「ん?これ何だろう?」と、「ああ、そういうことね」の間に起こる「何が何でも写っているものを同定したい」という抗えない欲求。そういうものに興味があります。
被写体ではなくって、見るという行為への関心。
2006-09-08
迷っていたのは、構成的な写真を撮るのかスナップを撮るのかということ。
わたしはスナップの可能性をずいぶん悲観していた。悲観しながら、自分の根本にあるのはスナップだという事実との間で、右往左往していたのだと思う。
「ただ」のスナップで何ができるのか。ましてや商業にのっからないところでスナップを撮り続けるなんて、趣味で終わってしまうんじゃないのか…。そういう思いが頭をかけめぐっていた。現代美術を前提として構成的な作品をつくるという方法もある。そのほうが傍目には「作品」と認識されやすい。でもね…本当にそんなことがしたいんかなぁって。
今日、ひとつの覚悟をする。
いまさらだけれど、わたしはスナップを撮る。
コンセプトをたてて構成して撮ることにも、同じような被写体ばかりを追うことにも、違和感を感じている。ごまかしてもしかたがない。
迷って立ちすくんでいるわたしの背中を押してくれたのは、批評家の丁寧で繊細なしごと。
2006-09-07

先の写真と対にするつもりで撮ったもの。下を向いて撮って、上を見たら鳥が飛んでいたのであわてて撮って。「田んぼのいろは、ほらこの空の色と同じじゃないか…」ということ。色への関心。
鳥と居合わせると必ず撮ってしまう。でも、運動神経が悪いので動く被写体は苦手。

鏡やガラスは、ものが映ると反射面のそのものの質感が退いて、その表面を認識しにくくしてしまうけれど、もの(ここでは田んぼ)がその表面としての体裁を保ったまま、反射面としての機能を持っているという事態に興味があります。
このときは、「映りこむってかたちだけでなく色も一緒に映るんだ!」という単純な事実を発見して感動していました。
そのわりにはそっけない。

逆光だからか、叙情的。
「いい写真を撮りたい」という気持ちをどう実現していこうと考えたときに、ただ感受性や気分に頼るだけではだめで、冷静な分析とあわせていかないといけないなとあらためて思っています。
自分がどういった被写体のどういうところに関心があって撮っているのかということを徹底的に洗い出して分析するところからはじめようと思います。いま自分が撮っているものの限界をみきわめて、そこからそれを超える方向に向かっていきたいなと。
ちょうどいま、写真批評の講義を聴講していて、「泣かせる」写真の手法というのは定石があり、「海のような空虚な写真は見るひとが感情移入をしやすい、フェティッシュなものもしかり…」などといった話をきいています。いい写真を…という思いが、結果として単なる「泣かせる」手法に回収されるようなことにはなりたくないなぁ。
初日ははずしてしまったけれど、清水穣氏の講義「森山大道研究」を3日間ぶっとおしで受ける。今年いちばん贅沢だった10時間と40分。
あらかじめ境界線を画定してそれを突き抜けるという、写真をとりまくモダニズムの二元論への批判を受けて、昨日の自分のコメントが、そのまんまモダニズムの言うところを引きずっているということに気づきドキっとする。「いま自分が撮っているものの限界をみきわめて、そこからそれを超える方向に向かっていきたいなと」…なんて。知らず知らずのうちに、ある思考体系を前提としているのは恐ろしいと思う。
展開が早かったからまだ未消化の部分も多いけれど、たくさんいいことがあった。森山大道の近作の読み方がやっとわかったこと。いつも煙にまかれるようであった写真論や写真批評について少しクリアになったこと。自分が抱える問題意識を整理できたこと。なによりも、スナップの可能性を信じる気持ちになれたこと。
感謝。
※最新号のInter Communication「コミュニケーションの現在・2006」に「荒れ・ブレ・暈け」再考 というタイトルで清水穣氏が寄稿されています。関心のある方はどうぞ。

透過物をとおりぬけてきた像は、いささか抽象性を帯び、事物そのものというより映像的に受けとられる。(「映像的」のほかにいい表現がみつからない…)
「これはあじさいだ」ではなくて、「これはあじさいの像だ」という感じで。物理的に一枚なにかがはさまるだけでなく、認識にもなにか一枚あいだにはさまるように感じられる。
クリアにあじさいが写っている写真とは違うものをこの写真から受けとるのはなんでろう…というところに関心がある。
2006-07-03
2006-06-26
投げかけられる影もまた、事物の指標となり得よう。
写真と影の共通項、指標(インデックス)性。
2006-06-20

先週から実験を開始。影のニュアンス、どのくらい制御可能か。ベランダの植木鉢を持ち込んでクリップライトでこじんまりと実験。
なぜ影なのか。ということ。
どこで、どういうかたちで見せるか。ということ。
動きのある影はおもしろい。
投影なのになぜ映像を使わないのかということ。
実体との関係性。
高松次郎の作品があたまをよぎったから(あれは絵画作品だけど)、図録を調べてみた。彼自身のコメントを読んだところ、一連の影の作品の制作意図はカンバスという媒体そのものの美しさを見せるところにあるらしい。
2006-06-19
キーワード
2006-06-15
コンペ用に過去の作品をまとめると同時に、あたらしい展示プランを考える。
いろいろ作業をするなかで見えてきたこと。
現時点でわたしは、
写真そのものよりも空間展示に関心の重心がある。
ホワイトキューブの展示を前提とするプランの公募で
わたしがしあげたプランは、写真を使わないインスタレーション。
写真を撮っているうちに鋭利になったのは、光と影に対する感覚。
特に、影に対してはフェティッシュなほどにひきよせられる。
言葉で説明はできないけれど、そこにわたしにとっての「必然」がある。
影をテーマに作品をつくりたいと思っていたことにいまさら気づき、
大きなホワイトキューブに写真を展示するより、
影で空間を構成することを考えたいと思った。
すこし実験をはじめたから、このまま続けてみようと思う。
2006-06-12
わたしの旧くからの友人知人で、すすんで現代美術に接する人はほぼ皆無である。
伝統的な芸術に親しんでも、現代美術は苦手だという人は多い。どうして、それほどまでに現代美術は人々の生活から乖離しまったのか。その原因を探りたいと思っている。
それ自体がそれによって切りとられた世界の断片の所有である絵を所有すること、それもできるだけたくさん収集することというコレクターの意思は、まさにルネッサンス以降の見る文化の一端であり、十八世紀末から十九世紀にかけて形を変えて、美術館や博物館というシステムへ回収されていくことになる。美術館や博物館はいわば十八世紀末に成立したブルジョア文化の現在における保存装置なのであり、かつての王権の変形した残骸なのである。(中略)
また、一方で美術館や博物館は十九世紀に入ってからの激しい時代変動と同調して最後の礼拝的な場所としての機能も果たすようになっていく。(中略)
“芸術の神殿”、芸術の絶対化といった考えが芽生えてくるのはこうした土壌からであり、この考えこそが芸術を芸術自身で自律させるという自閉的な近代の芸術観の根底をかたちづくることになる。芸術こそ最高の価値とみなすこの信仰は、いわば宗教の代用である。
ひきつづきジョン・バージャーの『イメージ Ways of Seeing―視覚とメディア』からの抜粋である。「芸術を芸術自身で自律させるという自閉的な近代の芸術観」という視座は、その芸術観をごくあたりまえの「芸術のありかた」として受けとめていたわたしにとっては新鮮な驚きであった。
芸術を芸術自身で自律させる。すなわち、社会の直接的なオーダーからはなれたことが、現代の芸術が一般のひとびとにとって難解な表現を生み出したひとつの要因であることは否めない。
短絡的に結びつけるのは危険だけれど、こと現代美術が敬遠される…その理由のひとつを見た気がする。
2006-06-08
しかし油絵の伝統ほど、傑作と凡作の差が大きい文化はないだろう。この伝統においては、差は技術や想像力の問題ばかりではなく、絵に対する精神の姿勢の問題でもある。十七世紀以降、ますますその傾向が強いのだが、標準的な作品は多かれ少なかれ冷笑的に生みだされたものである。つまり、画家にとっては、依頼された作品を制作したり売ったりすることのほうが、その作品が表現している価値よりも意義があった。凡作は、画家が不器用だったり乱暴だったりした結果生まれたというより、市場の要求が芸術上の要求よりも強い結果として生まれてくるのだ。
(『イメージ Ways of Seeing―視覚とメディア
』ジョン・バージャー著 伊藤俊治訳 PARCO出版局 1986年 より抜粋)
市場が活発であればあるほど売れ筋が顕著になる。それにのっかるほうを選ぶ作家が多かったということ。精神の姿勢の問題とは、なるほどそういうことか。
しかし、作品を「売ること」をどうとらえるかは難しい。
売れ筋を狙うようなあざとい作家はまわりにはいないけれど、まっとうな作家のなかでも意見は二つに分かれている。「売る」からこそ生まれる緊張感によって作品のクオリティがあがるという考え方と、売るのを意識することから自由になりたいという考え方。前者は無意識のうちに市場のニーズをとりこんでしまう危険性を、後者はいわゆる「趣味」のレベルに埋没してしまう危険性を孕んでいる。
どちらのリスクをとりながら制作するかはそれぞれの作家しだいだ。ただ単に、作品をつくっているのではなく、どう経済とかかわるかは、作家であれば誰しも考えるところなのだろう。
そういった制作活動の基本的なスタンスにはじまり、細かいことをひとつひとつ丁寧に繊細に選択していくことが、よりよい作品の生まれる土壌になるのかもしれない。
修士の担当教官から教えてもらった。
“constellation”
布置という意味ともうひとつ、星座という意味がある。
忘れられないことばだ。
大学のころ、美術の文脈を知ってしまうと、知らないうちにその文脈の範囲内でしかものを作られなくなるんじゃないかと不安で、美術史、写真史にはそっぽを向いていた。そんなわたしを諭すように手渡されたことば。
長い芸術の営みのなかで、自分の実践がどの位置にあるのかを把握したうえで制作をしたほうがいい…と。
それから3年ほどたって、やっとその言葉の意味がわかりかけているのかもしれない。画家や美術家が、成功・不成功にかかわらず、どのようなトライアルを続けてきたのかを知りたいと思うようになった。
2006-06-05
ジョン・バージャーの『イメージ Ways of Seeing―視覚とメディア』(伊藤俊治訳 1986年 PARCO出版局)を4年ぶりに再読した。原書は1972年に著されたとのことで30年以上も前のものだということを読み終わってから気づいた。そのくらい古さを感じさせないものだった。いくつかひっかかるポイントを抜き出してみたい。
しかし、いずれにしろ、今その原画が持っている独自性とは、それが”複製の原画”
であるということのなかにある。人が独自性を感じるのは、もはやその絵のイメージが示すもののなかにではなく、その絵のあり様のなかにある。(上述『イメージ Ways of Seeing―視覚とメディア』より抜粋)
先週末に見た「大絵巻」展。長蛇の列をつくっていたのは高山寺の「鳥獣戯画」だった。ほかにもおもしろい作品はいくつもあるにもかかわらず、また見るべき作品がほかにあるにもかかわらず、その列に並んだ背景には、グッズやモチーフに多く用いられ親しみ深い「鳥獣戯画」の原画を確認しよう、「ホンモノ」が複製とどうちがうか、その差異を見いだそう、そういうモチベーションが強く働いていたことは否定できない。
原画の意味はもはやそれがどのような特別なことを語りかけてくるかではなく、それがどのような特別な状態にあるかに見いだされる。(同書より)
複製とは複製物と割り引いて接し、原画(ホンモノ)は複製物との比較において接する。そのどちらも、真正面から作品と対峙することとはほど遠い。複製の出現によって奪われた体験。そういうものがあるということを再確認する。
わたしの記憶が正しければ、トーマス・シュトルートの美術館のシリーズはこれと同じ論旨で解説されていた。
2006-06-01
日々悶々と考えていること。雲散霧消してしまうまえに。
2006-05-30
写真は写真のままであるほうが、まだ自由なのではないだろうかと思うときがある。
写真を「作品」としてホワイトキューブで展示することにわたしはまだ違和感を感じている。
写真を展示をする際には、その空間で写真を見せる意味を考えたいと思ってきた。だからわたしの場合、写真の展示はインスタレーションとしかなりえない。どこでどのように見せるかは写真の内容と連動する。
話を戻そう。
写真はもともと複製物だからこそ写真集という形態が可能である。
提示の仕方としては、写真集の可能性もwebの可能性もあるのだ。
写真の複製物としての可能性をあたまの片隅で考えつづけること。
特にweb上を行き交うデジタルの、「質量0の写真」の可能性を。
いま写真はまったくのスランプ。
自分の撮っているものが自分でおもしろくない。
ひとつ土台として決めたのは、写真制作を経済活動とリンクさせようと目論むのはやめること。
どんな写真を撮ってもいい自由を確保する。
簡単にひとの感情や感傷に訴えるようなものはやめることにした。
わかりやすいものを撮るのもやめにする。
かつての級友はイラストレーターで生きていくと決めてから作風がかわった。
わたしは、同じ授業で緑やらオレンジやらきわどい色彩で描いていた彼のグロテスクな自画像が好きだった。絶対に万人ウケはしないけれど、ゴテっとした芯を感じていた。いまは、完成度の高い良いイラストを描いている。
わたしは、そうではないほうを選びたい。
たとえ受け入れづらかろうと何か言い知れぬ核のあるものをと思う。
経済活動と直結しようとすると無意識にも他者のニーズを意識する。
そこに不自由が生まれる。
そもそも、前サイトの「ことのは」は制作日誌のつもりではじめたのに、
ただの日記になりさがってしまった。
ことばをつむぐことは手段のつもりではじめたのに、それ自体が目的にすりかわっていた。
もう一度仕切りなおして意識的に制作日誌を書こうと思う。